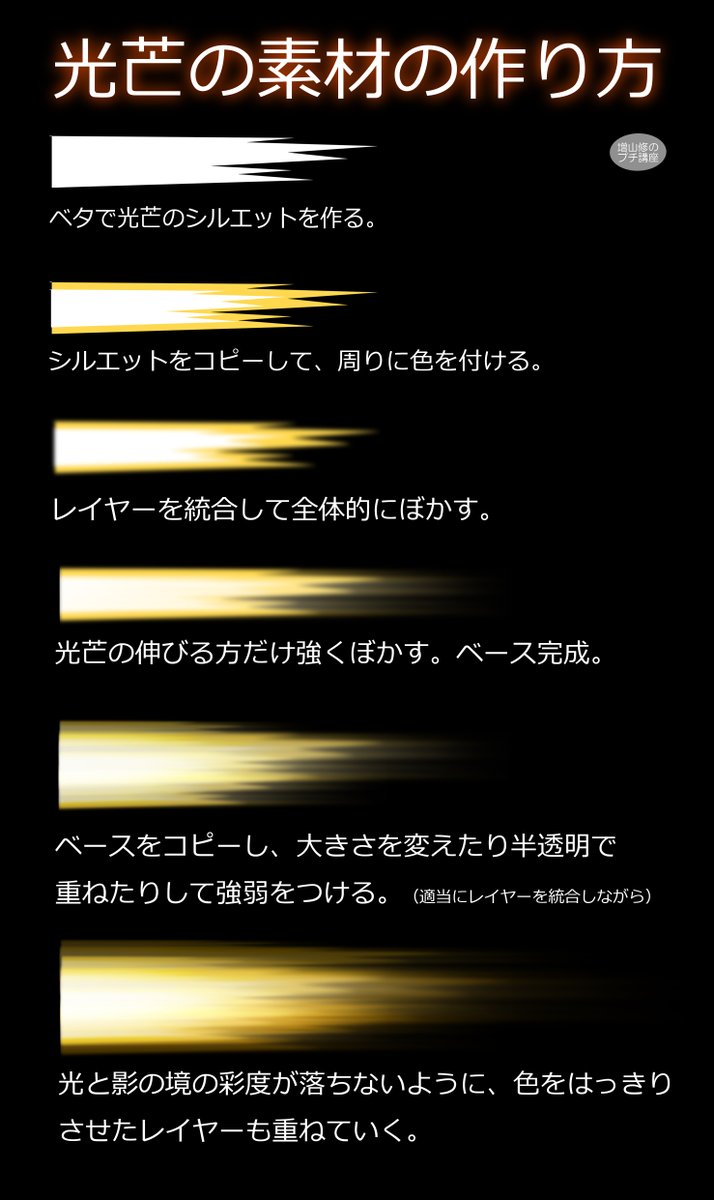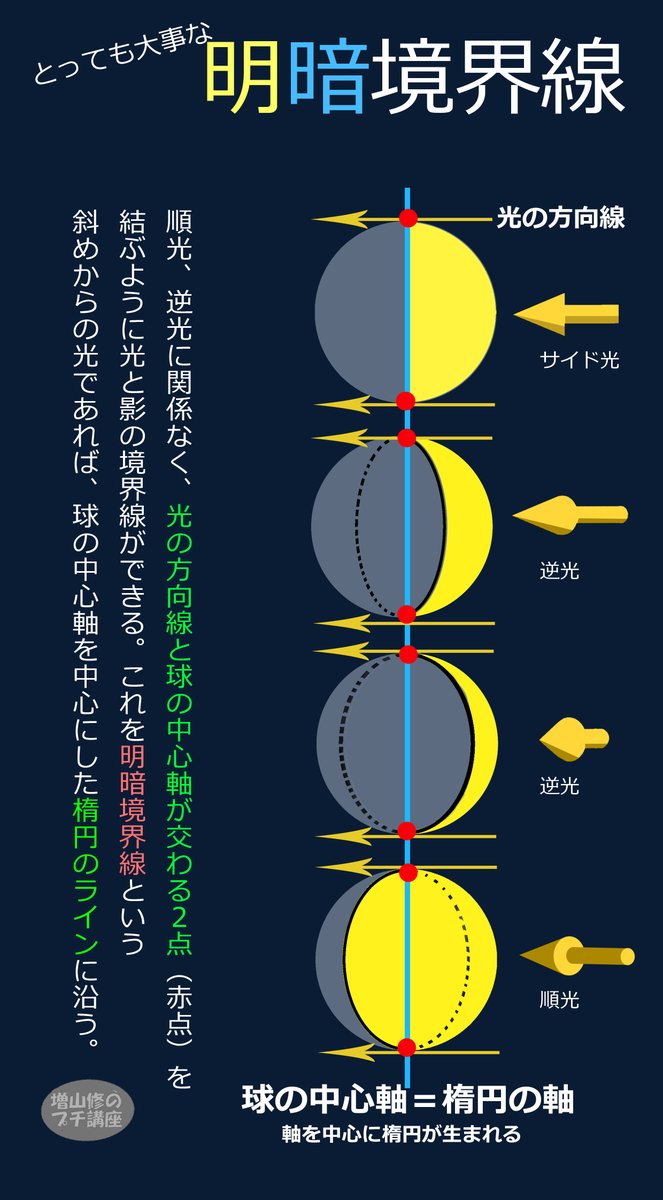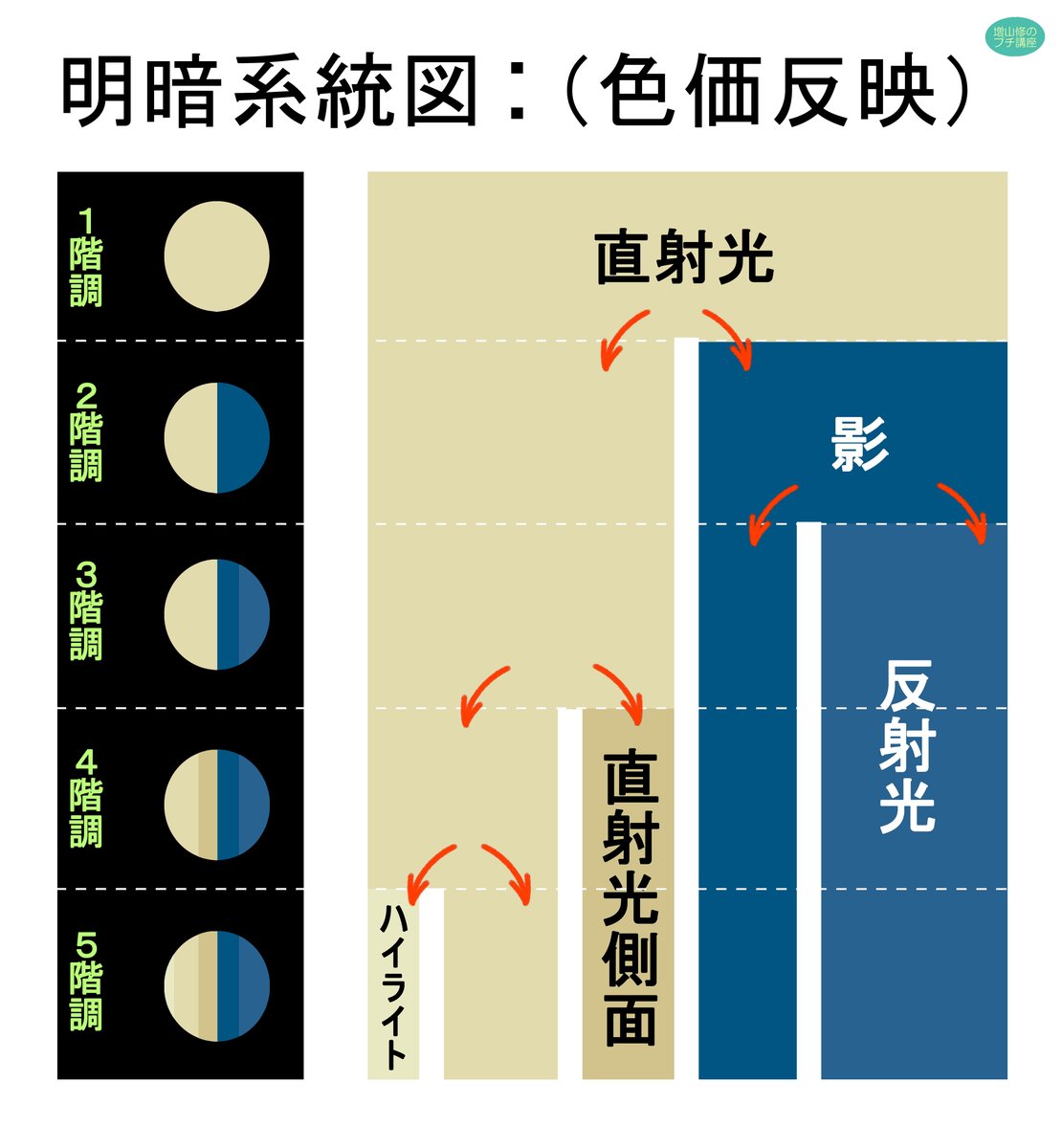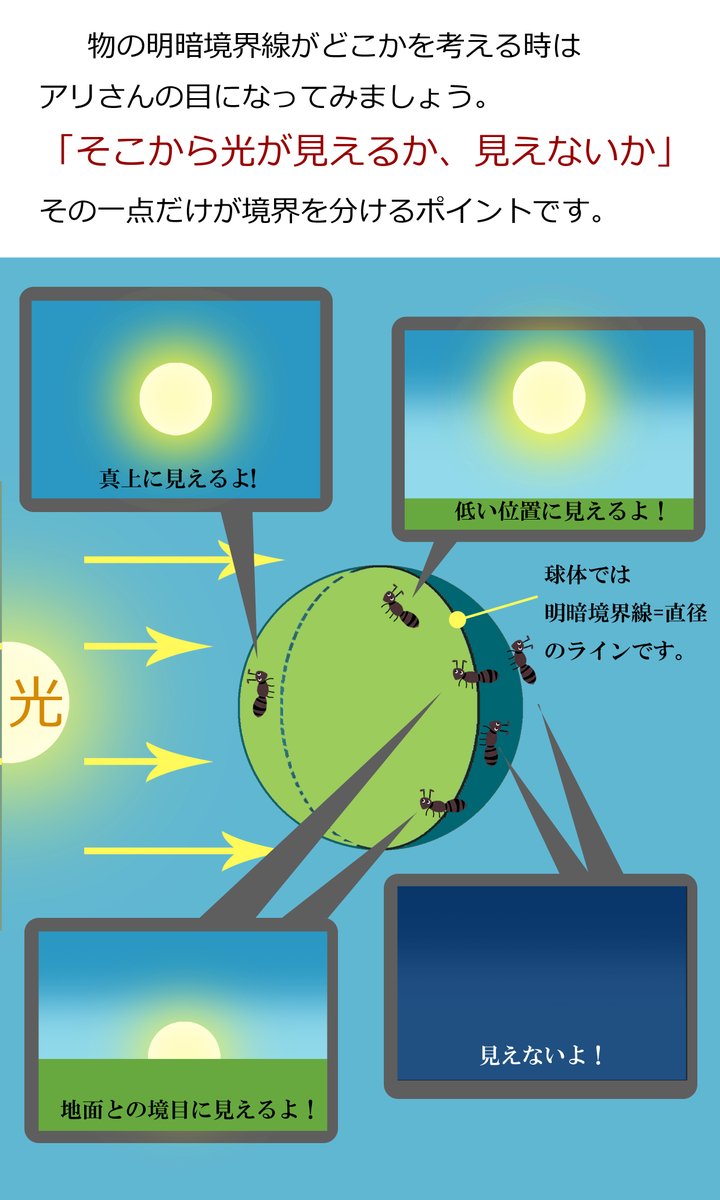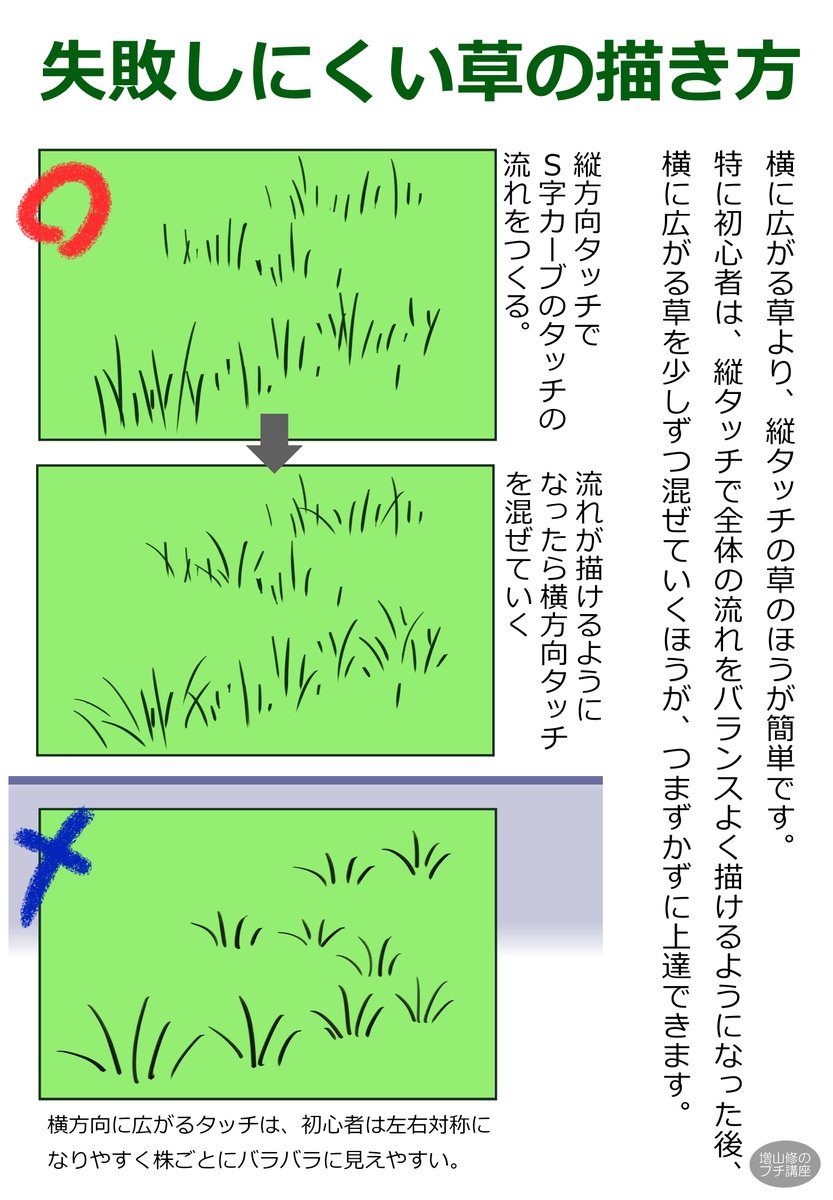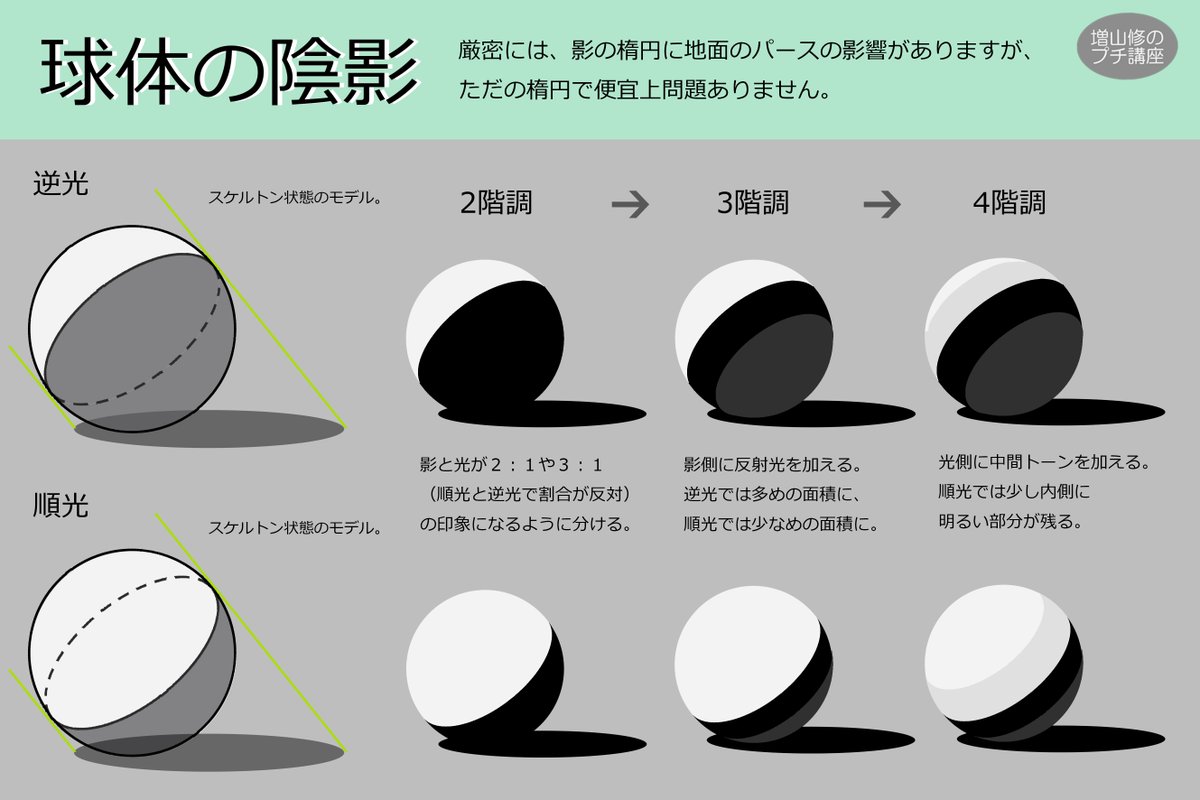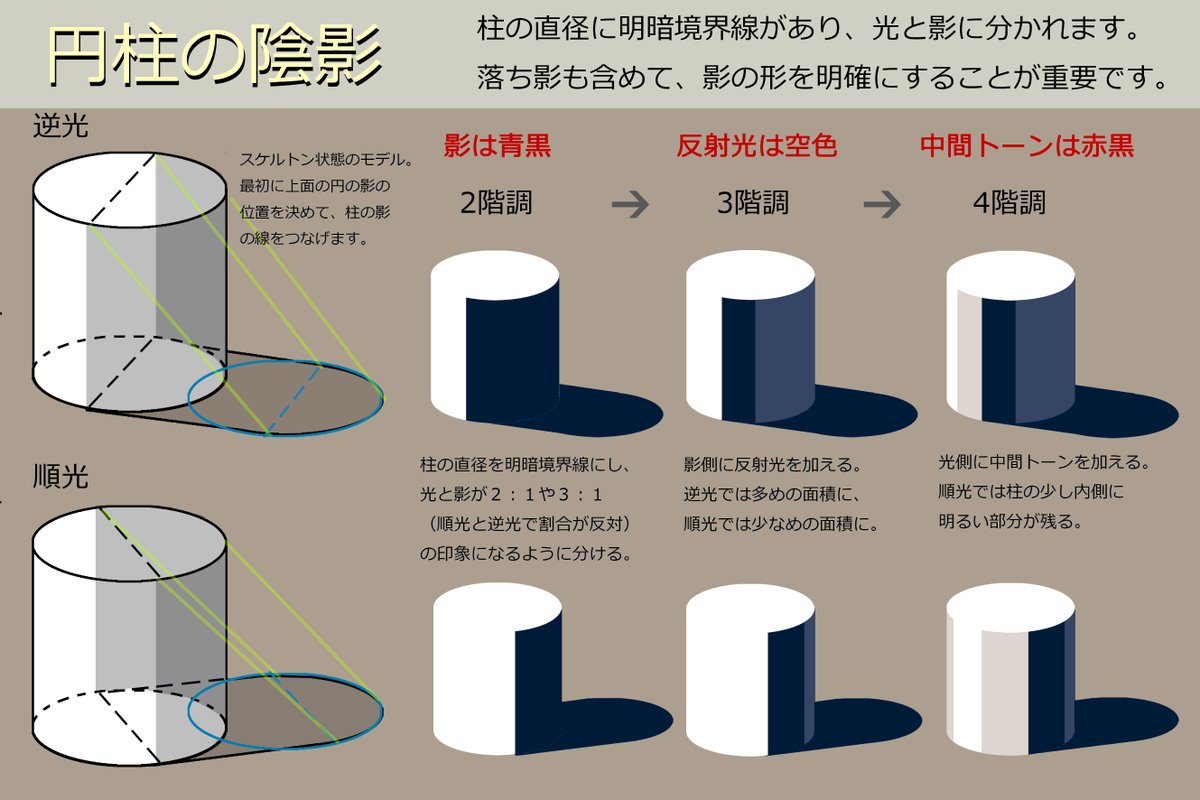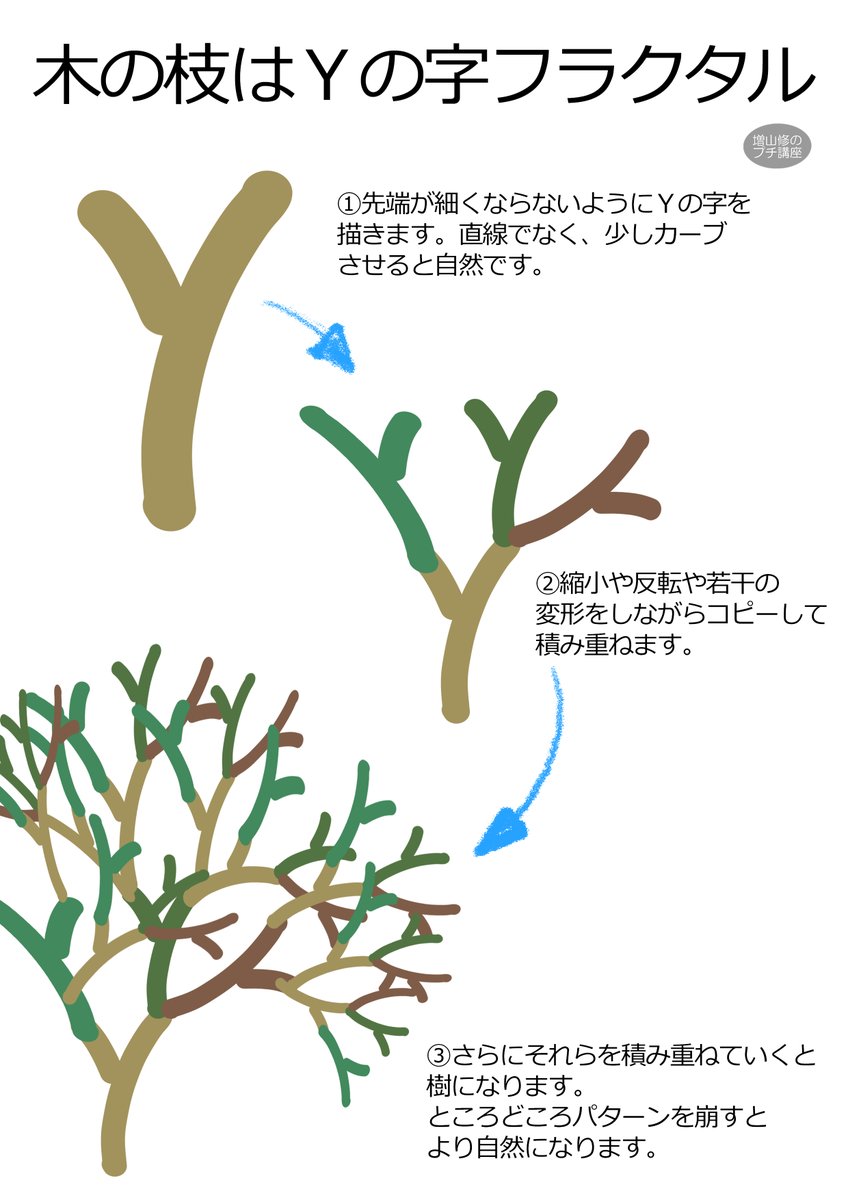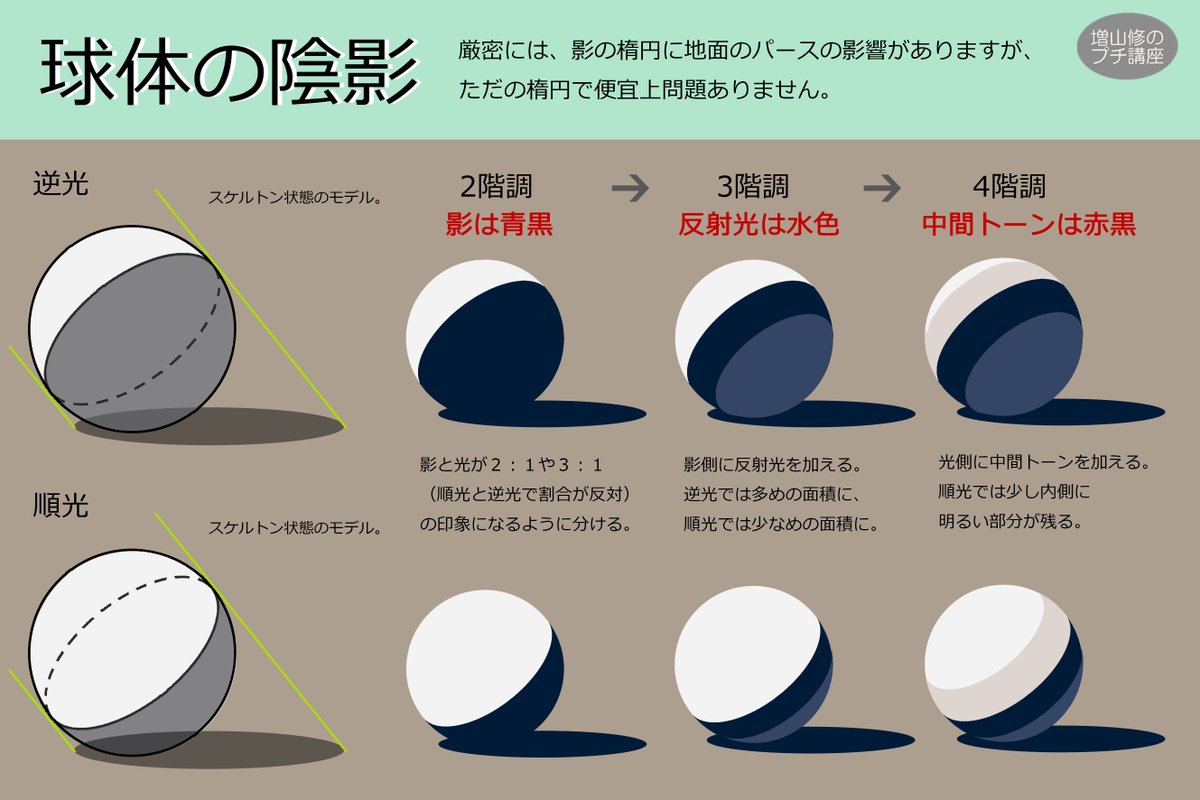176
#制作進行 の #説明会 終了です!コロナ対策で急遽WEBとなりましたが沢山の方に参加いただきました!ありがとうございました!
#アニメーター #背景美術 の説明会は4/8からです! #マイナビ2021 よりご予約ください!
※各回定員50名/開催2日前までに要予約/応募者参加必須
job.mynavi.jp/21/pc/search/c…
177
絵具によるイメージボード
#背景美術 (再掲)
178
182
【朝日による光の変化】
アニメーション美術では1カット内で光の変化がある時、背景を2枚描きます。
デジタルではコピーできるので色だけ変えれば良いですが、絵具で描いていた頃は紙の収縮によってずれる場合があり、気を使いました。
#背景美術 #maiabys 背景:西俊樹(@shirakabausagi)
184
185
朝日を浴びる街
画面の中のもの全体が遠くにある場合、影の色は全体的に青みになります。近景がある場合はそれより暖色系になります。
#メイドインアビス #背景美術 背景:西俊樹(@shirakabausagi)
187
188
190
199