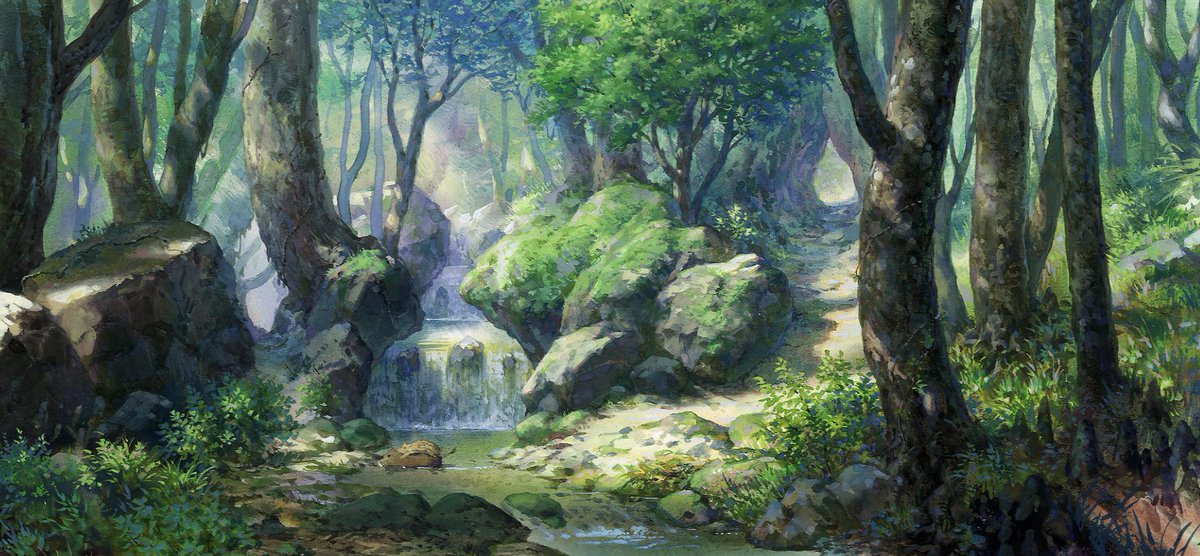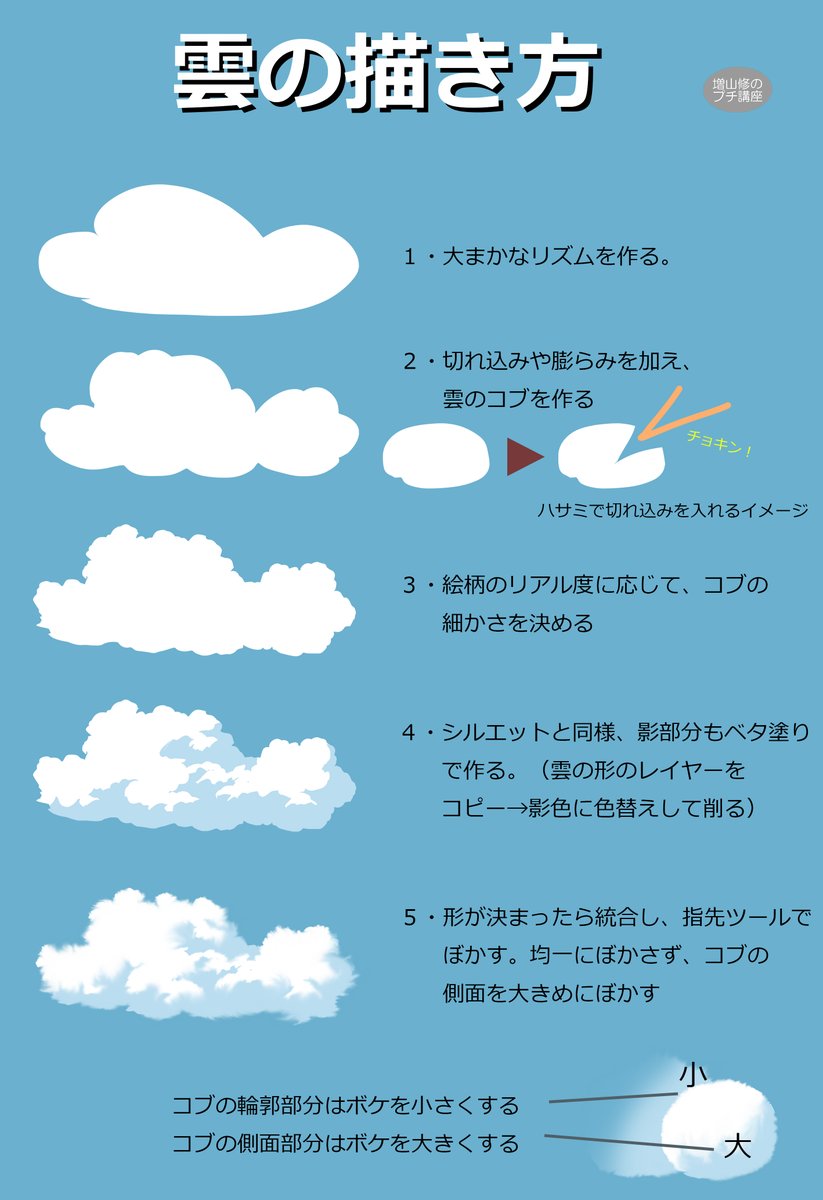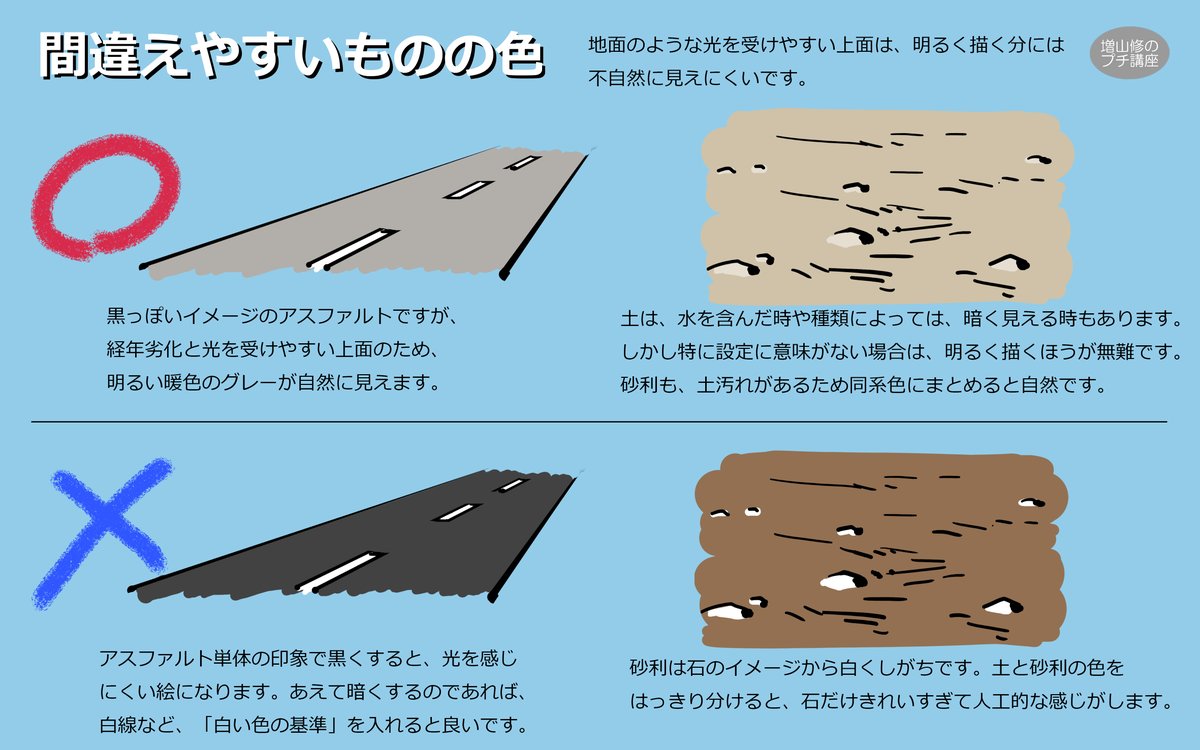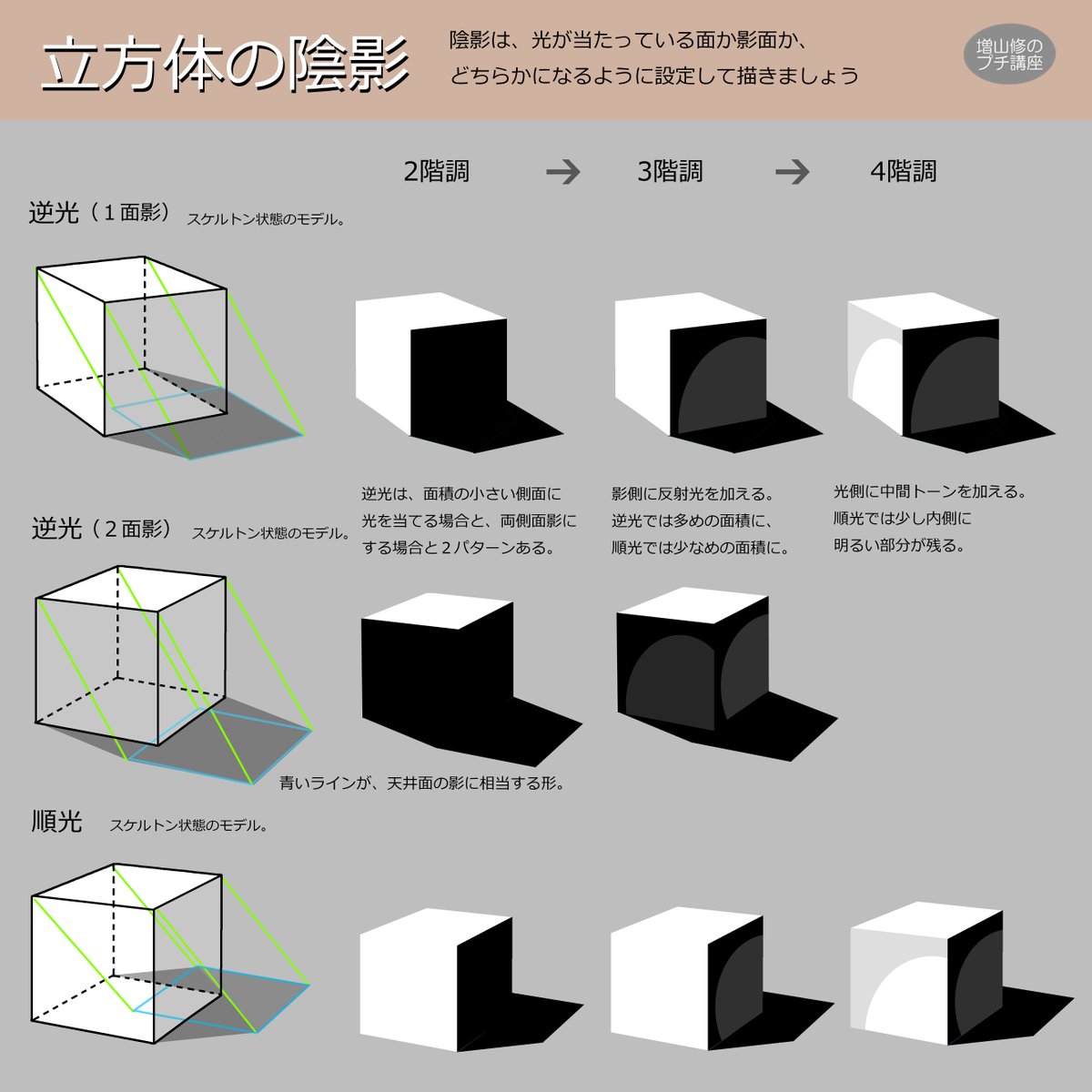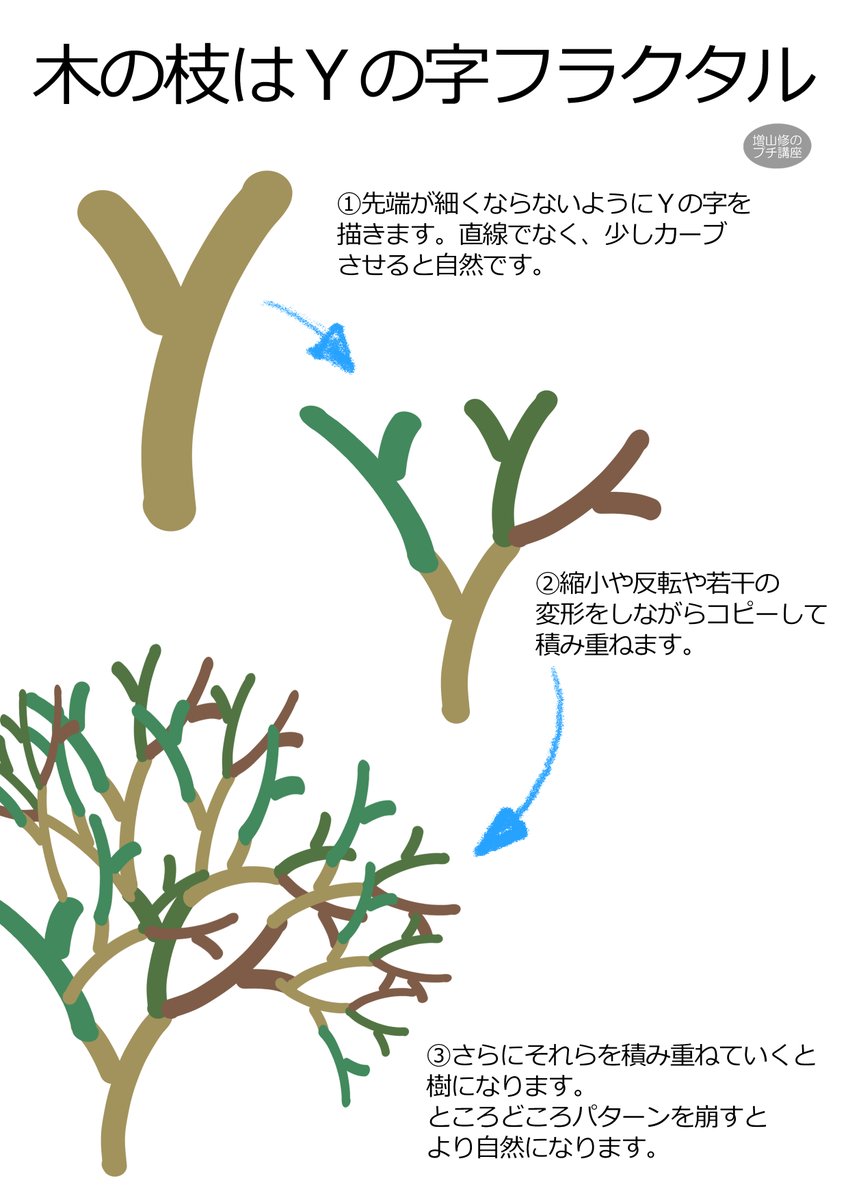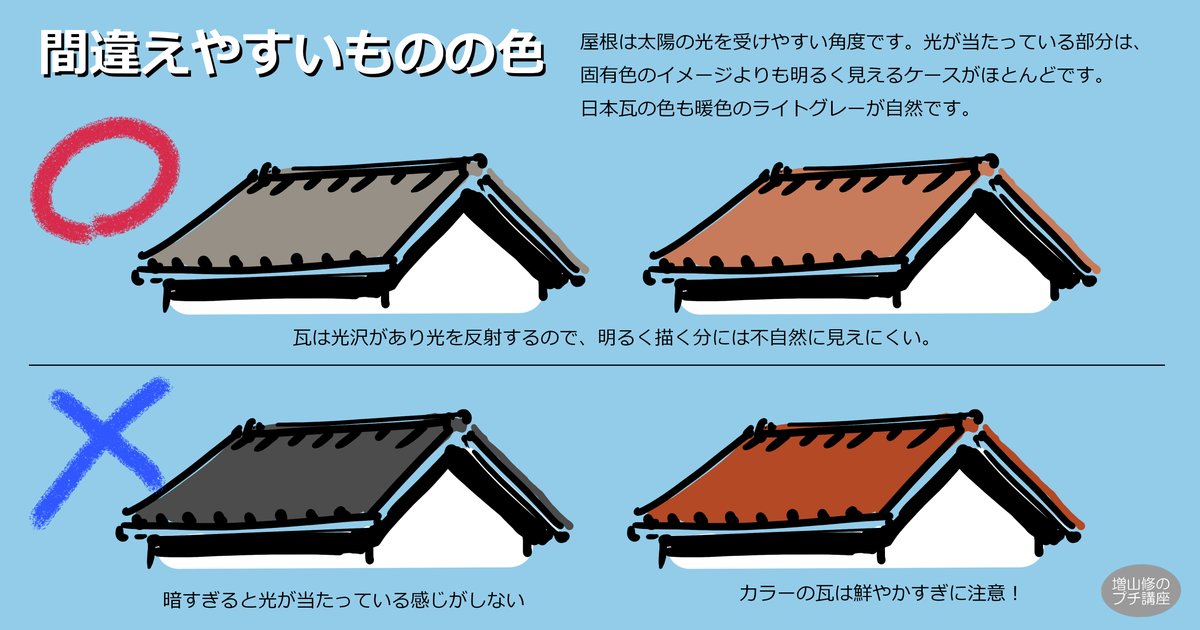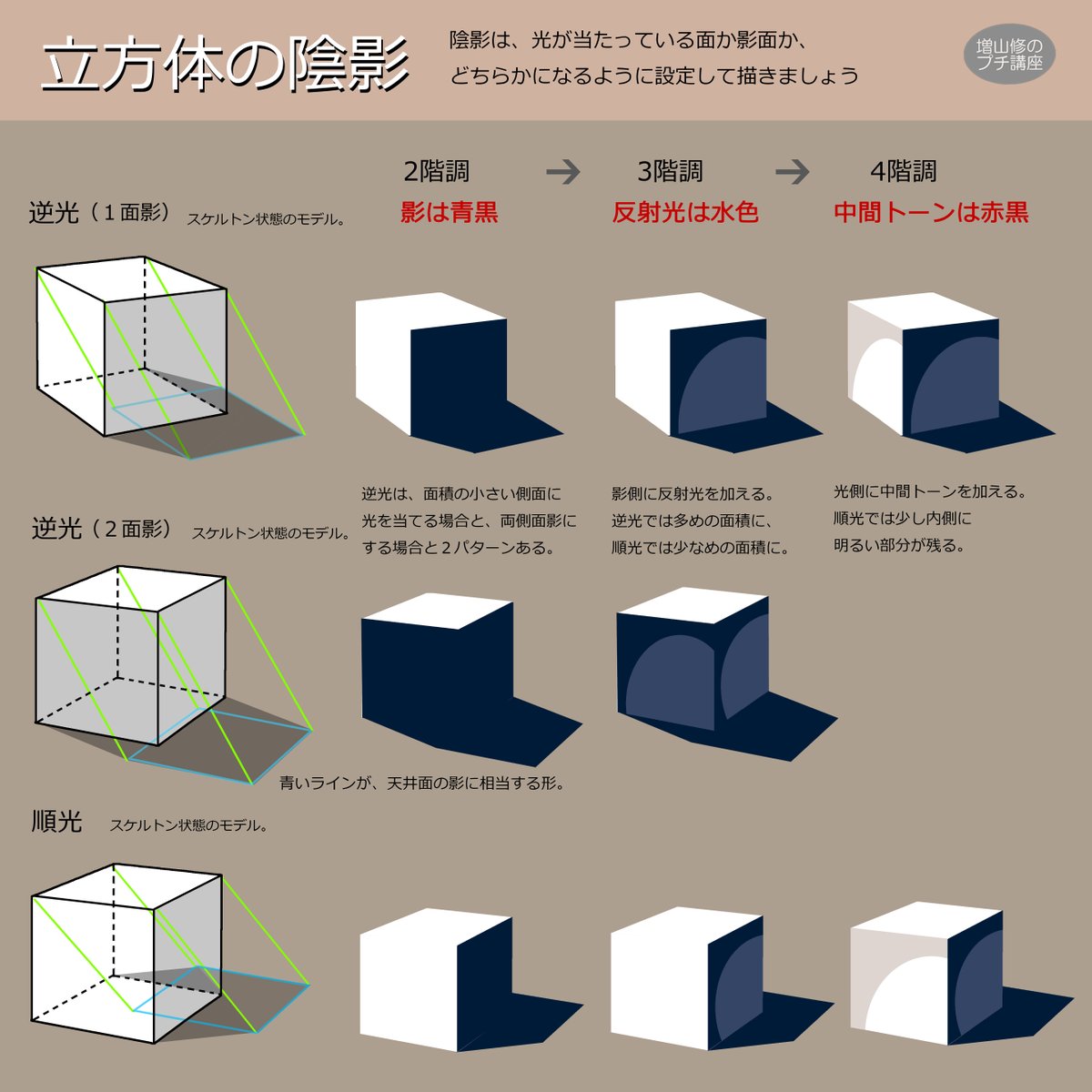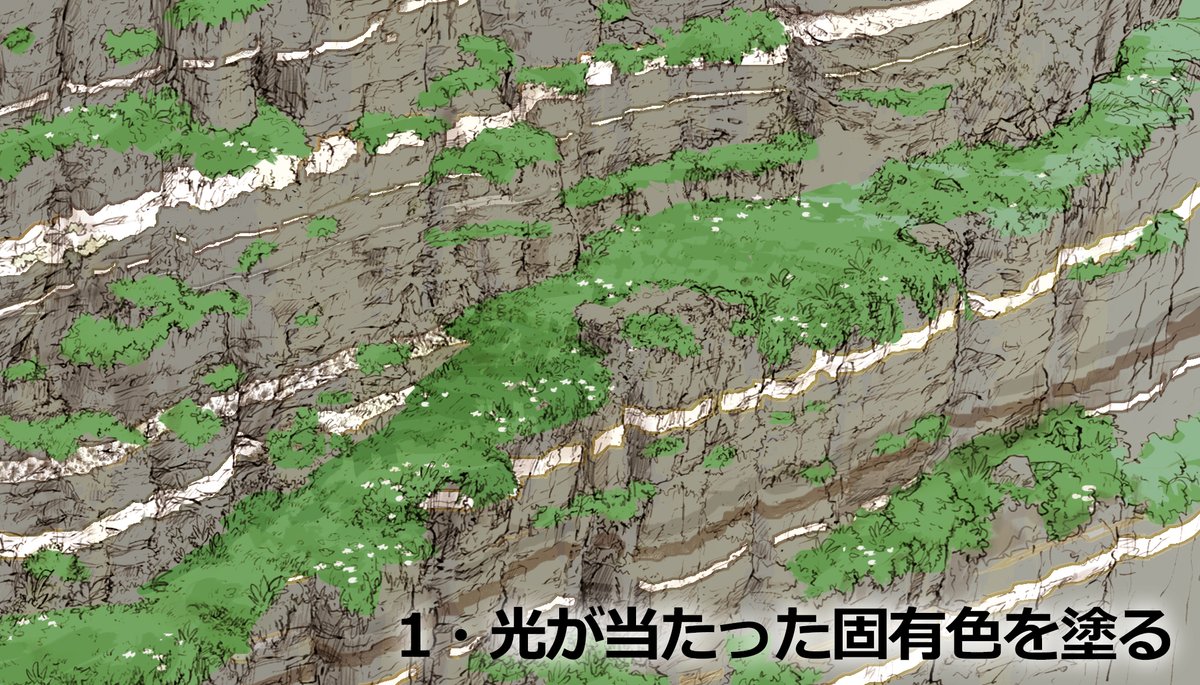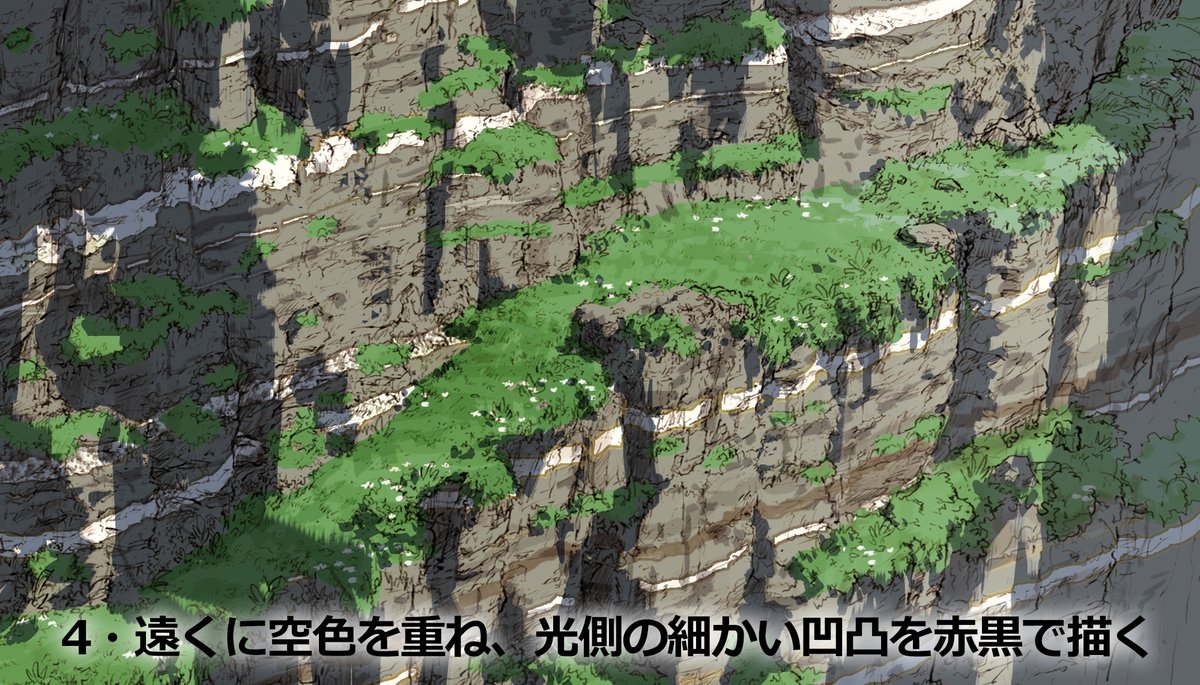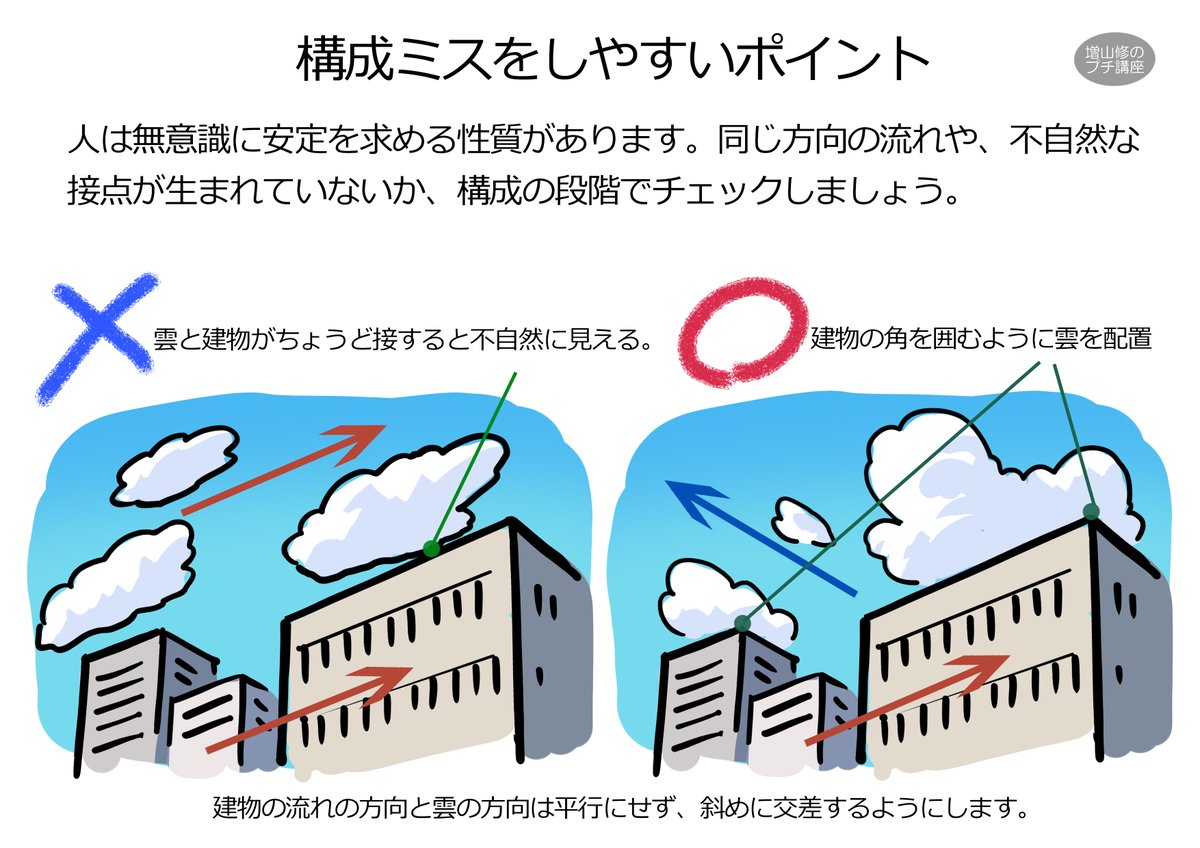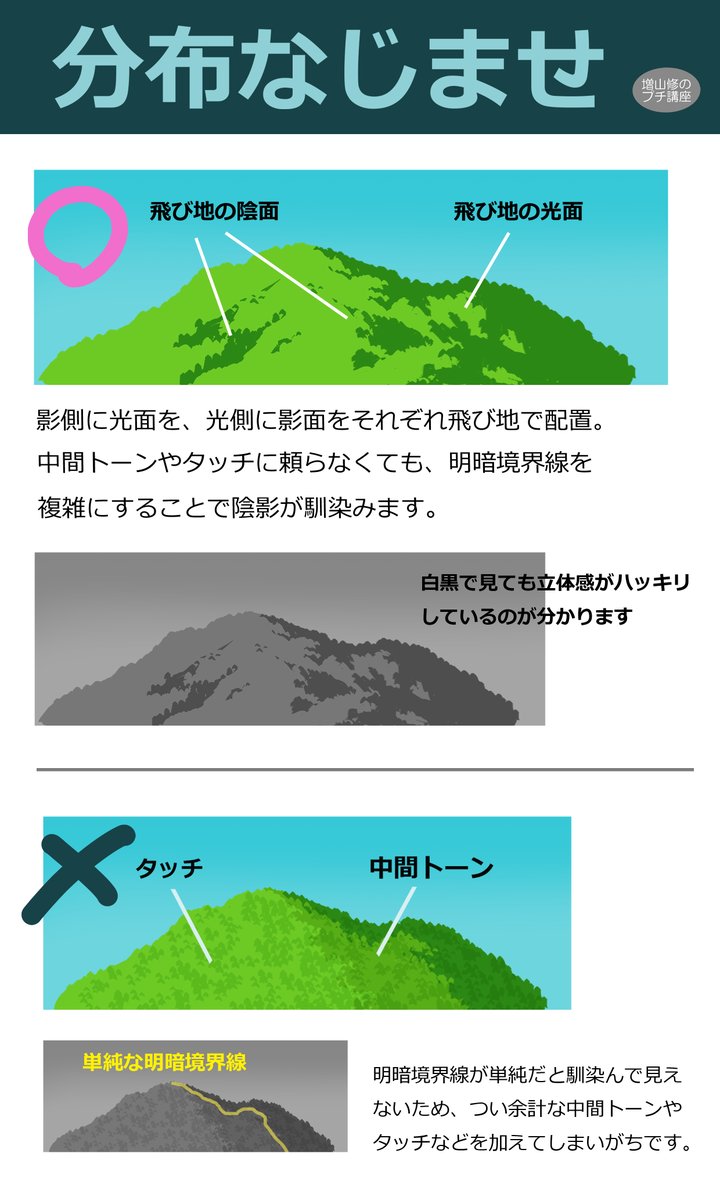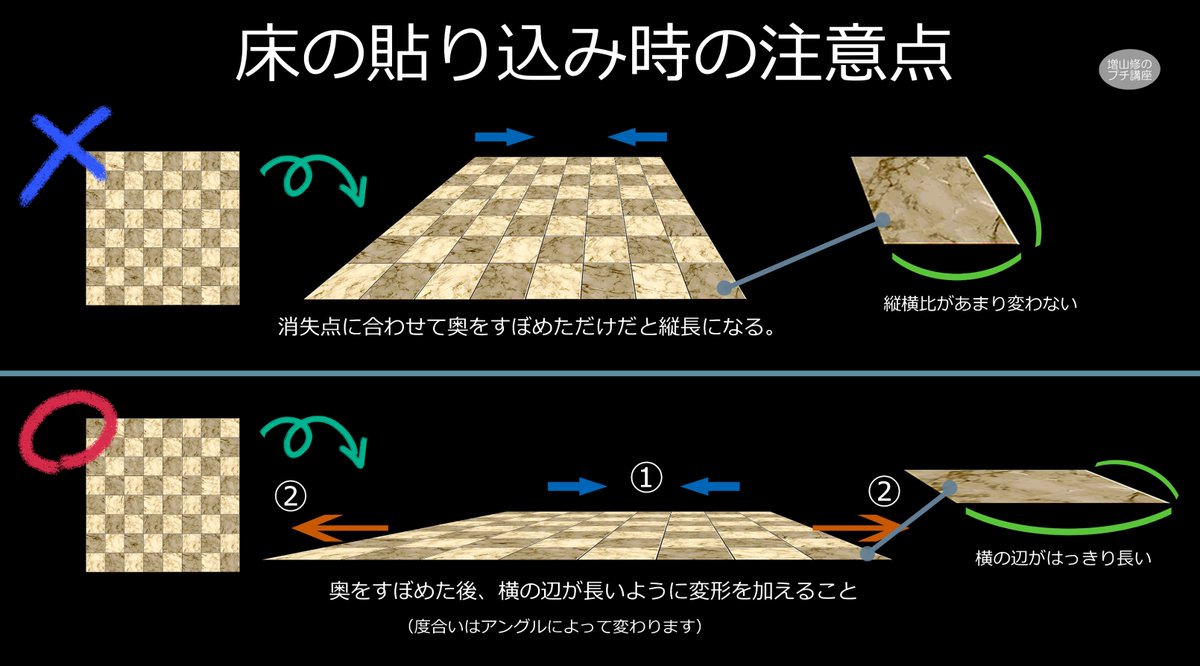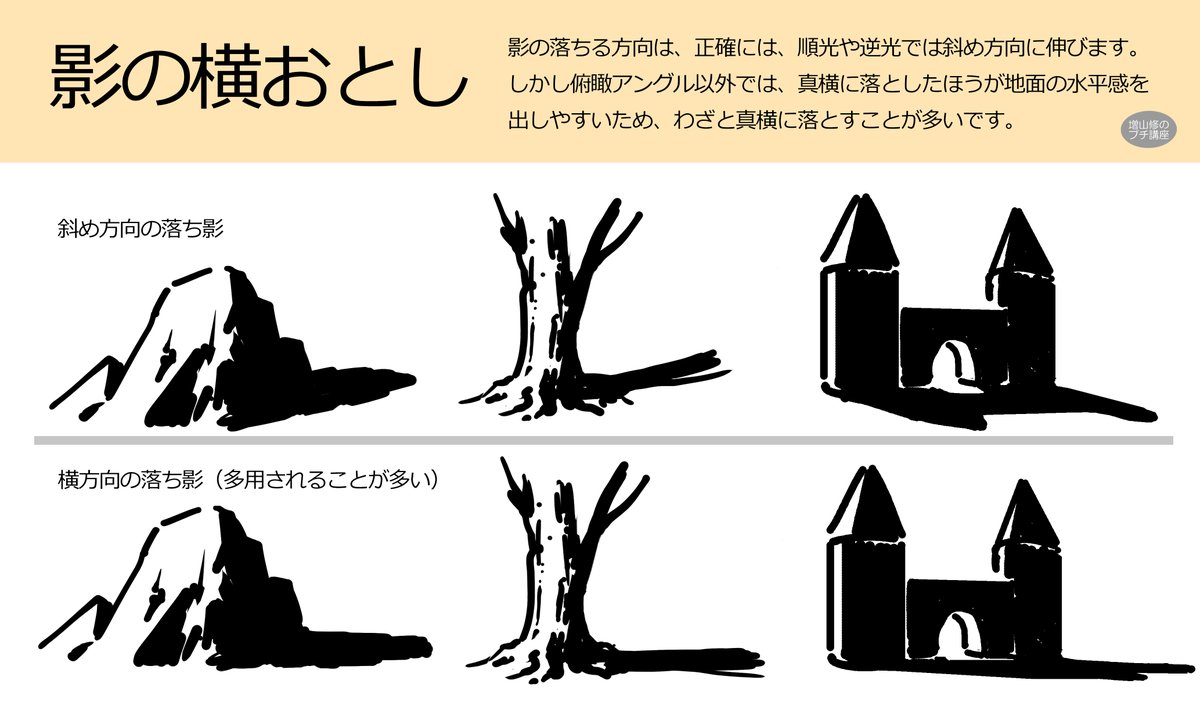152
154
絵具によるイメージボード
〈再掲〉#背景美術
156
157
夜の石畳。手前の影の境目はボケ幅が大きいですが、遠くの境目はハッキリしています。
このように、ボケ幅の差で距離感を付けるテクニックはよく使われます。
【Background Art staff's work】
#背景美術 #盾の勇者の成り上がり
159
161
170
173
175