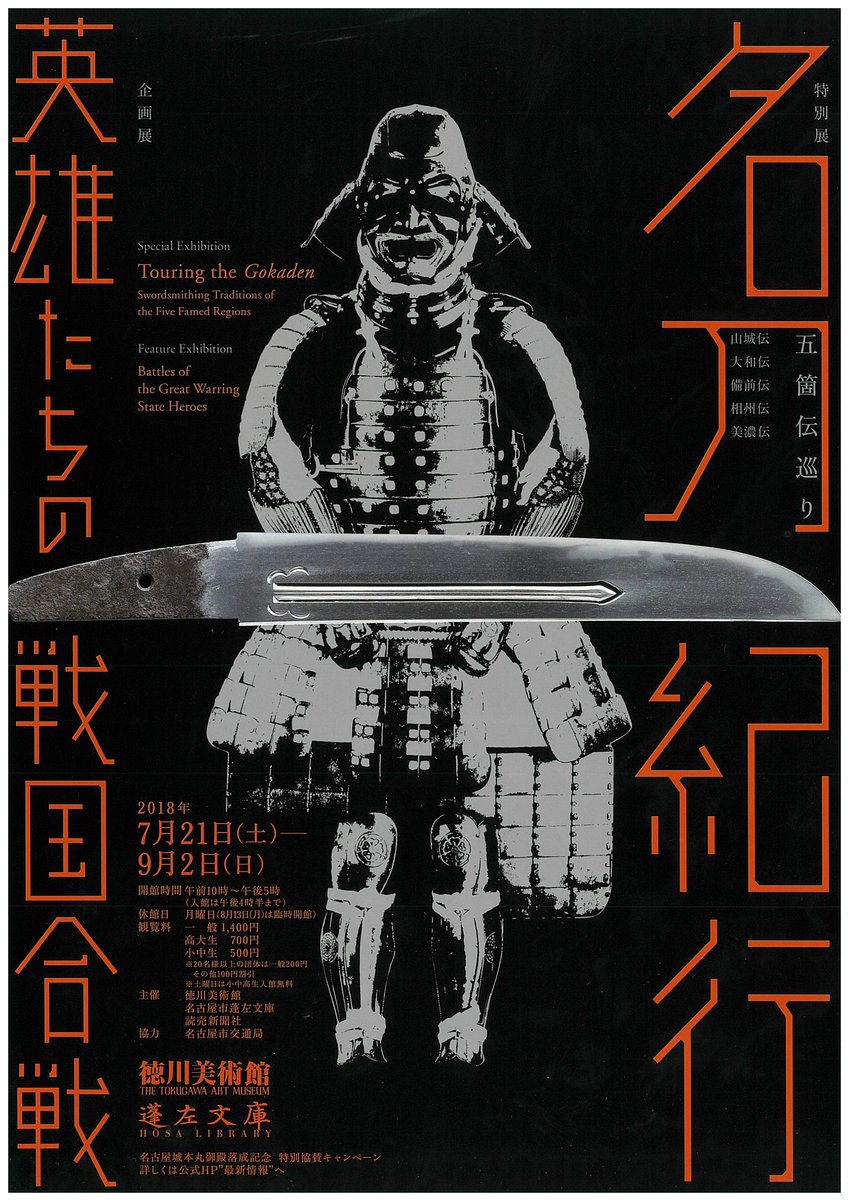27
ボンボニエールは皇室や宮家が、宮中の晩餐会やお祝い事などの際に配る小さな砂糖菓子の入れ物です。その多くは銀で作られていて、さまざまな意匠が凝らされています。鶴亀、本、鳥かご、茶の湯の釜などなど、本当にいろいろなデザインがあって見飽きることがありません。#担当のおすすめ
28
伊達政宗が愛娘の牟宇姫(宛名には「おむう」とあります!)に宛てたお手紙です(個人蔵)。おむうちゃんが贈ったアワビや煙草のお礼を伝えるとともに、元気な様子で安心したよと書いています。パパですね~ #担当のおすすめ
29
明治天皇に献上された刀剣です。平安時代に作られて、平氏政権を打倒するべく戦った武将・源頼政が高倉天皇から賜ったと伝えられています。源頼政は「ぬえ」という怪物を退治した武将として有名ですよね~。由来はわかりませんが、獅子王という号がつけられています。#担当のおすすめ
30
戦で武将の所在を示すために立てる「馬標(うまじるし)」。普段は名品コレクション第1展示室に展示されていますが、実はこんな専用の木箱に収納されているんです!単なる容れ物の役割を超えた存在感。その迫力をぜひその目で確かめてください!
#担当のおすすめ #お宝のうらなかそこ
31
見てください、この則重の地鉄(じがね)!見ていると吸い込まれそうな独特の渦巻模様。荒々しさと華やかさの競演です。
名品コレクション展示室で展示中。#担当のおすすめ
32
33
細川忠興の書状です。忠興は、尾張家初代義直が、秘蔵の茶碗「三島桶」を忠興に見せたいと話していた事を伝え聞き、天下無双の名品をなるべく早く拝見したい!という気持ちを義直に伝えるため、あちこちへ取成しを頼んだようです。忠興をなりふり構わず慌てさせた三島桶も展示中!#担当のおすすめ
34
名古屋市民にファンが多い尾張徳川家7代宗春は、派手好みのお殿様だったと言われています。こちらは宗春の火事装束です。大名は火事場でも目立つようファッショナブルな火事装束を着用していたのですが、宗春の装束は際だっています!本日は今年の開館最終日です。ぜひご来館下さい!#担当のおすすめ
35
こちらの鹿革の足袋は、足の裏が汚れていることから、徳川家康が実際に履いたと考えられます。革は少し縮んでいますが、家康の足のサイズが23センチ程であったことがわかる大変貴重な品!内側には職人の名前が記されています。
#担当のおすすめ #お宝のうらなかそこ
36
宝石箱??いえいえ実は、お菓子専用の鍵付きのタンスなんです。引き出しに、たぶん金平糖とか落雁などの砂糖菓子を入れておいて、「ちょっと人が来た」なんて時に一緒に食べたり差し上げたりして楽しんでいたんでしょうね。陶器をはめ込んだデザインもステキ!展示は12月13日まで!#担当のおすすめ
37
39
40
重要文化財「名物 南泉一文字」は、備前国の刀工集団「一文字派」による一振です。一文字派は多種多様な丁子乱(ちょうじみだ)れの華やかな刃文が特徴です。本刀は大ぶりな丁子乱れの豪華絢爛な刃文であり、鎌倉時代中期の一文字の作品の中でも優品として知られています。#担当のおすすめ
41
刀剣ファンのみなさま、お待たせいたしました!特集展示「刀身彫刻の世界」開催中です(~2/6)。かつて武士は自らの武功や護身の祈りを込めて、刀身に彫刻を施しました。不動明王に関する品が多いのも、にらみをきかせて邪悪なものから人々を守り導く力強い仏さまだからなんですね~!#担当のおすすめ
42
43
徳美アルアル!第1展示室では刀剣をご紹介していますが、刃文が見にくいとよくご指摘があります。
…そうなんです。実は、現代では刃文が美しく見えるような研ぎ方が主流ですが、当館では江戸時代の重厚な研ぎの姿を保存しつつお手入れしてるのです。刃文の見えにくさにも歴史あり!#担当のおすすめ
44
「婚」のイチ押しは?
担:国宝の「葵紋散蒔絵糸巻太刀拵」です。拵(こしらえ)とは刀剣の外装のこと。3代将軍家光の長女、千代姫のお嫁入り道具「初音の調度」に含まれています。
新:刀身の「太刀 銘 国行」(国宝)は名品コレクション展示室に展示中!
#担当のおすすめ #大名の冠・婚・葬・祭
45
「折紙(おりがみ)」といっても小学生の頃に遊んだ、あのカラフルな紙ではありません。
「正真正銘の庖丁正宗ですよ~」と証明する、二つ折りにしてある鑑定書のことを折紙と言います。今でも「折紙付き」という言葉が残っていますね。
#担当のおすすめ
46
江戸時代の離縁状、いわゆる「三行半(みくだりはん)」です。
江戸時代には意外にも熟談離婚が多かったそうで、再婚に差し障りがないことを証明する意味を持っていました。
#読み解き近世の書状 #担当のおすすめ
47
刈谷市歴史博物館企画展「徳川家康の遺産~徳川美術館所蔵品で綴る~」の展示作品をすこ~しご紹介します。
家康が着た辻ケ花(つじがはな)の着物、遺産として家康から義直に譲られた花生などなどを展示します。それに、物吉貞宗も刈谷に出張しますよ~。 #担当のおすすめ city.kariya.lg.jp/rekihaku/tenji…
48
彼の名前は鍾馗(しょうき)です。中国では病魔を退ける神様として信仰されました。日本でも魔よけの効果があるとされ、ひと昔前の中国・日本の端午の節供では、最もポピュラーなキャラクターでした。現代にもこの力が発揮されてほしいですね~!
#担当のおすすめ
49
三代将軍家光から祖父・徳川家康に対するお見舞い状です。手紙の書き方は現代と同じで、本文・日付・差出人・宛名がそろっていますね。
書状の読み解きは難しく感じるかもしれませんが、手紙に込められた人々の思いは今も昔も変わりません。
#読み解き近世の書状 #担当のおすすめ
50
加藤清正が着用した、烏帽子をかたどった兜です。なんと材質は紙!?…とはいえ防具としての役割はちゃんと果たせるよう、紙でできた張り子の烏帽子の内側には鉄製の鉢が入っています。清正自筆の「南無妙法蓮華経」と書いた数百枚の紙を貼り合わせて作ったと伝えられています。#担当のおすすめ