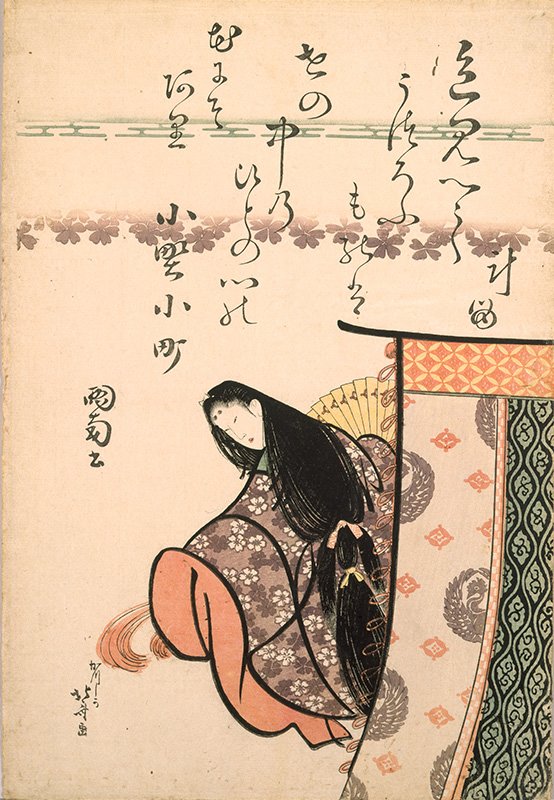51
52
日米修好通商条約の締結問題に巻き込まれ失脚した慶勝。謹慎した屋敷でふさぎ込んでしまうのか…。そんな苦境のなか慶勝がこつこつと作ったのがこちら、昆虫と植物の標本です。一つ一つ丁寧に貼られ、採られた場所も書いてあります。慶勝のマメで、根気のある性格が伝わってきます。#担当のおすすめ
53
幕末に活躍した慶勝と三人の弟、茂栄・容保・定敬。合わせて「高須四兄弟」の四人揃った唯一の写真です。右から慶勝(55歳)、茂栄(48歳)、容保(44歳)、定敬(33歳)です。みんな、実際の年齢よりもだいぶ年上に見えます。きっとそれだけこの時代を生き抜くのは大変だったんですね。#担当のおすすめ
54
1室では1/29まで、「火事装束」の特集展示をしています。火事装束は、大名が防火現場でも目立つよう華美をこらした装束です。こちらは、今も名古屋で根強い人気の尾張家7代宗春の火事装束です。派手好みの宗春らしく、色もデザインも際だっています!#担当のおすすめ
55
印籠と言えば、水戸黄門の葵紋の印籠のイメージが強いですが、大名家には家紋ばかりではなく、様々なデザインの印籠が伝わりました。
5室では1/29まで「印籠」の特集展示をしています。こちらは象牙製の印籠で、中央の牡丹や鳥には青貝や珊瑚をはめ、華やかに彩られています。#担当のおすすめ
56
天正20年(1592)の聚楽第行幸の際に、秀吉の詠んだ和歌が書かれた短冊です。署名には秀吉とありますが、実は、五奉行の一人、前田玄以が代わりに書いたと伝わる短冊です。どうして秀吉が詠んだ歌を書いたのか、どんなやり取りがあったのでしょうね?企画展「書は語る」は本日まで!#担当のおすすめ
57
近衛家から尾張家11代斉温(なりはる)に嫁いだ福君(さちぎみ)さまが持参したお雛さまです。男雛や随身の装束には、斉温の兄にあたる12代将軍家慶(いえよし)ゆかりの裂が使用されています。人形の顔もそれぞれで違った表情をみせており、特別なお雛さまであったとわかります。#担当のおすすめ
58
合戦は物語の中にも。京の姫君をさらって喰らう酒呑童子を、源頼光が討伐する「大江山絵詞」(逸翁美術館蔵、~8/18)にも、勇壮な武士たちの姿が描かれています。酒呑童子を押さえつけ、刀を振るう武士たちの動きはリアリティーがあり、いかにも力がこもっていそう!#担当のおすすめ
59
細川忠興の書状です。忠興は、尾張家初代義直が、秘蔵の茶碗「三島桶」を忠興に見せたいと話していた事を伝え聞き、天下無双の名品をなるべく早く拝見したい!という気持ちを義直に伝えるため、あちこちへ取成しを頼んだようです。忠興をなりふり構わず慌てさせた三島桶も展示中!#担当のおすすめ
60
写真だけでは本物の調度品かと思ってしまう、精巧なつくりの雛道具。こちらは33枚の櫛を収納する「払箱」(はらいばこ)という化粧道具のミニチュアで、高さ6cmほど。実は、お姫様が使った同じデザインの実物も揃って伝来しています。今年は展示室で2つを見比べることができますよ!#担当のおすすめ
61
この扇は「白鳩・龍図軍扇」といい、表は彩色の白い鳩、裏には水墨の龍が描かれています。展示室では表の白い鳩が見えるようになっていましたが、ここでは裏もお見せします!#担当のおすすめ
62
大胆なデザインの能装束ですね。紅色をベースに、様々な色糸で九曜星を入れた菱繋(ひしつな)ぎ文、さらに大きく全体に散らされた菊花文。ほの暗い舞台上にあっても大きな菊文様はさぞ鮮やかに映えたのでしょう。#担当のおすすめ
63
彼の名前は鍾馗(しょうき)です。中国では病魔を退ける神様として信仰されました。日本でも魔よけの効果があるとされ、ひと昔前の中国・日本の端午の節供では、最もポピュラーなキャラクターでした。現代にもこの力が発揮されてほしいですね~!
#担当のおすすめ
64
休館中ですが、せめて写真を通して、みなさんに徳川美術館の刀剣を愛でてほしい。そんな気持ちを込めて、今週ご覧いただけるはずだった刀剣たちをご紹介してまいります!
それでは・・・「とくび刀剣week」開始!
#とくび刀剣week #担当のおすすめ #刀剣
65
66
67
68
69
70
71
茶入には、見立ての形で名前が付けられます。
林檎(りんご)の形に見立てた茶入には「文琳(ぶんりん)」。
茄子に見立てた茶入には「茄子」。
そして、これはそのちょうど中間のタイプですので、1文字ずつ取って、「文茄(ぶんな)」!
#担当のおすすめ
72
写真ではわかりづらいかもしれませんが、兜や胴をよ~く見ると、実はところどころ凹んでいます。
凹みは火縄銃で試し撃ちをしてできた弾痕です。
これがあることが、具足の強度の保証だったので、あえて残したまま納品しました。決して不良品ではないですよ。
#担当のおすすめ
73
「白熊毛采配」の棒の先につけられている毛は、想像上の獣である白熊(はぐま)の毛と考えられていました。想像上の獣の毛をどうやって手に入れたのでしょう?本当はチベット・北インドなどにいる牛の一種「ヤク」の毛なんです…!
#担当のおすすめ
74
5 副葬品
2代光友(みつとも)の棺の中には遺愛品の刀剣などの副葬品も納められていました。光友への家族の思いや祈りのこころを感じます。
それからもう1つ!実はお墓の中は大量の朱で固められていたとか…。一瞬ぎょっとしますが、朱は防腐剤として使われていたんですって!
#担当のおすすめ
75
水色の生地に金色の柳のながれが映える、涼しげな狩衣(かりぎぬ)です。背景には、雷文(らいもん)繋ぎという幾何学模様がちりばめられていて、全体を引き締めます。ツバメの尾は上に下に、お互いに顔を向けあって楽しそうですね。
#担当のおすすめ