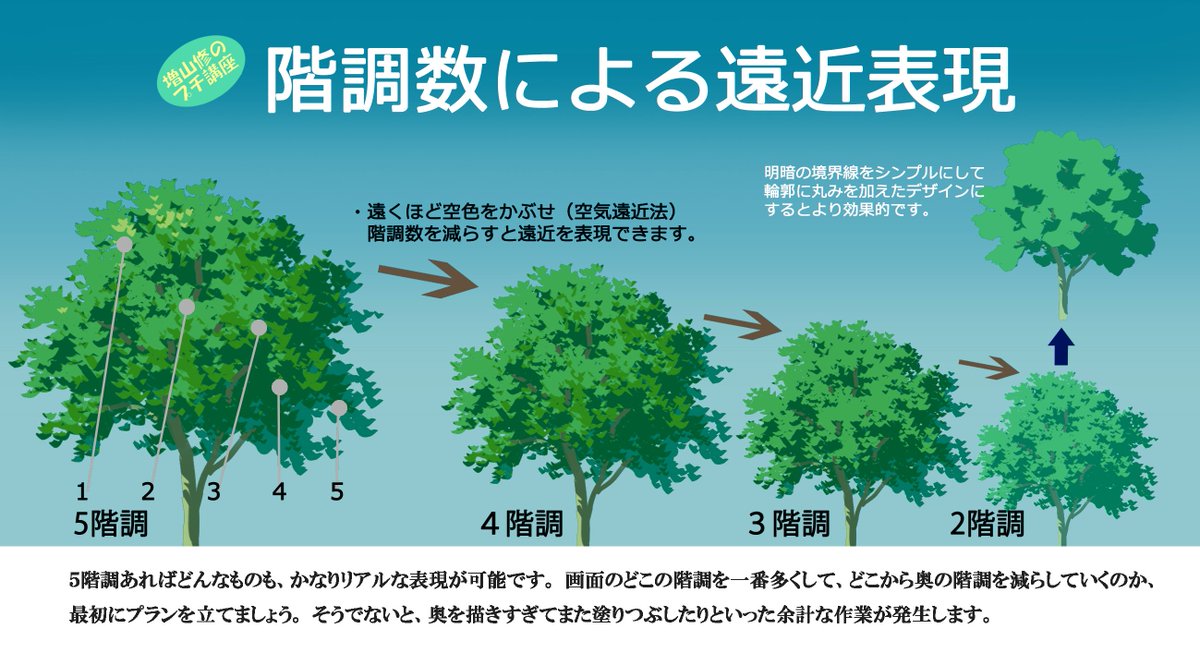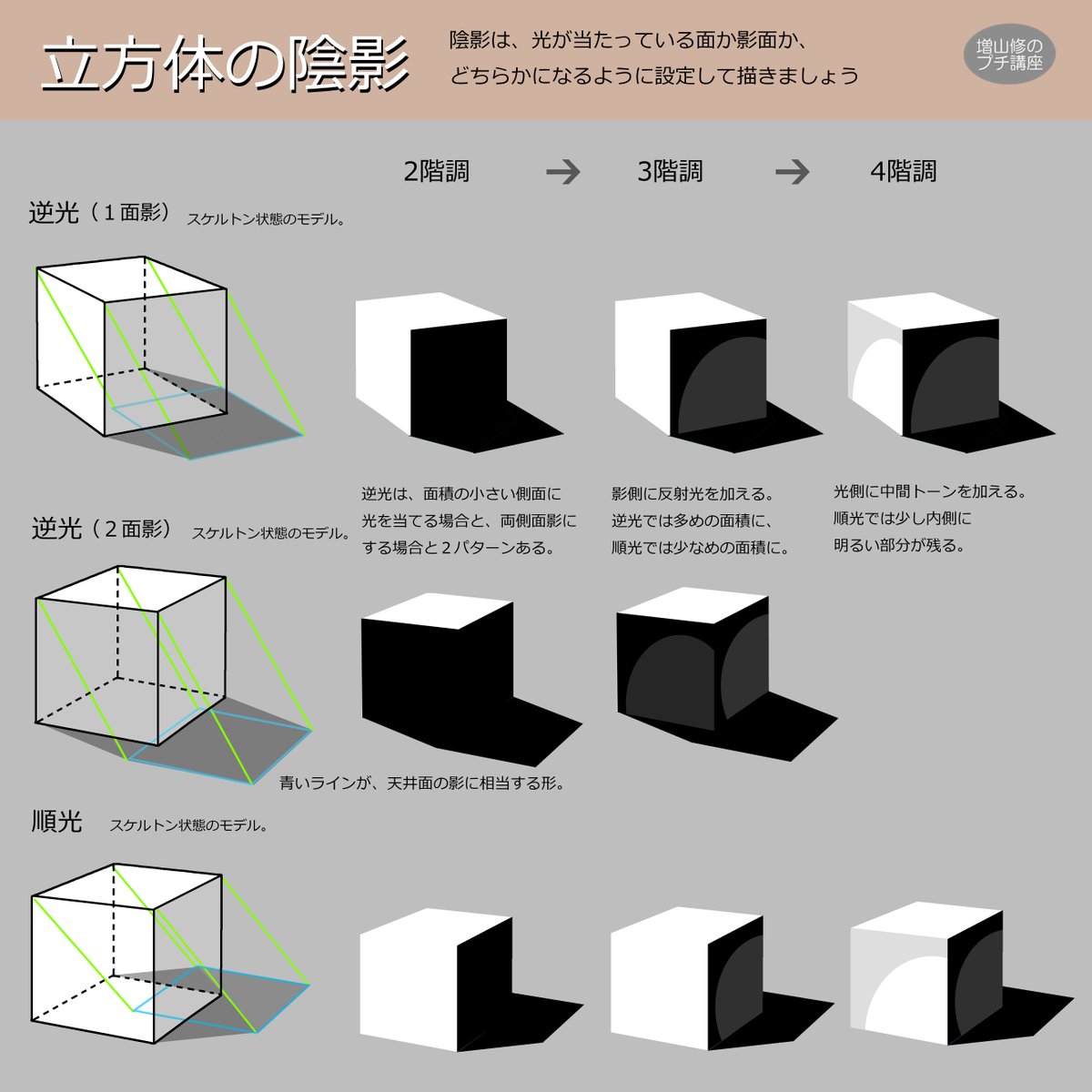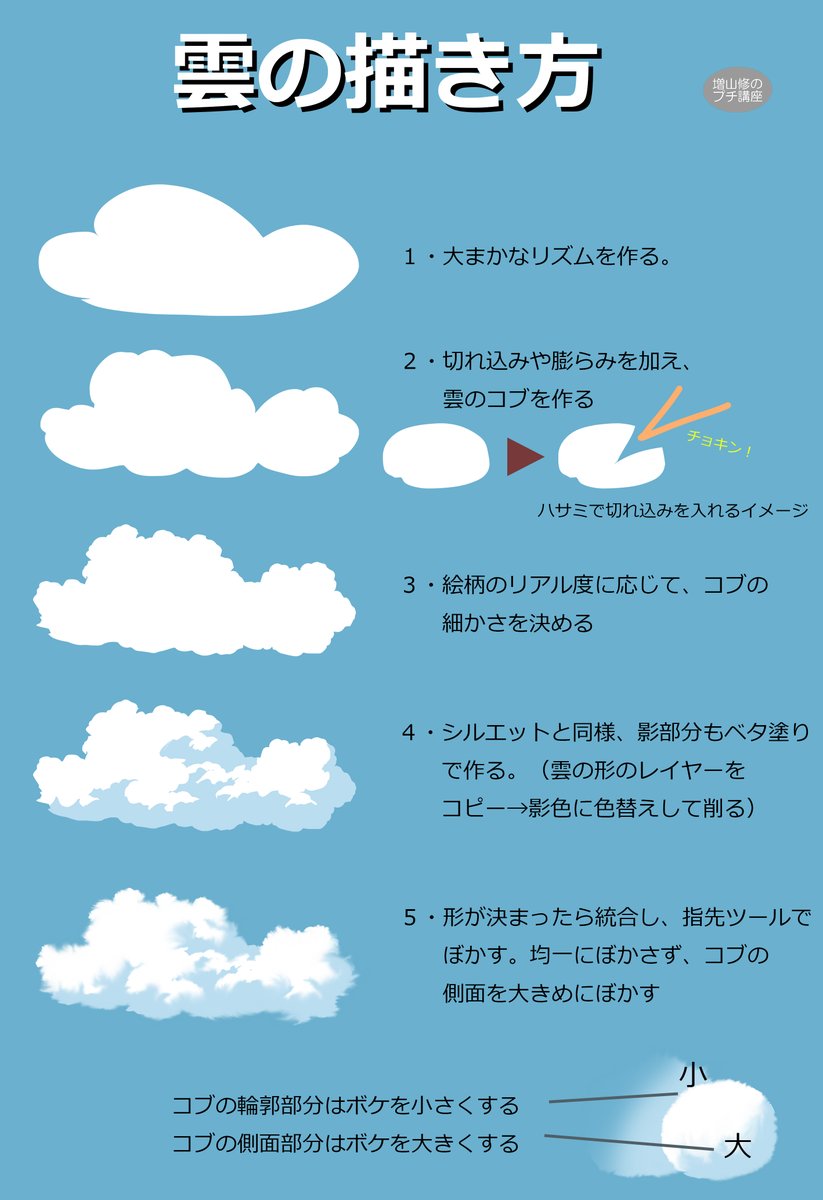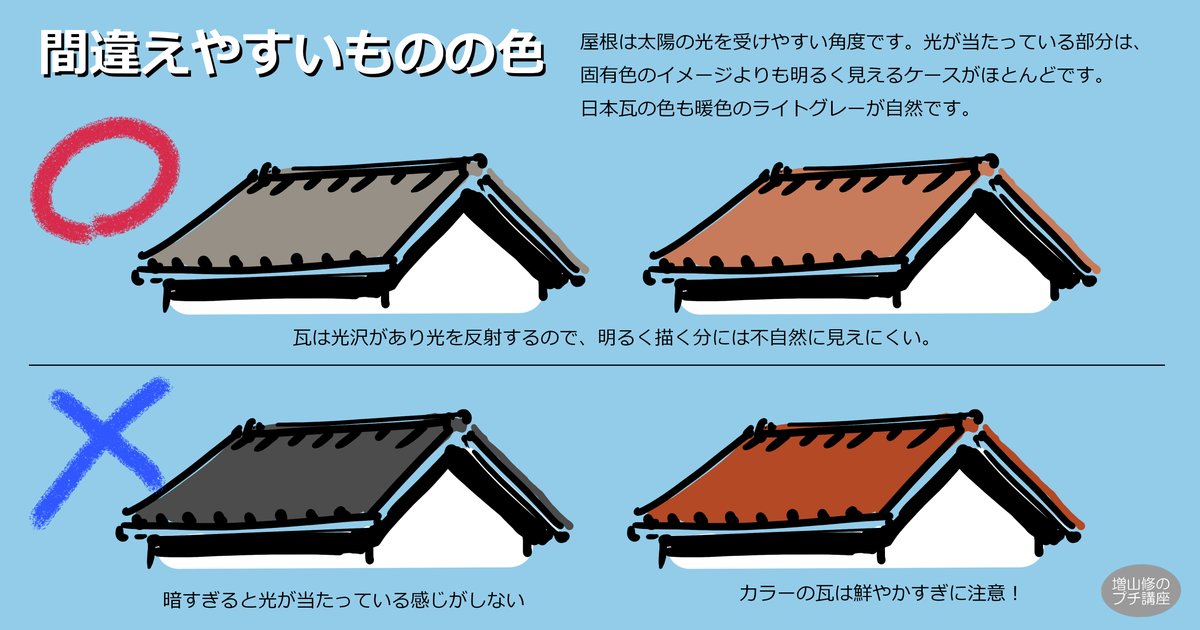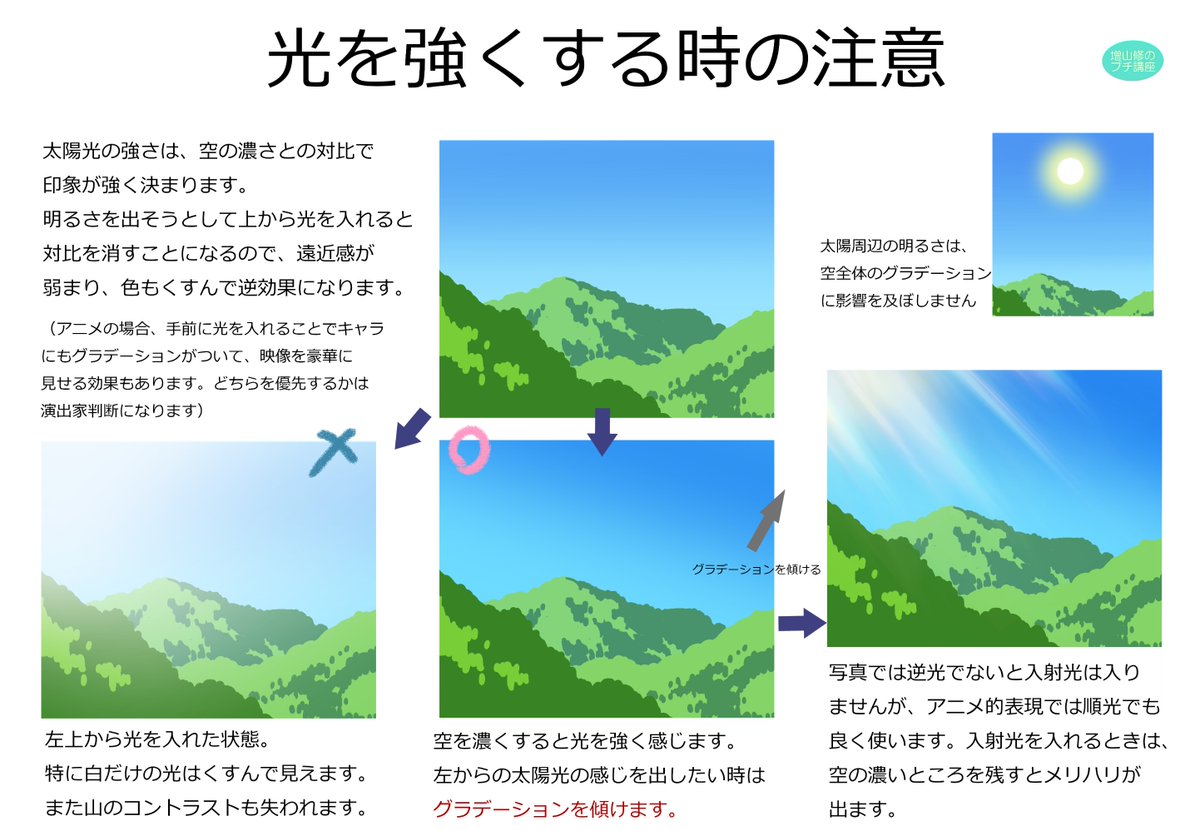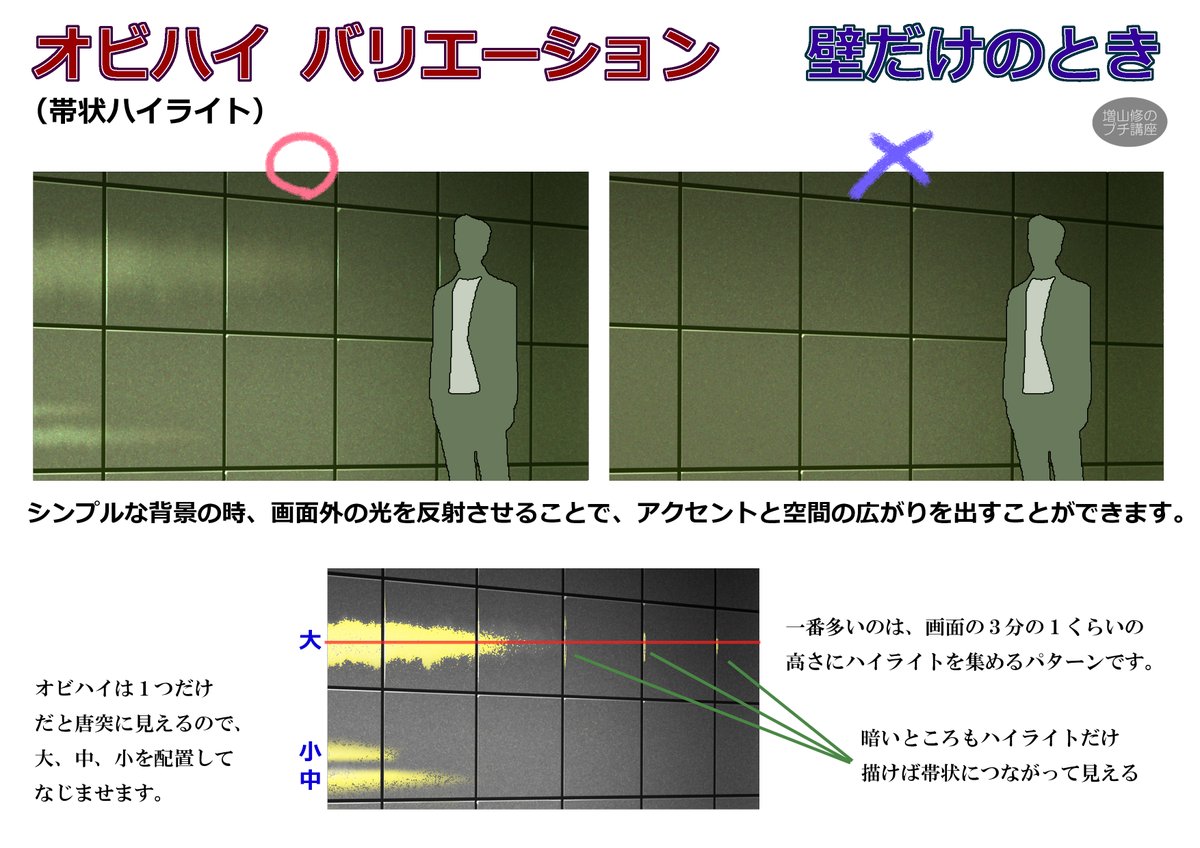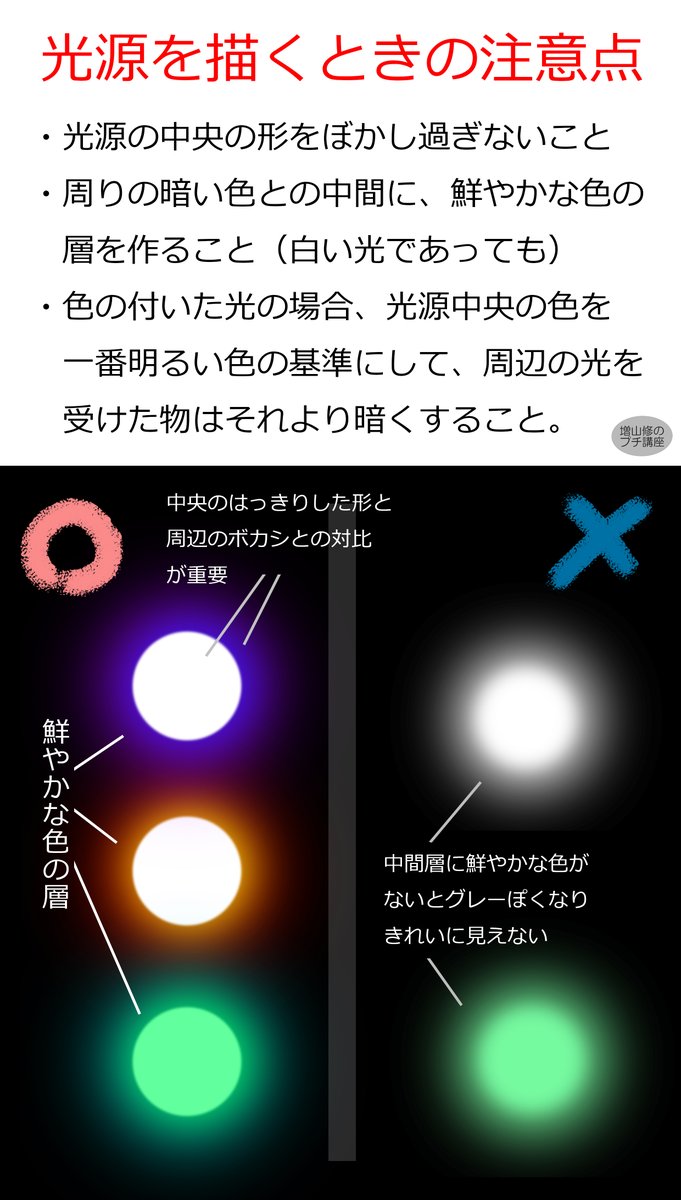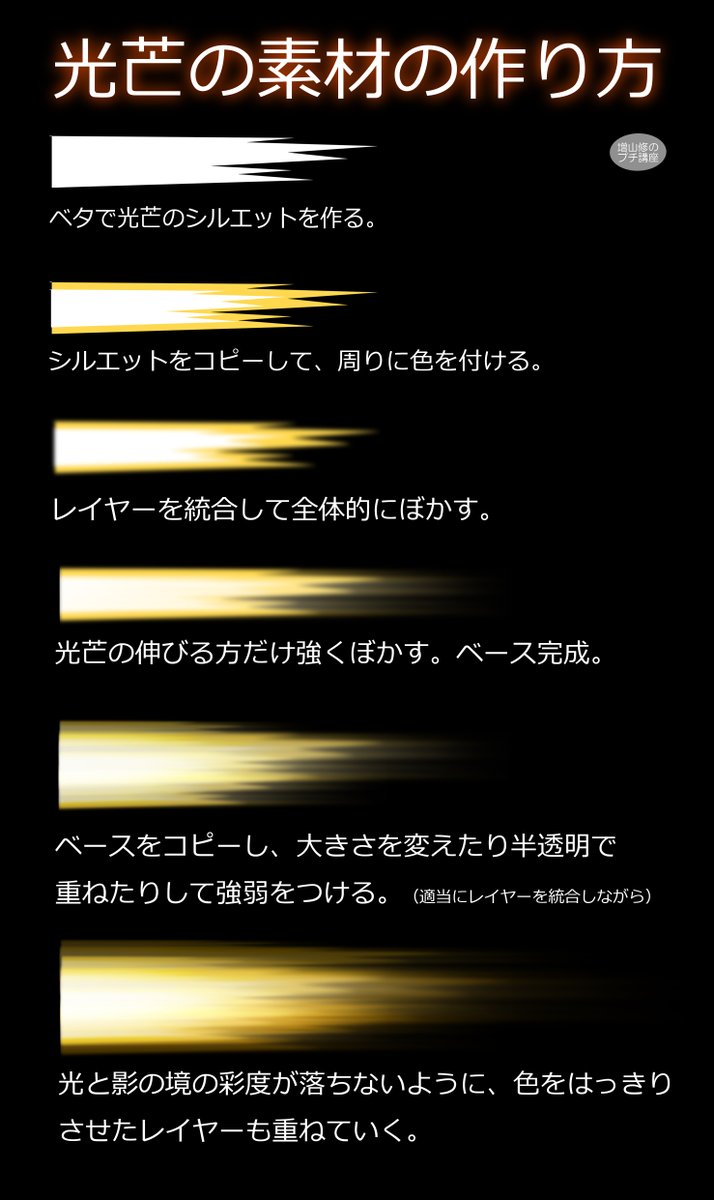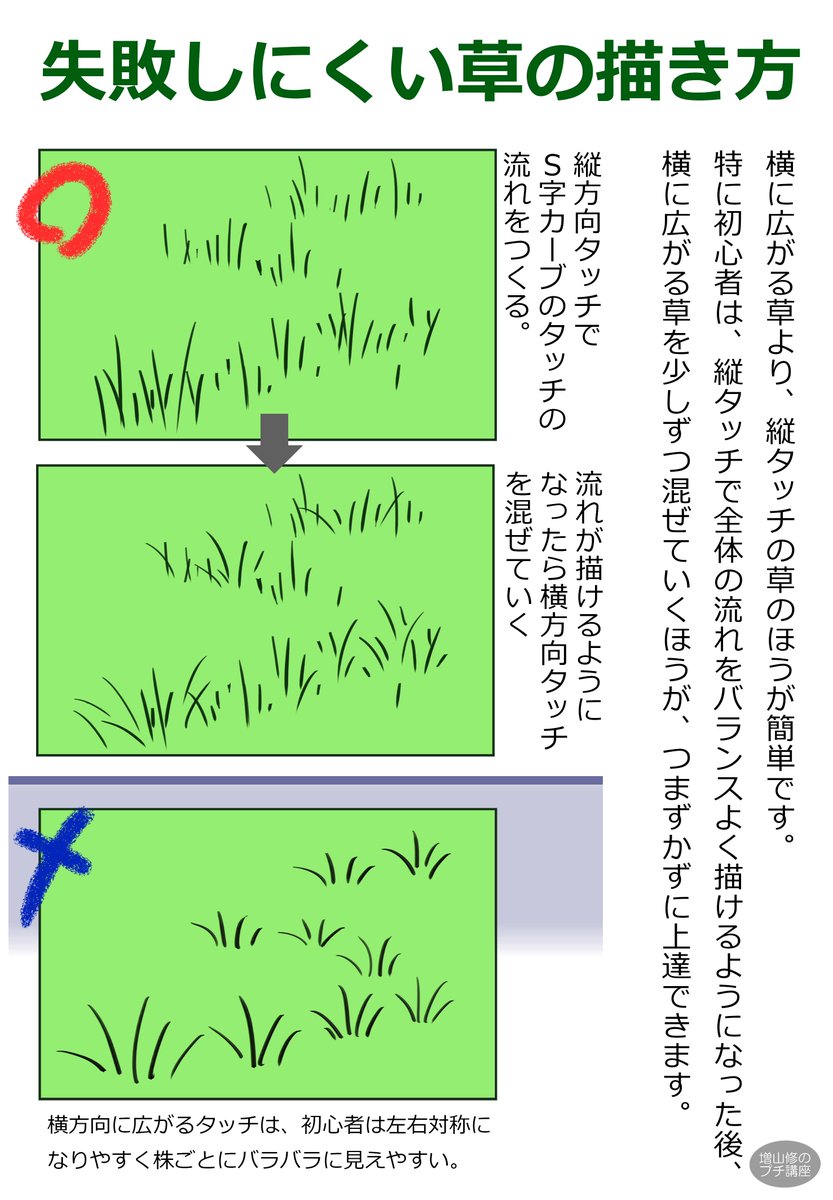202
205
河岸を描くときの注意点
#背景美術
206
アイテムは、光と影をまたぐように配置しましょう
#背景美術
207
石畳やレンガや瓦など、小さいパーツが集まっている面の情報量を上げたい時、無理やり「汚れ」を描き足してしまいがちです。
しかしそれより先に、ベース色と固有色の違うパーツを4分の1程度配置してみましょう。簡単に情報量を上げられます。
#背景美術 許可済
208
立体感を出すには部分的な処理に頼らず、色面同士の大きな対比をつくることが大事です。
#背景美術
210
雲を描く時、いきなりブラシで描かずに、シルエットや配置を吟味してからぼかすと、失敗が少なくなります。
#背景美術
213
塗りによる表現を行う時、この基本パターンの組み合わせであることがほとんどです。
#背景美術
214
水面を描く方法で、建物の窓を描く方法
#背景美術
215
逆光における単体の草は、光が透過して明るめに見えます。
#背景美術 許可済
218
色価の基本理解
#背景美術
221
絵具によるイメージボード
#背景美術 #backgroundart
222
浅い水の場合、特に俯瞰においては、水底が見えやすくなります。
#背景美術【Background Art staff's work:Made in Abyss】(許可済)
224
【失敗しにくい草の描き方】
草の細部も全体も一気に描けるようになろうとすると大変です。まずは全体的なバランスをとることに集中して、その後に細部の問題に取り組むほうが挫折せずに上達できます。
#backgroundart
#背景美術
#howtodraw
#描き方
225
【輪郭線を描く前に必要なこと~設定~】
植物は時間の流れを表現しやすいアイテムです。
ツタ植物はパース線代わりに使え、奥行きも表現しやすくなります。また作例のように物にまとわりつく場合、CGのワイヤーフレーム代わりになり立体感も補えます。
#描き方 #背景美術 #backgroundart