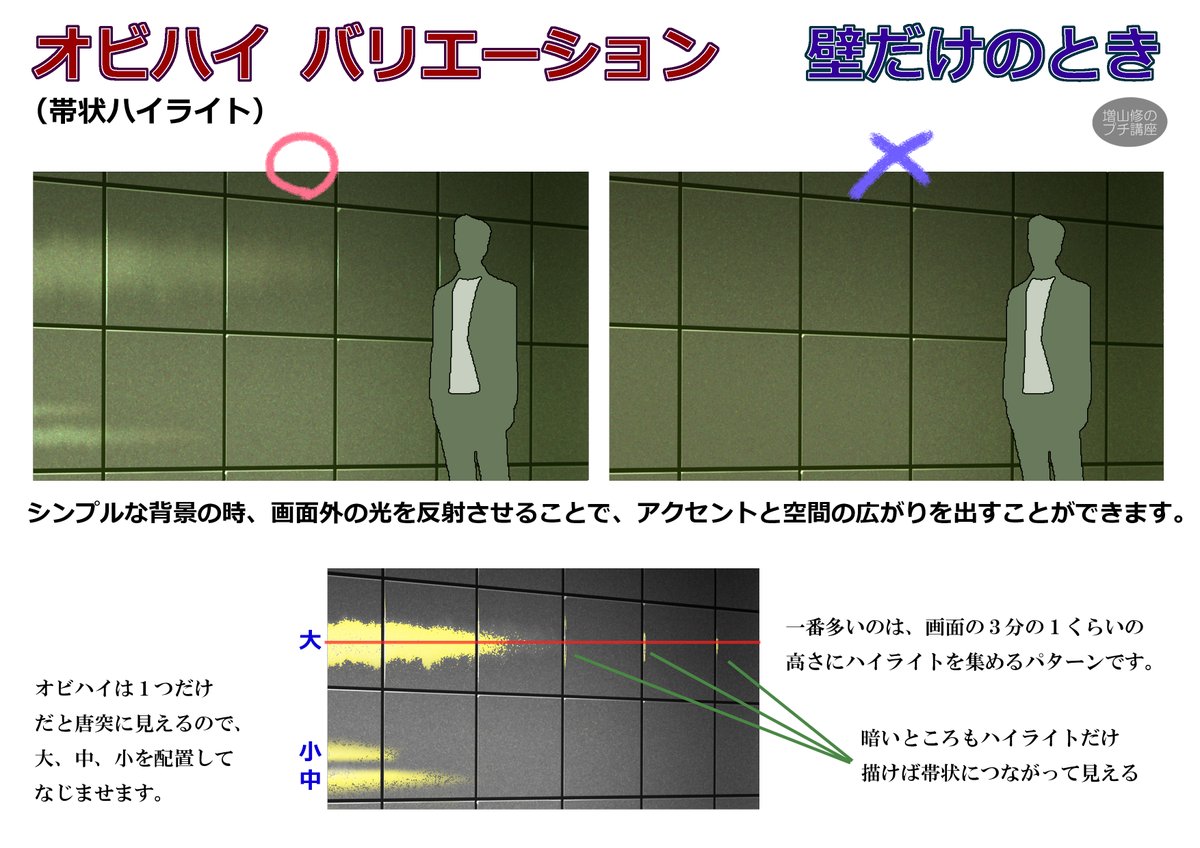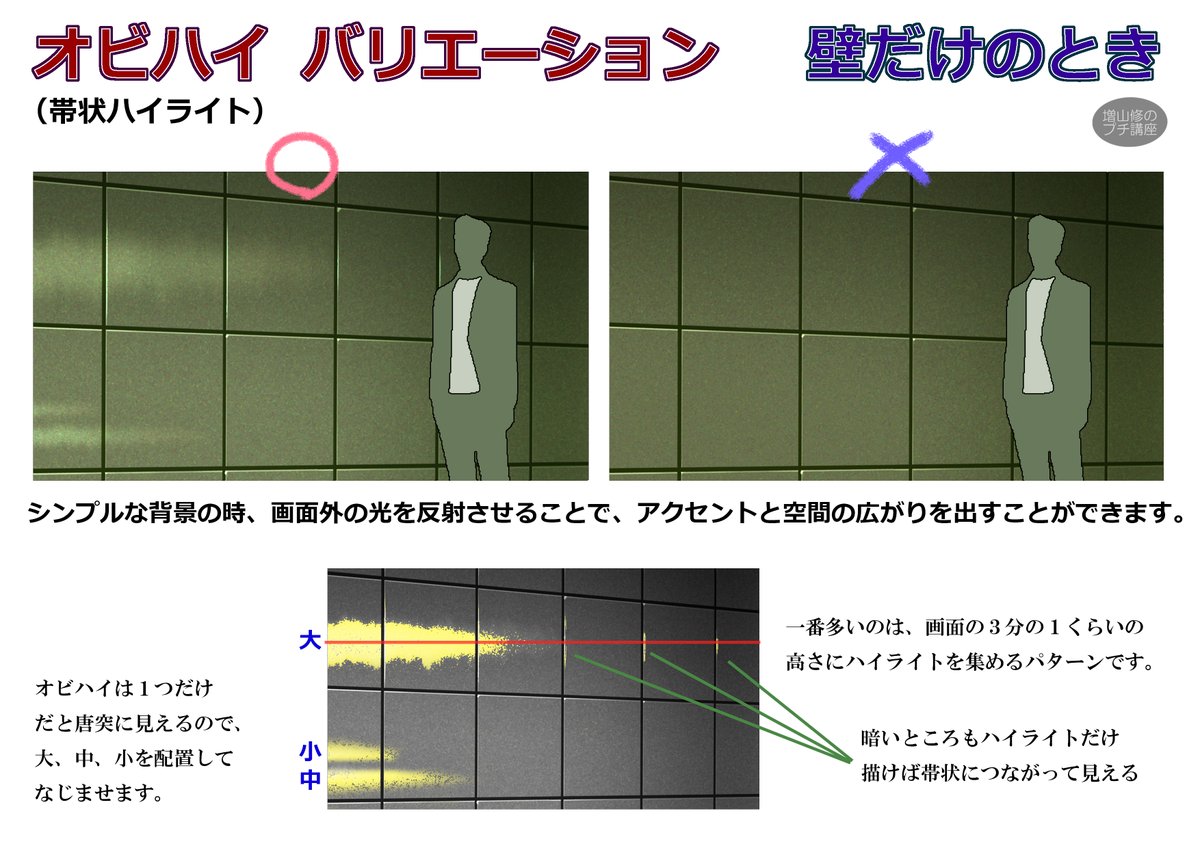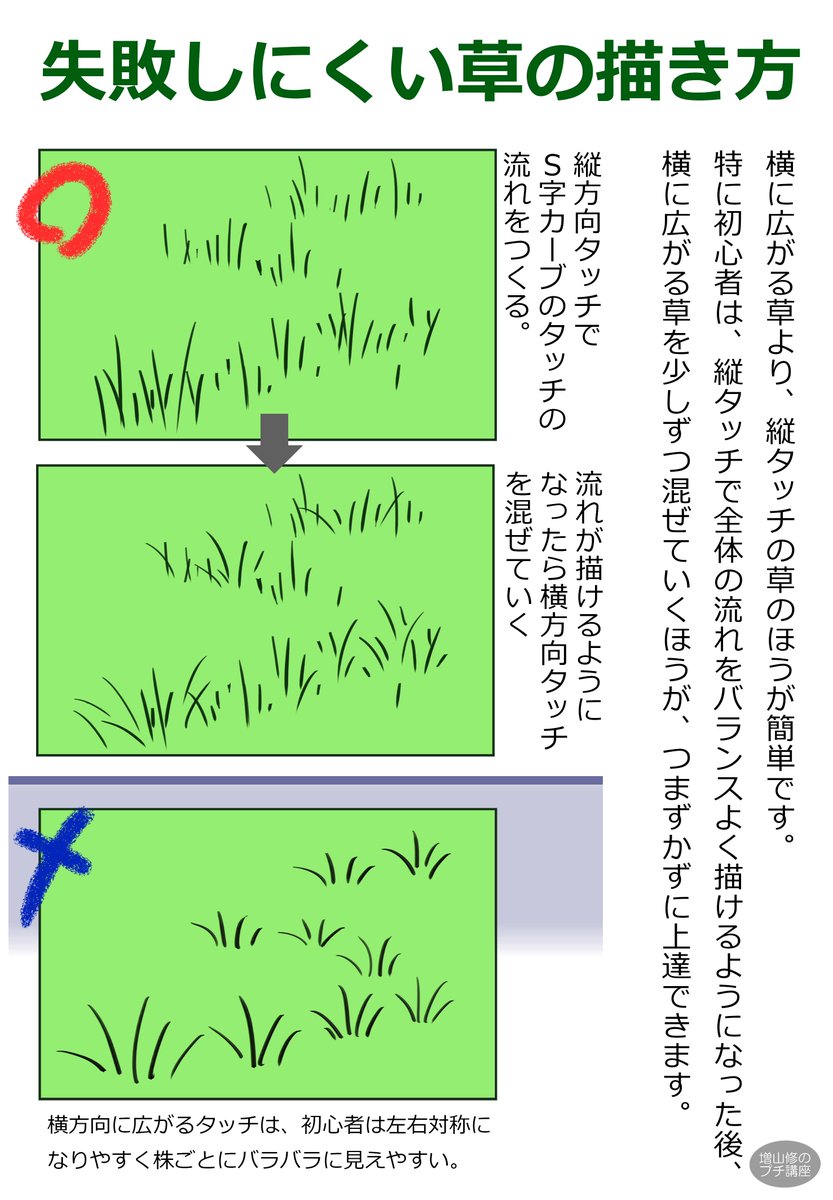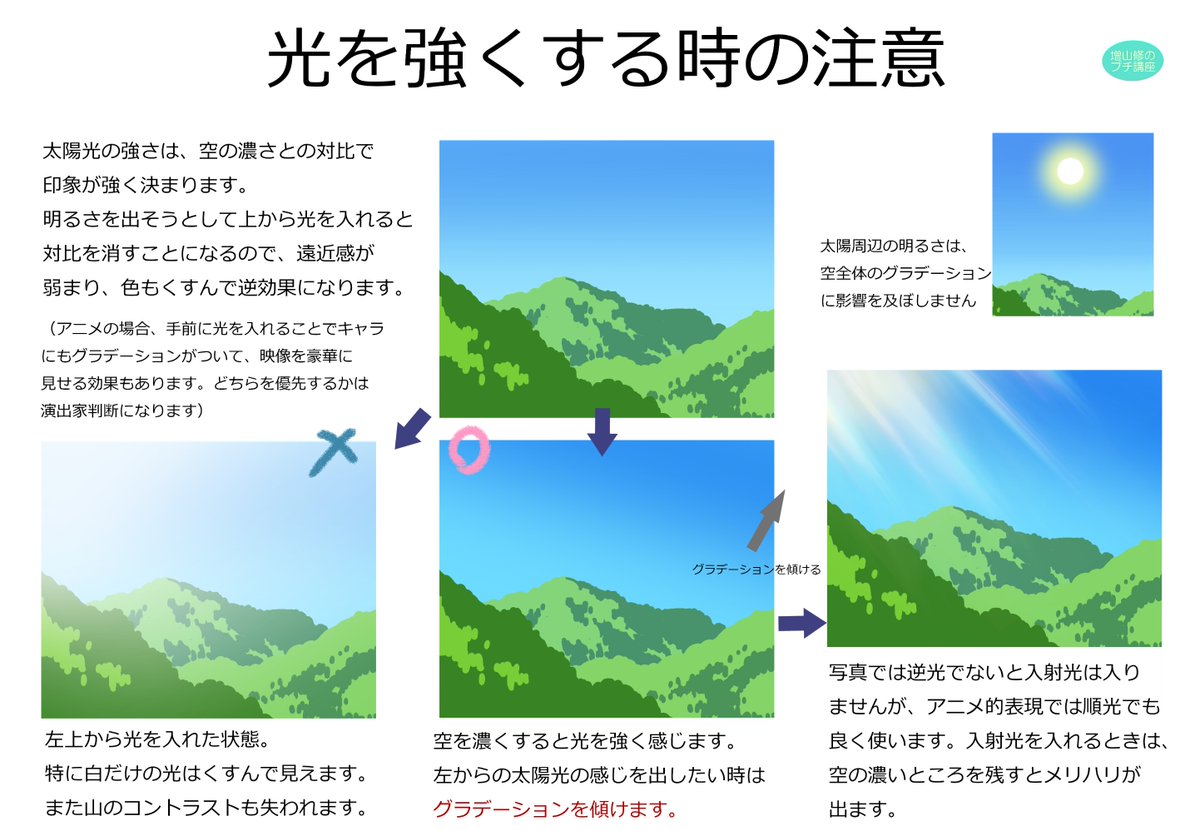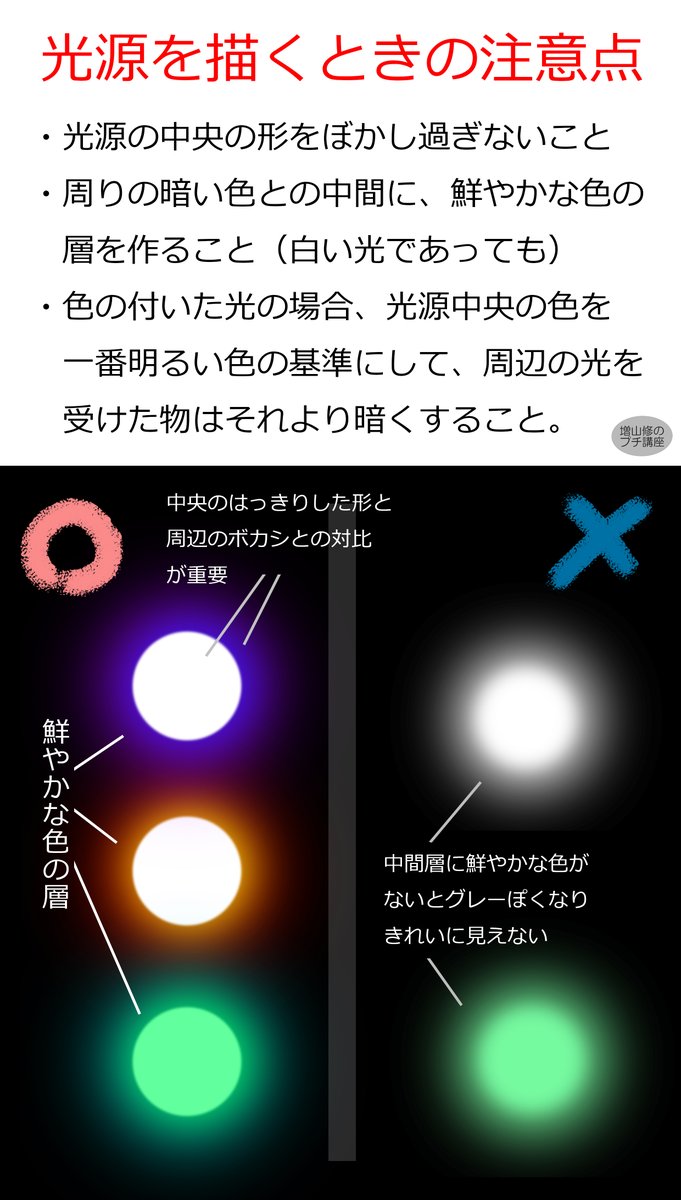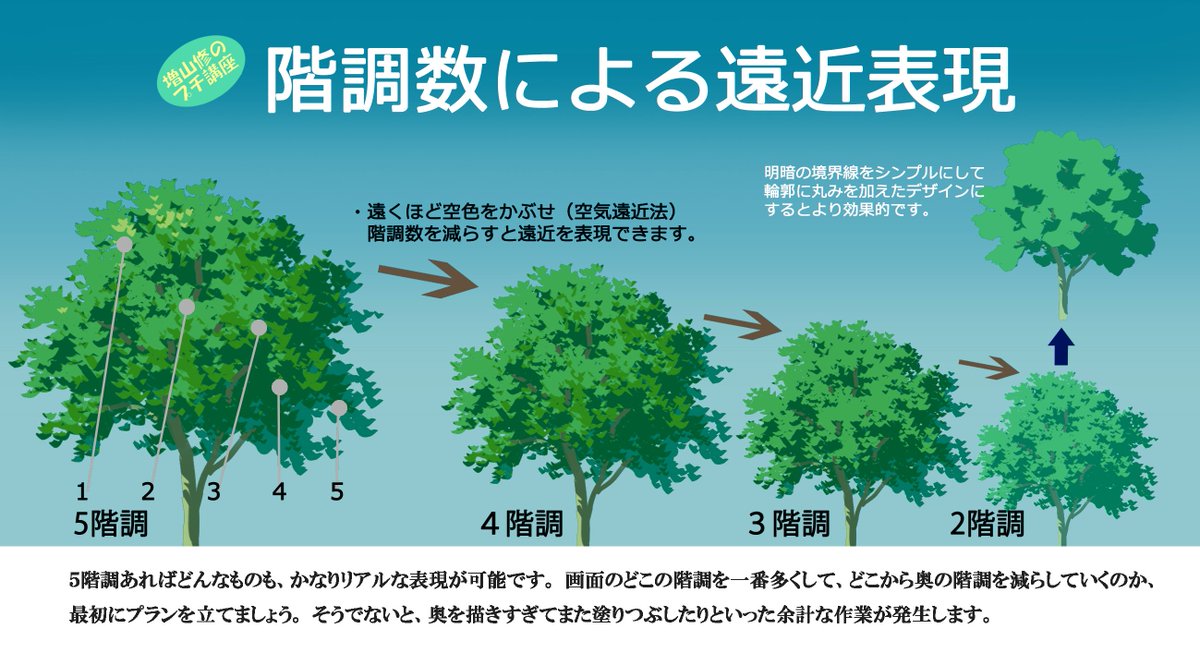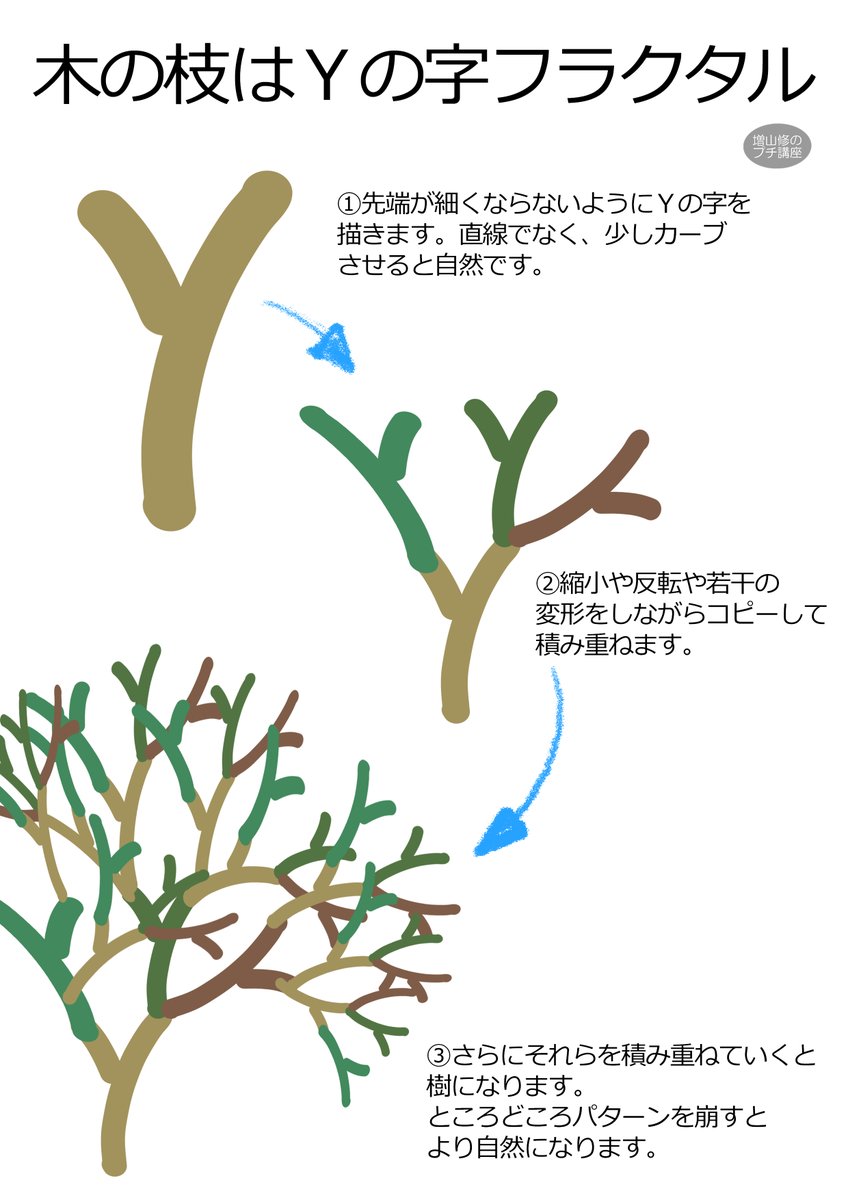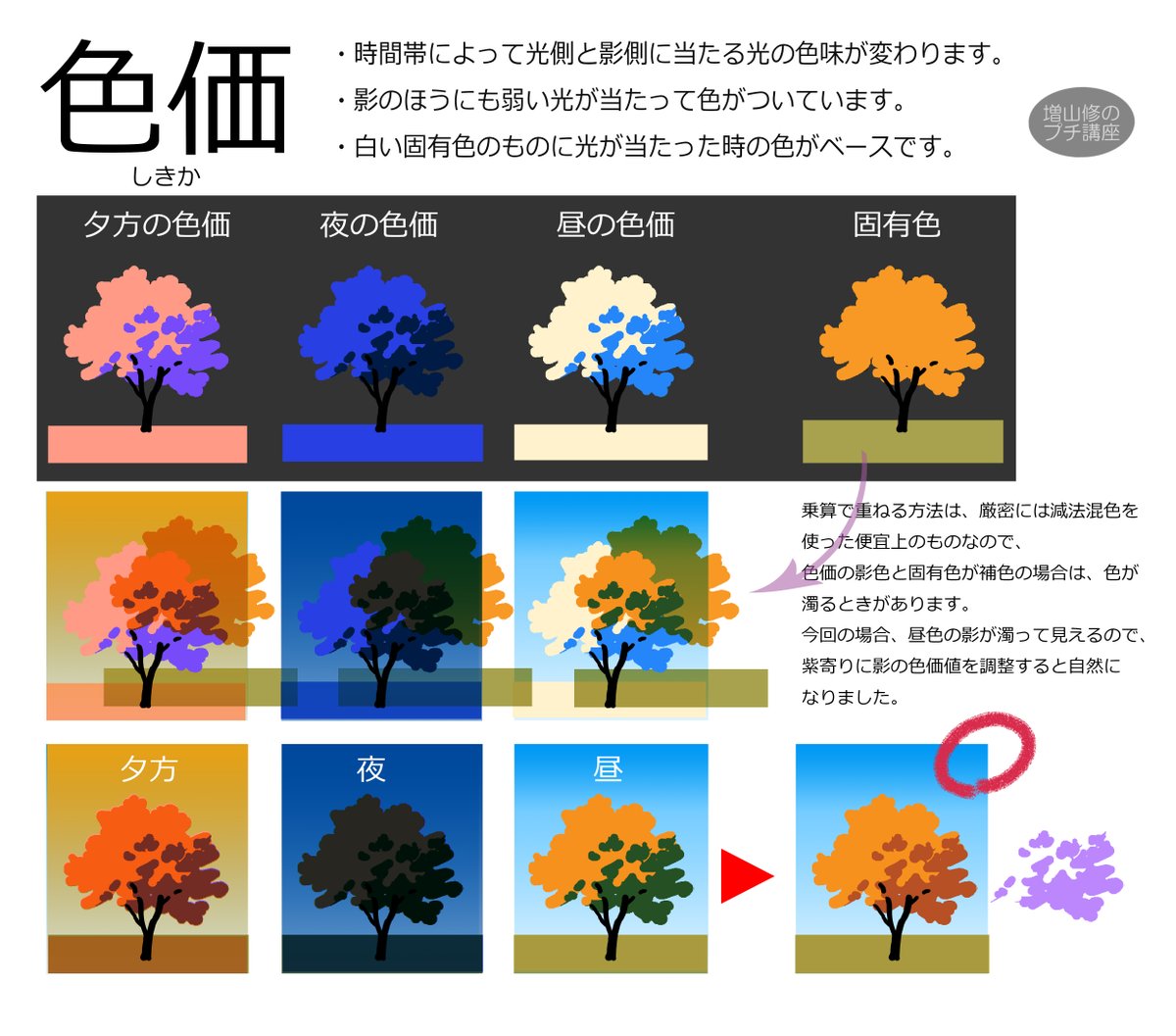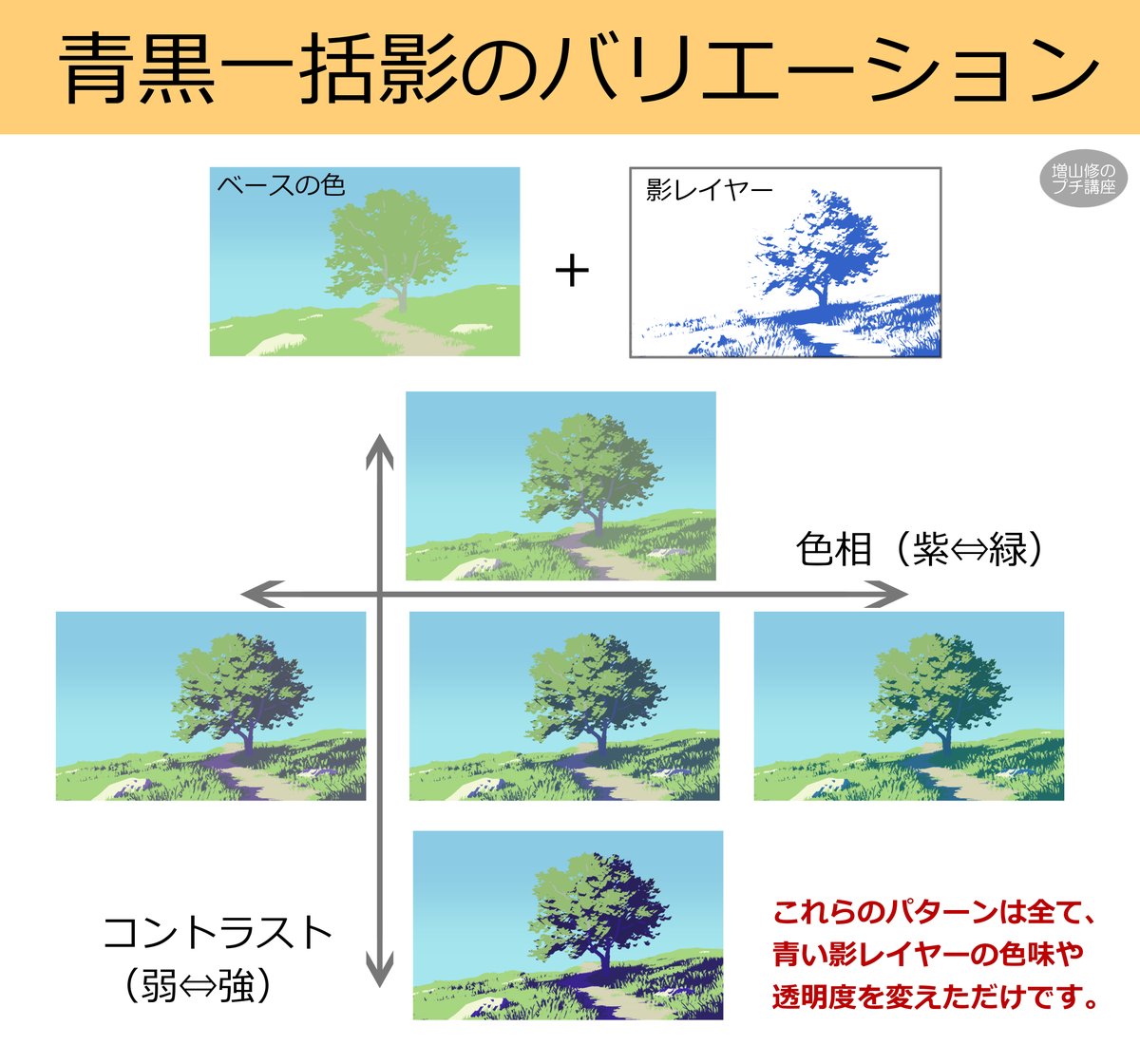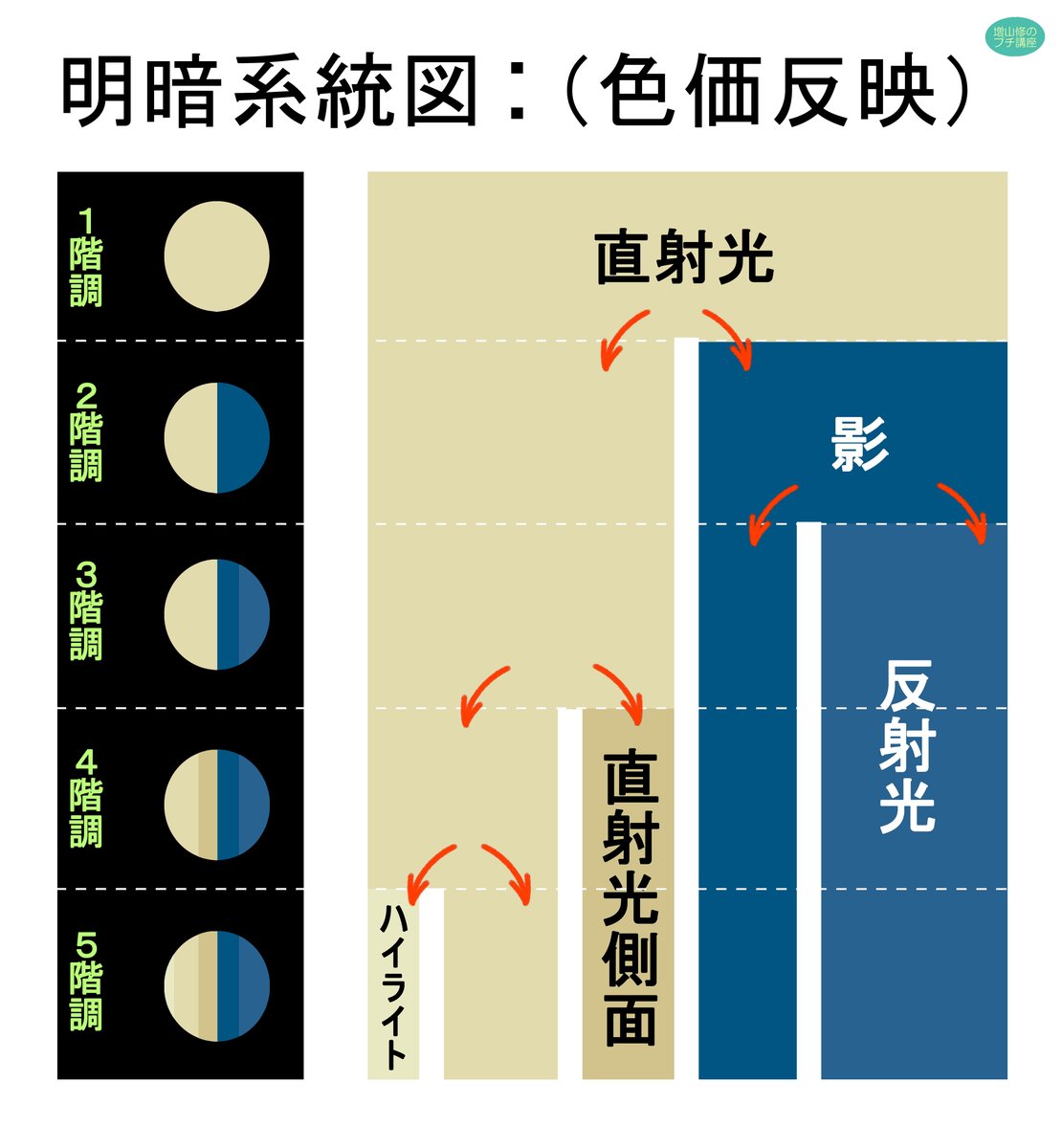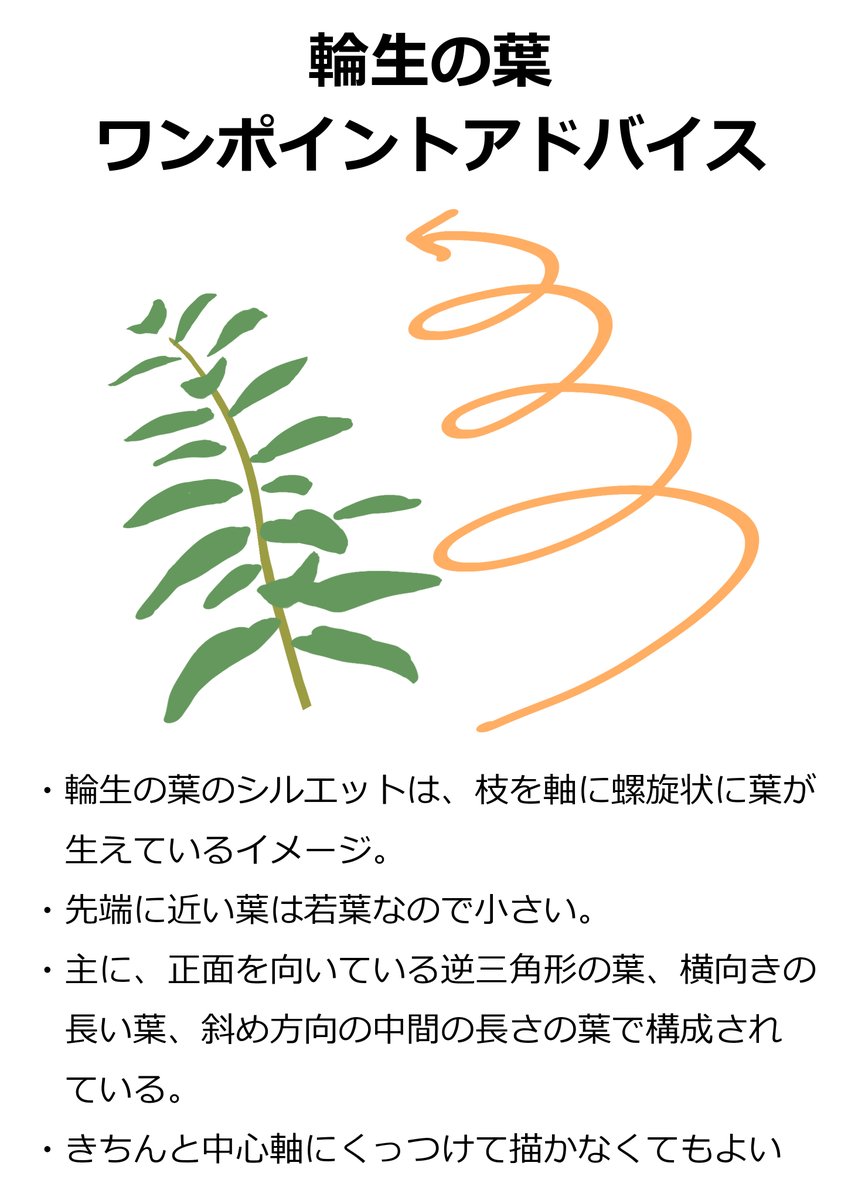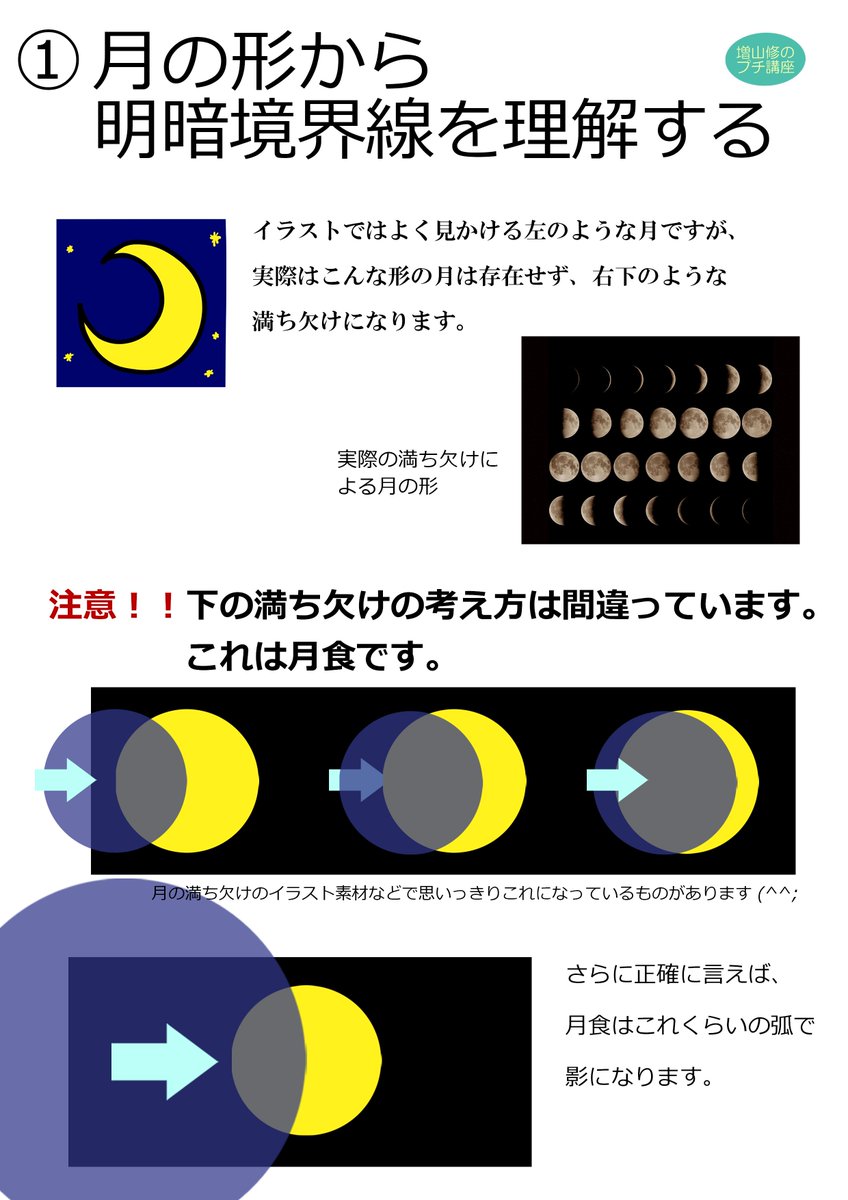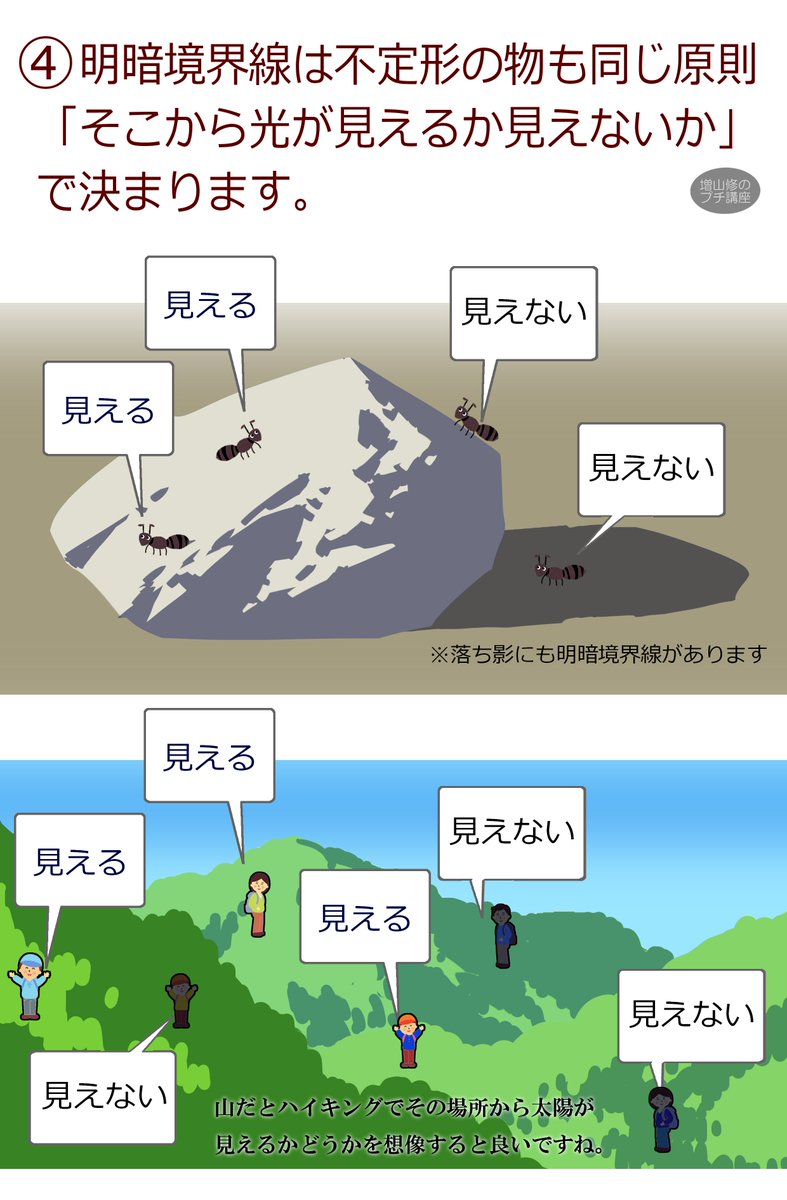82
84
【失敗しにくい草の描き方】
草の細部も全体も一気に描けるようになろうとすると大変です。まずは全体的なバランスをとることに集中して、その後に細部の問題に取り組むほうが挫折せずに上達できます。
#backgroundart
#背景美術
#howtodraw
#描き方
87
『カドダケハイライト』を使えるようになりましょう♪
立体感は、面の塗分けがされているかどうかでなく、輪郭と稜線を認識させることで生まれます。一昨日投稿した絵で8月15日の投稿の法則を説明。
#背景美術 #描き方 #backgroundart #howtodraw
88
91
Making of Chain (2015) #描き方 pixiv.net/member_illust.…
95
97
98
輪生の葉のポイント
#描き方 背景美術
100