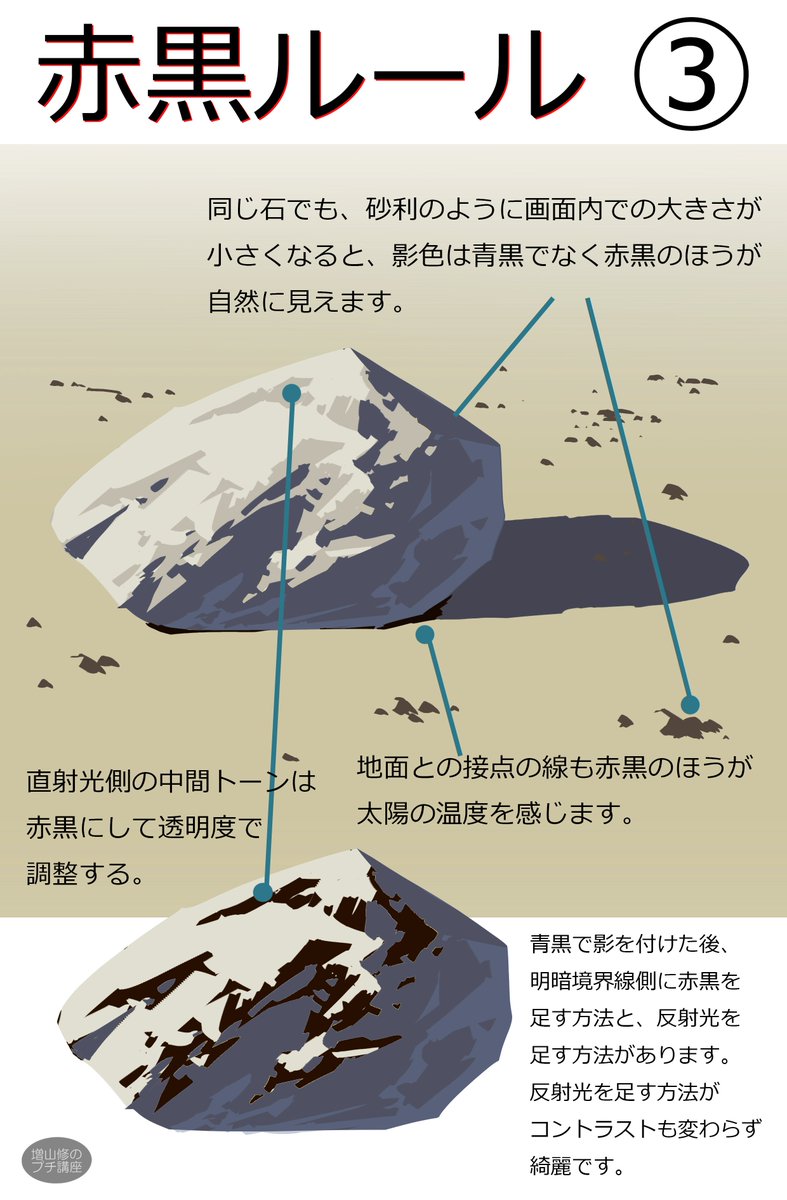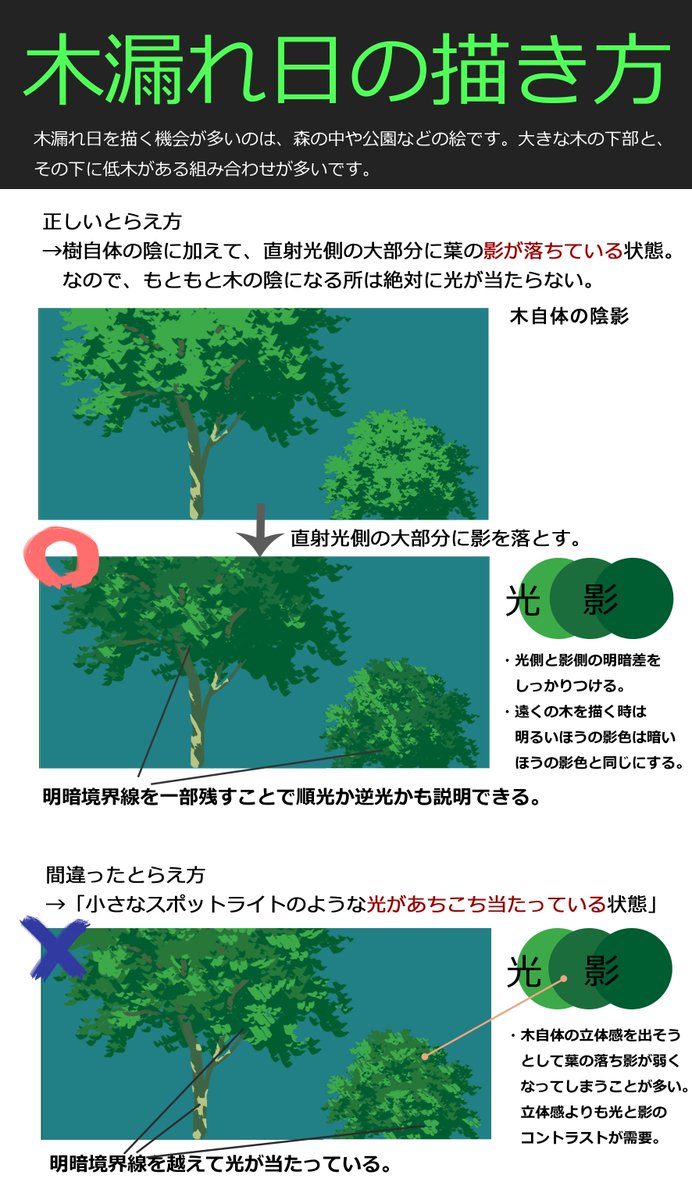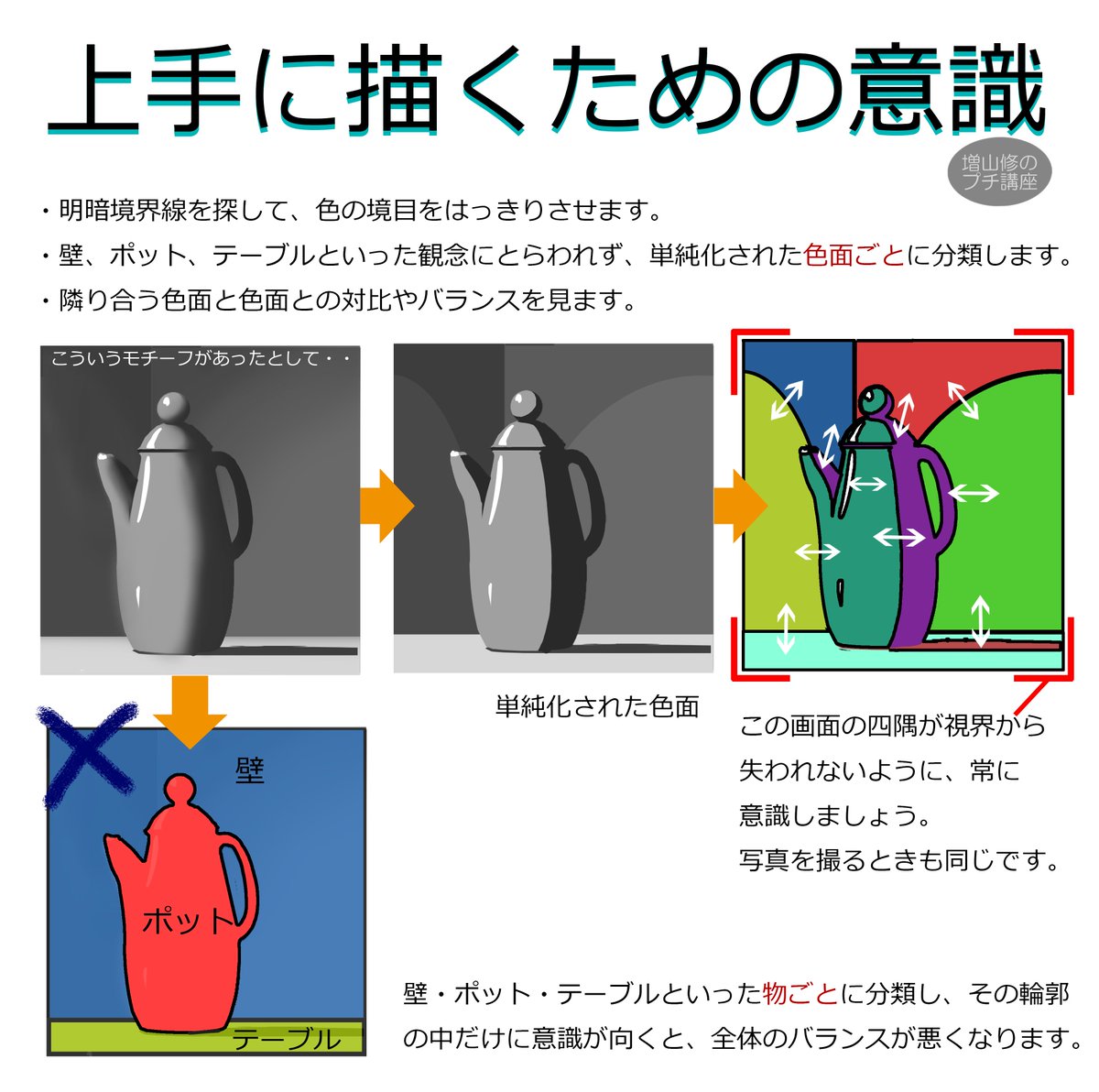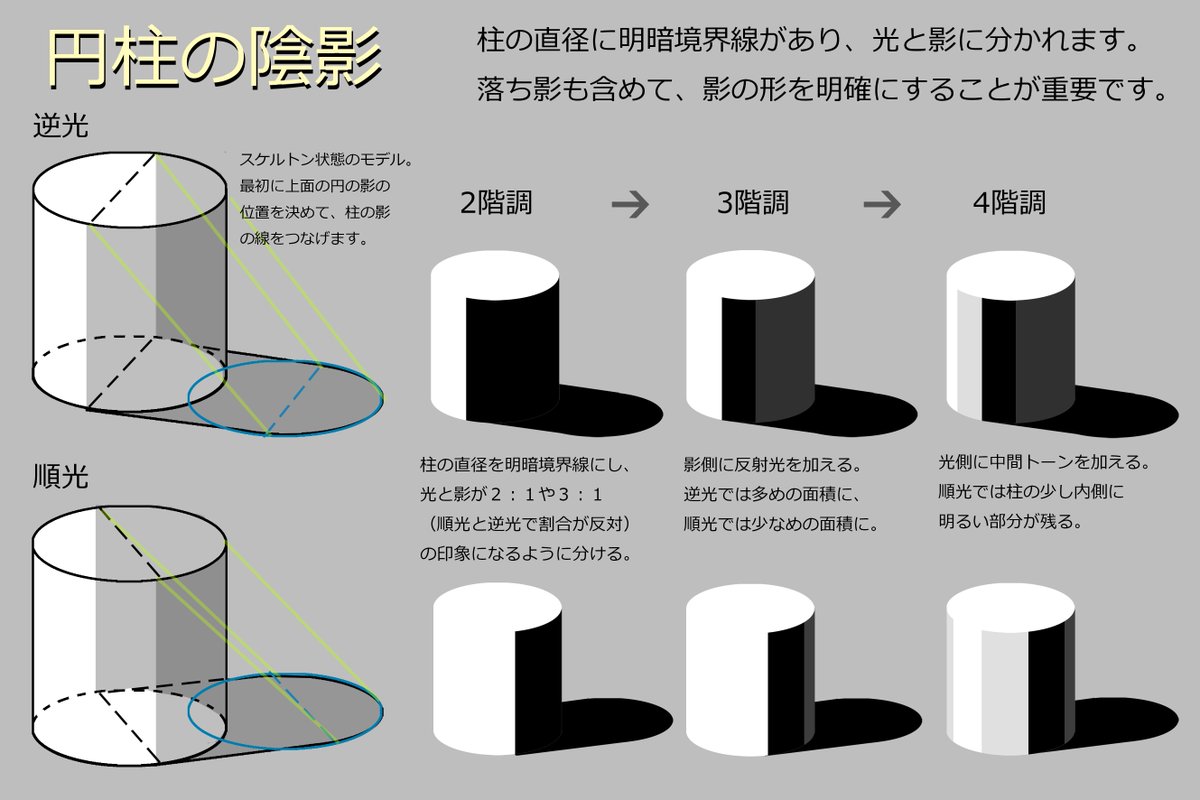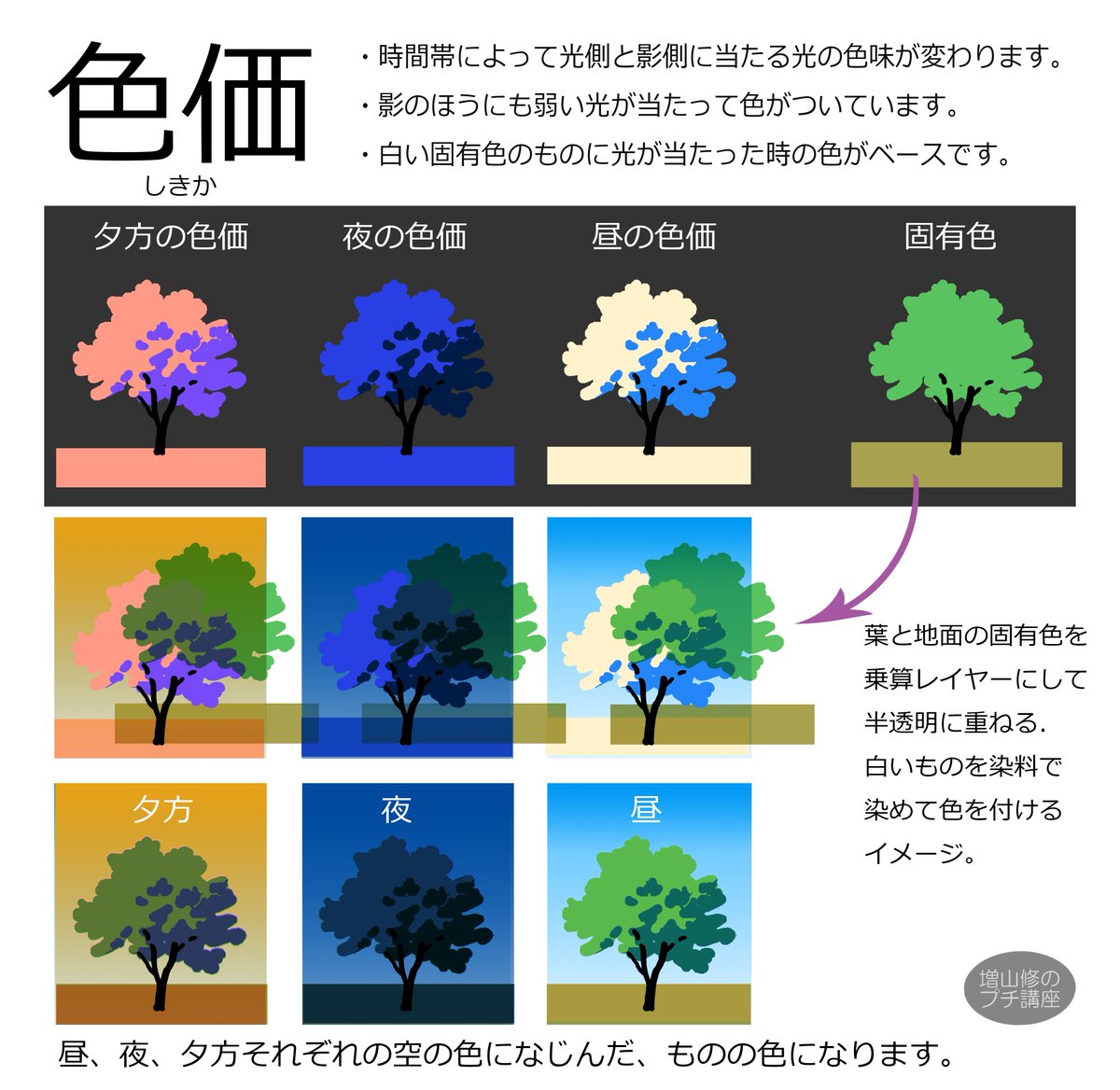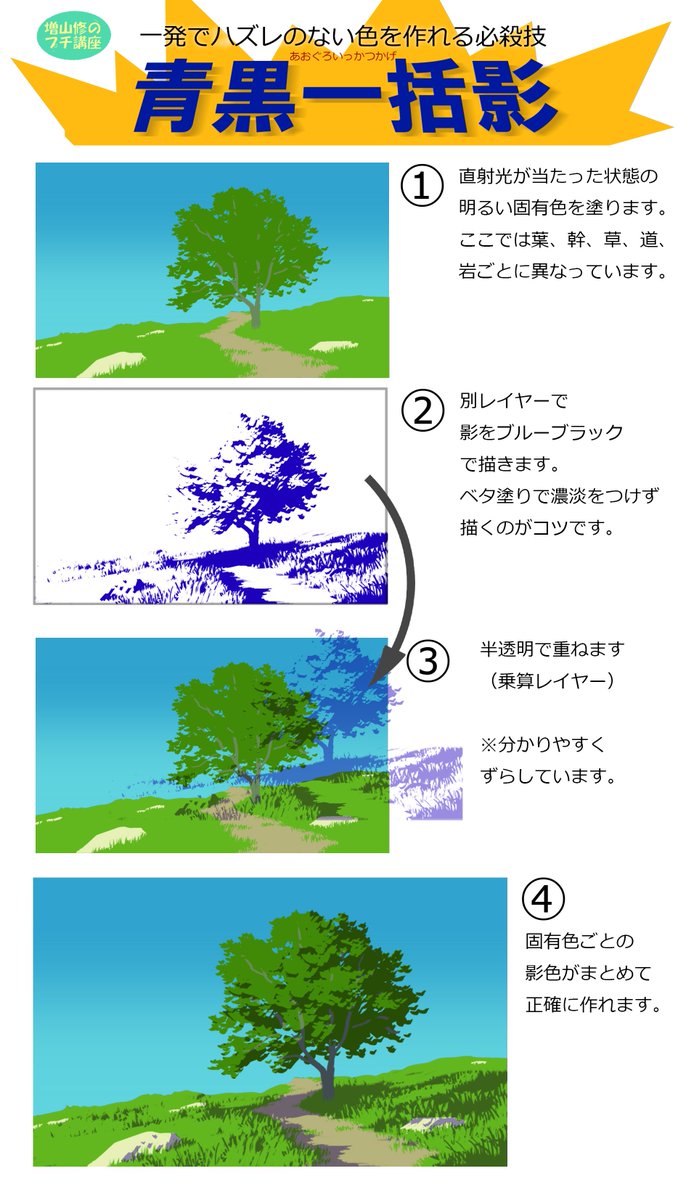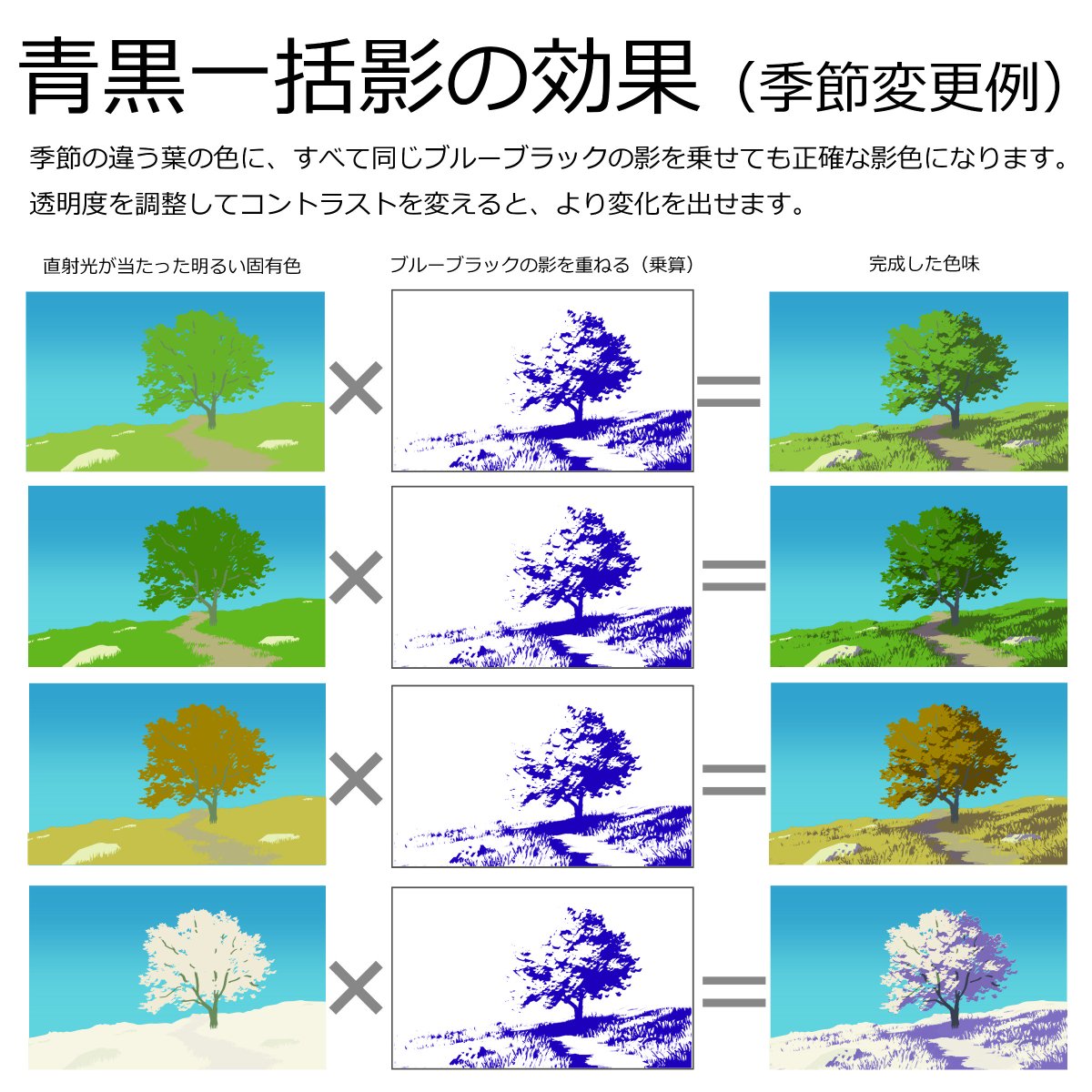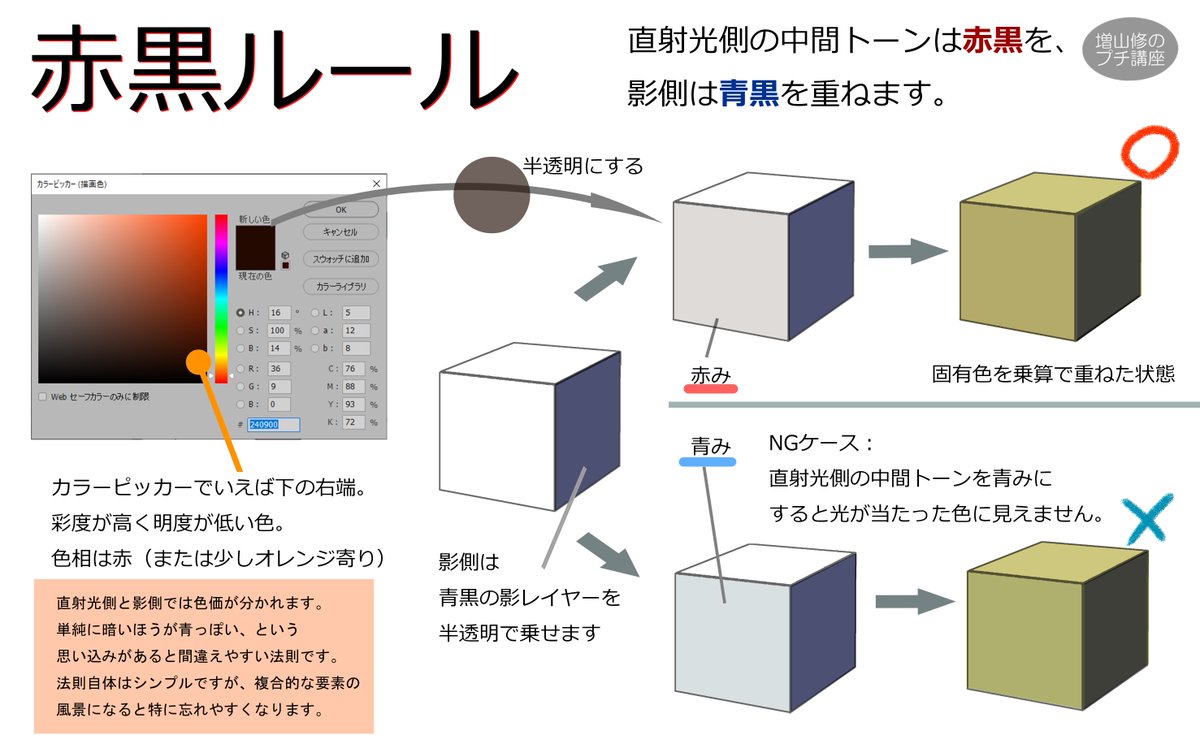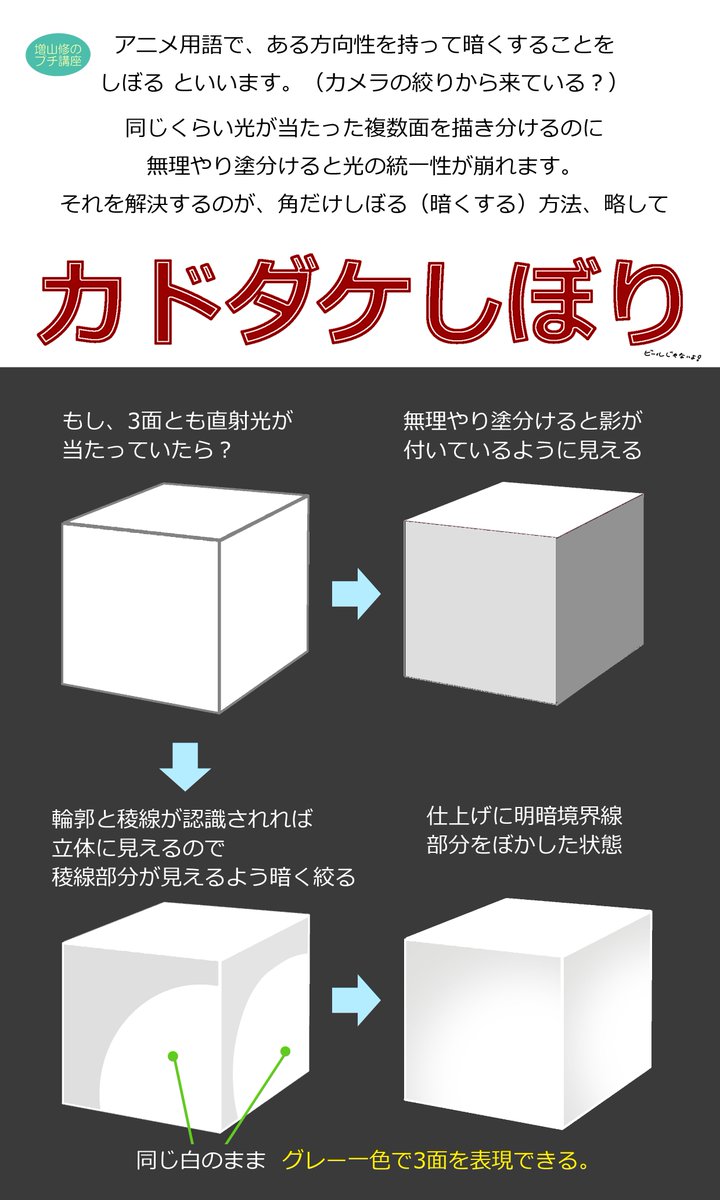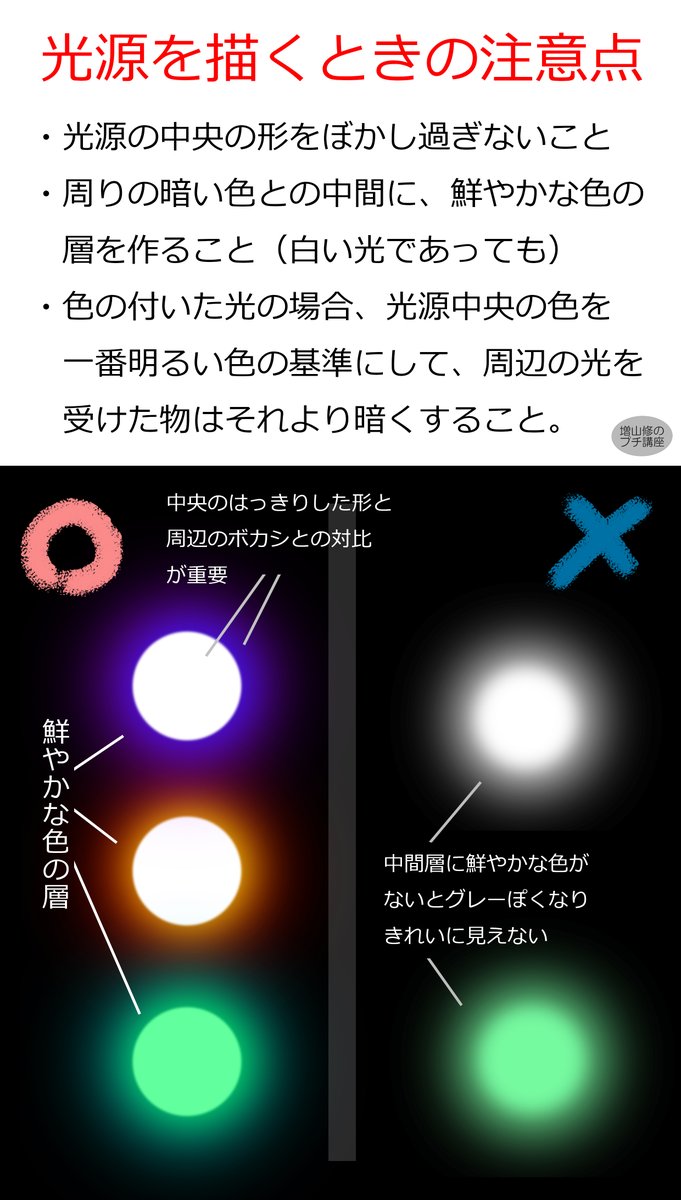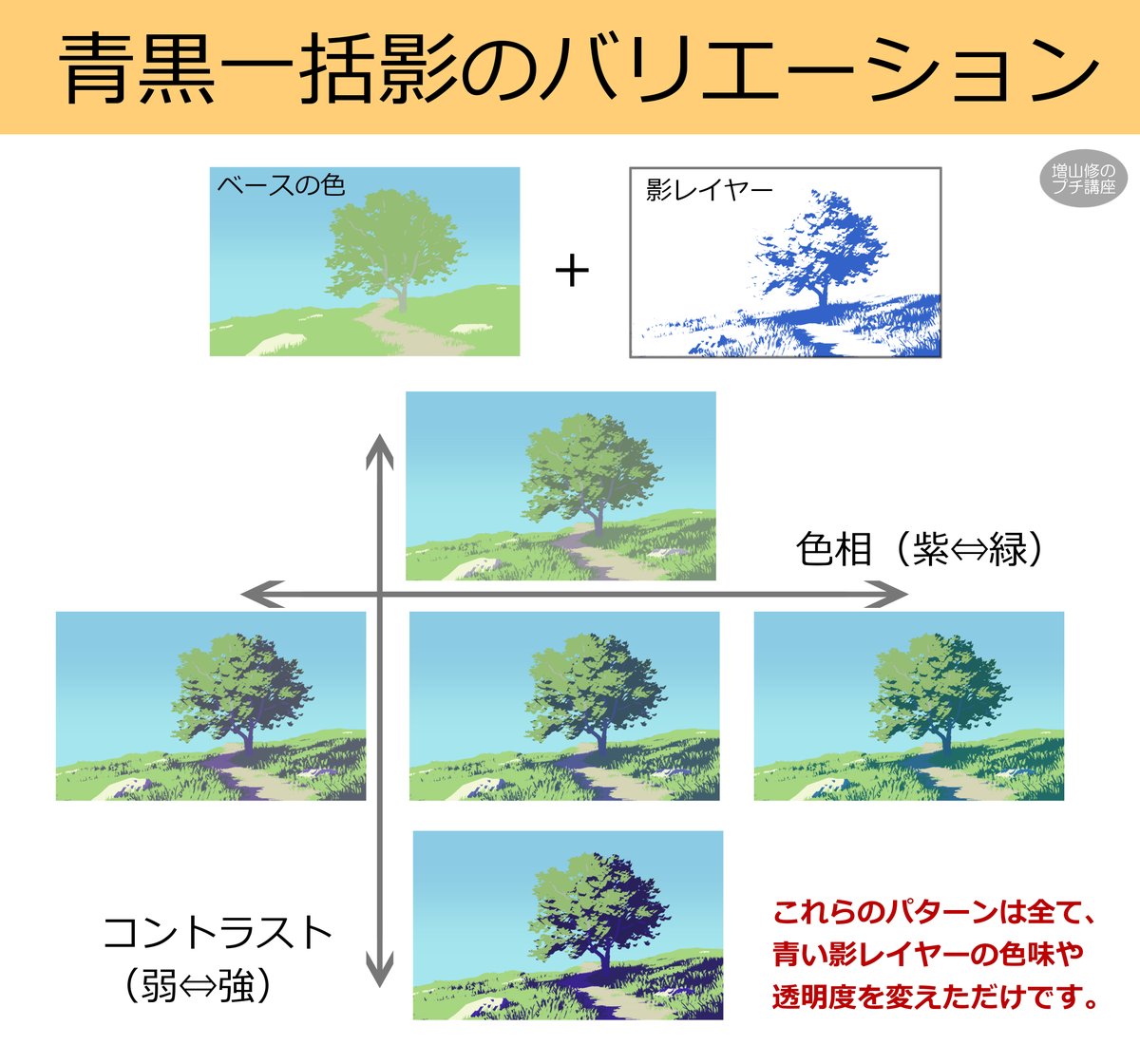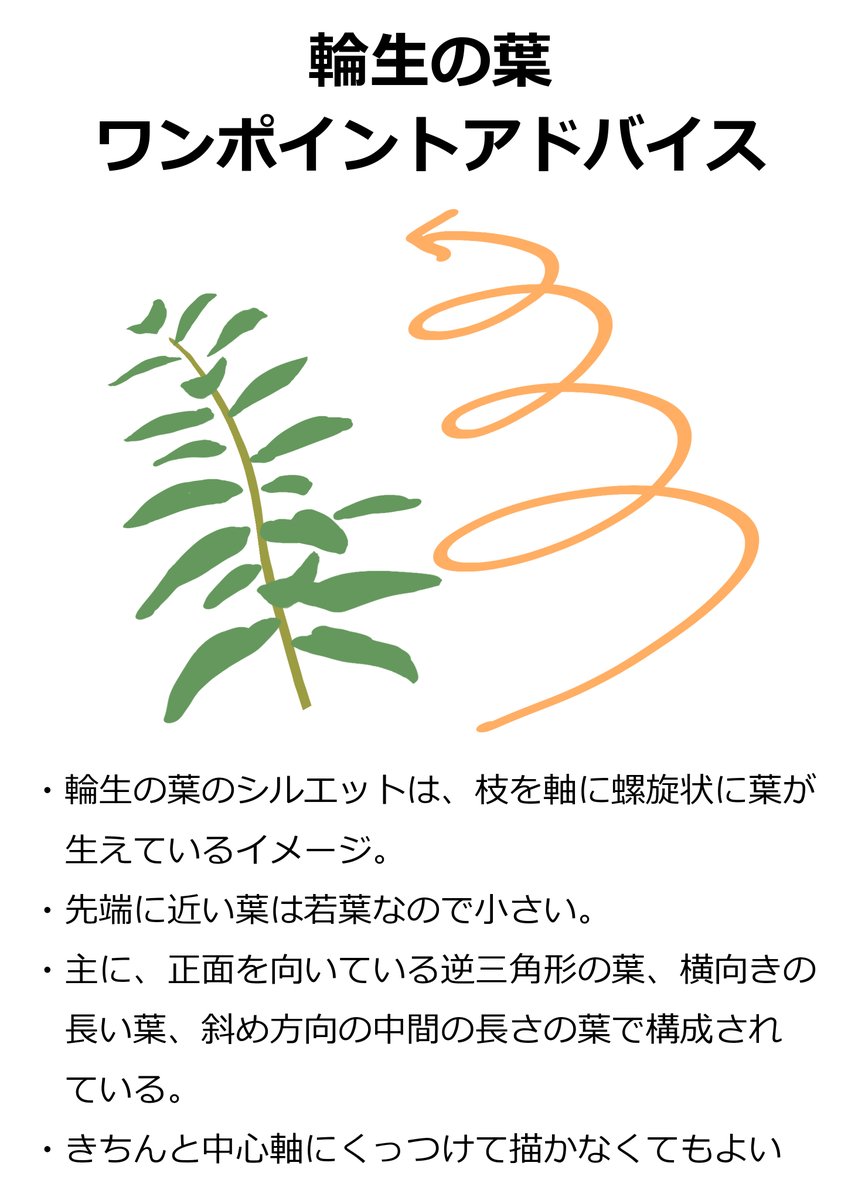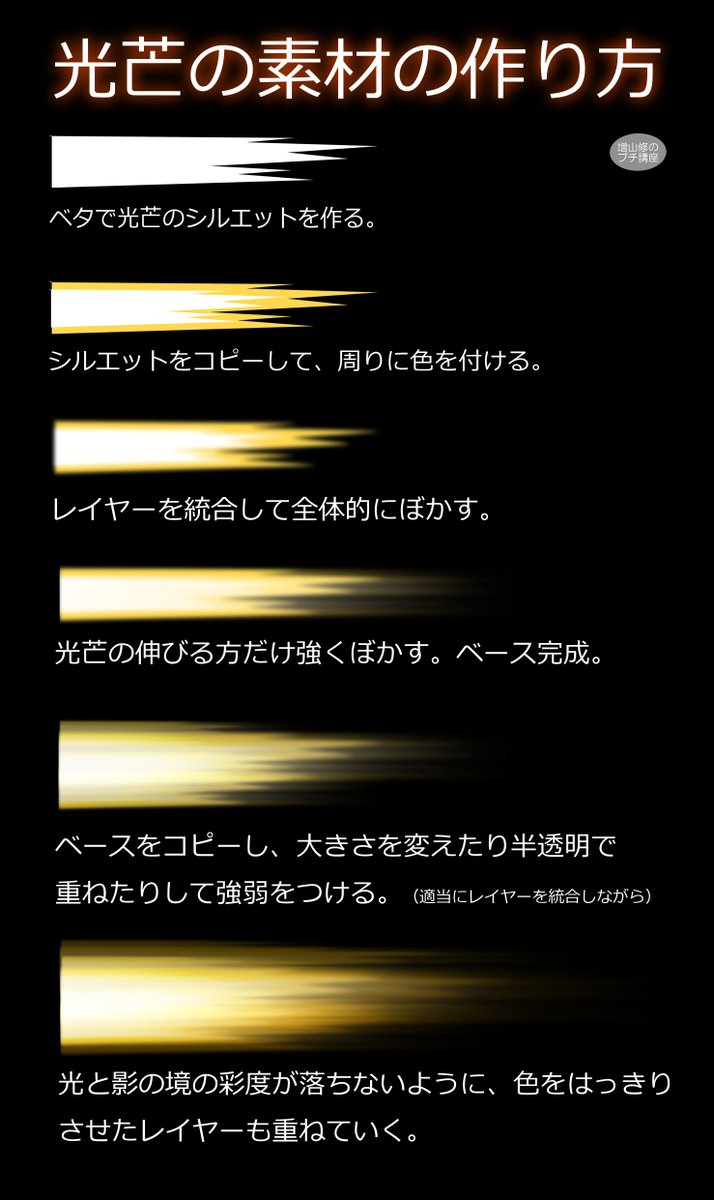27
赤黒ルール④
赤黒は溝や汚れにも使えます。
暗いほうが青い、という思い込みがあると影中の溝も青黒くしがちです。しかし実際は反射光のほうが青いので、暗い溝や穴は反対に赤みに見えます。
#howtodraw
#backgroundart
#描き方
#背景美術
28
29
木漏れ日の描き方
いくつかポイントがありますが、まずは光が当たる範囲について説明。「木漏れ日」という、光をイメージする言葉に引っ張られて、無秩序に光を入れてはいけません。
光でなく、葉の影が落ちたもの、という認識を持ちましょう。
#描き方
#背景美術
#howtodraw
#backgroundart
31
33
34
35
36
37
39
41
44
48
輪生の葉のポイント
#描き方 背景美術
49