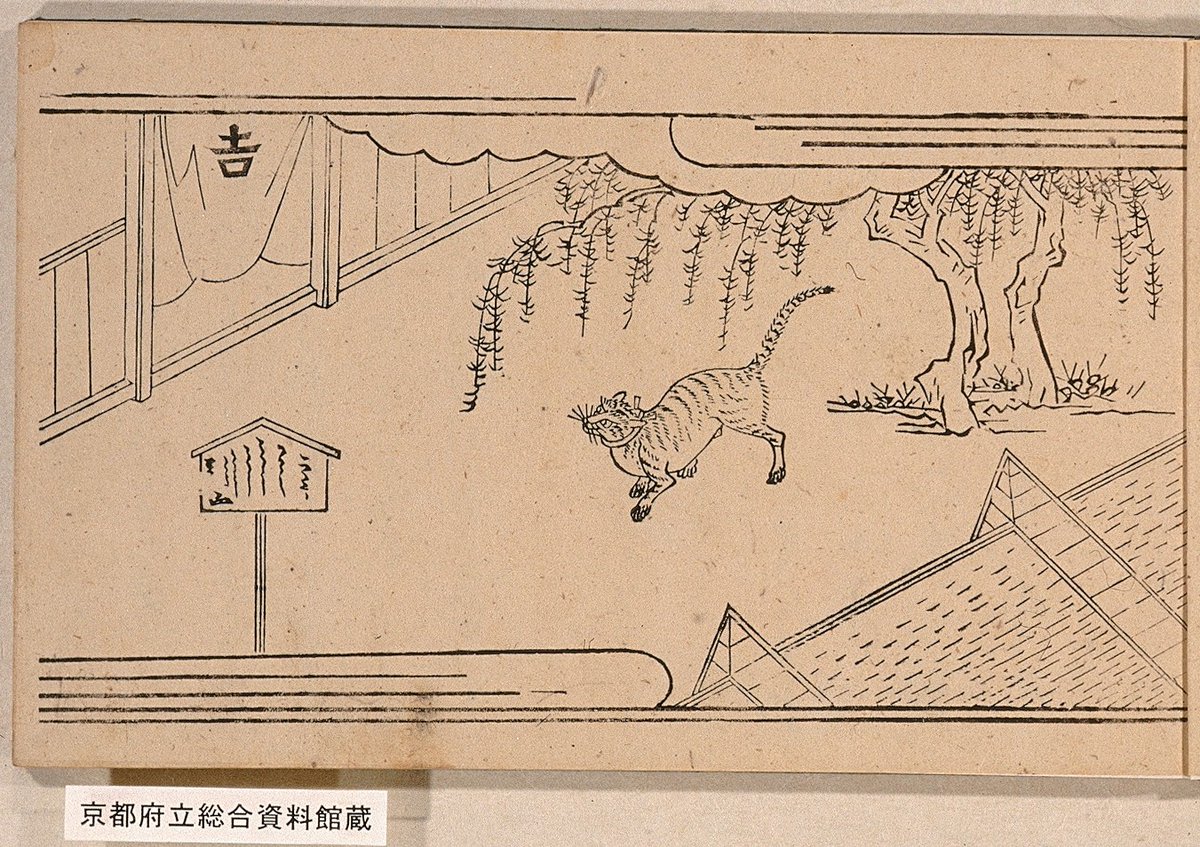1
2
3
4
遅ればせながら、京都学・歴彩館も #キュレーターバトル に参加いたします。
ご紹介するのは、京都画壇を代表する日本画家、竹内栖鳳が描いた「江口」。
「象」に乗る「遊女」の組合せは、初めて見ると、ナゾすぎる。
『栖鳳小品画集』より。
#京都あれこれ
#CURATORBATTLE
#ナゾすぎる
5
6