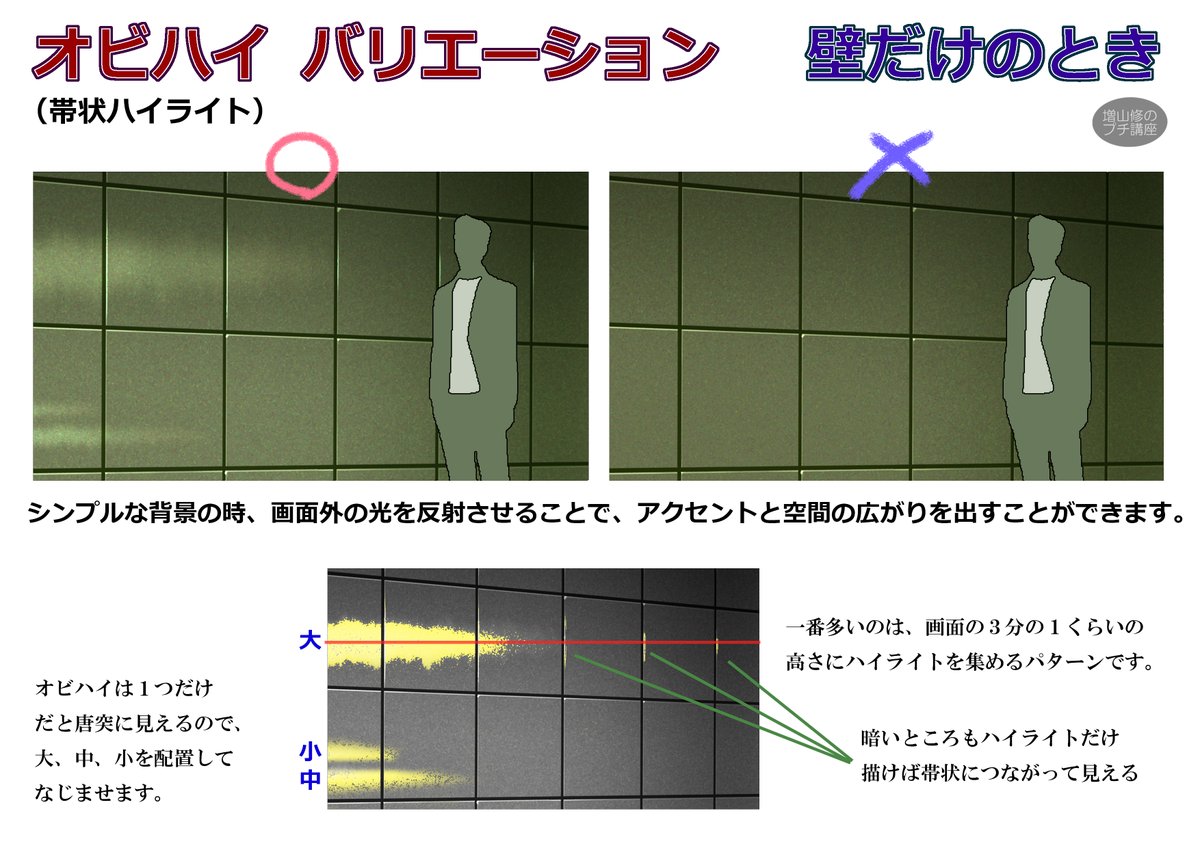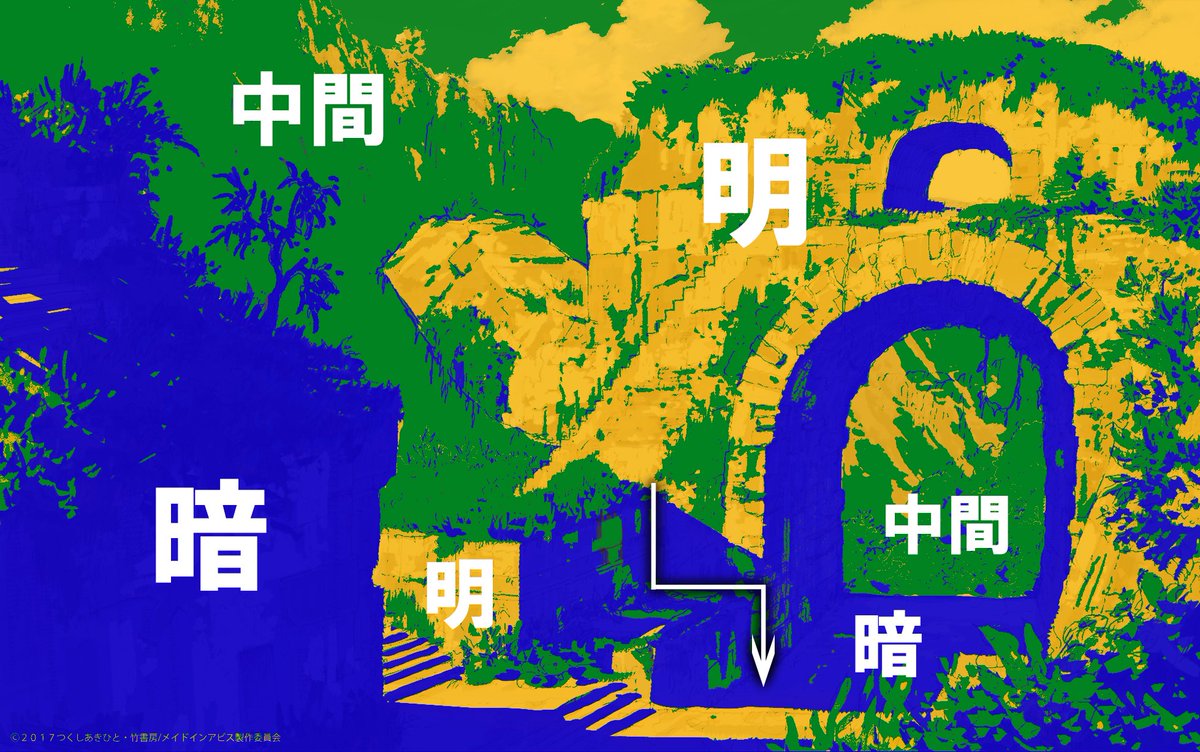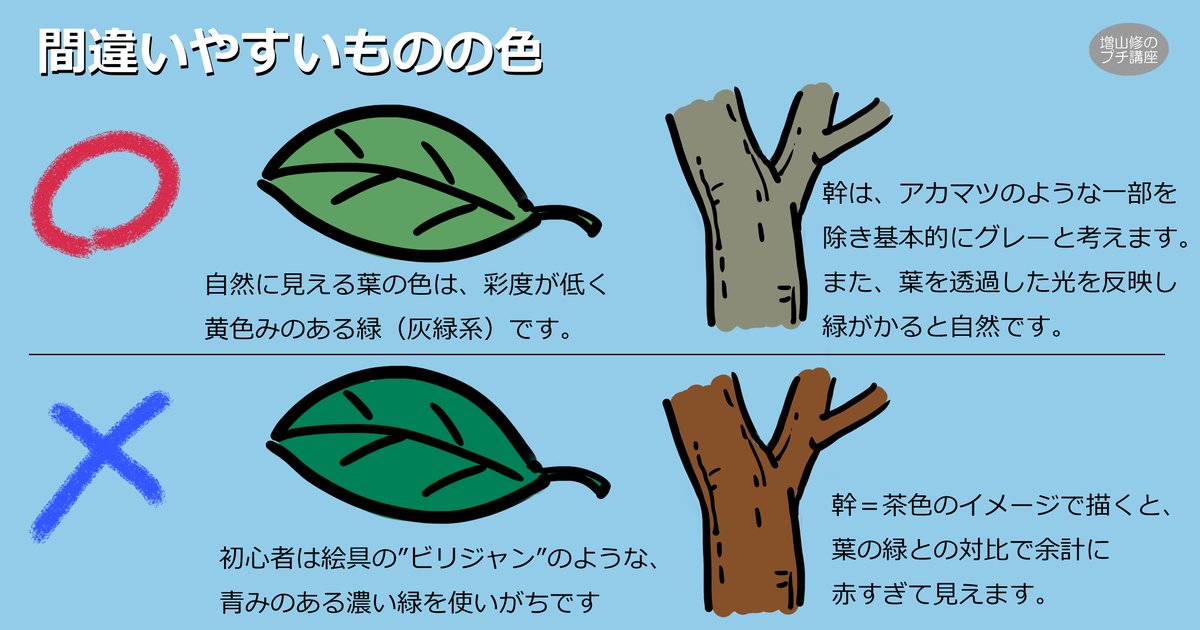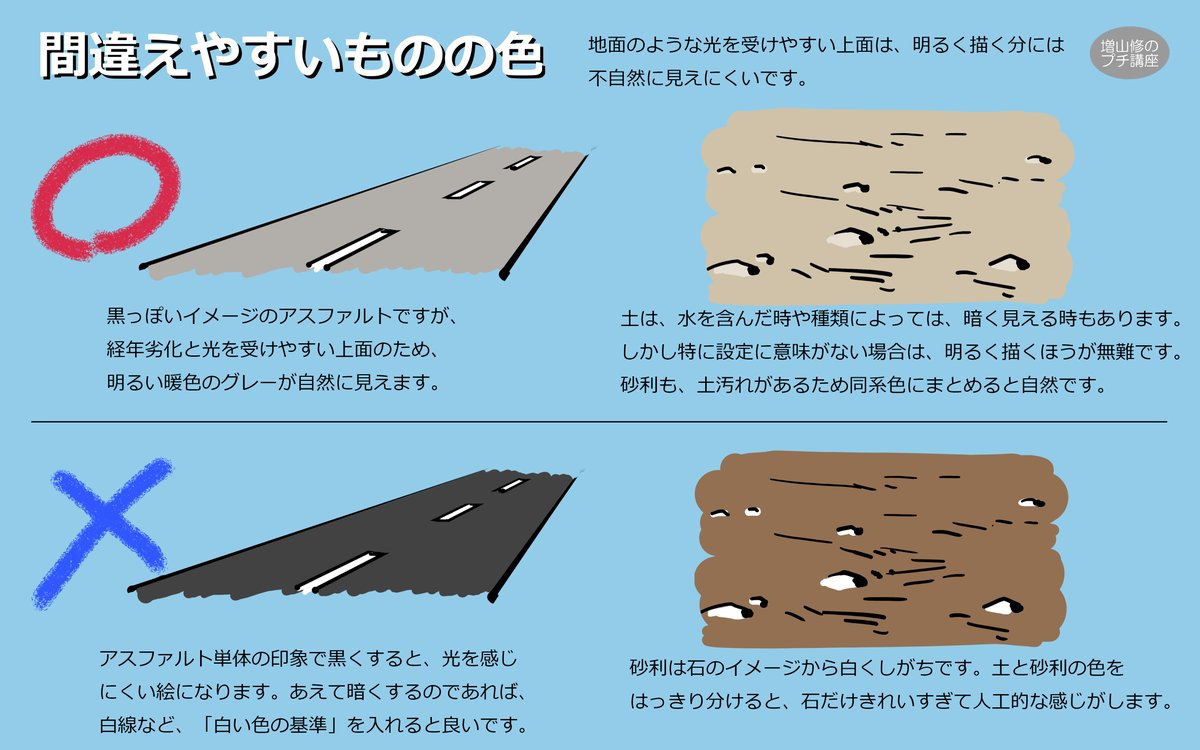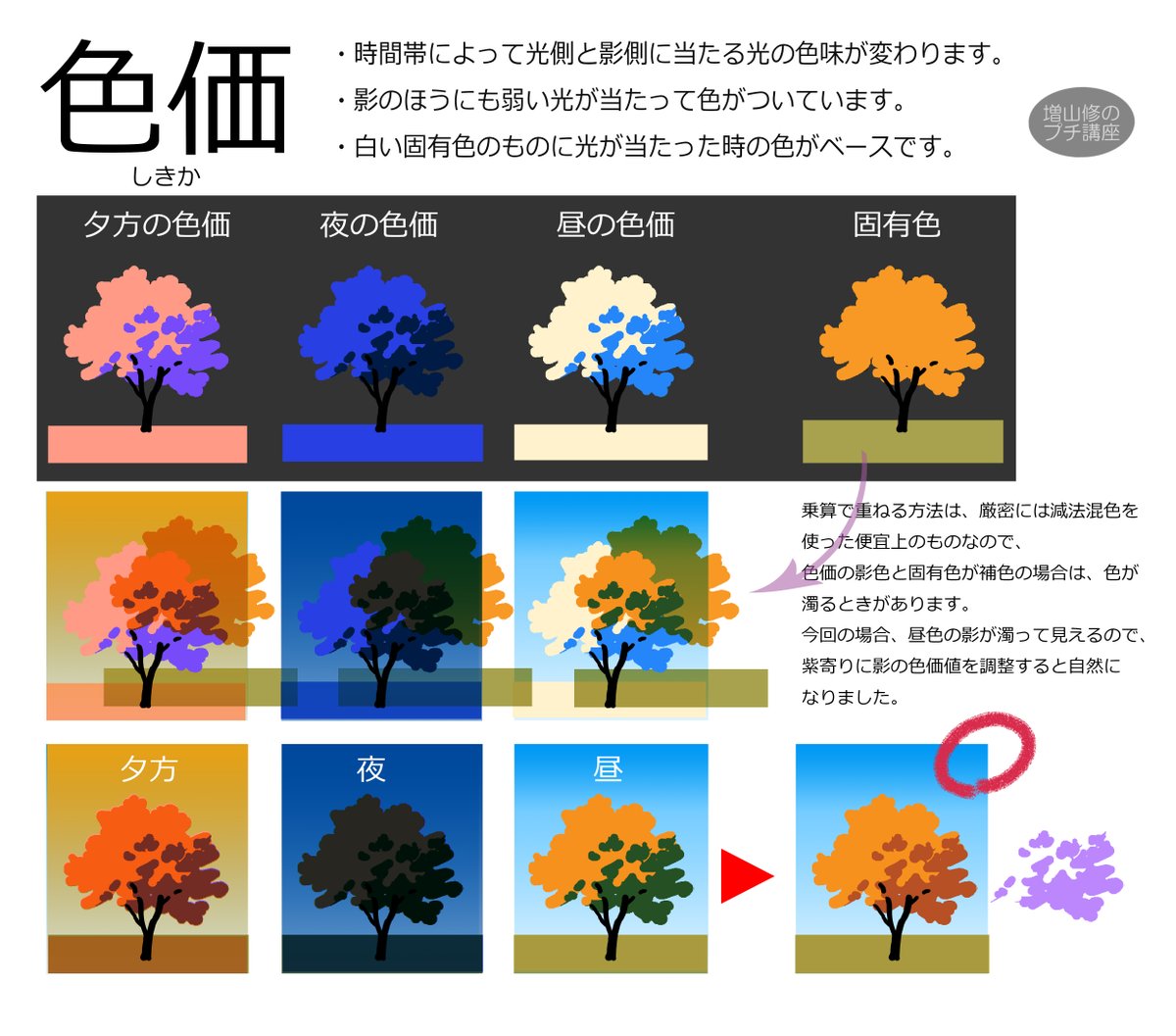377
381
【重なりの表現】
俯瞰アングルは、ともすれば平面的に見えます。前後が重なるポイントを意識的に見やすくすることが大切です。
#背景美術 許可済(再掲)背景:西俊樹(@shirakabausagi)
383
筆ペンだけで風景を描く
388
影を入れる時、こういう効果を考えて位置を決めています。同時に複数の効果を満たす場所を発見出来たときは、パズルが解けたときのような嬉しさがあります。
#背景美術 許可済
390
391
392
【ラフボード/その明暗簡略図】
ラフに描くという意味は、明暗パズルに集中するということです。
白い矢印の部分に注目。明るい石の色をL字に配置することで、段差を表現しています。
また階段は、ストライプの影だけで表現されています。
#背景美術 (許可済)
399
#色の見え方 トレンドに乗ってみました・・