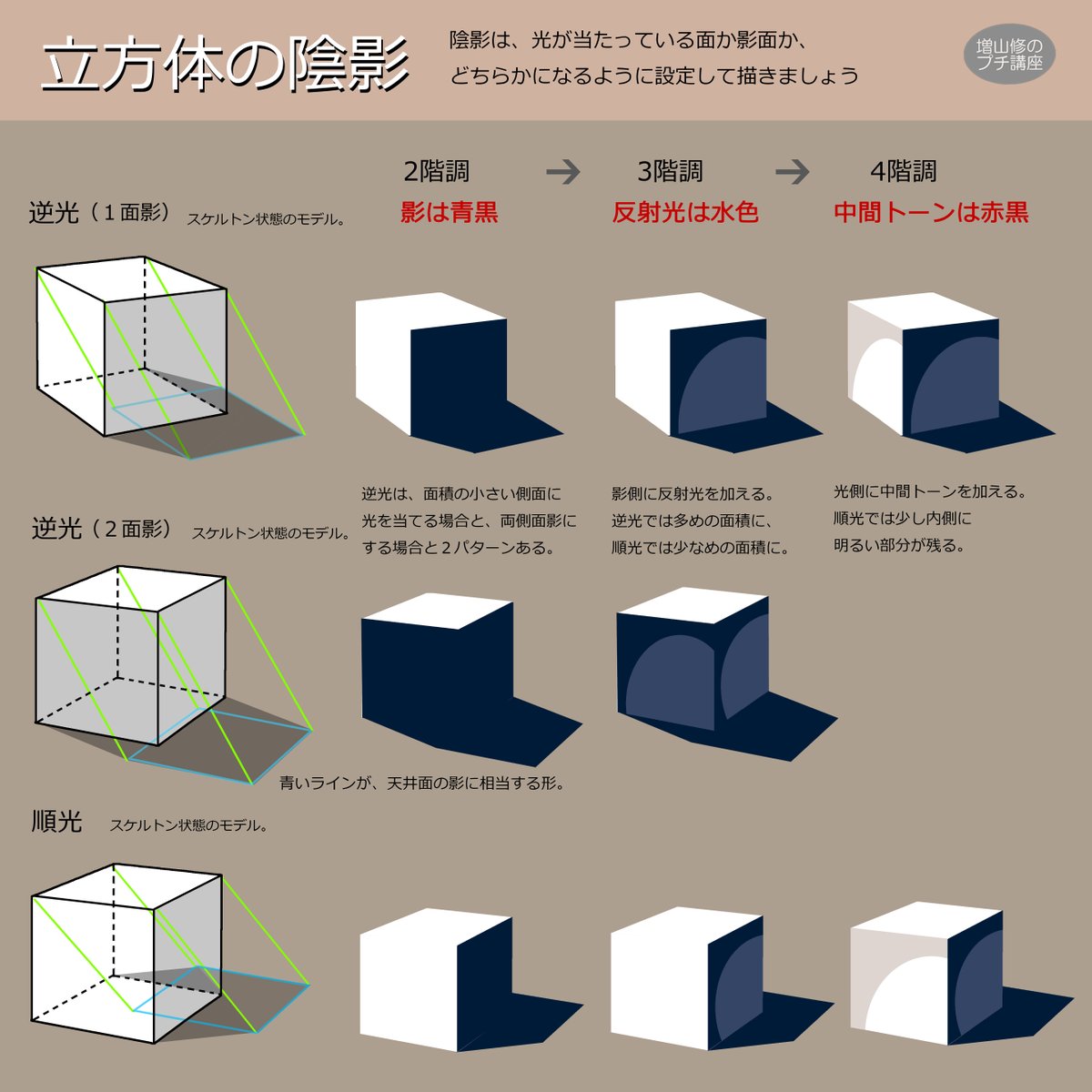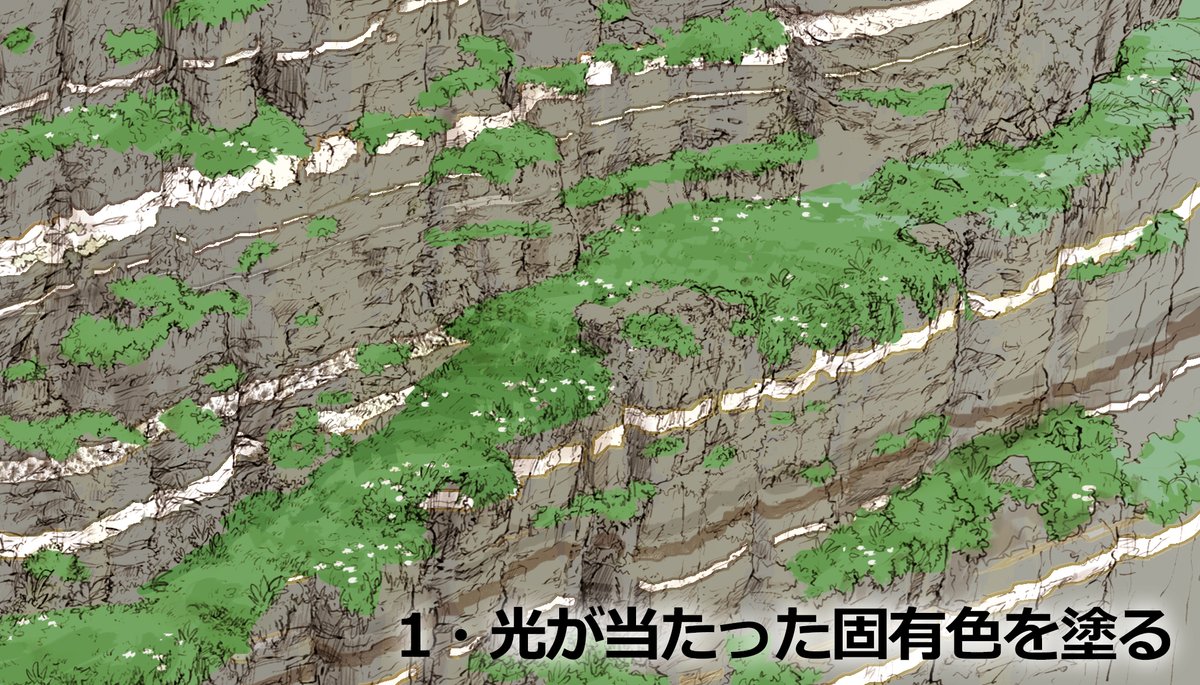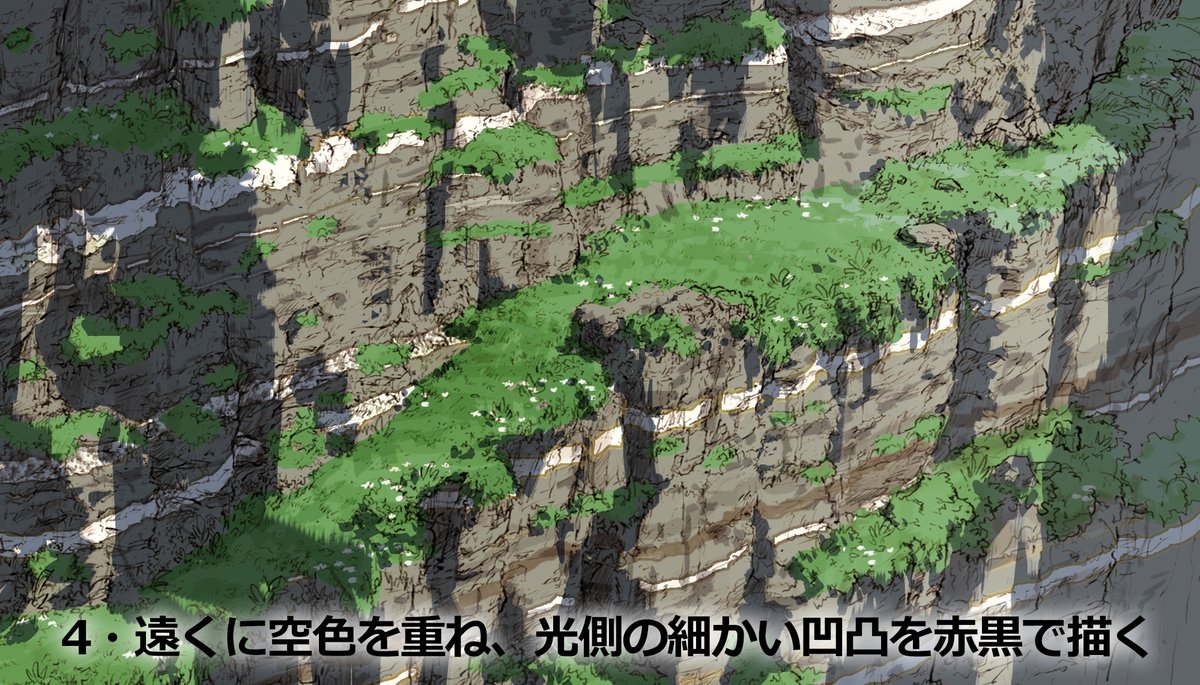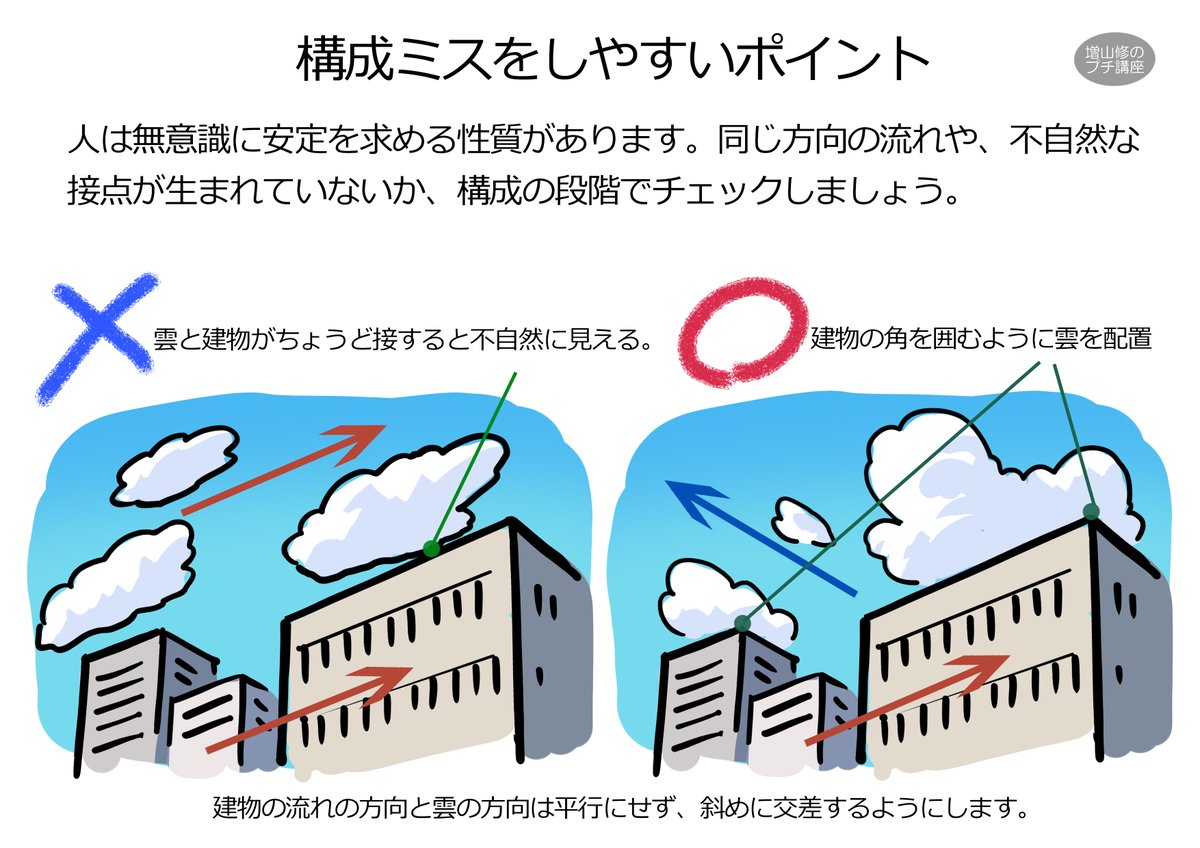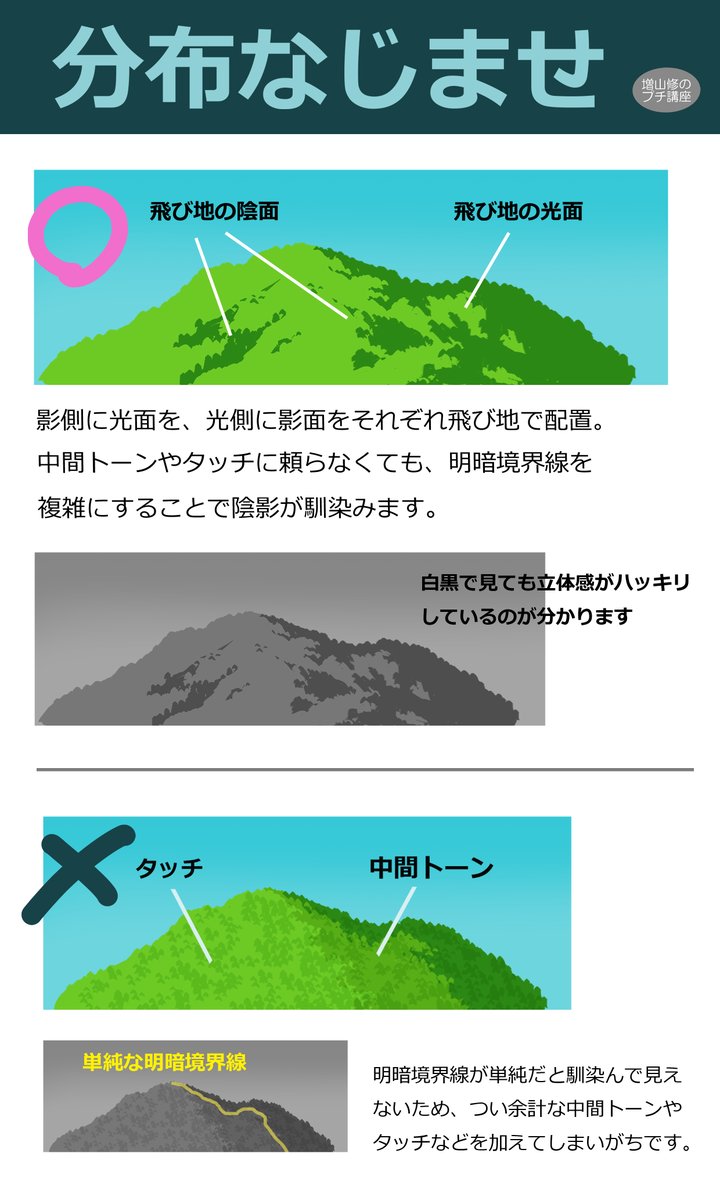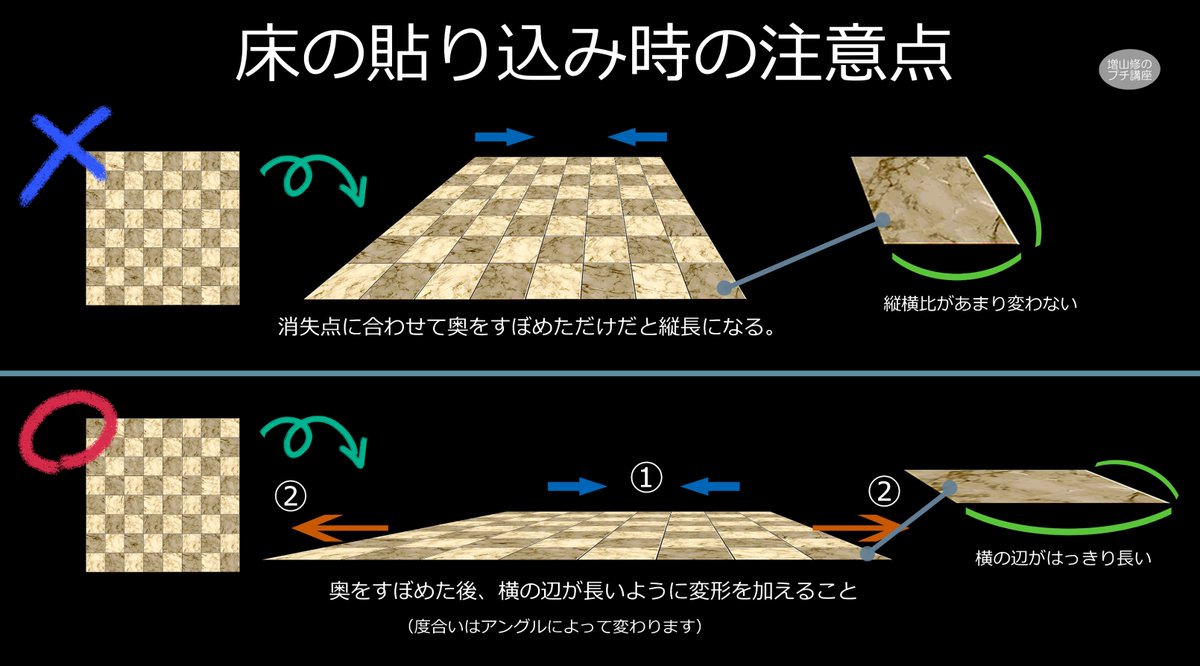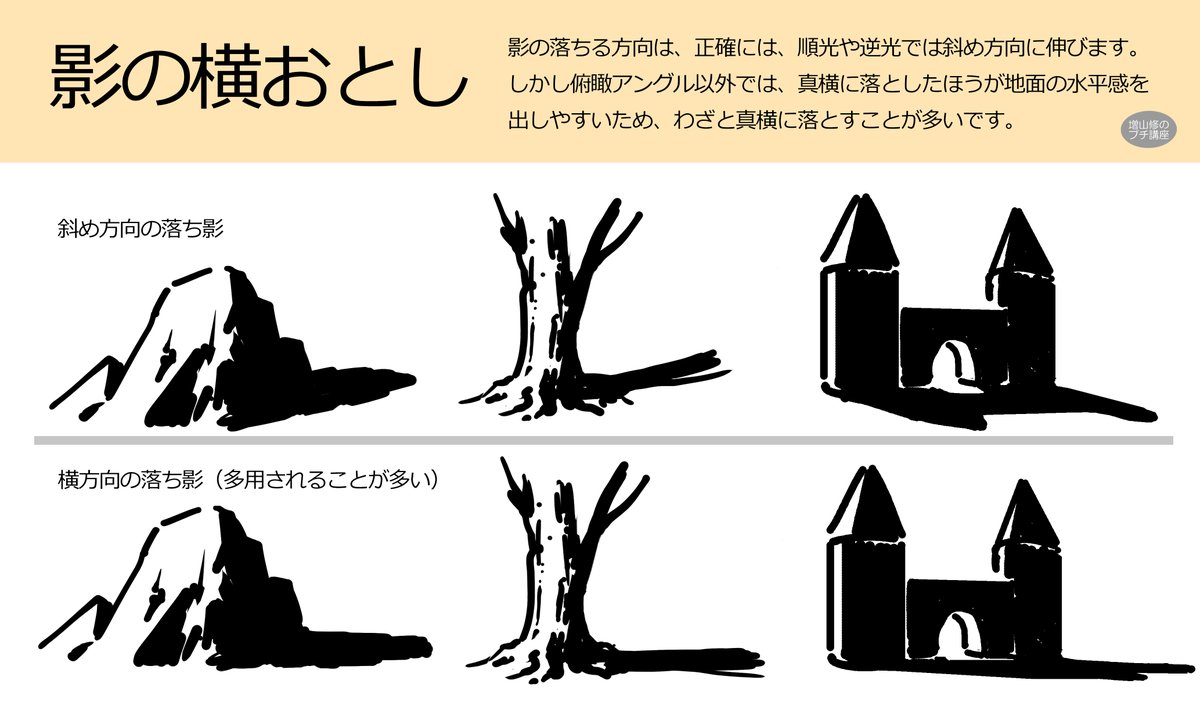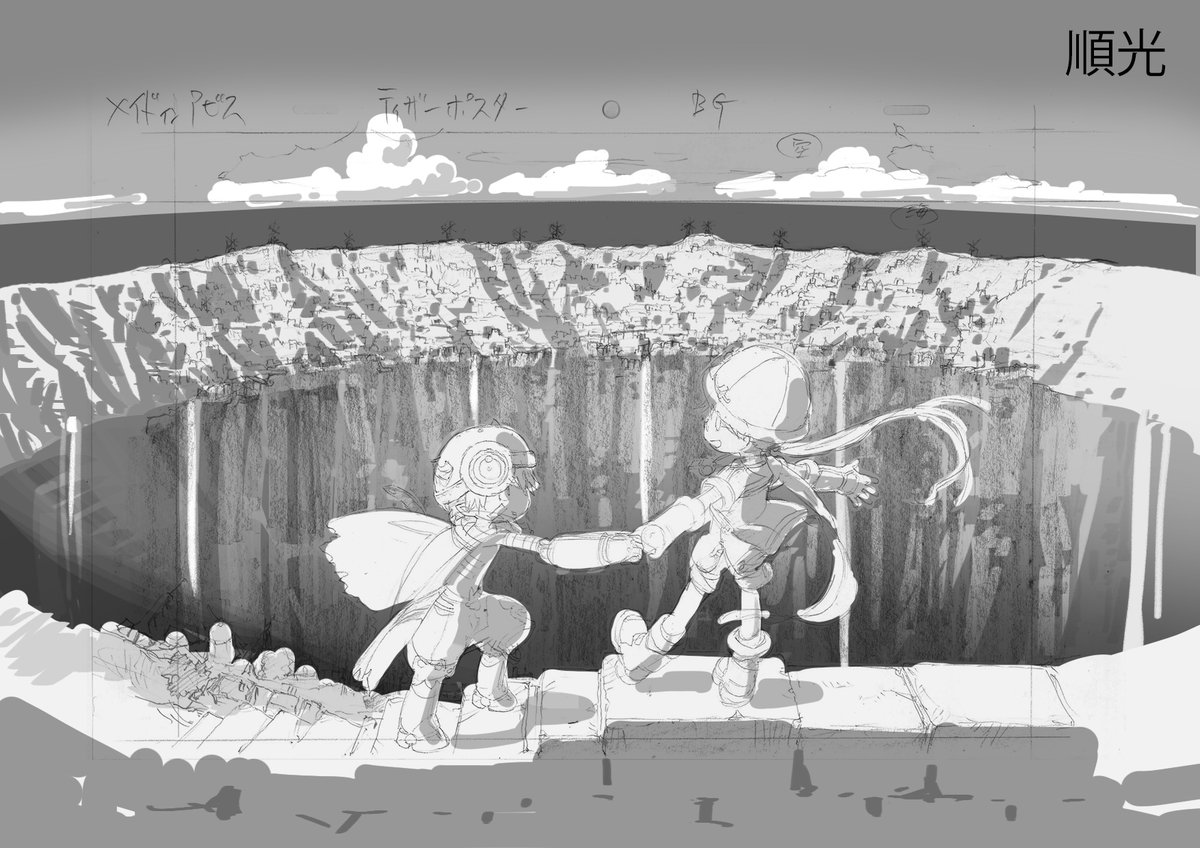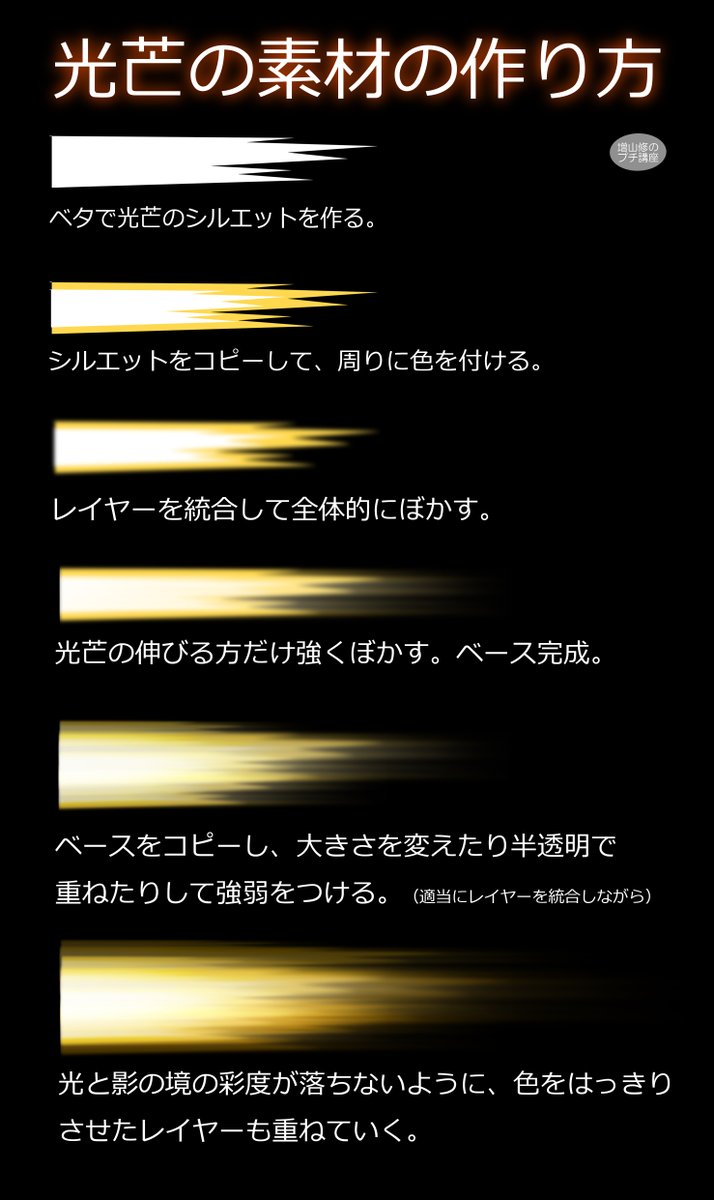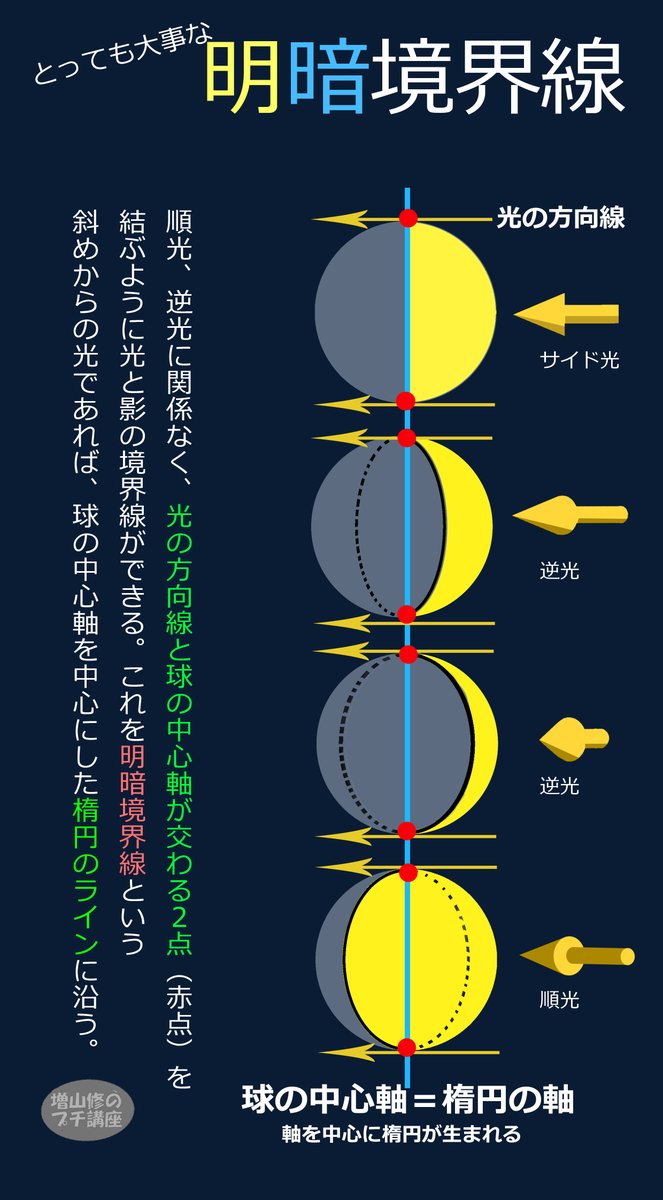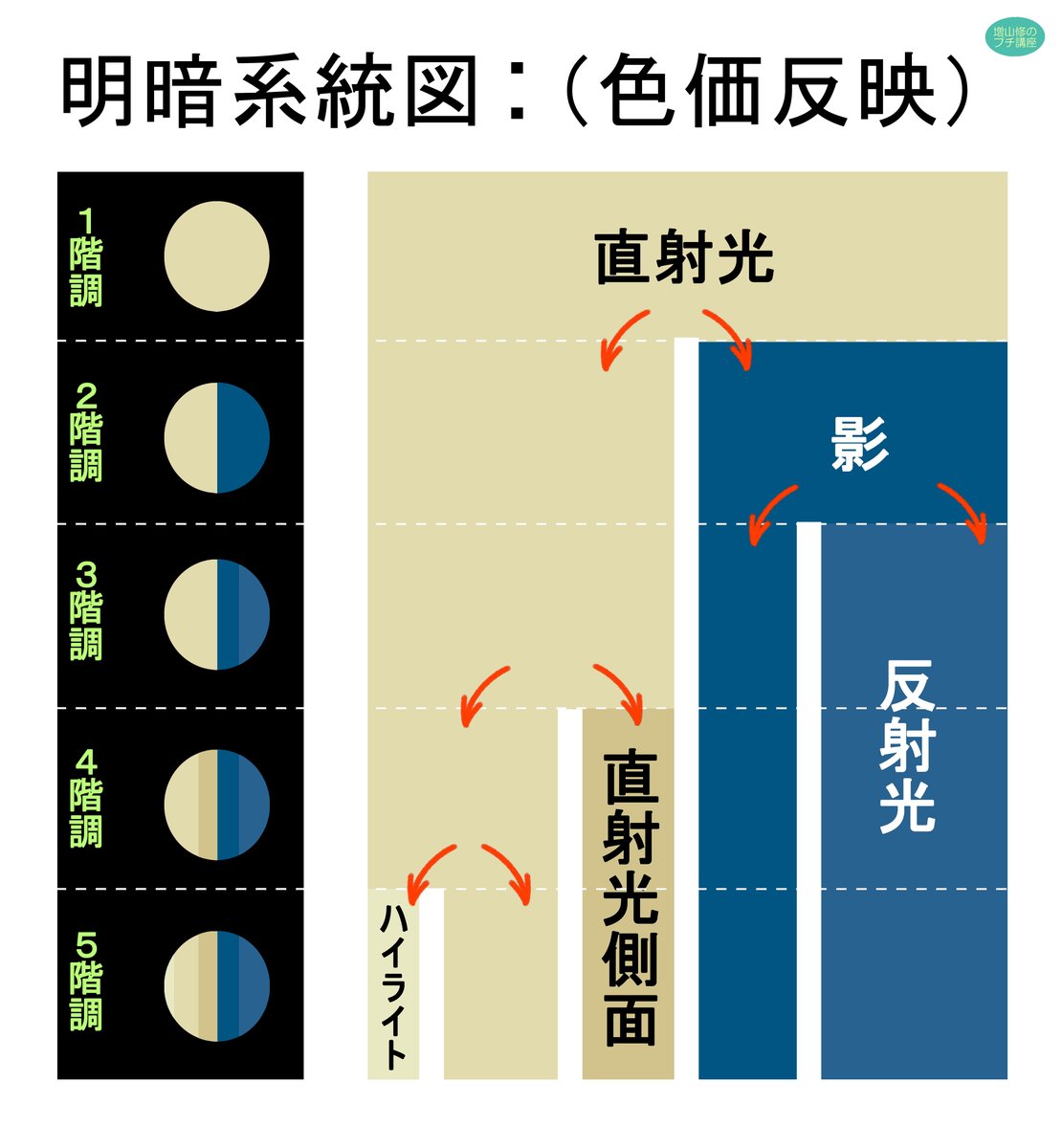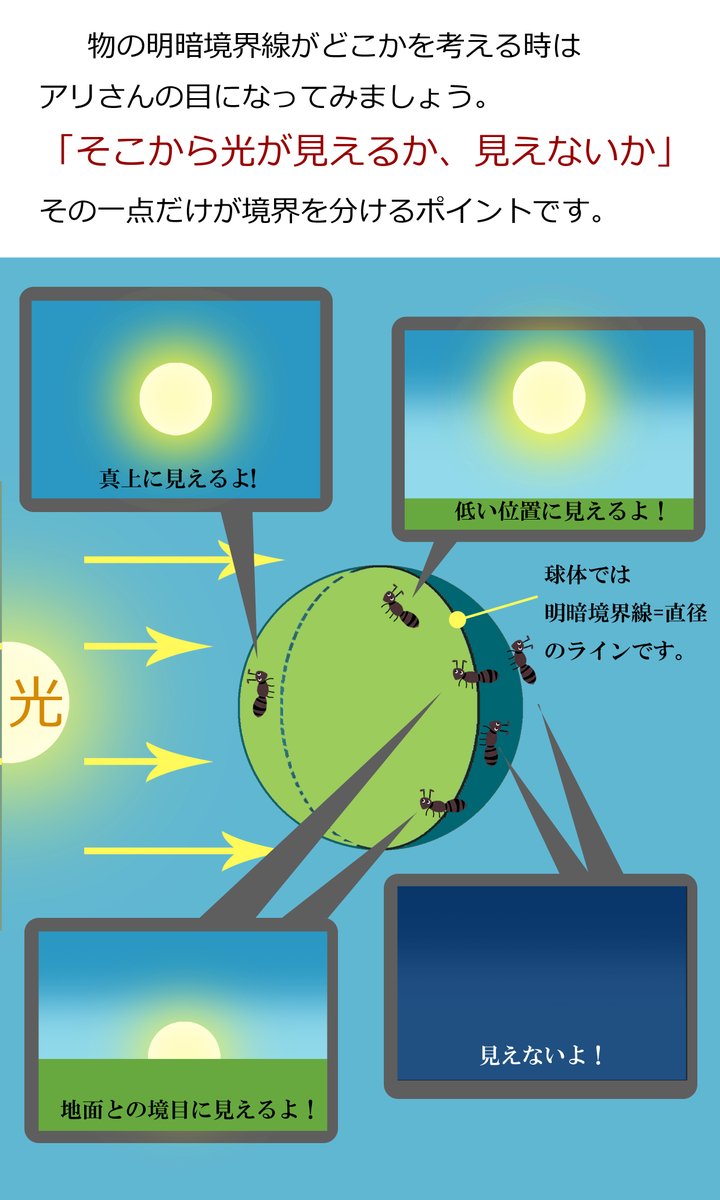232
235
237
238
239
240
絵具によるイメージボード
#背景美術 (再掲)
242
243
247
【朝日による光の変化】
アニメーション美術では1カット内で光の変化がある時、背景を2枚描きます。
デジタルではコピーできるので色だけ変えれば良いですが、絵具で描いていた頃は紙の収縮によってずれる場合があり、気を使いました。
#背景美術 #maiabys 背景:西俊樹(@shirakabausagi)
250