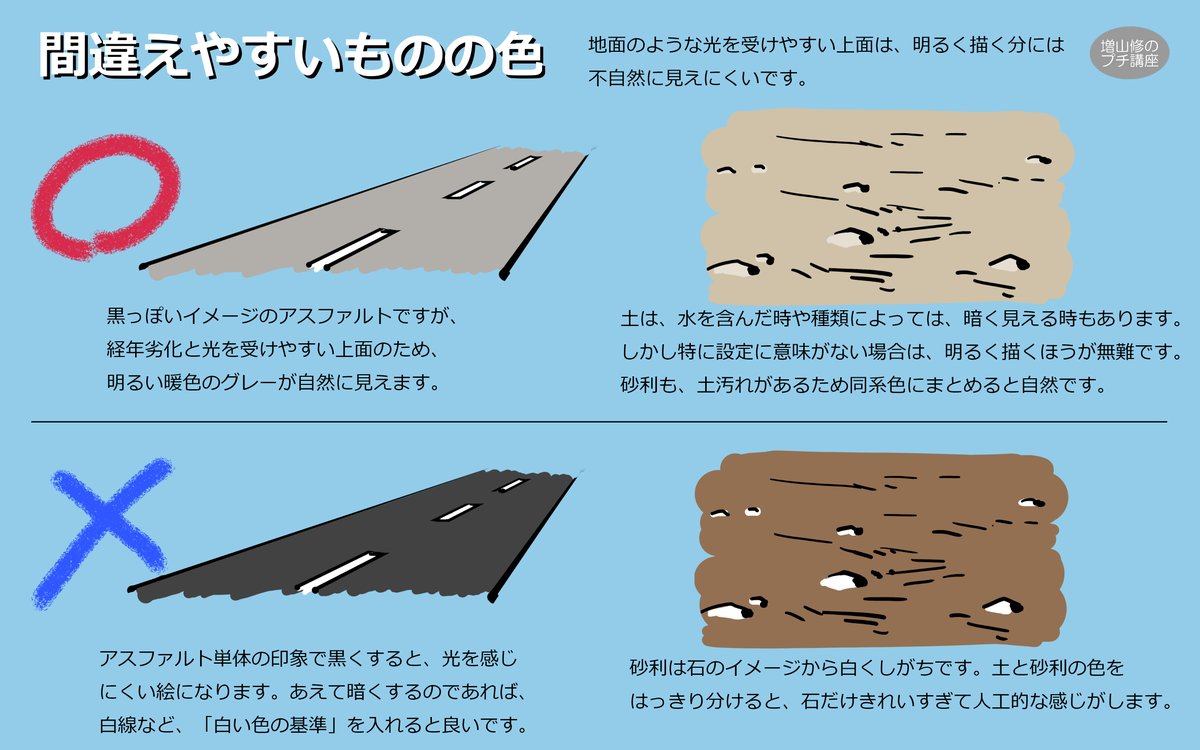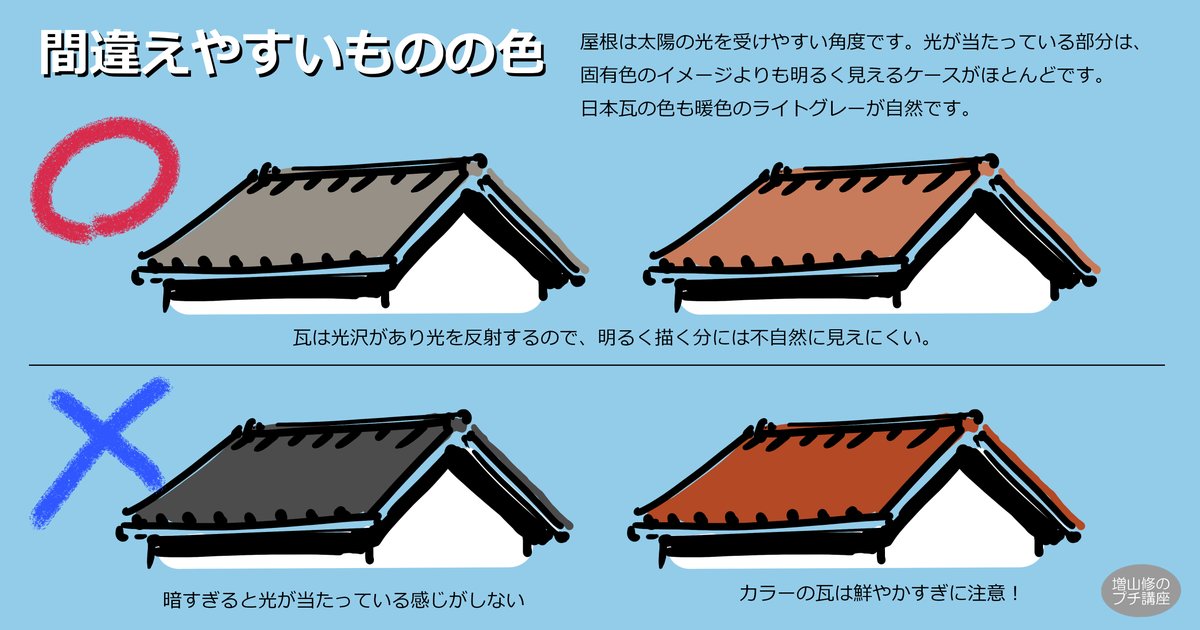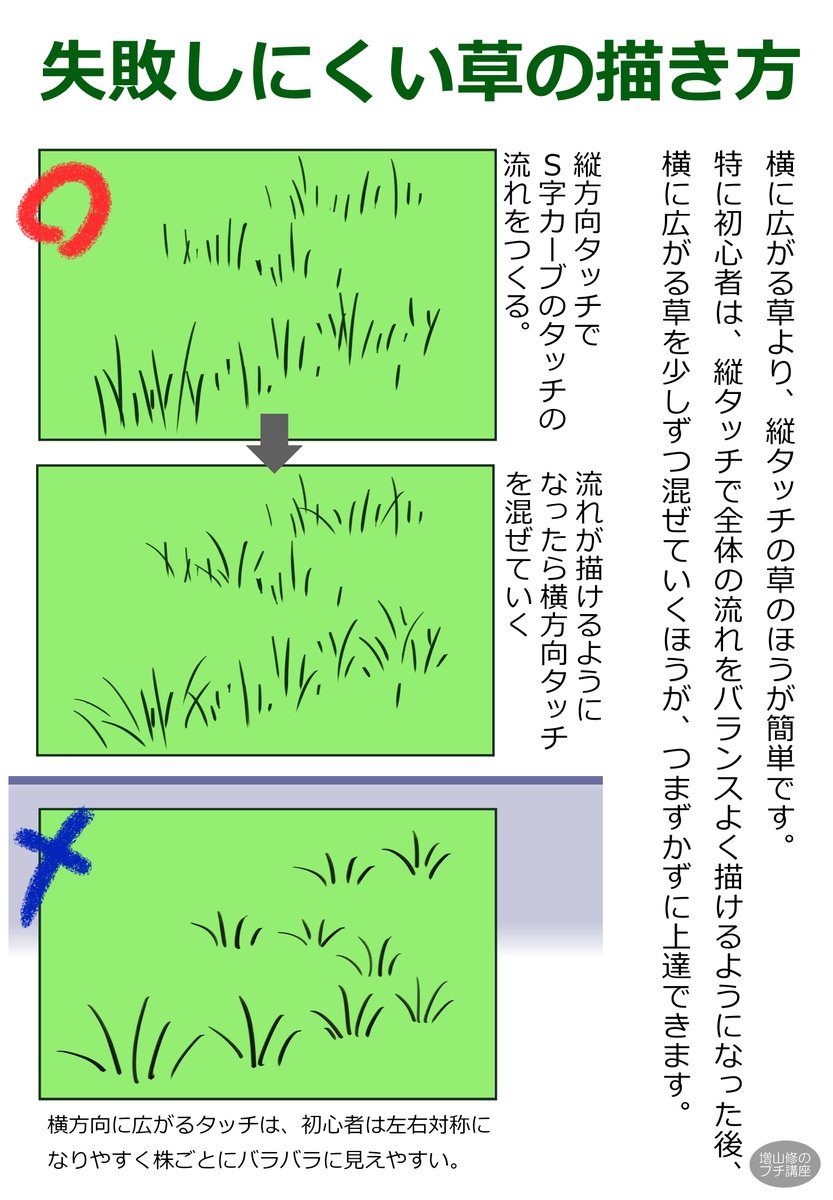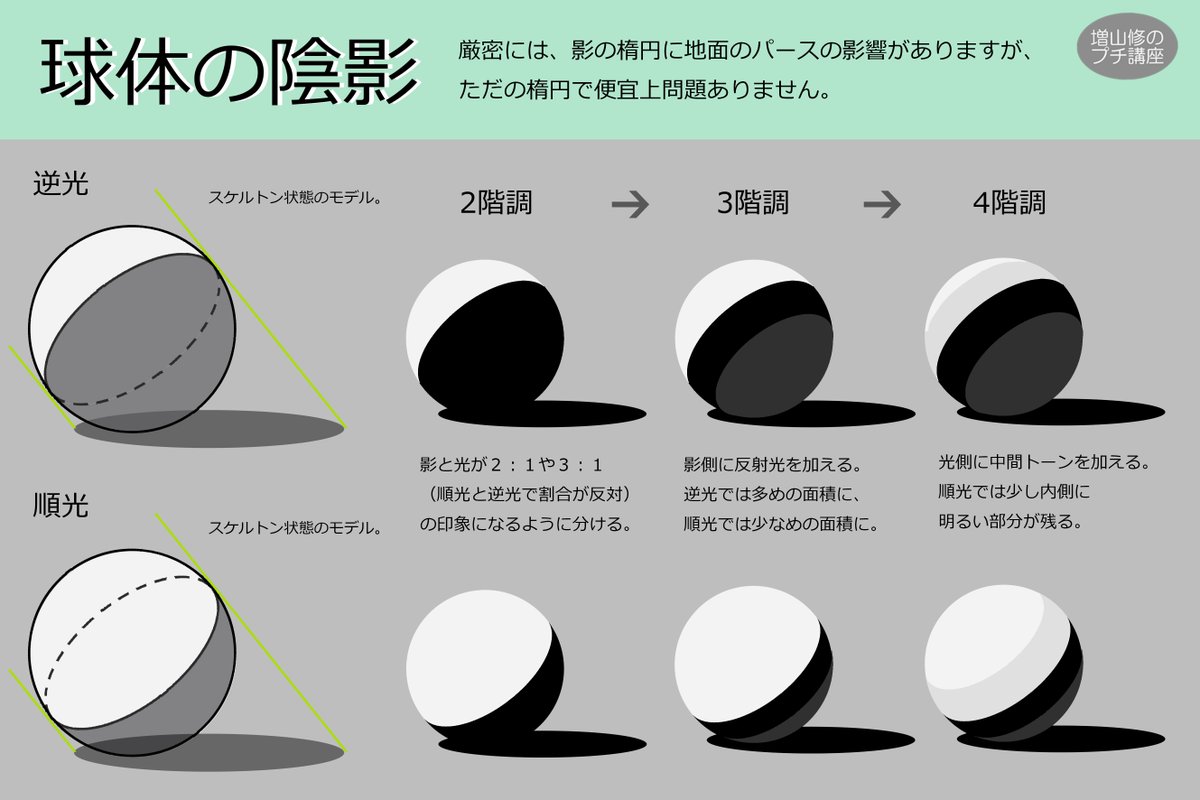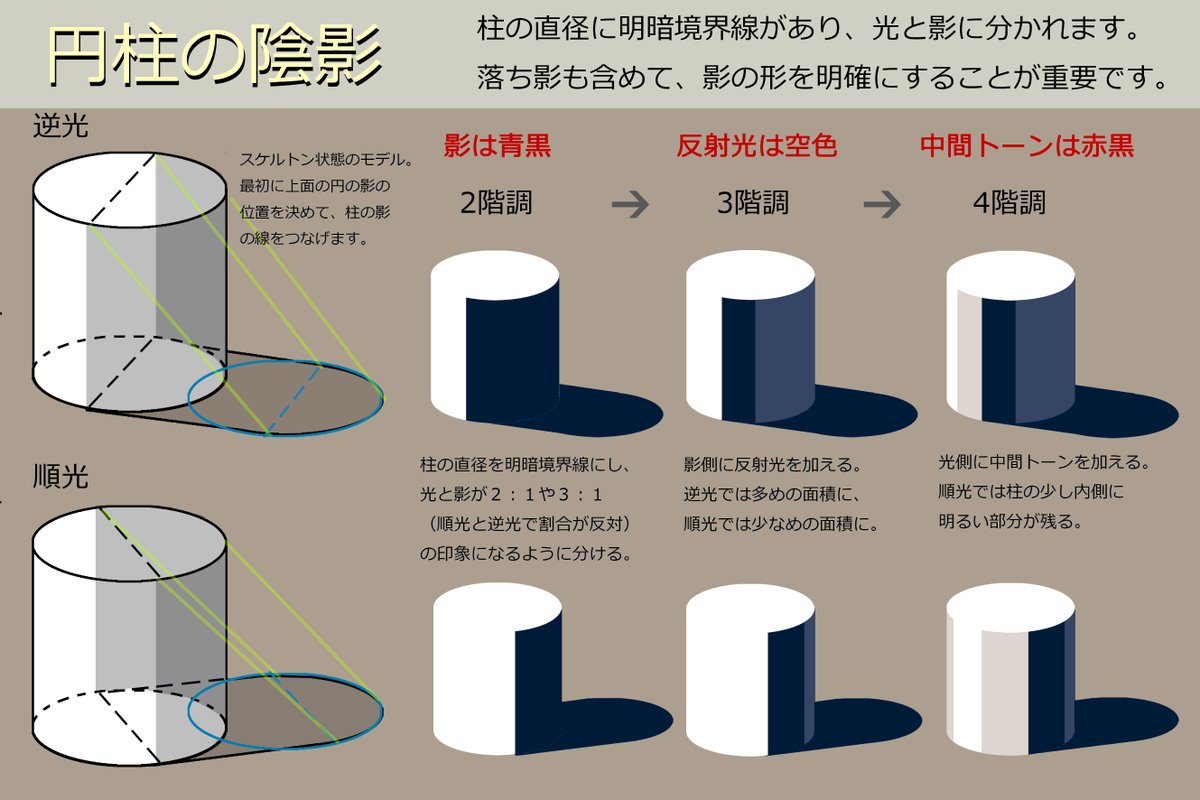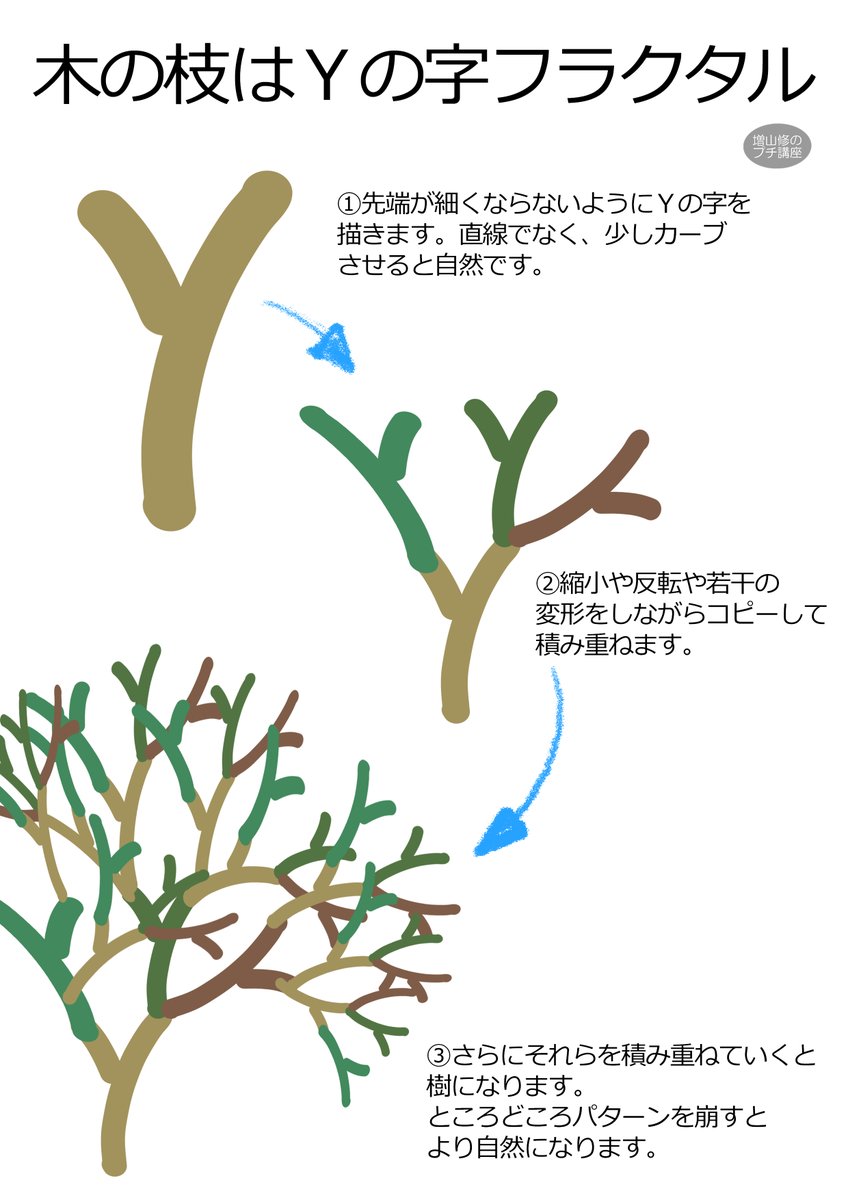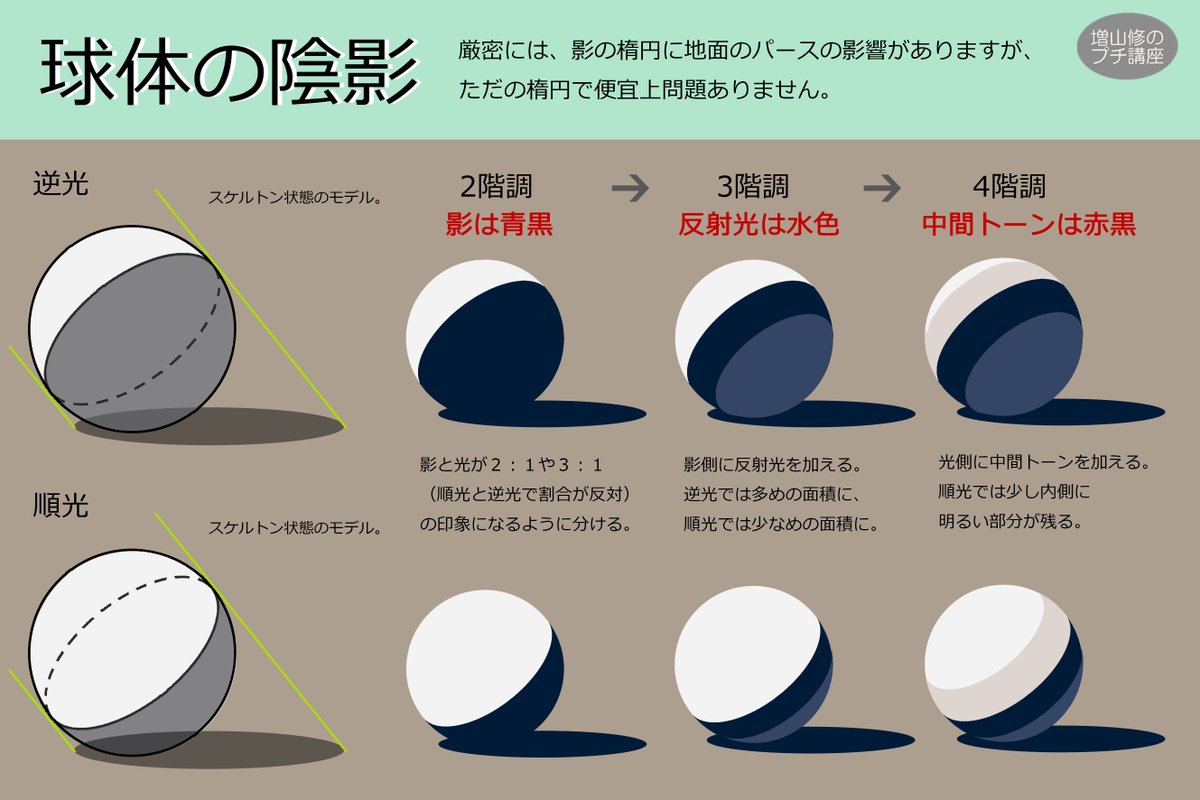252
【絵の情報量について】(再掲)
大事なのは
画面内の情報量でなく
観客に伝わる情報量
画面内の10の情報で
観客に1しか伝わらないと
情報量1
画面内の5の情報で
観客に5伝われば
情報量5
画面内の1の情報で
観客に10の想像を与えれば
情報量10
優れた絵やデザインほど後者になる
253
朝日を浴びる街
画面の中のもの全体が遠くにある場合、影の色は全体的に青みになります。近景がある場合はそれより暖色系になります。
#メイドインアビス #背景美術 背景:西俊樹(@shirakabausagi)
255
256
258
259
261
絵を描くということは、「手を動かすこと」と思われがちですが、「判断すること」が本質です。
263
絵の要素を突き詰めてみれば、「形」と「色」と「配置」になります。
上手く描けない時は、この要素ごとに見直してみましょう。
264
陰影で描く勉強からスタートした際に生まれやすいのは、”すべての物に立体感を付けなければ落ち着かない病”。
もしなってしまったら、暗い部分を塗りつぶしてみたり、明るいところを白とびさせてみましょう。
情報を少なくする部分を作ることで画面にメリハリが生まれます。
265
上手く描けない時はたいてい、本来シンプルな法則を自らバラバラに分解して、問題を複雑にしている時。
272
273
写真をベースに加筆するときのコツ。
ポイントは余計な情報を減らしていくこと。写真は細かいところまでグラデーションがあるので、そこをベタっぽく塗りつぶす必要があります。
特に光が当たっている側の情報量を減らすと良いです。
275
勉強開始
国語「あいうえおカキクケコ」
算数「1+1=2、2+2=4」
音楽「ドレミファソラシド」
習字「とめ、はね、はらい」
図工「自由に描いてね」
この差は一体・・?