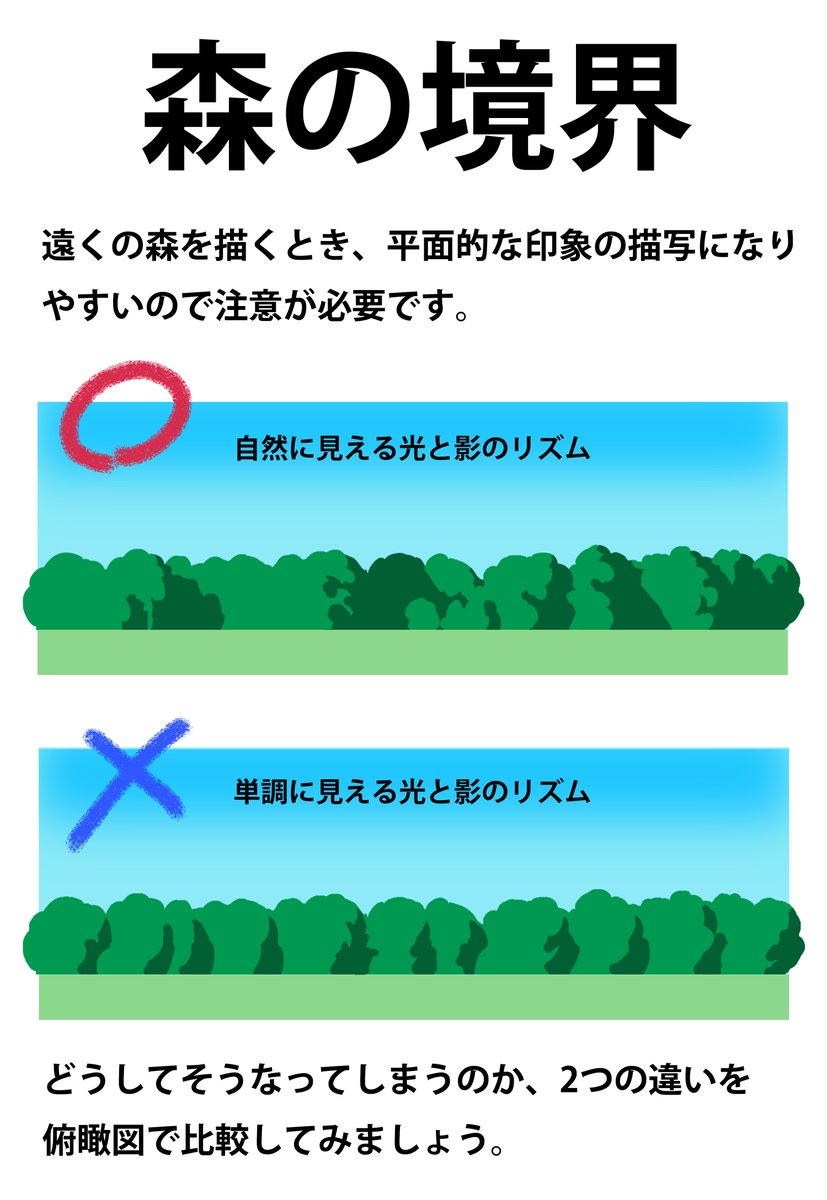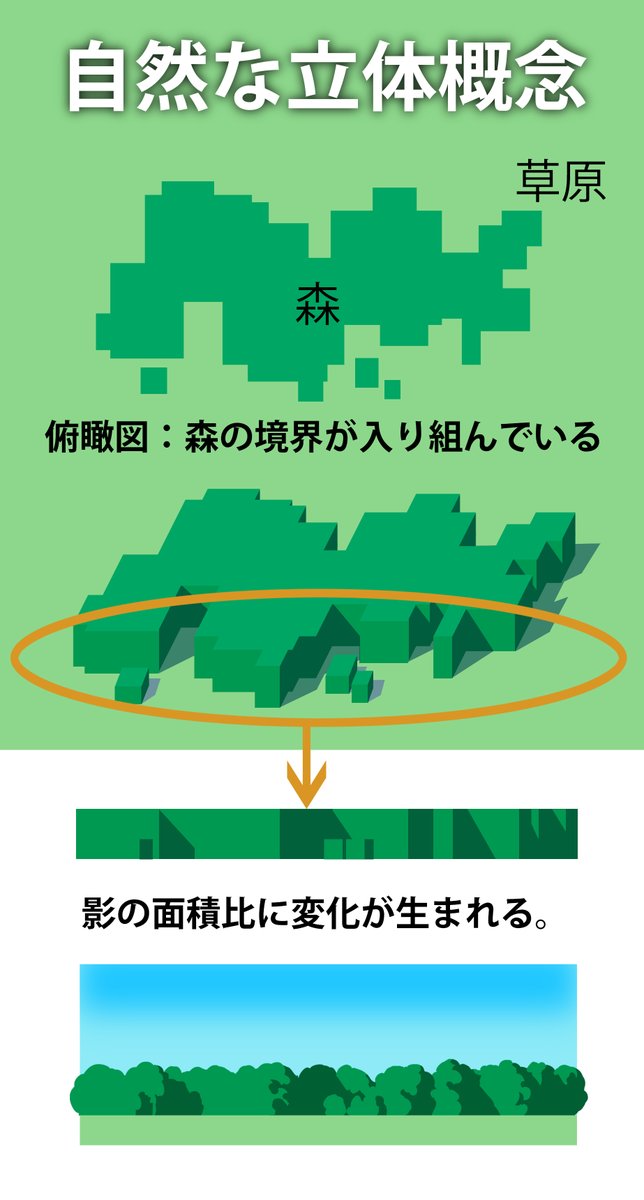277
夕方の水面
水底の絵に、水面の絵を半透明で重ね合わせて描かれています。
#背景美術
278
モチーフごとに意識が分断されると、画面全体のバランスが崩れやすくなります。
#背景美術
279
空気遠近
手前の木も遠くの山も、近くで見れば同じ葉の色です。
そこにブルーのフィルターを重ねることで、遠近感が生まれます。
#背景美術
280
ラフボード制作過程
手前のシルエットを一番暗い基準にして、中間のトーンを足していきます。
#背景美術 許可済
281
光の回折を描く時の注意点
明るい面に接する影部分に鮮やかな色が出ますが(鮮やか縁取り)、その際、細い窓の桟などは全体が染まります。
#背景美術
282
ラフボード制作過程
明るい固有色のベースに、ブルーブラックの影を乗算レイヤーで重ねて立体感を出します。そのあと空気遠近や入射光、ハイライトなどの要素を足します。
#背景美術 許可済
283
【ボカシのコツ】
目的によって、ボカシの種類を変えると良いです。さらにブラッシュアップしたい時は指先ツールなどを使います。
#背景美術
284
遠近表現 遠景は2階調にして情報量を少なくしています。
#背景美術 許可済
285
室内 ラフボード
調度品は、明暗を無理に面分けするのでなく、角のハイライトを強調することで面を描け、また艶も出せます。
#背景美術 許可済
287
【固有色の差による面表現】
白い石や漆喰部分を黄色で表示したもの。レンガや石組みを描くときに、はっきり固有色の違うパーツや汚れなどを入れることで、面の違いを出すことができます。その場合、光側と影側にまたがるように配置することがポイントです。
#背景美術 許可済
288
モチベーションは機械のようなもの。自ら学習という油をさし続けて問題意識を深化させなければ、やがて錆びついて止まる。
289
290
努力すること以上に、努力する方向を間違えないことのほうが難しい。
291
292
立体感や距離感を出すための工夫
#背景美術 許可済
293
【光の回折】
光源や明るい空に接する影面は、光が干渉して色が変わります。
明度をほとんど上げることなく、色相と彩度を調整するのがコツです。またその際、輪郭をぼかす必要はありません。
#背景美術
294
光芒の作り方と、その応用例
#背景美術 許可済
295
色の意味。大抵の場合、1から順に必要に応じて階調を増やしていきます。
#背景美術
296
画面内に光源があると、そこに接する部分も光の影響で色が変化して見えます。(光の回折)ここではふちにピンク系を使っています。
#背景美術 許可済
297
俯瞰は距離感が出にくいアングルですが、落ち影によって「遠近を意味づける」ことができます。
#背景美術 許可済
298
夜の風景を描くとき、空や遠くを真っ暗にしてしまう人がいます。
太陽の光が月の光に変わっただけですので、基本的には昼と同じように考えましょう。
すなわち(照明が当たらなければ)空より建物のほうが暗く、空気遠近によって遠くが淡くなります。
#背景美術 許可済
299
300
【色価】秋色で影色の変化を見てみましょう
#背景美術