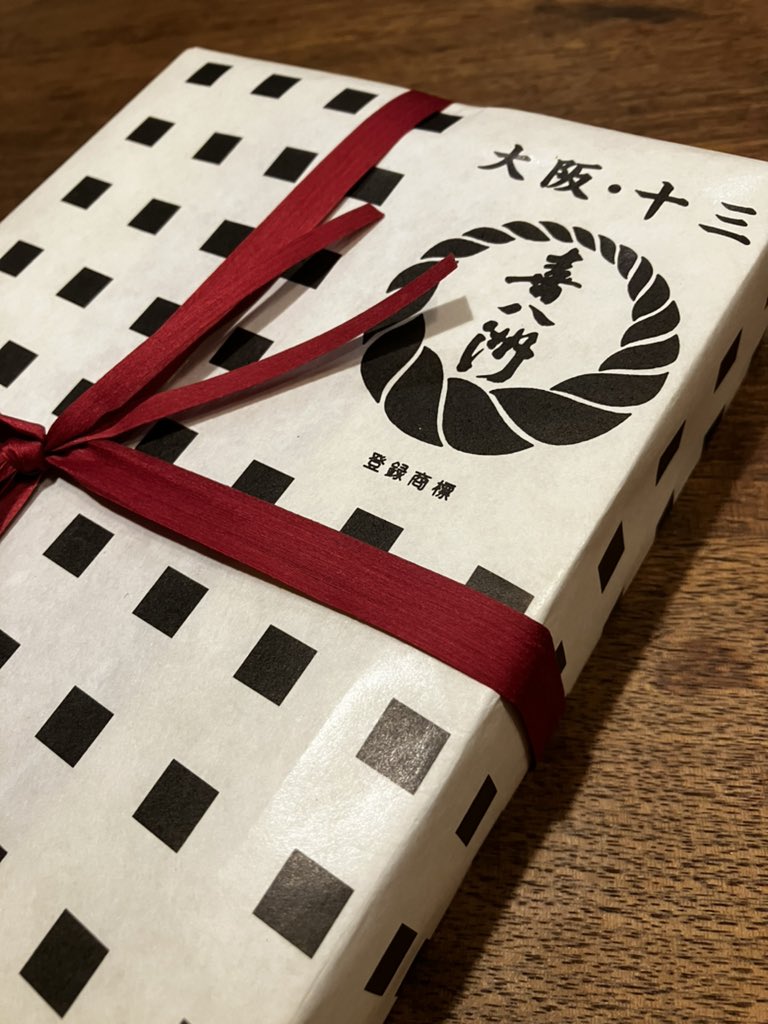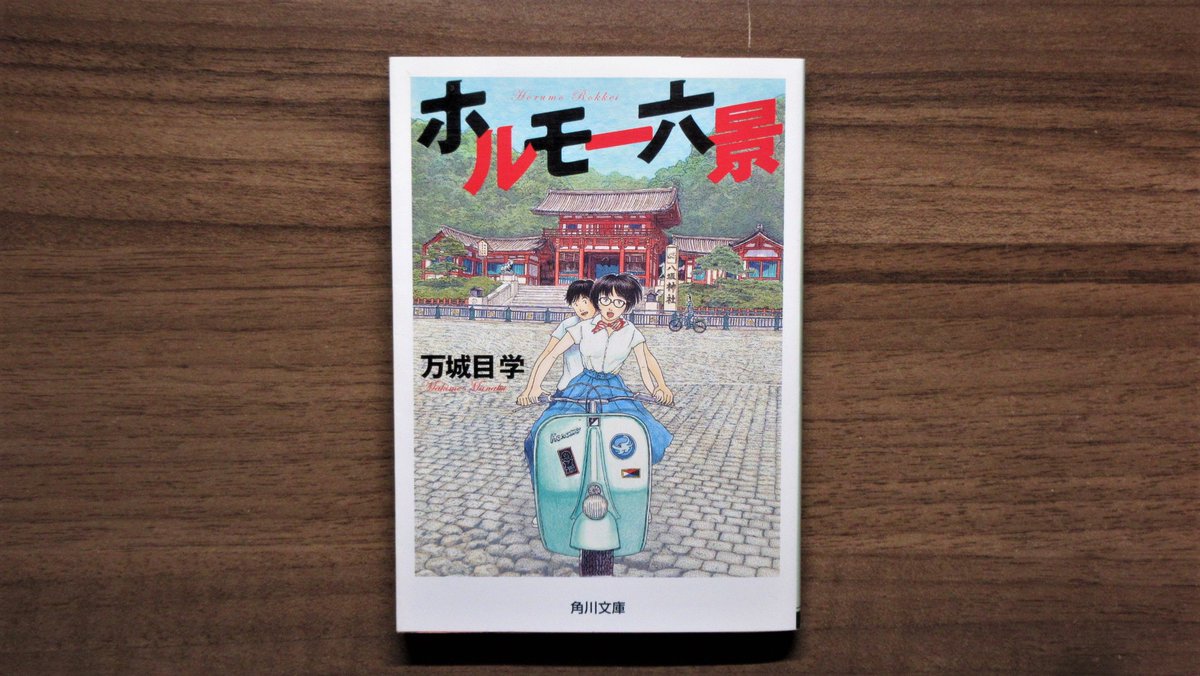151
『夜は短し歩けよ乙女』の舞台を観てきました。フィクション永久機関の充実の仕事ぶりを目の当たりにするとともに、改めて作者の森見登美彦氏は会っても3回に1回は「体調イマイチなんでコーラにします」とか言っているのに、なぜこんなおいしそうなお酒の描写ができてしまうのか、ほんと不思議。
152
図書館の新作の貸し出しについては、寛容であろうと思っています。文化の多様性を支える一翼でありたいからです。でも、これをやられると、やはり心が冷えます。もしも、すべての図書館がこのやり方で本を集め、タダで貸し続けたら、作家は死にます。city.takaoka.toyama.jp/library/riyo/k…
153
当時の状況を補足しますと、京都市内ではテレビ大阪が受信できず、「エヴァンゲリオンなるものがはやっている」という情報は回るも、誰もその中身をリアルタイムで見ておらず、正月実家に帰り、3日間の年末テレビ大阪全編一挙放送を見た者だけが映画に進むという、非常に限られた需要だったのでした。
154
本日、39歳になりました。人間誰しもよわいを重ねると、「むかしジャックナイフ、いまバターナイフ」と丸みを帯びていくものですが、同じ学年、同じ誕生日(らしい)声優の田村ゆかりさんが本日17歳になったというのを聞き、人はいつまでもジャックナイフでいられるのだと勇気づけられましたね。
156
京都祇園にて、今年も森見登美彦氏とヨーロッパ企画上田誠氏と忘年会を開催す。心に矢傷を負い、弱り気味の私を、二人があやしげなアルカイックスマイルで励まし、また来年さらなる矢傷を負うことを期待されながら、深夜二時の川端四条交差点でお別れする。八時間よくしゃべることあったものですナア。
157
160
本来明日締め切りの原稿を引き延ばしてもらわんと担当編集者にメールし、その理由を「御社社長のことで全然原稿に手がつかない日が発生してしまったため」と付記してみた。完全無抵抗で締め切りが延びた。私も大人げなかったかもしれない。締め切り攻防戦、それは作家と編集者のだましだまされの戦い。
161
大阪駅。
162
小島監督と話していると「まっつさん、ええ人なんですわー」(まっつ=マッツ・ミケルセン)、「じぇーじぇー、すぐメール返してくれはるから」(じぇーじぇー=JJエイブラムス)などなど、世界のVIPが謎の近所のおっさん化する瞬間があります。小島さんご自慢のカメラがうなりを上げている模様。
163
大阪の友人の親族がコロナに罹患したとの知らせを聞き、電話で詳しく状況を聞くに、昨日PCR検査陽性で多少の息苦しさがある状態でも即時入院とはならず、役所からの連絡待ち、役所は今もパンク状態で連絡に2,3日かかると言われたとのこと、一気に生々しさが増す。
164
【京都へ】最後の紹介は、ふたたび頭に舞い戻っての『ホルモー六景』。恒例の左京区から鴨川、祇園を経て、京田辺、伏見稲荷、さらにははるか東京丸の内まで。ついでに時空もしばしば超えるかも。そうそう、今年はこの「六景」執筆以来、13年ぶりに現代の京都を舞台にした作品を書く予定です。#読書旅
165
166
自分に漢文の授業が必要だったか否か。その答えを知ったのは『悟浄出立』を書いたときでした。漢文の授業がなければ、司馬遷の「虞や虞や」の原文に触れることもなく、作品も生まれなかった。高校生のとき自分が小説家になるなんてゆめ思いませんでした。20年以上経って芽吹く。そんな学びもあります。
167
「病院で検査をしてもとくに体に異常は見つからないのに、のどに何かつまった感じがする方におすすめ」って、そんなピンポイントな薬あるのかよと。半夏厚朴湯。まるで夢の中で花が咲く、その種を薬で渡されたような不思議さです。
169
「スター・ウォーズ」EP1でアナキンがC3POを作ったのはおかしい、EP4~6で再会したとき、いくら何でも本人なら覚えているだろう、と長年難癖をつけていたわけですが、EP6まで見直し、何とベイダー卿はC3POと1秒も顔を合わせていないことが判明しました。ごめんなさい、ルーカス。
170
静岡マルイ閉店と聞き、静岡で働いていたとき、1Fに入っていたキルフェボン(静岡発祥でマルイから少し離れた細い路地の小さな店からスタート)に行ったこと思い出しました。キルフェボンかフェルキボンか覚えるのに3年くらいかかり、ひょっとしたらここからしゅららぼんが来ているのかもしれない。
171
四階のテナントを借りているから「四条さん」と自分で名付けたのに、「肆」のプレートを見て、「ええと四条さん、何階の人やったっけ?」と本気で読み方を考える。#バベル九朔第1話の思い出
172
かつて「森見登美彦氏が8割、僕が2割で京都を焼け野原にした」と発言した私であるが、「現代を舞台に小説を書く隙間がないので、戦国時代の物語を書いた」という文脈上での表現であった。されどその後、創作における「京都」はますますその世界を広げ、様々な書き手がそれぞれの京都を描き今に至る。
174
ちなみに私は小説の連載の仕事を受けるのは、常に一本だけにしています。それは小学生の頃に『まんが道』を愛読し、売れっ子になった二人が次々と依頼を引き受け、結果盛大にパンクして、全部連載を落としてしまうシーンのおそろしさに震え上がり、「無理はアカン!」と脳髄まで刷りこまれたせいです。
175