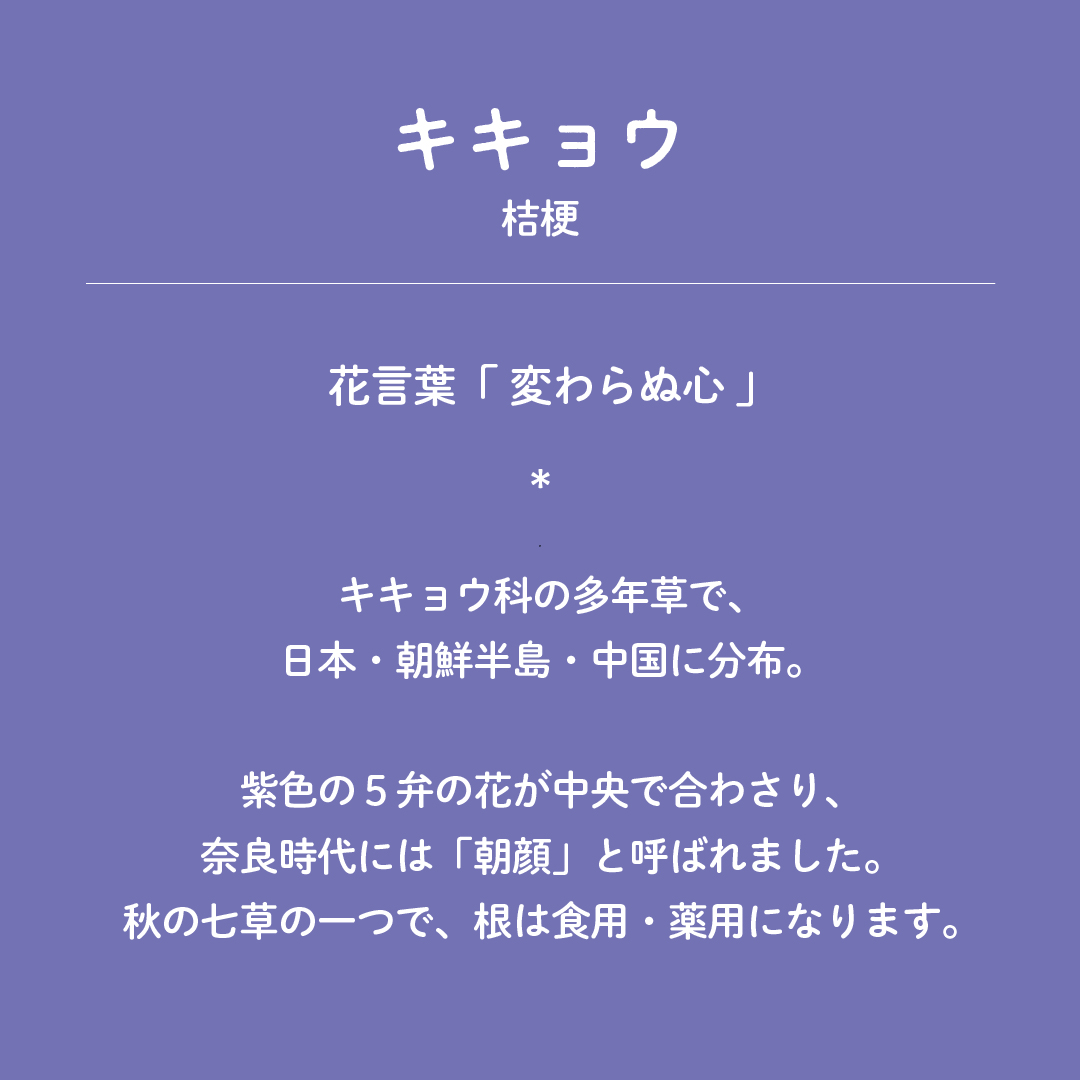1326
1327
裏葉色(うらはいろ)|にっぽんのいろ
葉の裏の色。繊細な感性を持つ日本人らしい色名ですね(^^)
夏の日差しのもと、葉の表と裏のコントラストが際立ち、その美しさに思わず見とれてしまいます。
▼1日1つ、季節のお話を配信中♪
543life.com(暦図鑑)
1328
【季節湯(きせつゆ)】
旬の植物を湯船に浮かべることで、その力を享受しながら季節の変化を楽しむ、日本に古くから伝わる入浴文化です。
平安時代に弘法大師・空海が医療用の薬湯として「薬草風呂」を広めたのがルーツとされています。
どくだみ湯|今日の読み物
543life.com/shun/post20210…
1329
8月8日(旧7月11日)の月曜日。
七十二候は「涼風至(すずかぜいたる)」へ。
立秋は小さな秋の誕生であると同時に、夏のピーク。
日中はまだまだ暑いですが、朝や夕、ふと涼しさを感じ、秋の気配が少しずつ漂い始めます。
和暦研究家の高月美樹さん(@takatsukimiki)
543life.com/seasons24/post…
1330
5月9日(旧暦4月17日)の土曜日
新茶(しんちゃ)|旬のもの
冬の間に栄養をしっかり蓄え、あたたかくなると蓄えた栄養が枝の先端へ送られるので、芽吹く頃にはうまみがギュッと凝縮された新茶ができあがります。
ライターの松下恭子さん(@kyoko_toirodori)
543life.com/shun/post20200…
1331
3月15日(旧2月3日)の月曜日。
今日の読み物は、七十二候「菜虫化蝶(なむしちょうとなる)」。
アブラナ科の野菜を食べられるのは、じつはモンシロチョウの幼虫だけだそう。そこには、意外な秘密がありました。
ライターは和暦研究家の高月美樹さん(@takatsukimiki)。
543life.com/seasons24/post…
1332
御召茶(おめしちゃ)|#にっぽんのいろ
落ち着きのある、緑みの深い青色。
11代将軍である徳川家斉(いえなり)が愛用した高級縮緬の色とされ、御召料と呼ばれた縮緬が、そのまま色名になりました。
とても好きな色です♪
4月のいろ #にっぽんのいろ|暦生活
543life.com/nipponnoiropal…
1333
洗朱(あらいしゅ)|#にっぽんのいろ
清らかで深い朱色が魅力的。
明治時代後期、日本文化を大切にしようとする意識の高まりとともに生まれました。
澄んだ朱を生み出すために繰り返す「朱を洗う」作業が色名の語源とされています。
3月のにっぽんのいろをまとめました。
543life.com/nipponnoiropal…
1334
今日の誕生花は「キキョウ/桔梗」。
花言葉は「変わらぬ心」です。
紫色の5弁の花が中央で合わさり、奈良時代には「朝顔」と呼ばれました。
秋の七草の一つで、根は食用・薬用になります。
『誕生花日めくり 2023』ができました💐
543life.net/?pid=169491549
1335
8月2日(旧7月5日)の火曜日。
七十二候は「大雨時行(たいうときどきふる)」を迎えました。
雷や夕立も多くなり、これから9月にかけて次々に台風がやってきます。台風は昔は「野分(のわき)」と呼ばれていました。
和暦研究家の高月美樹さん(@takatsukimiki)
543life.com/seasons24/post…
1336
おはようございます♪
7月2日(旧5月12日)の木曜日。
半夏生(はんげしょうず)|七十二候
半夏は、カラスビシャクというサトイモ科の薬草。
農家はこの日までに田植えを終え、休みをとりました。梅雨のさなかで、雨の多いときでもあります。
暦生活編集部(@543life)
543life.com/seasons24/post…
1337
鉛白(えんぱく)|#にっぽんのいろ
少し灰色を帯びた白が、真夏の空の入道雲を思わせるよう。
塩基性炭酸鉛という鉛の化合物を原料とし、白色の重要な顔料として古来、重宝されてきました。古くは顔に塗る白粉(おしろい)にも用いられたそうです。
8月「にっぽんのいろ」
543life.com/nipponnoiropal…
1338
葉緑色(ようりょくしょく)|#にっぽんのいろ
「葉」と「緑」という似た意味の言葉を繰り返すことで、よりいっそう緑っぽさが際立っています。
梅雨の雨で濡れた、深く生い茂る木々の葉のような緑は、少し心を癒してくれるようです。
6月「にっぽんのいろ」はこちらから
543life.com/nipponnoiropal…
1339
藤黄(とうおう)|#にっぽんのいろ
日の光のようにあざやかな黄色。
日本画や友禅染めで使われてきた、とても美しい色です。眺めていると、そっと寄り添い支えてくれるような不思議な気持ちになります。
5月のいろ #にっぽんのいろ|暦生活
543life.com/nipponnoiropal…
1340
本紫(ほんむらさき)|#にっぽんのいろ
紫根(しこん)染の手法で染めた紫。
紫の染色は手間もかかり非常に高価なものだったそうです。一般庶民は禁じられ、茜や蘇芳などの代用品で染めた「似紫(にせむらさき)」が流行しました。
4月のにっぽんのいろ、ご覧ください。
543life.com/nipponnoiropal…
1341
江戸紫(えどむらさき)|にっぽんのいろ
青みの強い美しい紫色。江戸っ子が愛し、守ってきた色です。当時流行していた渋めの紫「古代紫」に対抗して名付けられました。
▼8月の色まとめはこちらから♪
543life.com/nipponnoiropal…
1342
柑子色(こうじいろ)|#にっぽんのいろ
温かみのある橙色。
柑子とは、日本で古くから栽培されてきたミカンの一種です。柑子色は、柑子の果皮に由来し、クチナシと紅花などを合わせて染めると伝えられています。
優しい色をしていますね。
543life.com/nipponnoiropal…
10月のいろ|暦生活
1343
8月19日(旧7月12日)の木曜日。
とても美しいハト「アオバト」。
全身が緑色で、オスは羽が紫色。ふだんは山の森に棲んでいますが、毎日何十㎞もの距離を飛び、海水を飲みに海へやってきます。
科学ジャーナリスト・サイエンスライターの柴田佳秀さん(@shibalabo)
543life.com/shun/post20210…
1344
今日は、お釈迦さまがお生まれになった日を祝う「灌仏会(かんぶつえ)/花まつり」。
"甘茶は、お釈迦さまがお生まれになったとき、天から降り注いだという祝福の甘い雨をあらわしています。"
記事を書いてくださったのは僧侶の小島杏子さん(@kaminouenokumo)2020/4/8
543life.com/koyomi/post202…
1345
10月9日(旧8月23日)の金曜日
日本で冬を越すために、雁がやってきます。
大空を群れで飛ぶ雁の姿は美しく、昔から様々な文学作品に登場し、絵画の題材にも取り上げられてきました。
暦生活編集部(@543life)
▼「鴻雁来(こうがんきたる)」について、もっと読む。
543life.com/seasons24/post…
1346
10月13日(旧9月8日)の水曜日。
七十二候は、「菊花開(きくのはなひらく)」に。
菊というと栽培品種を思い浮かべるかもしれませんが、野生の菊の美しさはまた格別です。
今回は、そんな野辺に咲く菊たちをご紹介します。
和暦研究家の高月美樹さん(@takatsukimiki)
543life.com/seasons24/post…
1347
1月5日(旧12月3日)の水曜日。
新しい年が明け、今年最初の二十四節気は「小寒(しょうかん)」です。
ここから寒の入りを迎え寒さが厳しくなりますが、そんな季節は七草粥を食べ、温かくして過ごしたいですね(*^^*)
イラストレーター、エッセイストの平野恵理子さん
543life.com/seasons24/post…
1348
緑青色(ろくしょういろ)|#にっぽんのいろ
「緑青」は孔雀石(くじゃくせき/マラカイト)を砕いた顔料で、その緑色を緑青色(ろくしょういろ)といいます。歴史は古く、飛鳥時代に中国から伝わってきたとされています。
5月「にっぽんのいろ」はこちらからご覧ください。
543life.com/nipponnoiropal…
1349
紅絹(もみ)|#にっぽんのいろ
力強さを感じさせる紅赤。
鬱金(うこん)やクチナシで黄色に染めた後、紅花で染めたあざやかな色。紅花を包んだ袋を揉み、色を出したことから名付けられました。
4月のいろ #にっぽんのいろ|特集|暦生活
543life.com/nipponnoiropal…
1350
今日は、昨日に続いて「一粒万倍日」です。
"お金に限らず、どんな小さな一歩もいつか大きく実るのだと思えると、うれしくなります。一粒万倍日は「自分の可能性を信じたくなる日」だと、わたしは解釈しました。"(読み物「一粒万倍日」より)
543life.com/koyomi/post202…
読み物「一粒万倍日」