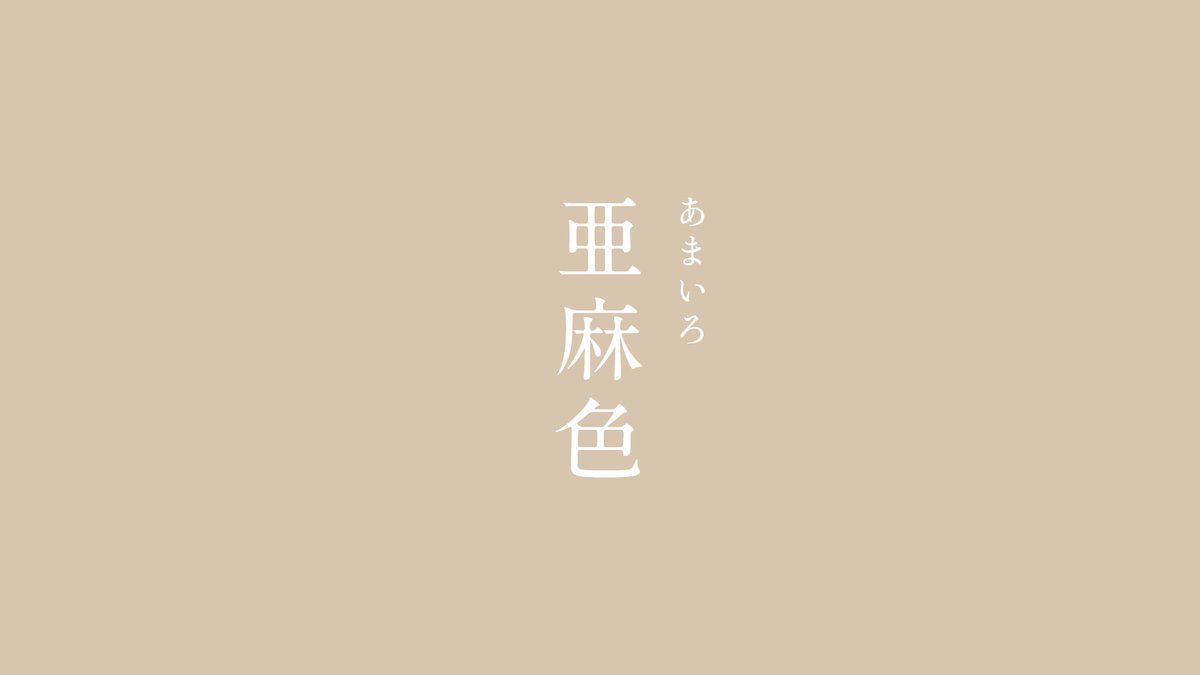976
8月1日(旧6月23日)の日曜日。
今日は「花火の日」。
日本で最初に花火を見たのは、徳川家康だといわれています。今も昔も、日本の夏に欠かせない、大切な風物詩ですね。
花火の日に、花火の由来や歴史をご紹介します(*^^*)
ライターの松下恭子さん(@kyoko_toirodori)
543life.com/shun/post20210…
977
緋色(ひいろ)|にっぽんのいろ
少し黄みがかった明るい赤色です。
赤は古来より神聖な色とされ、太陽、火、血を象徴する色でした。今も巫女装束として、緋袴が用いられています。
▼暦生活の暦図鑑
543life.com
▼にっぽんのいろのインスタ
instagram.com/nipponnoiro/
978
6月10日(旧5月12日)の金曜日。
今日は「時の記念日」。
671年、天智天皇が「漏刻」という水時計を建造し、時を知らせる儀式を行い、日本ではじめて正式な「時」が刻まれ始めました。
今日は「時」について考える日に。
巫女ライターの紺野うみさん(@konnoumi)
543life.com/koyomi/post202…
979
銀色(ぎんいろ)|にっぽんのいろ
銀は、古来から金に次いで貴重な金属であり、金は太陽、銀は月にたとえられ、並び称されてきました。冬が深まり、雪が降り積もると、あたりいちめん美しい銀世界に変えます。
▼12月の色まとめはこちらから♪
543life.com/nipponnoiropal…
980
緋色(ひいろ/あけいろ)|#にっぽんのいろ
茜と灰汁(あく)で染められ、ほんのり黄色を帯びています。
奈良時代の『養老律令(ようろうりつりょう)』では紫色に次ぐ上位の色とされ、身分の高い人々だけが身に付ける色でした。
▶︎ 4月「にっぽんのいろ」はこちら
543life.com/nipponnoiropal…
981
日本には、二千年蓮と呼ばれる「大賀蓮」がありますが、これは二千年前の弥生時代の種を、大賀一郎という植物学者が発芽させたもの。二千年前の種が発芽し、花を咲かせるなんて驚きです。なんという生命の神秘。大賀蓮、ぜひとも一度この目で見てみたくなりました。
▼つづき
543life.com/seasons24/post…
982
今日も昨日に引き続き「一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)」です。
一粒とは、お米のこと。この日に蒔いた籾(もみ)は万倍にもなって実ることから、縁起がいい日として知られています。
今日をいい日にしていけたらいいですね♪
543life.com/goodday/
日本の吉日をご紹介します。.:*・゜
983
4月4日(旧2月23日)の日曜日。
二十四節気は、今日から「清明(せいめい)」になりました。
草木が芽吹き、花が咲いて、いよいよ春爛漫。これからは万物がぐんぐんと伸び栄えるとき。
ライターはイラストレーター、エッセイストの平野恵理子さん。
ぜひご覧ください♪
543life.com/seasons24/post…
984
桃色(ももいろ)|#にっぽんのいろ
春を彩る桃の花のような、ほんのり薄いピンク色。
淡い紅色は、桃の花で染めたのではなく、紅花や蘇芳(すおう)を染料に使って、桃の花の色を再現しました。
3月のにっぽんのいろをまとめました。
543life.com/nipponnoiropal…
985
薄浅葱(うすあさぎ)|にっぽんのいろ
浅葱色をさらに薄くした爽やかな色。
涼しげな印象を受ける、夏にぴったりな色ですね。
▼7月の色まとめはこちらから♪
543life.com/nipponnoiropal…
986
相思鼠(そうしねず)|にっぽんのいろ
名前の由来となった相思鳥(そうしちょう)はスズメ目の美しい小鳥。
身を寄せ合って羽づくろいし合う様子からその名前がついたそう。
▼7月の色まとめはこちらから♪
543life.com/nipponnoiropal…
987
深縹(こきはなだ)|にっぽんのいろ
「ふかきはなだ」とも読まれる、とても古くからある色です。藍染の中でももっとも濃く、わずかに紫も含んでいます。平安時代から鎌倉時代にかけ、おもに男性の服の色として用いられてきました。
▼7月の色まとめはこちらから♪
543life.com/nipponnoiropal…
988
猩々緋(しょうじょうひ)|#にっぽんのいろ
「猩々」とは中国の空想上の生き物で、猿のような姿をしています。その血は濃い赤色とされ、インドでは染め物の染料として使われていると信じられていました。
●にっぽんのいろ日めくり(限定発売)
543life.com/np2021/
#365日にっぽんのいろ図鑑
989
4月9日(旧暦3月17日)の木曜日
鴻雁北(こうがんかえる)|七十二候
冬の間を日本で過ごしていた雁(がん)が北国へ去っていくころ。
"また元気に、日本にやってきて欲しいなと心から思います。
また会える日まで、しばしのお別れですね。"
暦生活編集部(@543life)
543life.com/seasons24/post…
990
藍鉄色(あいてついろ)|#にっぽんのいろ
青を重ねた藍色と、深く沈んだ鉄色を混ぜることから生まれました。江戸時代を代表する人気色です。
掛け合わせによって青寄りにも緑寄りにもなる、夏の森のような美しい色です。
『【2023年】にっぽんのいろ日めくり』はこちら。
543life.net/?pid=169491526
991
葵色(あおいいろ)|#にっぽんのいろ
葵の花のような、優しい紫色。
高貴な印象を抱く紫ですが、葵色は馴染み深く、暮らしの中にも取り入れやすい色です。梅雨の雨に映える、美しい色。
6月のいろ #にっぽんのいろ|暦生活
543life.com/nipponnoiropal…
992
藍鉄色(あいてついろ)|#にっぽんのいろ
深く渋い青緑色です。力強く青を重ねた藍色と深く沈んだ鉄色を混ぜることから生み出されました。江戸時代を代表する人気色です。
掛け合わせによって青寄りにも緑寄りにもなる、夏の森のような美しい色です。
8月のいろ|暦生活
543life.com/nipponnoiropal…
993
今日は「八十八夜(はちじゅうはちや)」。
立春から数えて、88日目。
「八十八夜の別れ霜」というように、農家にとっては怖い遅霜の時期でもあります。
昔から八十八夜は茶摘みや籾まきなどの目安とされてきました。もうすぐ立夏。季節は夏を迎えます。
読み物「八十八夜」
543life.com/koyomi/post202…
994
1月12日(旧11月29日)の火曜日
七十二候「水泉動」(しみずあたたかをふくむ)
凍っていた泉の水が少しずつ動き始める頃。目には見えないけれど、繊細な目で自然を見やった、先人のやわらかい眼差しを感じる七十二候です。
暦生活編集部(@543life)
543life.com/seasons24/post…
995
8月23日(旧7月16日)の月曜日。
二十四節気は今日から「処暑(しょしょ)」。
処暑とは、夏の暑さがおさまるという意味です。
今日は、残暑から体を守る「ひんやり手拭い」の作り方と、活用方法を教えていただきました。
イラストレーター、エッセイストの平野恵理子さん
543life.com/seasons24/post…
996
桔梗納戸(ききょうなんど)|#にっぽんのいろ
「桔梗色」の青みをさらに深くし、強いくすみを持たせています。
物置のような暗がりを表現するとされる青暗い「納戸色」を、桔梗色に掛け合わせて生み出されました。
『にっぽんのいろ日めくり 2023』
543life.net/?pid=169491526
997
鉄紺(てつこん)|#にっぽんのいろ
江戸時代に生まれた美しい色。
鉄瓶(てつびん)のような鉄の焼き肌を連想させることから、この名が付きました。東洋大学が箱根駅伝で選手に継ぐたすきの色としても知られています。
▼1月のいろまとめ
543life.com/nipponnoiropal…
#365日にっぽんのいろ図鑑
998
6月29日(旧6月1日)の水曜日。
今日は、氷の朔日(こおりのついたち)。
冷蔵庫はもちろん冷凍庫など存在しなかった昔は、冬にできた氷や雪を氷室(ひむろ)に保存していました。その氷を、氷の朔日に宮中まで運んだそうです。
巫女ライターの紺野うみさん(@konnoumi)
543life.com/koyomi/post202…
999
亜麻色(あまいろ)|にっぽんのいろ
亜麻のような淡い色。
明るい金髪の色から、赤みを含んだ色まで、亜麻色の色域には幅があります。
明治時代以降に使われるようになった色名です。
#にっぽんのいろ
1000
古代紫(こだいむらさき)|#にっぽんのいろ
「古代」と名前についていますが、誕生したのは江戸時代です。
当時流行した派手目な紫に対し、平安時代に愛された紫を、推測をもとに誕生させ、それを「古代紫」と呼びました。