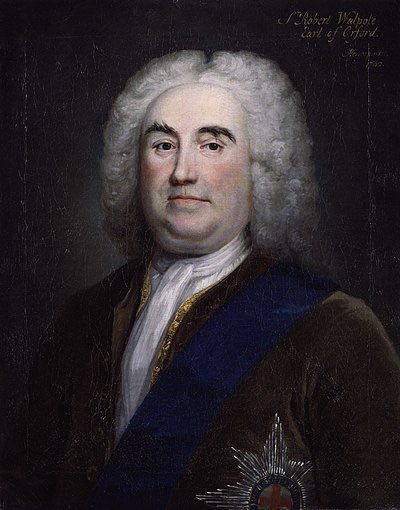451
452
453
454
おはよう。少し長い休暇だったけど、戻りました。大禍なく皆は過ごせたかしら?
休暇中も一応書いてたからよければ読んでいって。さて、お仕事に行ってきますね。
@elizabeth_munh #note note.com/elizabeth_munh…
455
456
457
458
お昼のTIPS。
バグパイプと言えばスコットランドの誇り。古くから突撃の際の士気高揚や、遠く離れた味方への情報伝達のために用いられたバグパイプは、味方には勇気を、敵には恐怖を齎した。
バグパイプ吹き達はパイパーと呼ばれ、尊敬を集める。
459
スパイ行為は地味なもんだけど、中にはものすごい事をやってのける人もいる。
それが、オットー・スコルツェニー。ナチスドイツのSS(親衛隊)中佐。
スコルツェニーは生来の冒険家気質で、戦時下の軍隊に居なければ登山家か、紛争地帯での傭兵にでもなってそうな危険人物。
460
しかしパルマンティエは実のところ、警備に意図的に穴を開けていた。
「ありがたい物だと思わせれば、より普及するだろうし、まして、危険なものとは思うまい」
このやり方はじゃがいも先進国であるプロイセンの模倣だった。
「盗まれる度、じゃがいものファンが増えるのさ」
461
462
これはライフハックだけど、Twitterで暴れ狂ってる作家の名前を控えておくと、本屋に行った時に悪著を自然と排除できるわ。
463
464
18世紀のフランスは天下の美食大国であり、じゃがいもなんて鼻から無視する。パルマンティエも家畜の餌か、貧民の窮余の食べ物みたいなのを食べさせられる捕虜の惨めさと共にじゃがいもを嫌々食べる。ところが表情が変わった。
「……美味いじゃないか」
パルマンティエはじゃがいもを完食。
465
お昼のTIPS。
独裁者の常だけど、ナポレオンはまず自らをこき使い、次に使える順番に部下たちをこき使った。
中でも酷い目に遭ったのが参謀長のベルティエで、戦争の天才ナポレオンの意図を理解し、それを現実の軍務に落とし込んで各指揮官を指導し、また現在の戦況をわかりやすく正確に伝えられた。
466
467
知り難き事陰の如し
動く事雷霆の如し
と、本来の孫氏だと続くみたい。
なんで信玄は風林火山に後の二つを入れなかったのか。
多分、単に語呂が悪かっただけではないかと思う。風林火山と風林火山陰雷ではやはり前者がしっくり来る。
468
Twitterはすぐ炎上するから話題は避けないとならない。
燃えない平和的な話題。つまり、政治、経済、宗教、ジェンダー、コロナ、野球、サッカー、芸能の話をみんなでしましょう。
469
「俺はここの生まれだ。ここで死ぬ方がよっぽどいい。みんな、そうしようぜ!」
こうしてエヤム村は前例がない、自主隔離体制に入った事を周囲の村や領主に通告し、誰も入らないように境界線の石を並べ、彼らは村の中で孤独にペストと闘い始めた。
470
「もし24時間、海峡に霧が立ち込めれば、歴史を変えてみせる」
とはイギリス上陸を遂に果たせなかったナポレオンの言で、上陸されたら後がないイギリスはフランス艦隊を24時間365日監視し、動きがあればすぐに潰しにかかった。
しかしそんなイギリスもフランス軍の上陸を許した事がある。
471
『ビグラント議員とバーケンヘッドのバンタム大隊、結成さる』
と新聞紙は報道し、きっかけになった男はBBBと刻まれたエナメルバッジを受け取った。
バンタム大隊は期待通り、命知らずの勇戦敢闘を繰り返す。とは言え勇気だけで戦える戦争ではなく、バンタム大隊は消耗してきた。
472
473
テューダー朝の時代から新大陸アメリカへの進出を始めたイギリスは、初期の段階で自国民を植民地へと送り出していた。厳しい環境下、高い死亡率から植民地を維持するためであり、また、ロンドンの人口が飽和状態になり、余剰人口を抱えたためだった。
貧しい移民達は年季奉公者として新大陸へと渡った
474
とは言え、やがてヨーロッパ人もじゃがいものポテンシャルに気づく。痩せた土地でもよく育つ。栄養価が豊富で、しかもありとあらゆる料理に合わせやすい。
「貧民のパン」
やがてじゃがいもは密かにそう呼ばれ出した。一方で偏見も根強い。マトモな人の食べるものではないともされる。
475
「当然だろ。ブレイドウッド隊長だぜ? 死んだって、炎は怯えて近づかないに決まってるさ……」
ブレイドウッドの構築した体制は近代消防組織の先駆けとなり、やがて諸国がこれを模倣する。根っからのファイアファイターは、消防の父となった。