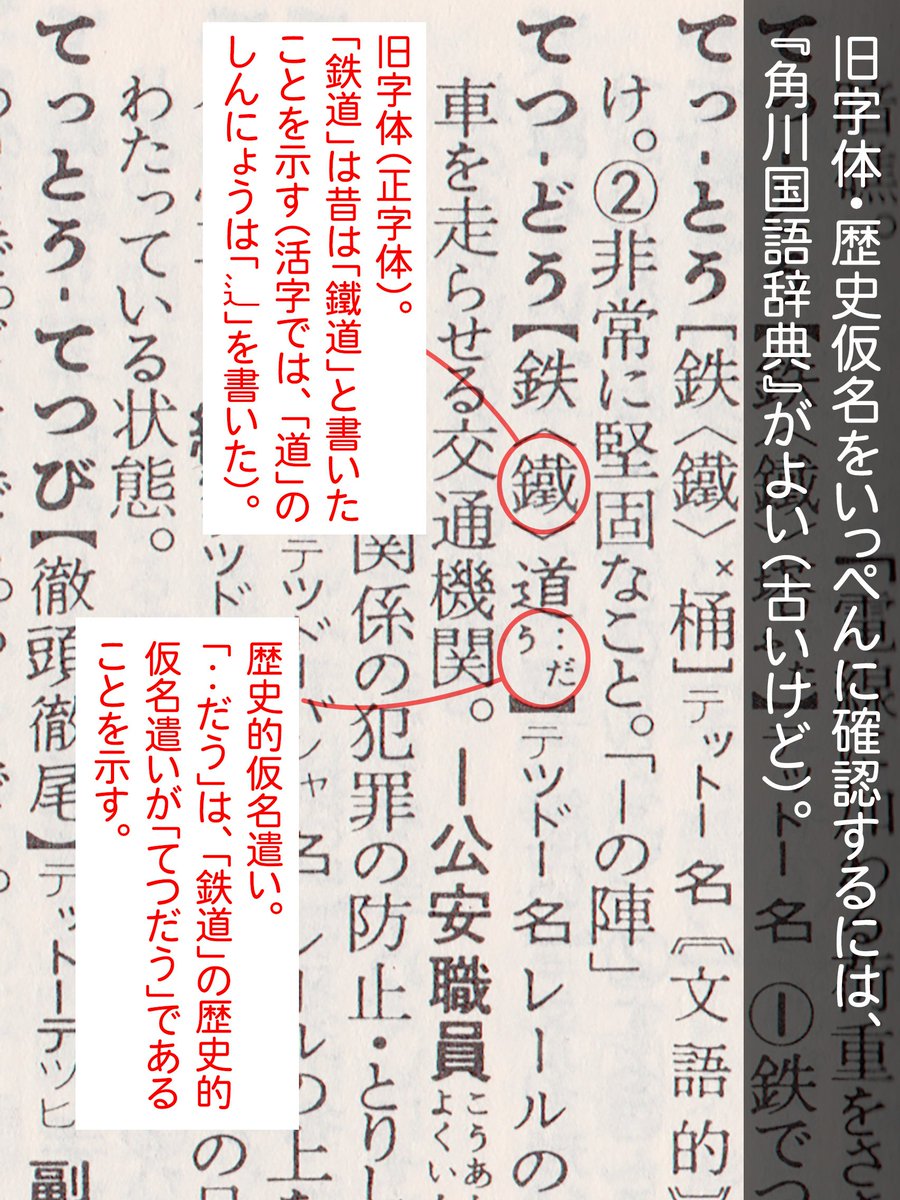76
「座り込み」についての各辞書の説明の違いは、このデモンストレーションをどう捉えるかに幅がありうることを示しています。法律の条文とは違って、「これこれの条件を満たせば座り込み」と辞書が決めるわけではありません。まず先に現実の言語使用があって、辞書はそれを後追いしているのです。
77
78
『広辞苑』の説明の誤りが複数指摘され、ニュースになっています。これは悪いことではありません。指摘によって辞書の説明が改善されるからです。ただ、「辞書の誤り」について、一般には誤解もあるようです。「『広辞苑』に誤りがあるとは! もう買わない!」といった意見もありますが、短絡的です。
79
作文を書くのは苦手だという人でも、学校外では、進んでSNSに書き込み、言いたいことを言う、という人も多いはず。皮肉にも、学校の外で文章修業をしているわけです。匿名で書けるとか、成績に関係ないとか、いろいろ理由が考えられます。この雰囲気を文章教育の場に持ち込めないでしょうか。
80
熊本の阿蘇山とか、鳥取の大山とか、高さの順で言えばかなり下の山でも、名をよく知られ、愛されている山はいくらでもあります。そう考えると、「1番にならないと認知されない」という話に対する反論材料がおのずとできてしまった。「世の中順位じゃないんだよ」という、なんかいい話になりました。
81
大臣の「がっかり」発言に関し、先日テレビの取材を受けました。結局放送されませんでしたが、問答の全文を読んでも、「本当にがっかりしております」はやはり不適切というのが私の考えです。質問者が金メダル候補の話に持って行ったせいもあるけれど、「その話はまた」と断ってもかまわなかった。
82
椎名林檎「人生は夢だらけ」は、「だらけ」を新しい語感で使う例です。従来「泥だらけ」「傷だらけ」など、よくないものに使うことが多かった。ところが、最近は「幸せだらけ」のように言い場合に使う場合も一般化しています。「もういやになるほどいっぱいあって、幸せ」という語感でしょうか。
83
84
ネットの反応を見ると、「わい」は「2ちゃんねる(なんJ板など)が発祥だろう」という意見が多いです。私も掲示板で「わい」が流行している様子をリアルタイムで見ていました。その前段階として、「わい」はアニメの人物のキャラづけに使われました。そういう経緯は、放送では無視された形です。
85
「反社会的勢力」の定義に関する政府見解が複数出される事態は、辞書の作り手として大変困ります。「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して…」という法務省の定義と、「定義は困難」という今回の決定は両立しないはずですが、はたして従来の定義は上書きされたのか。▽毎日新聞 mainichi.jp/articles/20191…
86
記事中(そば粉を使わず)小麦だけで作る「沖縄そば」も「そば」と名乗れるとあって、なるほど。茶葉でなくても「昆布茶」、発酵食品でなくても「甘納豆」というのまで含めたら類例は多そうです。▽麦みそに「みそと名乗るな!」 老舗店あぜん、行政の不可解な指導 | 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20221…
87
『朝日新聞』に国語辞典に関するロングインタビューが掲載され、さっそく読者の方から反応をいただきました。中に、「自分は日本語を正す活動をしている。ぜひご協力を」といった内容のものが複数。「日本語を正す」という考えに疑問を呈したはずなのですが、そこを読解していただけなかった模様です。
88
あることばに違和感を感じ、「自分はこのことばを使わない」と言うのと、「他者がこのことばを使うのも認めない」と言うのとではまったく話が違います。誰にでも前者の自由はあるが、後者の権利は必ずしもない。これは他者が自分(の方式、主義)と違うことをどれだけ許せるかという話でもあります。
89
Aに遅刻を批判されたBが「Aこそよく忘れ物するじゃないか」「Cだってドタキャンしたよ」と責任逃れするのを whataboutism と言う。“What about...”(じゃあ…はどうなんだ)と話をすり替える論法だからです。ネットでは冷戦期に生まれたことばとされていますが、普及は2010年代後半と考えられます。
90
手紙で「貴いあなた」の意味で使われた「貴様」が、いつしか罵倒語になったのも、元は「貴様って何か失礼じゃね?」という一種の謎マナーが原動力だったろうと思います。敬語にはそういうことかよくあります。ただ、その説が広まると、従来の愛用者が無礼者にされてしまう。そこに問題があります。
91
作文教育では、子どもが思ったこと、考えたことを素直に書かせようとします。「何を書いてもいいんだよ」と。空気を読まず、教師や友だちの評価を気にせずに、考えたことをどんどん書けば、それはとてもいい訓練になります。でも、「空気」に支配されている子どもに、そんなことができるでしょうか。
92
93
富士山というのは、日本一の高さもさることながら、円錐形が美しく、四方の山から隔絶して高いから愛されているわけです。もし仮に、「正しく計測してみたら、日本一は北岳でした。富士山は2番目です」となっても、なおも日本の象徴的な山として愛され続けるだろうと思います。
94
メディアでは今回「女性蔑視発言」という表現が多い。「差別」よりも「蔑視」のほうがマイルドだと考えて使っているふしがあります。でも、両者は別物です。ニューヨークタイムズは「会長が会議での女性の制限を提案」と本質を突いた表現をしています。要するに実害を与える差別だと言っているのです。
95
仮にこんな発言があったとします。「女性は優秀で、尊敬する。女性は活発に有意義な発言をするので、女性の理事が増えると発言時間の規制が必要になると言われる」。賛辞に満ちた発言ですが、女性理事の増加を牽制したり、行動を規制したりすることにつながる可能性がある。すなわち、差別発言です。
96
ネットで嫌なこと言われたら、まずその人の過去の発言(リツイートとかでなく)を多く熟読することをお勧めします。「この人あちこちで喧嘩売ってんな、気の毒に」「最低限の常識ないな」と哀れんだり、「おっ、いいこと言ってんじゃん、同類じゃん」とわかったりして、いずれにせよ戦意が消えます。
97
98
「てぇてぇ」。「とうとい」の変化形。「推しが尊い」などという「尊い(=神々しいほど素敵)」を変化させて言う。江戸なまりなら「とうてぇ」になるはずですが、後部の「てぇ」に引かれて前部も「てぇ」になった模様。#今年の新語2020
99
100
時事問題などに関するSNS上の発言を読みながら、罵倒・嘲笑などの「贅言」を消去していくと、後に何も残らない、という発言も多くあります。そうした発言を読むのは、まさしく時間の浪費です。「贅言消去」の習慣が身につけば、有益な議論を選んで読むことが自然にできるようになります。