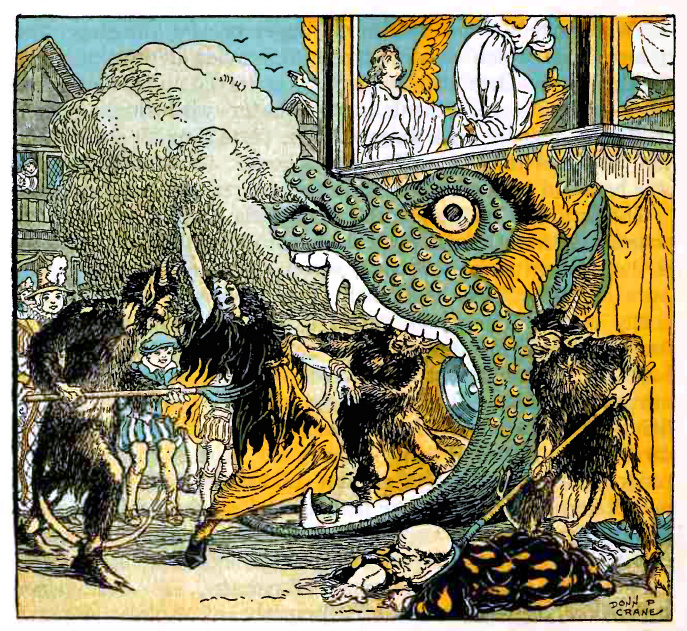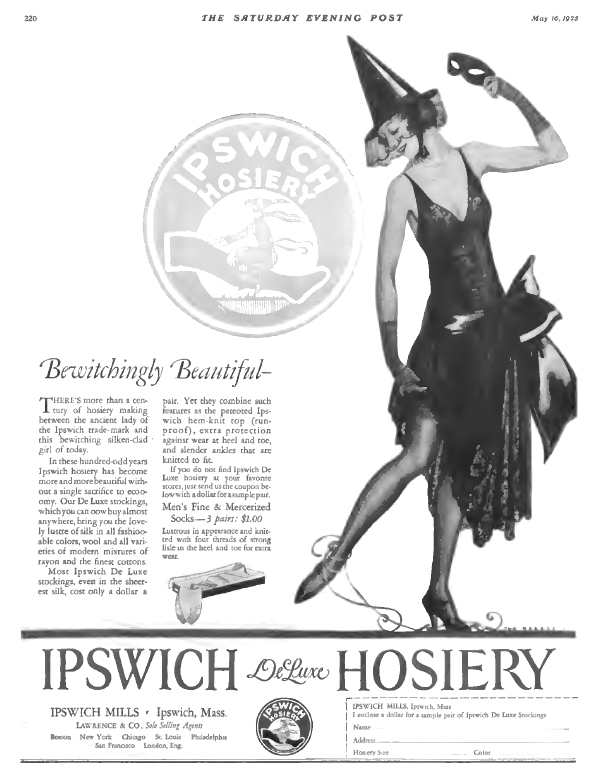1601
1602
1604
1605
1606
こちらも天井ワニの資料として。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1607
#わたしを作った児童文学5冊
小公子
アンデルセン童話集
小川未明童話集
秘密の花園
Child's Garden of Verses
なおアンデルセンは「赤い靴」と「パンを踏んだ娘」。
小川未明は「月夜と眼鏡」を。
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
図版は吸血鬼ではなく棺桶で眠るサラ・ベルナール。もっともヘンリー・アーヴィングもそうですが、素晴らしい役者は吸血鬼に例えられることが多いのであります。それはそれは魅力的で、また不死の如き若さを保つからです。近しい人間ほど犠牲になるのも同様かと。
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
・持ってるはずの本が見つからず、また買うはめになる
・異なる版を集めて内容が同じかどうか確認したくなる
・100ドルは100ドルであって円換算などしなくなる twitter.com/kodaigirisyano…
1624
聖ヨハネ関連で再掲。ローマに複数。アミアン、ダマスカスのも有名だとか。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1625