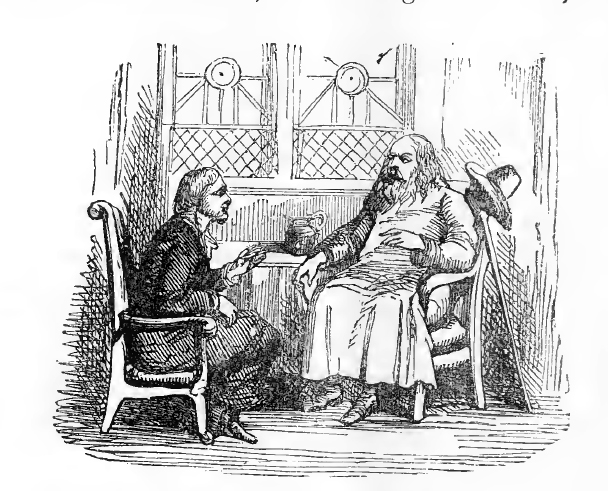1551
ーーミットフォードは『佐賀怪猫伝』をもとに記しているため、龍造寺の因縁はカット。吸血猫が側室に化けて殿様を襲うのですが、正体を見破られるとハルバードを手にして戦います。いきなりファンタジー度がアップ。イサハヤ・ブゼンといった人名も漢字で読むよりかっこいいのであります。
1552
1553
1555
ーー告解の火曜日のパンケーキ、聖金曜日のホットクロスバン、ハロウィンのソウルケーキなど、この種の祝祭食物には無病息災などの効能を認める向きが多く、いわば「食べるタリスマン」と言えましょうか。タリス饅頭なども考えてよいと思います。
1556
1557
1558
#スズランの日
タロットでスズランといえばライダー版の魔術師の足元にあるわけですが、これがヴァージョンによってえらく差があるのです。モノクロ画はもっとも原画に近いとされる1909年のOR版。一方、1942年頃に製作されたパメラBは複写士がいまひとつ線の意味を理解していないのであります。
1559
1560
1561
1562
天井ワニの資料として再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1564
1565
1566
1568
1569
船上でのウサギの禁忌に関して再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1570
養蜂はガーデニングの一部門として良家の子女の趣味となり、また蜂社会の神秘性が多くの魔術的伝承を育てていったのであります。ラストメッセージをミツバチに託す人情話もあります。窓辺に現れるミツバチはまさに「虫のしらせ」ということで。
1571
1572
で、白秋の「まざあ・ぐうす」で読みますと
「だァれがころした、こまどりのおすを」
「そォれはわたしよ」すずめがこういった
となりますので、かの「音頭」の冒頭部を想起せざるを得ないのであります。
1573
ーー棒の部分が笛になっていて、簡易バグパイプとして機能するものもあったようです。それは奇怪な音を出し、こちらでも笑いを取れるわけです。一発芸で人を笑わせるのは魔法のうちです。場の雰囲気を変えるのは重要なスペルブレイクでありましょう。
1574
1575