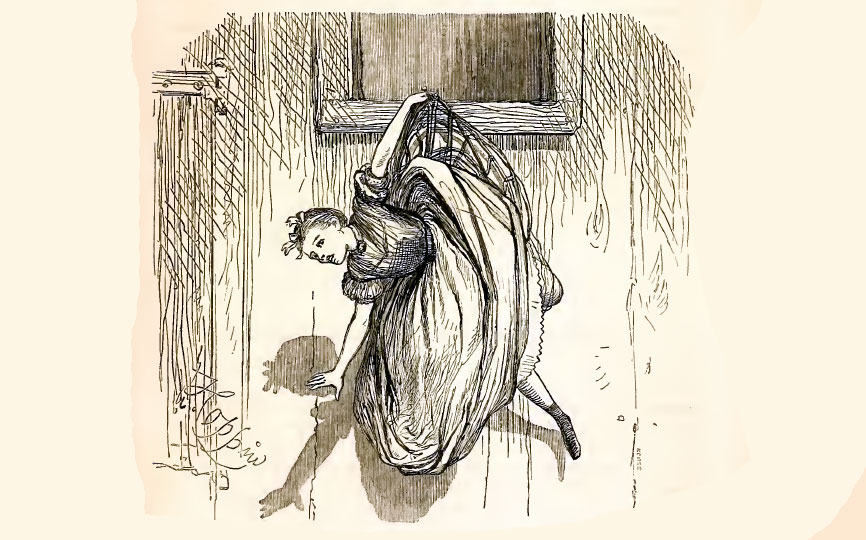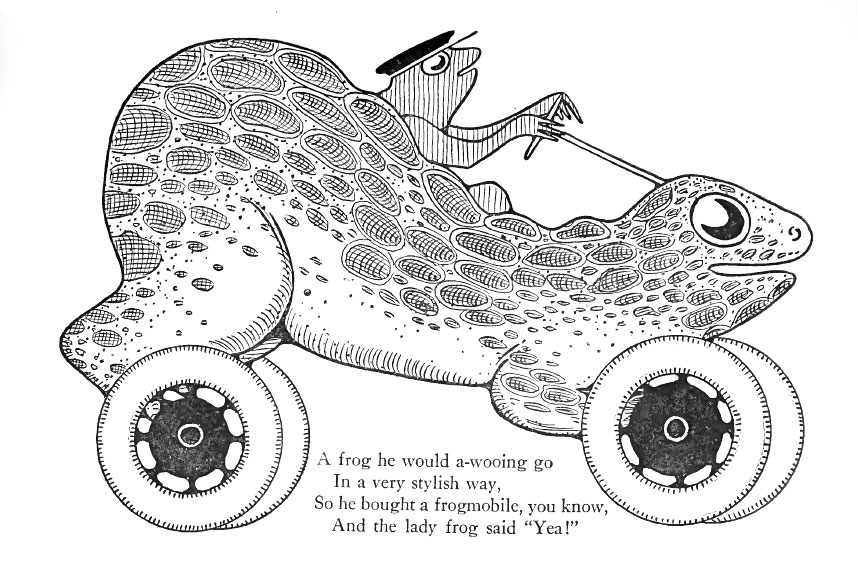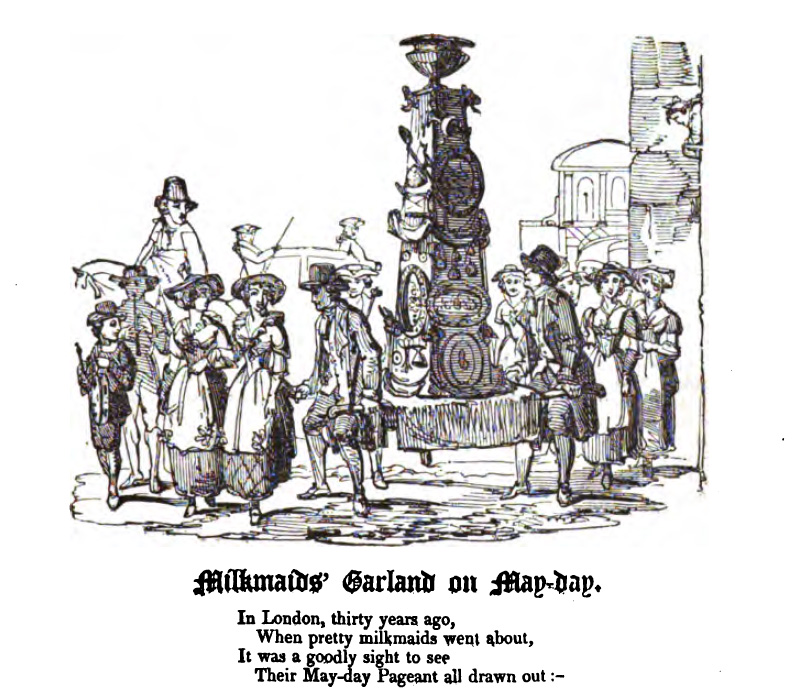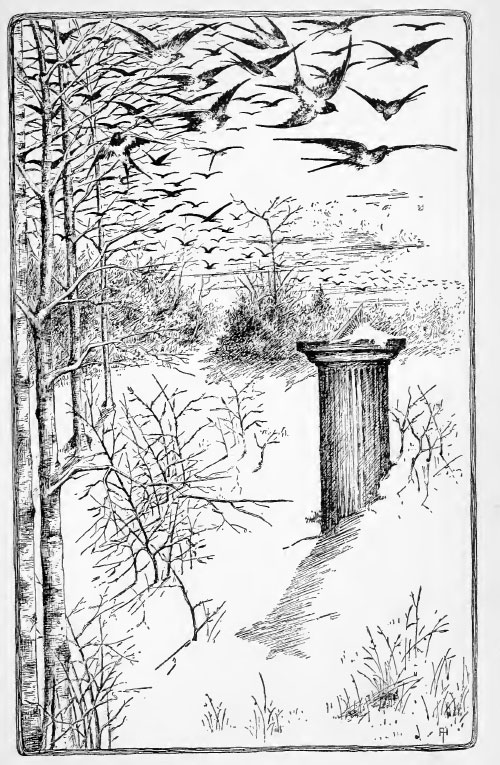1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
ーー結局、警察や教会関係者が出動して騒ぎを鎮圧するはめになりました。この件はタイムズなどでも報道され、いまだ蒙昧の輩の多いことよと有識者の嘆くことしきり。なお19世紀半ばともなれば水泳は婦女子も嗜むべしとして、婦女子読本でも奨励されています。図も同書から。
1641
猫たちのパーティーに関して再掲。青いドレスのお嬢様猫がフランス帰り、大胆にも青年猫を自分からダンスに誘うのであります。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1642
1643
このTWはクリスマス向けなので再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1644
1645
暦。#ペンの日 とのこと。
さればとペン関係の伝承を探そうとするも意外に見つからないのであります。金属ペンは比較的近世の製品ですし、羽ペンは消耗品ですので魔力保持器には今一つ。重要なのは文章の内容と美しい筆跡でありましょう。写真は当館所蔵の19世紀の矢立と羽ペン。
1646
出典はこちらから。
archive.org/details/stnich…
小節内に絵が入り込んだのはこれと後半にもう一本あります。
1647
メイデイにつき再掲。とある映画とコロナ禍のせいでこの行事がまた廃れたとの声も聞こえてまいりました。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1648
1649
1650