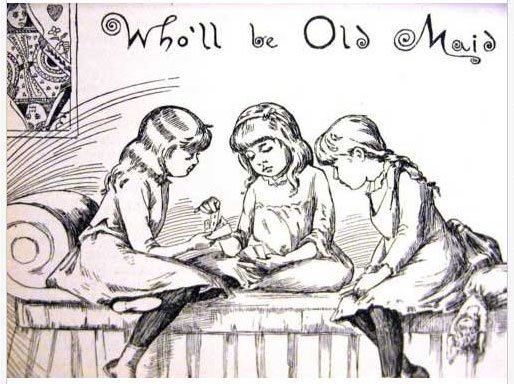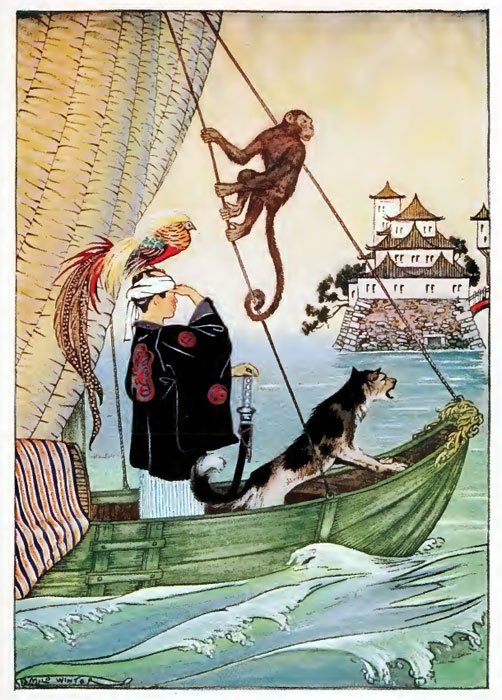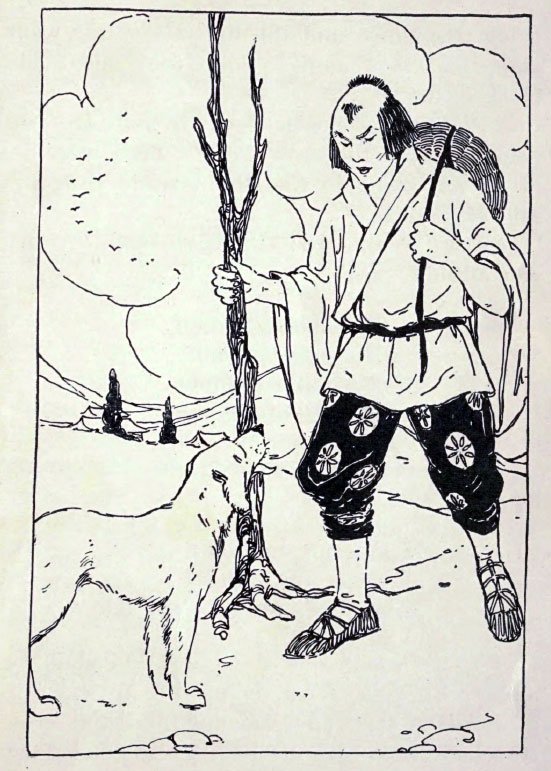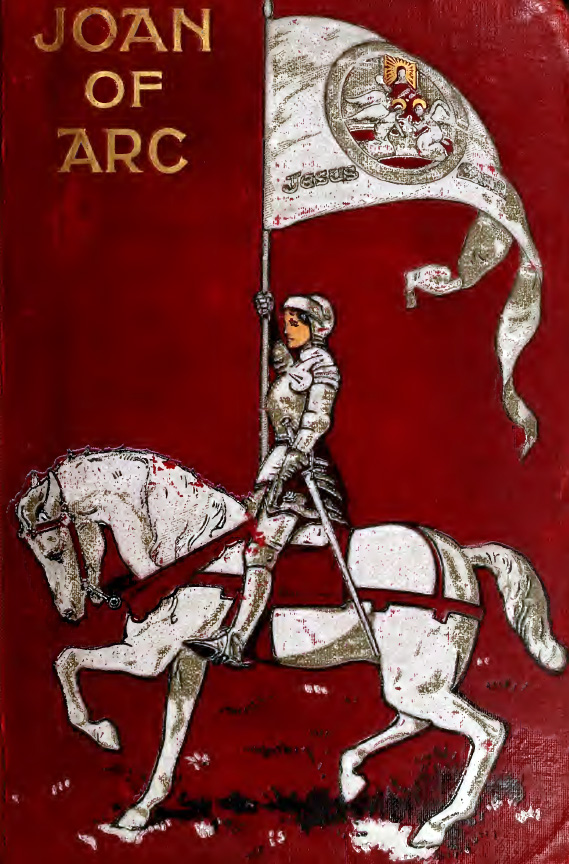1326
1327
1328
#天使週間
アンデルセンの慰霊童話「天使」に登場する天使は厳密には守護天使ではないのですが、数々の挿絵が人の心に残り、全体として守護のイメージを醸し出します。カウルバッハはすでに紹介しましたので、それ以外を若干。
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
ストーンヘンジがトレンド入りしているので再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1336
1338
1339
1340
#あの名画にひどい邦題をつける
『悪役令嬢スカーレットの華麗なる冒険』
1341
1342
1344
1345
1346
1347
1348
1349
本日は #たばこの日 でもあるそうで。
"Three on a match" といって、「一本のマッチで三人が煙草に火をつけると一人がほどなく死ぬ」という伝承が1次大戦後に英米で爆発的に広まったとのこと。おそらくこれも13恐怖症の一種。一本と三人で13を形成しておるのです。同名の映画も作られました。
1350