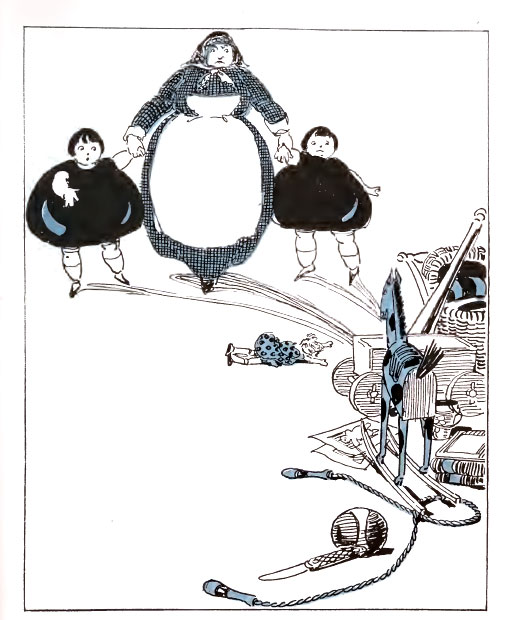1351
1352
1353
1354
1355
#StDavidsDay 3月1日はウェールズの守護聖人聖デイヴィッドの祝祭日。当館でもたびたび取り上げておりますが、冒険活劇「七聖伝」ではドジ役をふられていて、呪いの剣を手にして七年間昏倒したりします。ともあれファンは赤いケープをまとい黒い円筒帽子をかぶってネギをふりまわすのであります。
1356
1357
#天使週間
細い橋を渡る子供たちと守護天使。この構図は多色刷り絵葉書でさんざん利用されたあと、19世紀末頃から実写化されてさらに大量投下されていきます。一応「幸運絵葉書」の範疇にあるような。商業レベルでの天使のイメージの固定化の資料として。
1358
1359
1360
1361
1362
ーー使い魔とはおよそ命令を聞きそうにない動物がつとめるのであって、犬や馬を使い魔と称する例はまずなかったように思います。なお猫さまはこちらが使い魔にされる可能性がきわめて高い存在であります。実例に関してはみなさまお心当たりがあるかと。
1363
当時の英国議会がジェンナーのワクチン普及に三万ポンドの予算を計上したことにも反発する勢力がいて、医学界の保守派と組んで一大キャンペーンを繰り広げたようです。ワクチンとナポレオン・ボナパルトが世界を滅ぼすといった刺激的なキャッチフレーズも登場しています。
1364
#メリーさんの羊の日
もちろんメアリーと子羊という組み合わせは聖書的解釈を呼び込みます。もともと日曜学校用のブロードサイドに記された詩ですし、中世の「ユニコーンと乙女」を連想してもよいのであります。ヴィネットに囲まれた絵はご存知ウィルビーク・ルメール。
1365
1366
聖ニコラスが「悔い改めた泥棒」の守護聖人とされる点を鑑みると、ここに描かれているのはサンタその人ではなく「OB組」ではなかろうか、と思ってしまいます。聖ニコラスの下にかつての怪盗や大泥棒が勢揃いして、厳重な警備網をかいくぐって玩具を配っていく話も面白そうです。
1367
今でこそ世界に冠たる幽霊好きの英国でありますが、19世紀中頃までは普通に怖がっていたようです。幽霊屋敷の家主が苦肉の策で「七年契約で最初の一年は100ポンド支給、二年目は無料、三年目から家賃を請求」といった条件を出した例も(ただし途中で逃げたら罰金1000ポンド)も。
1368
「借りた三日間」に関して再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1369
この頃の記述に、少し短めのスカート丈にしてホワイトコットンとショートブーツを組み合わせ、1インチほど白い部分が見えるようにすると男はいちころというものがありました。なんとか領域のヴィクトリア朝ヴァージョンでありましょう。面白いのであります。
1370
1371
1372
1373
1374
1375