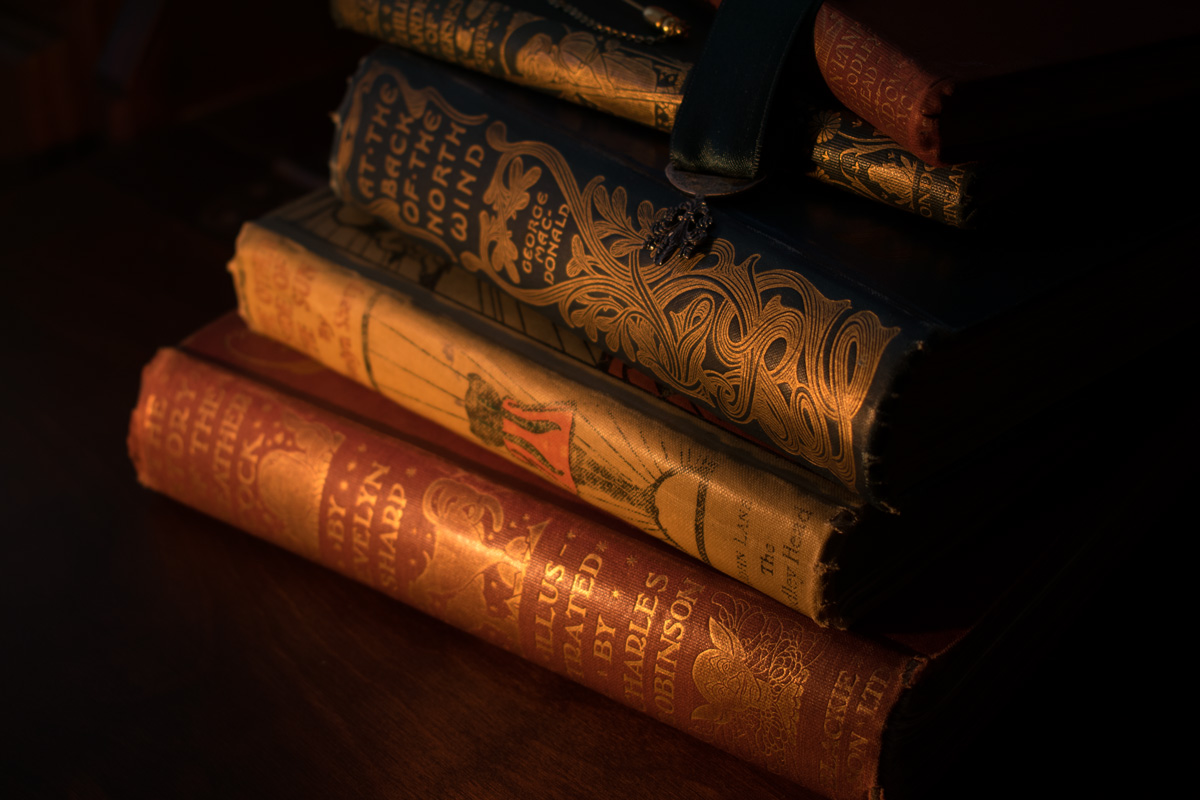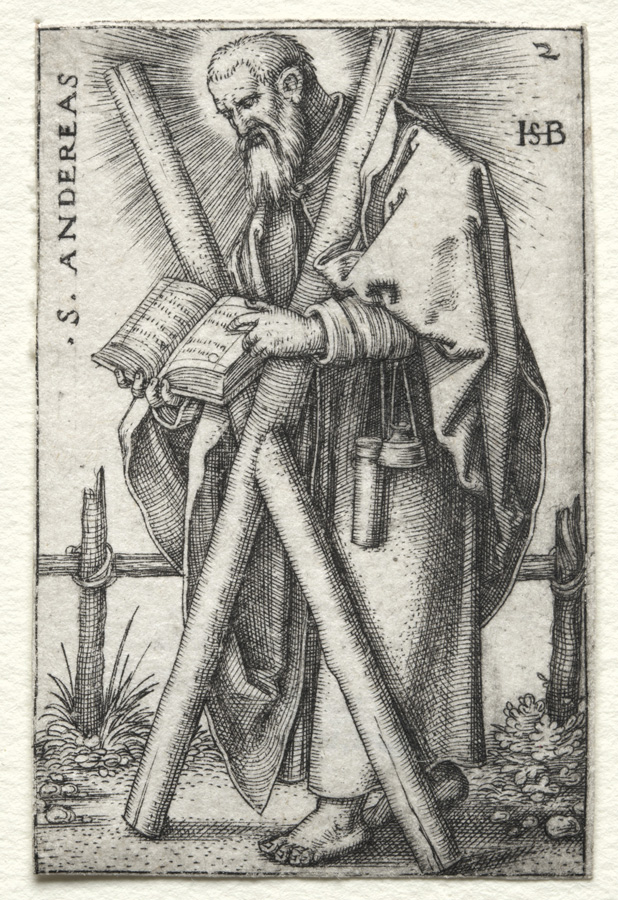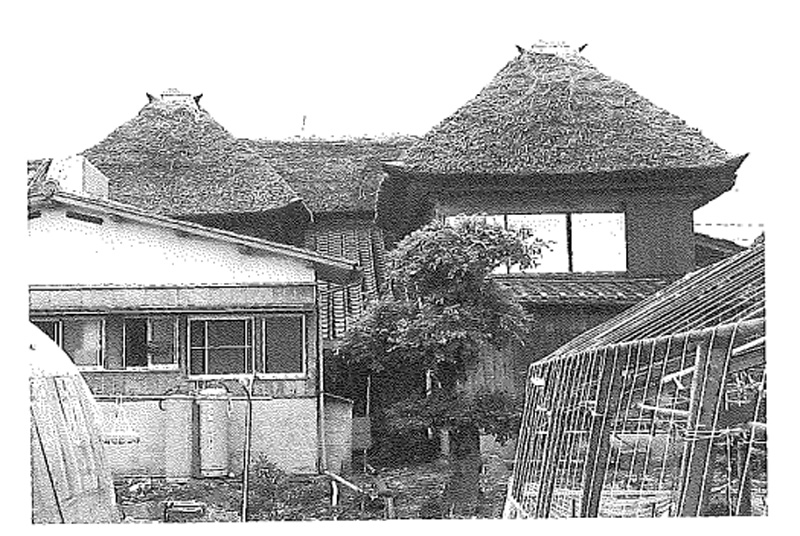1376
1377
「借りた三日間」に関して再掲。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1378
1379
1380
1381
1382
1383
ジャック・フロストの作品、ですねえ。見事なものです。 twitter.com/jackiesearle09…
1384
英国の鳴く虫に関して再掲。虫の声は西欧人には雑音にしか聞こえない、などということはないのであります。 twitter.com/MuseeMagica/st…
1385
燃え続ける炉のなかでいろいろな残滓が残留/成長するのはよくある話でしょう。竈から逃げた火が大災害を引き起こすのもありがちな話。さよう、9月2日はロンドン大火の火であります。火の用心さっしゃりませ、と。
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
暦。1月5日はグレース・ケリーの結婚記念日なので #シンデレラの日 とのこと。シンデレラ物語の逆境からの逆転劇だと思うのであります。ネズミ捕りにかかって処分寸前のハツカネズミ、ドブネズミ、庭の隅っこのトカゲたちも魔法で変身するところが重要かと。
1400
『久保田町史』下巻にあった写真がわかりやすいかと。
city.saga.lg.jp/main/5080.html