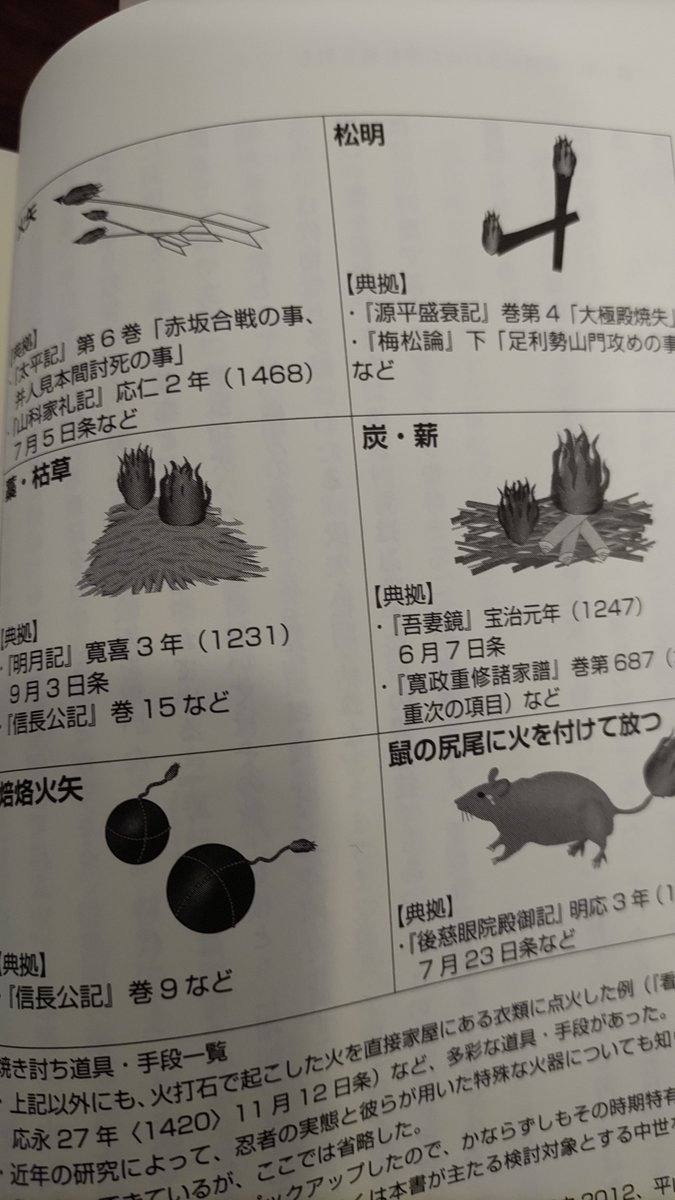576
中世という時代はやっぱり、どの階層の人々も常に切羽詰まっている、という感を抱かざるをえないですね。自力救済社会というものの、あらゆる意味での余裕の無さが、間接的にも溢れ出してきます。
577
有名な所領一直線分割
#鎌倉殿の13人
578
そーいえば歴史IF解釈といえば、僕は織田信忠が何故か『秋田城介』なんて割りとマイナーな官位に任じられた所から、信長は信忠を同じ大将軍でも征夷大将軍ではなく、建武政権下で「征夷大将軍と同格」とされた『鎮守府大将軍』に任官させ、足利とは別系統の「将軍家」を打ち立てようとしたと思ってる
579
織田信長は天正2年11月に権大納言・右近衛大将に任官して、いわゆる公家の仲間入りをするわけですが、それと同時に公家・門跡の借銭破棄を認める徳政出したり義昭幕府から没収した土地を公家に分配したりと信長自身もかなりの負担を強いられていて、信長が任官に慎重だった理由もなんとなく見えてくる
581
しかしそういう事だとすれば、豊臣(羽柴)宗家まで巻き込んでおきながら、勝ち筋が無いと見るや即座に東軍と勝手に和議を結んだ「総大将」毛利輝元という人物はちょっと信じられないくらいの胆力を感じますね、或いは無責任力。
582
まあ実際には、これ以前から家康は「源家康」を名乗っているんですけどねw #どうする家康
583
ホント広島が周辺県から尽く警戒されているの実に興味深いw
東西でここまで違うとは... 「苦手な都道府県といえば?」地域別マップが興味深い(2/4)|Jタウンネット j-town.net/2020/01/022992… @jtown_netより
584
ウマ娘のグラスワンダー、アニメ版からアプリ版が出た時のキャラクター印象の変化について、「ヤンデレだと思っていたら鎌倉武士だった」という言葉がかなり好き
585
「戦のない世」を「うすっぺらい」。言うなあw
#鎌倉殿の13人
586
一種の諦観すら感じられる
中世武士選書45 足利義輝と三好一族――崩壊間際の室町幕府 歴史、城郭、神道など書籍の出版・販売|戎光祥出版株式会社 ebisukosyo.co.jp/item/612/
587
言われていることが実にごもっともな上にいちいち面白いw電子書籍版もあるのでオススメです
戦国日本の生態系 庶民の生存戦略を復元する honto.jp/ebook/pd_32238…
588
まー、家康の特性として「我慢」「堪忍」「忍耐」なんかが美徳として強調されたのは、あくまで後世の都合からであり、実際の家康とは正直何の関係もないですね。
589
茶店の婆さんが三方ヶ原逃走の折食い逃げした家康を追いかけたという逸話がこちら #どうする家康
銭取由来 iiwarui.blog90.fc2.com/blog-entry-389…
590
本願寺の大阪退去まで木津川口周辺はずっと毛利水軍が抑えており、「制海権」はまるで確保出来ていなかった模様。そりゃあ「鉄甲船」が後世に継承されないわけですね。
591
大久保忠教は「三河物語」の中で織田信長を、少なくとも対徳川家に関しては、ほぼ終始一貫して徳川家に対しての理解者であり、徳川家中の者達に非常に甘い、と描写しています。無論これもある種の「徳川史観」ではありますが、少なくとも徳川家中に、信長への一定の好印象があったと見ていいのではと
592
いやあ、男も女も京も鎌倉も恐ろしい
#鎌倉殿の13人
593
「関ヶ原」についての論争、「小山評定」についてはもう言葉の枝葉みたいな話になってて、小山だったかどうかはともかく「評定自体はあった」で良いと思う。あと関ヶ原の合戦では1、2時間程度であっというまに西軍が崩壊した、という部分は信憑性高いと思う。
594
よく秀吉の死後、家康が様々な陰謀を駆使して「豊臣勢力」を追い込んでいったと考えられがちなのですが、実際には陰謀を駆使していたのは反徳川勢力の方で、家康はそれらに対処し一つ一つ潰していった事で結果的に天下の主権者になってしまった感があります。
595
「徳川家康」を見る上で、「今川権力の継承者」という側面は割と大切だと思う
596
まあ家康の話に限らず、戦国武将(にも限りませんが)について現代人が面白がったりドラマチックに感じたりするような逸話はその殆どが後世の作り話と捉えておいたほうが良いですね。逆に、後世の作り話だからこそドラマチックで面白くしているわけです。
597
何が凄いって本当にどの角度から見ても全部不穏か絶望のまま2期に続くってことだろうな。もう丹念に丹念に希望を殺していった。このスタッフに人の心はないのか(褒め言葉) #水星の魔女
598
そもそも秀吉の出自を「農民出身」と安易に言っちゃう時点で既に学問的な話ではないよね #なんか見た
599
豊臣秀吉の妻ねね(おね)が「北政所」と呼ばれた事は有名ですが、本来関白の正妻を指す用語に過ぎないこの言葉が、何故か彼女の代名詞のようになり、関白の位が秀吉から秀次に譲られても、朝廷から「高台院」の号を賜っても、何故か世間からは「北政所」と呼ばれ続けた、というのはなるほど興味深い
600
そう言った意識を持った連中に対し中世権力、鎌倉幕府、室町幕府、戦国大名などは「紛争は話し合いと裁判で解決するようにしよう。頼むから!」と訴え続け、その帰結としての江戸時代なのである。