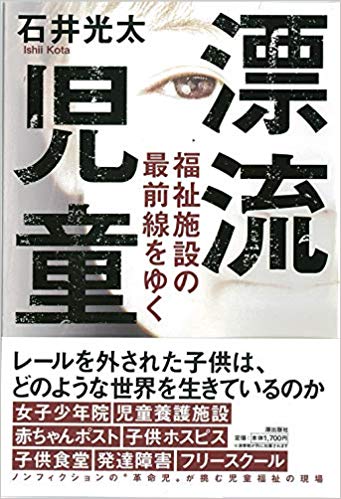126
大阪のコロナの最前線の一つが『こどもホスピスの奇跡』の舞台・大阪市立総合医療センター。コロナ第三波で、ここのAYA世代(15歳~の思春期等)の病棟がついに閉鎖。小児がんなど重度の難病の若者の人生にまで多大な影響が及んでいる。しわ寄せは常に弱い立場の者に……。asahi.com/articles/ASNCZ…
127
グラミン銀行のことをはじめて知った時、「最貧国の問題を解決する素晴らしい仕組みだ」と思った記憶があるが、まさか十数年後、日本に進出する日が来るとは想像もしていなかった。⇒グラミン銀行が日本進出へ 貧困層向け融資でノーベル賞 asahi.com/articles/ASK9Q…
128
新潮社はすごい優良出版社。が、多くの小さな出版社は読者のためでなく、「図書館が買ってくれる本」を薄利多売で作りまくってる。企画も書き方も営業もすべて図書館向け。ぶっちゃけ、げんなりする。⇒新潮社社長、1年間の新刊貸し出し猶予を要請へ-headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?…
129
5歳でひらがなを覚えて、あれだけの文章を書くというのは、相当勉強してなければできないよな。親も「ひらがな表」を買ったり、大学ノートを与えたりしていたんだろ。はじめは虐待の認識はなかったんじゃないかな。これは虐待親によくあること。
130
竹田圭吾さんが病気療養したときにお見舞いの葉書をだしたら、すぐ返信が来て「厄介な病気になってしまいましたが、かならず戻って最後まで仕事をつづけます」と書いてあった。その後復活して痩せた姿でがんばってるのを見た時は最後までというのは、「最期まで」の意味だったんだなと思った。
131
すごい調べてる。取材の裏を知ってる身からすれば驚くぐらい。けど、それぞれの家族が抱えていた問題、地域の問題、個人の問題などの真実を描かなければ、なぜこんな異常事態に発展したのか、なにも知らない視聴者にはわかりにくいかもね。けどテレビでは難しいだろうな。
132
ある児童書をつくるために「いのちの電話」にかけてみたが、まったくつながらない。何十回かけてもダメ。内部の人いわく、相談員がおらず、全国的にパンク状態だとか。相談員はボラ&高齢化、相談者は増加、SNSなどアクセス方法は多様化。保護司もそうだが、ボラの不足の問題は大きい。
133
思い出すのは、震災の時に真っ先に声をかけてくれた編集者が小学生の時に阪神大震災の被災者だったり、『遺体』の映画化やイベントの関係者が御巣鷹山の墜落事故の関係者だったり、「中越地震で何もできなかった」とつぶやいていたりしたこと。後悔こそが行動を生むのだとすごく実感した。
134
最近よく子供の環境が社会問題になっている。子供の貧困、DV、シングルマザー。しかし、そういう家庭の子が難病になったらどうなるか。現実に、日本では20万人の子供が難病を抱えている。今回子供のターミナルケアの現場をいろいろ取材して、非常に「家庭」の在り方について考えさせられた。
135
小児の終末期医療を取材していても、本当に必要だと思う。重症になってどこへも行けなくなった難病の子供たちが、いつでも親や友達とつながることができる幸せ。特にコロナ禍で家族との面会さえままならない状況で、それがどれだけ大きい事か。できることからはじめてほしい。
news.yahoo.co.jp/articles/a6ace…
136
祝い金の代わりに、何かした方がいい。昔、高齢者自殺を取材した時、彼らが自殺する日で多いのが「敬老の日」「誕生日」だったから。記念日こそ、余計に孤独を感じるのだろう。⇒敬老祝い金、廃止続々…高齢者増え費用膨らむ(読売新聞) - headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160913-…
137
本日の終戦記念日に合わせて、戦災孤児についての記事を書きました。➡️戦争が生んだ「浮浪児」は3万5000人 当事者が語る路上生活【石井光太】「大人は『自由になった』と喜んでいたけど、一人じゃ生きられない子供にしてみれば『国に捨てられた』が本音だった。」
dailyshincho.jp/article/2020/0…
138
よく作家が出版社を通さずに電子書籍で出すことをどう思うかと聞かれる。僕は「無理です。編集や校閲の力は読者が思う千倍大きいんです」と答える。新潮社の校閲部の井上孝夫さんの『その日本語、ヨロシイですか?』を読めば、その意味が少しでもわかるはず。電子書籍に携わる方に読んでもらいたい。
139
140
慈恵病院の院長は、高齢の上、透析して車椅子。「こうのとりのゆりかご」設置から10年以上経っても今なお反対する行政と戦って、特別養子縁組を広めようとしているパワーはすごい。寄付も足りず、病院側が運営費の半分以上を負担としているとか。世の中を変える人の情熱は感動する。
141
先日広島で、この写真の持ち主にお会いした。耳の不自由なお父さんが一家の幸せな写真を数多く撮影。が、原爆で一家は「消え」てしまう。残されたのは膨大な家族写真。泣いた。現在資料館の地下に展示中→消えた家族、幸せは写真の中に 広島原爆: asahi.com/articles/photo…
142
今週の水曜日のクローズアップ現代+の「路地裏に立つ女性たち」で、歌舞伎町の街娼を取り上げました。ここで話しきれなかったことを、番組のHPのインタビューで語ってます。ぜひ、ご覧下さい。
nhk.jp/p/gendai/ts/WV…
143
3月10日は、東京大空襲によって一夜で約100万人が被災し、8万人以上の人が無差別に殺された日。毎年この日が近づくと、『浮浪児1945‐ 戦争が生んだ子供たち』で取材した、東京大空襲によって6歳で戦災孤児となった方からハガキが届く。誰にも語れない悲しい過去を共有してほしいのだろうろう。
144
3月10日は東京大空襲の日。原爆を除けば、1回の空爆としては人類史上最大の犠牲者を出した無差別攻撃で、一晩で約10万人の死者、約100万人の負傷者が出た。大勢の子供たちが戦災孤児となり、浮浪児と呼ばれ、生きていくことに。『浮浪児1945-』の取材の際、どれほど多くの子供たちがPTSDから(続く)
145
自殺を報じる時、マスメディアはよく申し訳程度に自殺予防サイトや電話番号を載せる。が、コロナ以前から、これらの番号はパンク状態で、まともにつながらないところも少なくない。連絡したのに繋がらなければ絶望感は増幅する。紹介するなら、そういうところまで確認した上で載せるべき。
146
国は「更生ありき」で少年院等で矯正教育をしているけど、元々の特性や病気や環境(多くは複合的要因)で更生しない人もいる。こういう人たちには矯正教育はほとんど意味をなさず、出院後に様々な環境整備、規制、治療をしなければならないのだが、それが野放しになっているのが一番の問題。
147
今日、夕方に久々に仕事で歌舞伎町に寄ったら、驚くぐらいガラの悪い人だけがウロウロしていた。コロナでまともな人が「浄化」され、怪しい人だけが残ったのだろう。警察の人いわく、大手チェーンの××ホテルが格安で部屋を提供し、家出少女や売春の巣窟になっているとか。見回りも大変らしい。
148
漫画雑誌の編集者との打ち合わせで「最近の読者は感動モノが響かない。殺しまくるエグイシーンを見せなければ逆にリアルを感じない」という話を聞いた。そういえば、少年院に取材に行った時も同じ話を聞いたな。「感情未分化の子」(感情が未発達で、感動や共感ができない)が年々増えている、と。
149
150
近年は、「少年院を出たくないと言う子供たち」が、増加しているそうです。ずっと少年院で暮らしたい、と。その闇に光を当てました。➡️クスリに売春…「少年院を出たくない」と言う彼ら彼女らの特殊事情 | FRIDAYデジタル friday.kodansha.co.jp/article/203895 #事件