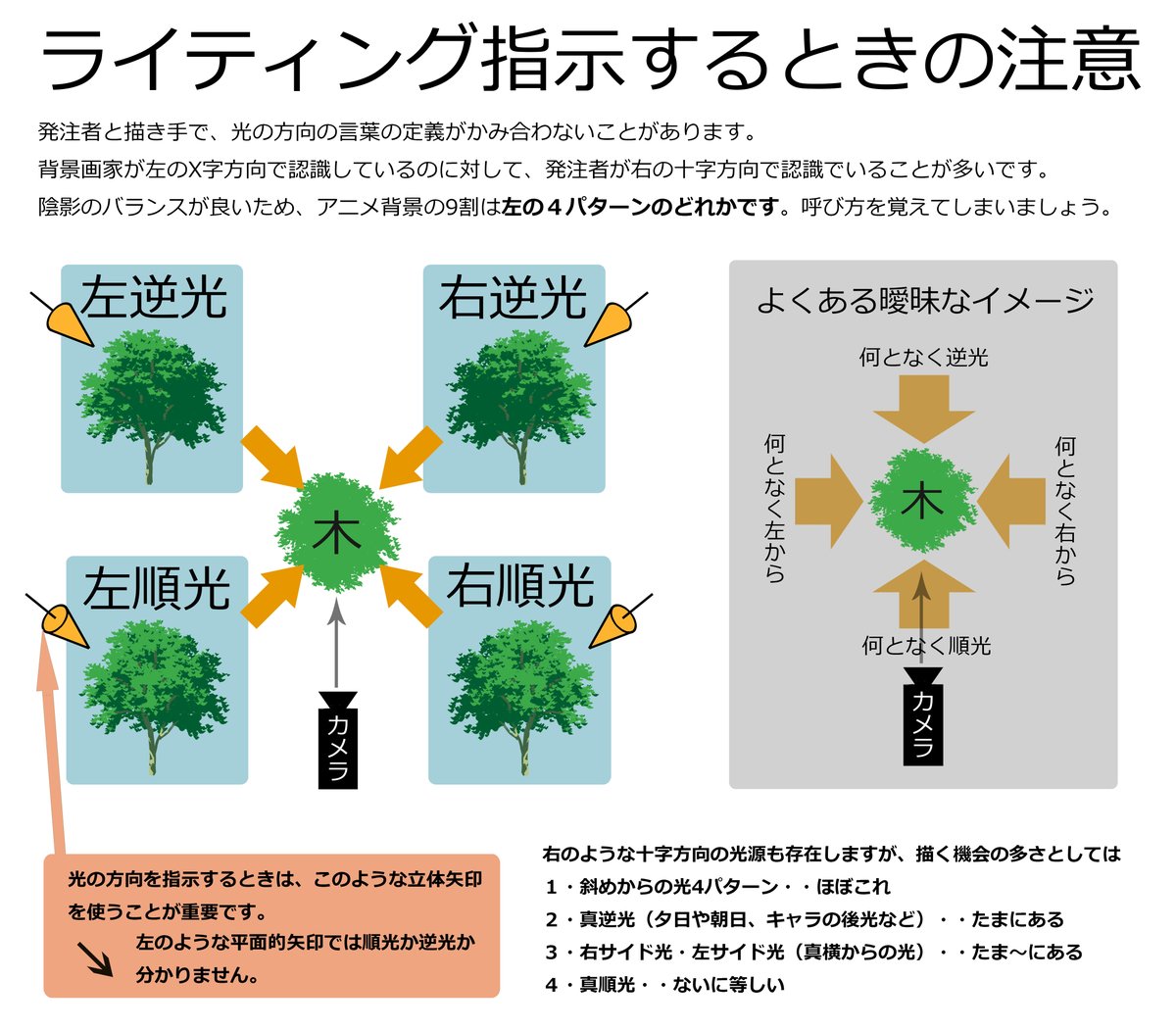627
白い物体に色を染めるイメージで考えると、様々な固有色に惑わされにくくなります。
#背景美術
628
【絵の情報量について】
大事なのは
画面内の情報量でなく
観客に伝わる情報量
画面内の10の情報で
観客に1しか伝わらないと
情報量1
画面内の5の情報で
観客に5伝われば
情報量5
画面内の1の情報で
観客に10の想像を与えれば
情報量10
優れた絵やデザインほど後者になる
629
球体の陰影
#背景美術
630
枝は少し曲線を描いて、しなやかさを出すのがコツです。
#背景美術
631
生え際の草は丈を短めにし、あまり影をつけないほうが自然に見えます。
#背景美術
632
古典絵画にみる明暗構成の例。同じ建物に雲の落ち影を落とし、舞台のようなドラマチックさを演出。明るい面には暗い面、暗い面には明るい面が接するようパズルしています。
#背景美術
633
陰影をつけるときは、3種類のエリアを意識すると、立体感や質感が出ます。
#背景美術
634
窓を描くときは、ポイントである窓の周囲の色に注意しましょう。
#背景美術
635
川岸を描くときのコツ
#背景美術
636
光の強さを出すには、それと対比する暗いトーンが必要です。
#背景美術
638
紅葉の色の作り方。光側、影側の光の色を決めたのちに、葉の色を重ねます。
#背景美術
639
石畳の情報量を上げたい時は、無理に汚れを足したりするのでなく、部分的に固有色を変えると良いです。
#背景美術
640
【フラクタルスタンプ】全体の形の縮小版が、部分を構成しているものに使えます。
#背景美術
641
間違った形を直すのに「間違ったところに合わせたパース線」を引き直す初心者と時々出会う。せっかく描いたところを消したくないという心理的抵抗が作る、間違った物差し。
でも学習によって、自分の心理と原理との距離感を測れるようになると難なく直せる。言ってみれば人の成長の法則かもしれない。
642
絵が上手い人は「全体のための細部」を描こうとするが、下手な人は「細部のための細部」を描こうとする。
643
秋桜の道
#スケッチ
644
仕事の絵しか描いていないことで、疲れていく人がいます。 ちゃんと仕上げなければいけない、という強迫観念にいつも縛られるためです。 スケッチよりもさらに肩の力を抜いた「メモ描き」を気軽にすると、原点を思い出しやすくなります。
645
「そうはいっても真っ白い画面を見ると、つい仕事モードにリセットされてしまう!」という方。 あえて100均のメモ帳(罫線とか入っていても気にしない)や安っぽいアプリなどを使うと、緊張がほぐれやすくなりますよ。 小中学校でノートの片隅に落書きしていた、あの感覚です(^^)
646
葉の配置は全体的なリズムでとらえましょう。
#背景美術
647
フレアに頼る前に、光源の照り返しをしっかり描きましょう。
#背景美術
648
画面外からの光の影響を描く時、空間が広がった感じがします。
#背景美術
649
光芒を描く時は、背景と一番明るい光色の間に、鮮やかな色のエリアをつくります。
#背景美術
650
ハイライトでものの稜線を感じさせることができれば、面の陰影も省略できます。
#背景美術