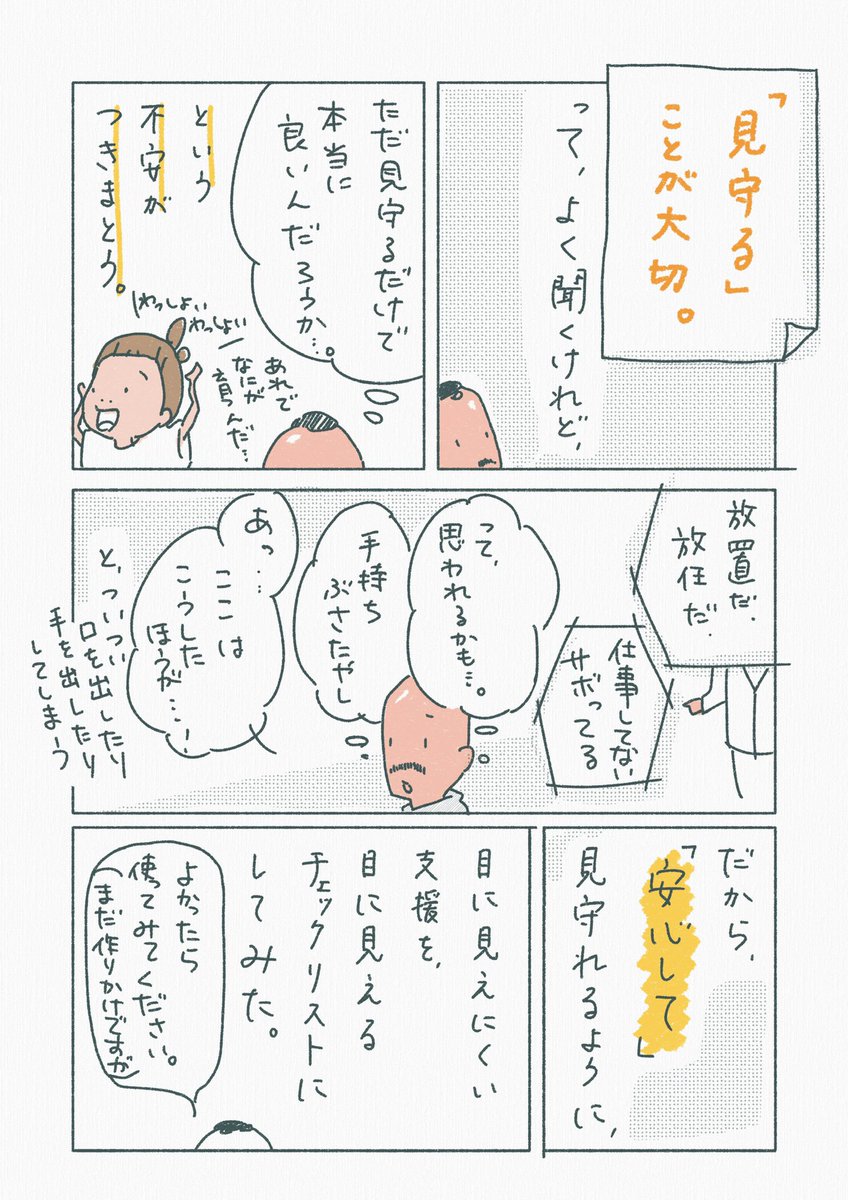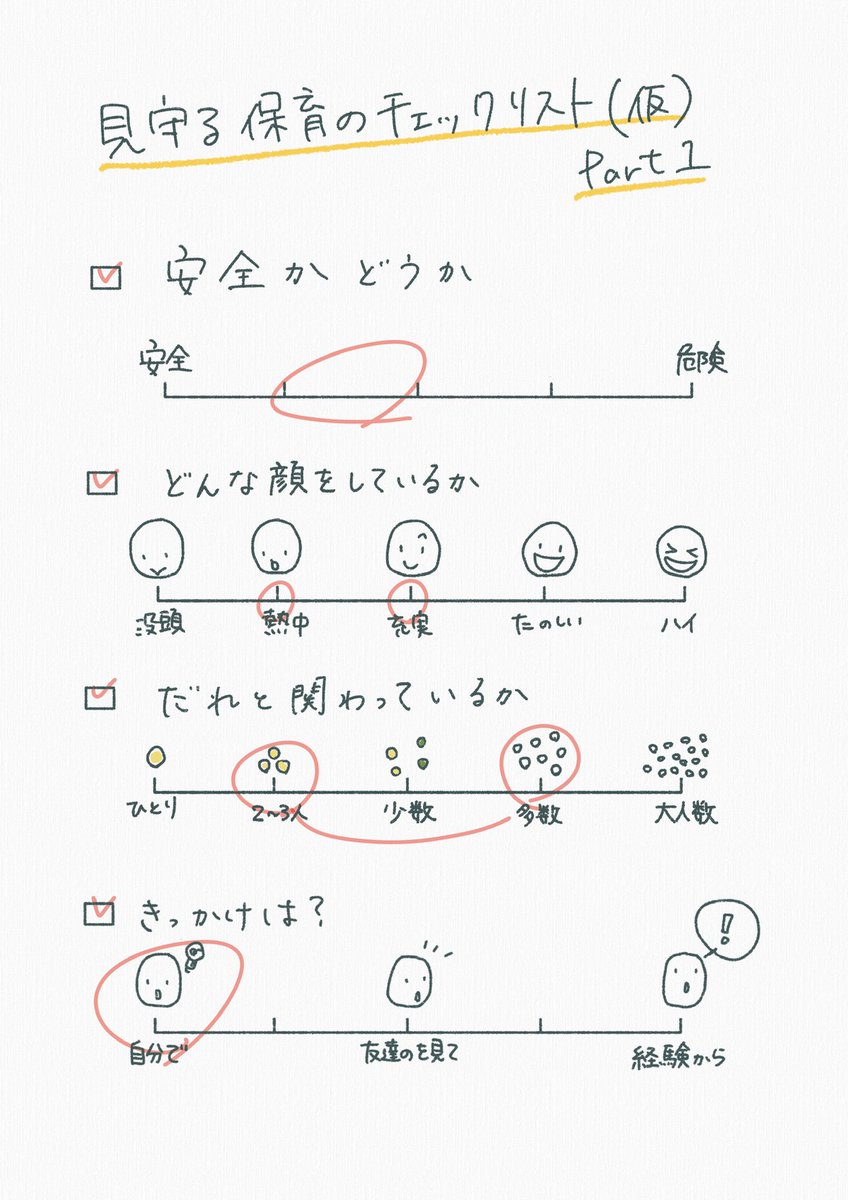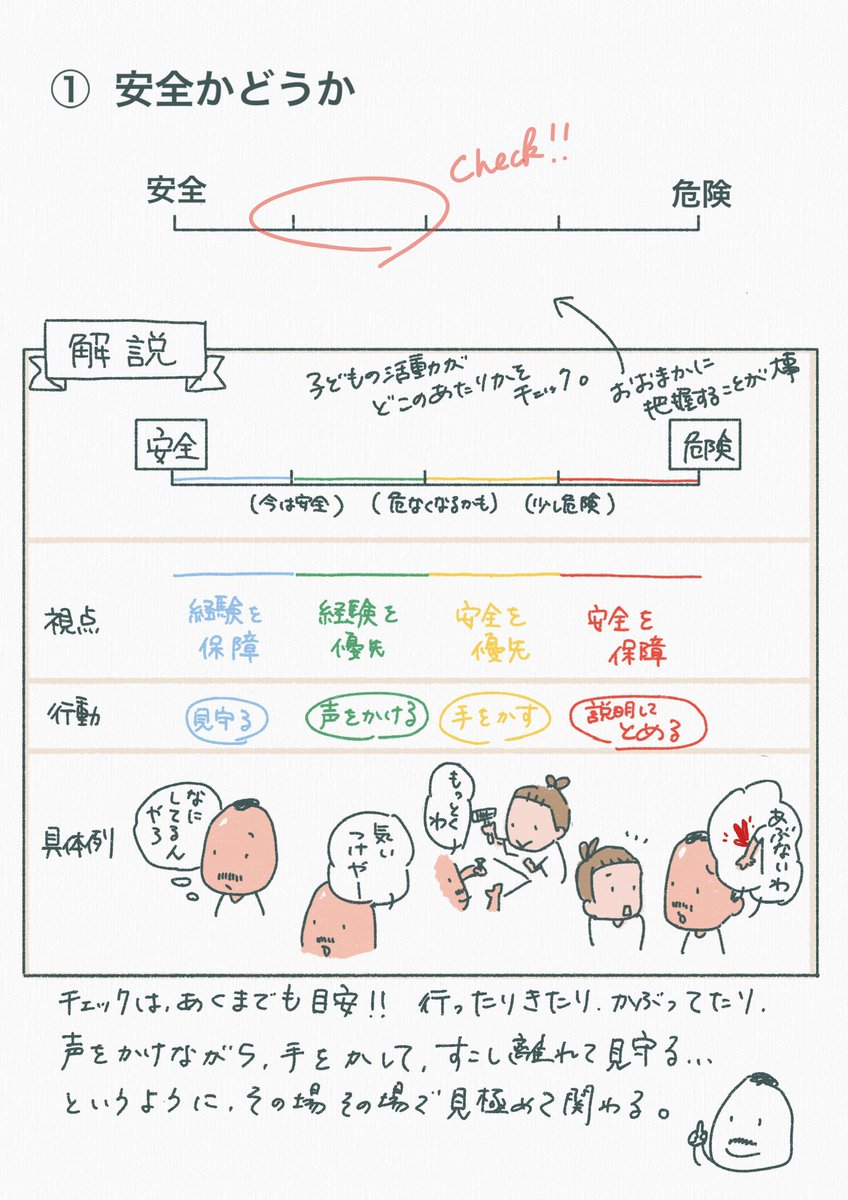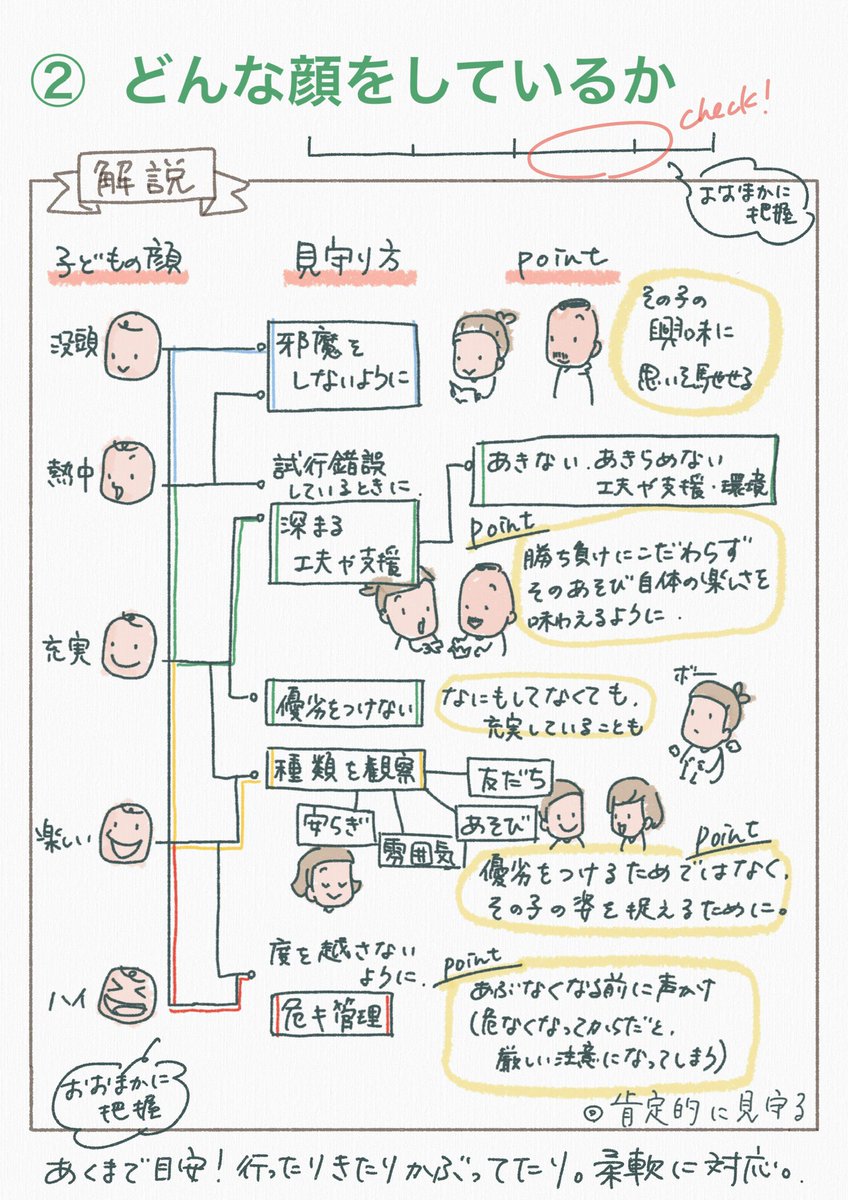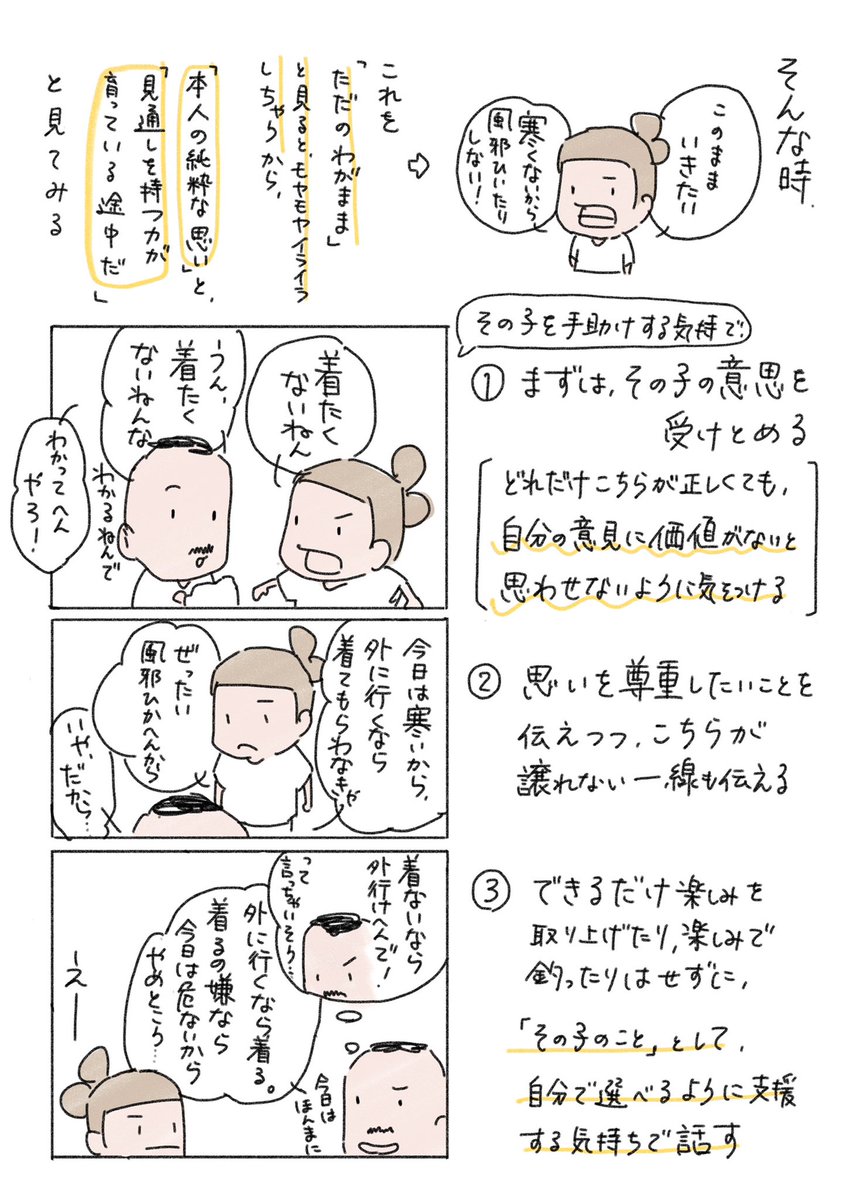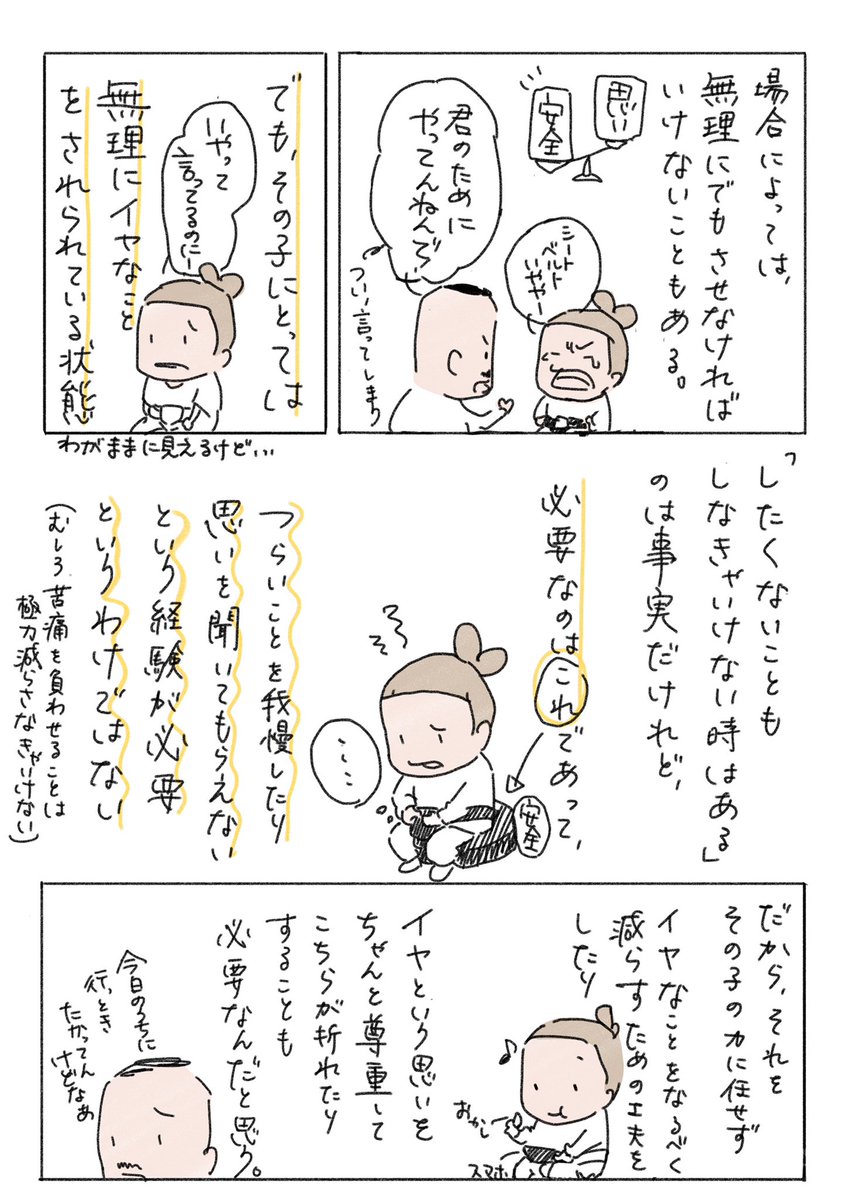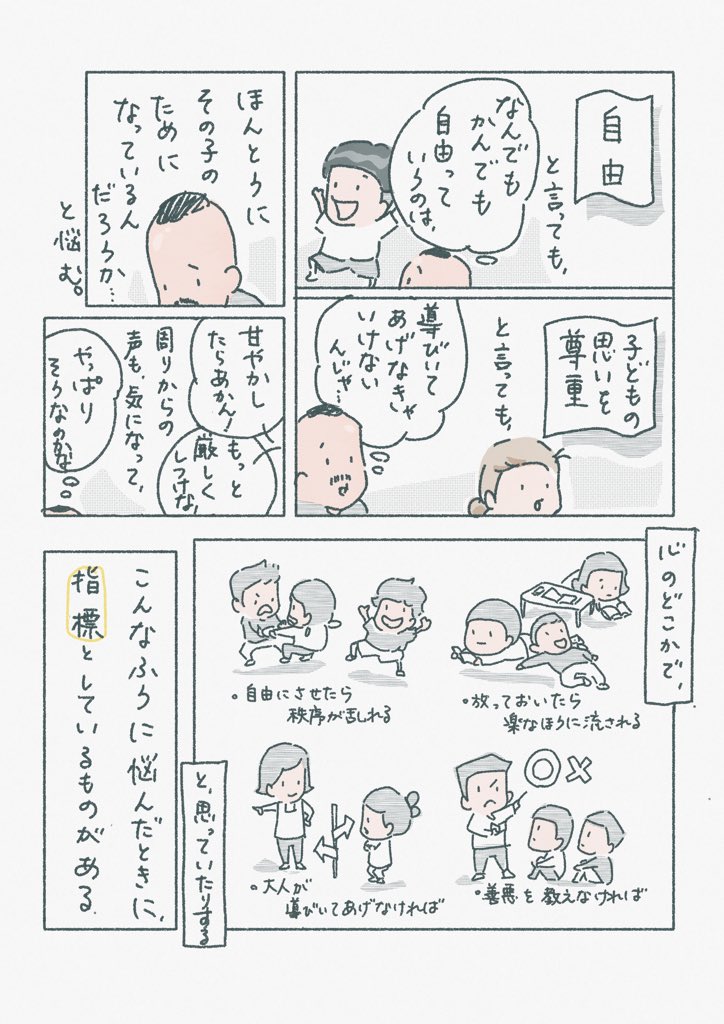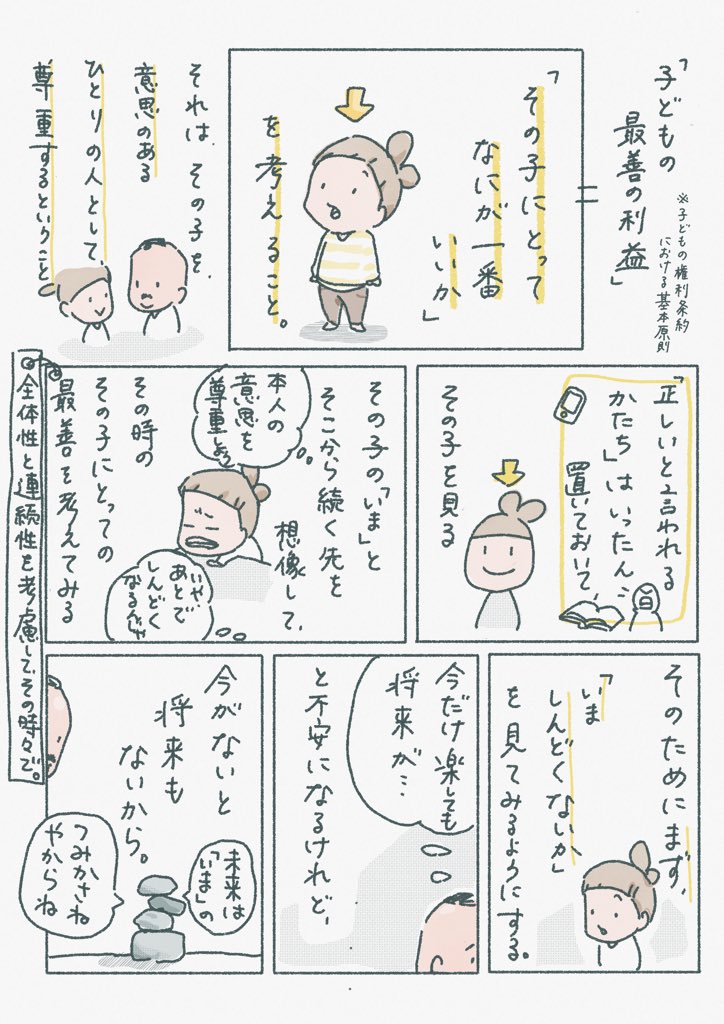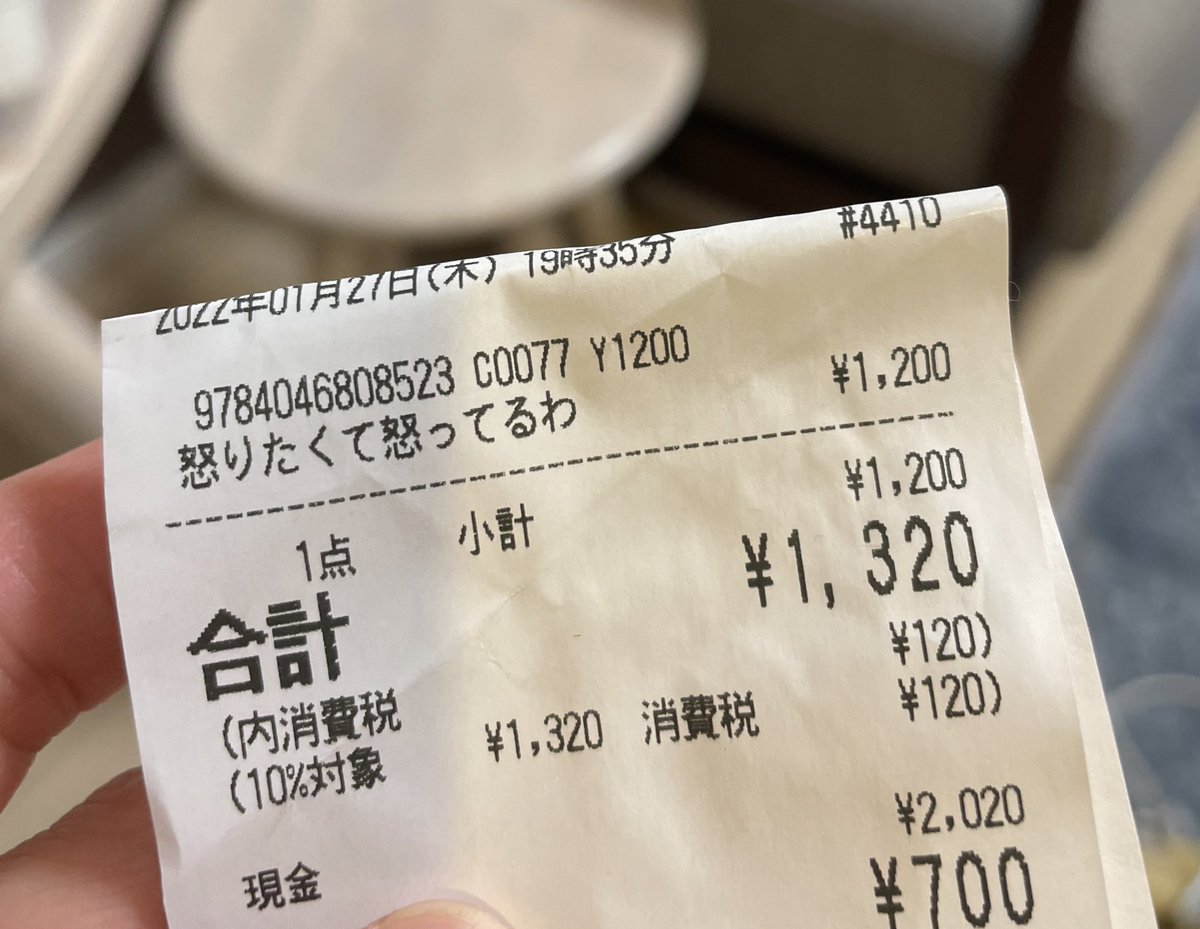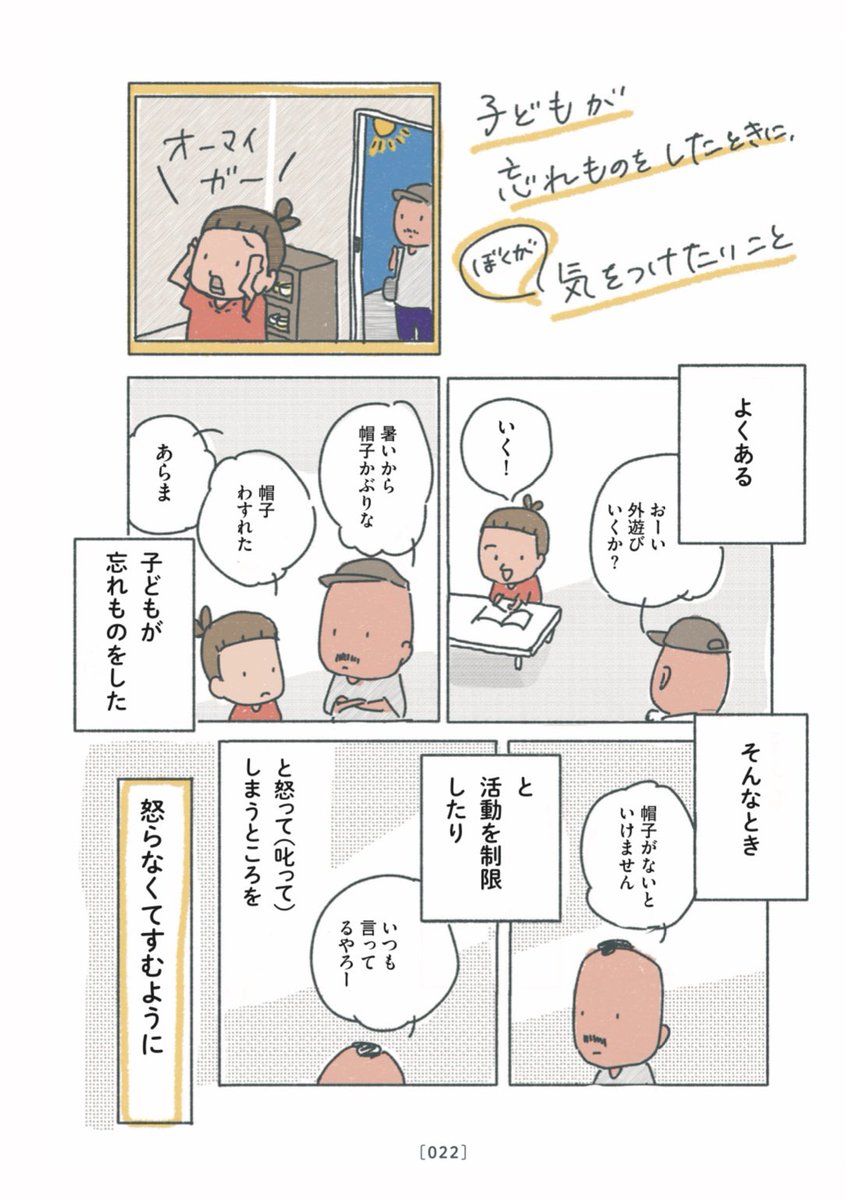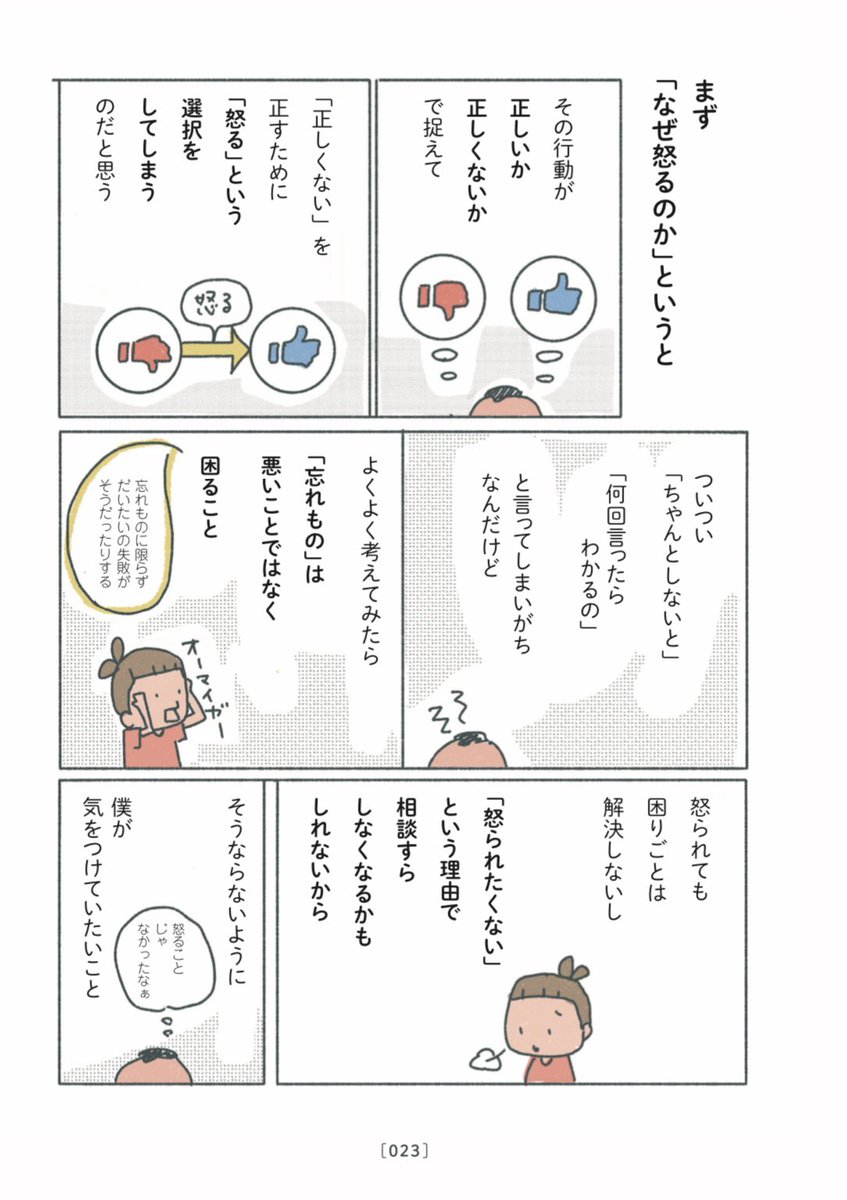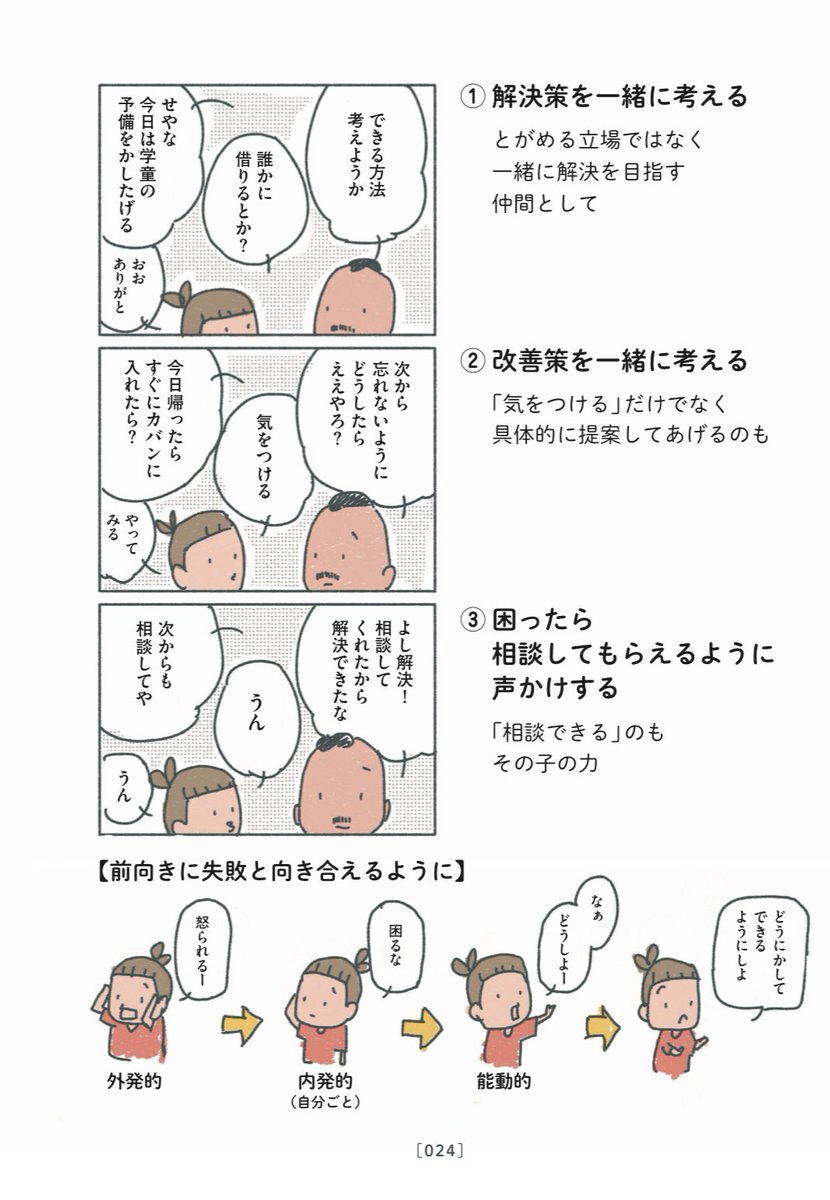126
「〇〇な親はダメ」「〇〇な子に育たないように」といって不安を煽ったり「こんな子に育つ」と謳うのを見るたびにしんどくなる。それを見てどれだけの人や子どもが追いつめられるんだろうって。
子育て支援で一番大切なのは、その人が前向きに子育てに向き合えることだよ。それができて、ようやく→
127
大人同士だけでなく子どもとの関係も、お互いを尊重し合ってやっていきたいという思いで書いた本が1月に出版されました。
無自覚に傷つけてしまっていた話から何を気をつけていきたいかなどを漫画と文章でまとめています。よかったら手に取ってもらえたら嬉しいです。
amazon.co.jp/%E6%80%92%E3%8…
128
今日から新しく連載が始まりました。
子どもと関わる中で葛藤することを共有する気持ちで書いていきます。いつもより短いです。答えはでないので、一緒に考えるきっかけになれば嬉しいです。
初回は、乱暴な物言いをしたりはっきりと言わない子との関わりで感じたことです。
chanto.jp.net/childcare/baby…
129
子どもに暴言吐かれたとして、子どもの言うことだから多めに見ようとは思わないし、嫌なことは嫌だよと伝えるべきだと思うんだけど、その嫌だという表明をするときにはちゃんと大人と子どもとの間にある力の差は意識しておかなければいけないなとは思う。ひとりの人として僕は嫌なんだと伝わるように。
131
否定語→肯定語にすることが基本とされているけど、そうとも言えないよなあと最近は思っている。例えば「走るな→歩こう」の場合、走ったらダメな場所は走ったらダメなだけで歩かなければならないわけでないんだよね。だから、正しくは「走ったら危ないから走らない方法で移動しよう」だ。で「具体的に
132
何度でも言うけど、「子育ての第一義的責任は親」というのは「親がちゃんとやれよ」ではないよ。難しいことや困ることがあったら公助や共助が備えていて支えるから、まずは安心してそれぞれの家庭で子育てをしてみようねってことだよ。周りがするのは責めたり追いつめることではなく支援することだよ。
133
色んな経験をしてほしいという思いで嫌がることを少し強引に誘ってしまう時には、その子がその経験とあわせて「やりたくないことをやらされた経験」もしていることを心に留めておきたい。結果的に楽しめていたとしても、それは誘った方の手柄ではなく、嫌なことでも楽しめたその子の力だということも。
134
135
過去の記事にこの話を取り上げています。いじめや誹謗中傷についてどんな風に解決の方を向いていくかを書いています。
note.com/1kani1dai/n/nb…
136
その子がその子の生活のために必要なものを自分で買っている(のを横で大人が見ている)だけだから、ゆっくりでいいんだよね。
そこに保護者がいると、管理できてない躾ができていない、そのせいで自分は待たされていると感じるのかもしれないな。
ただでさえレジって、誰も悪くないのに待たされている
137
排除されていく見えない人たちがいることを想像したい。
小銭を出すのに手間取ってるその人はもしかしたら、自分の大切な人かもしれない。自分には見えていないものがたくさんあるんだよね。
みんなに優しい社会は自分にとっても、自分の大切な人にとっても優しい社会のはずだ。そこを目指したいな。
139
危険な思想や人権を無視した発言を「許せない」と表明して、それをみんなが確認し合うのは大事なことだけど、その人をみんなで徹底的に叩き潰そうとする空気はただのイジメじゃないか。ダメなやつは排除していいという考えこそが許せなかったはずなのに、自分がそれを体現してしまってないか。怖いよ。
140
今ちょっと苦手なことやってるんだけど、こないだ8歳の友人が「プール苦手やってんけど、できなかったらできるとこまでやればいいって思ってやってたら嫌じゃなくなった」って言ってたの思い出して、5分おきに投げ出しそうになるたびに「できるとこまでやればいい」って言い聞かせてがんばってます。
142
誰かを気に食わないと思った時には、その気に食わないという感情がどこからきているのか探ってみる。真っ当な理由があったとしても、それでその人を攻撃することを正当化せず、その気に食わないという気持ちを自分が持つことを自分で肯定してあげるだけにする。「気に食わない、けど傷つけない」やで。
144
子どもが嘘をついていると気づいた時に、その嘘を見抜いて良い気になってしまうことがあるんだけど、子どもの嘘を見抜くのが僕の仕事ではないよなって最近思う。なんで嘘をついてしまうのか、嘘をつかなきゃいけない環境を自分が作っていないか。その嘘を責める前にできることはたくさんあるよなって。
145
多様な社会な実現で、しつけとマナーが滅びるという仮説
note.com/1kani1dai/n/n6…
146
嘘をつかせないのではなく、嘘をつかなくてもいい関係でありたいな。嘘を見抜く力ではなく、嘘だと分かったうえでなんで嘘をついてしまうのかを考えられる思慮深さがほしいな。正直でなければならない、ではなくて、正直であっていいという環境を作りたいな。
147
「愛情不足」なんて言葉は無視していい。測ることもできない曖昧なもので一方的な価値観を押し付けて責める言葉だよ。子育てに必要なのは行動だよ。叩かないとか、病気になったら病院に連れて行くとか。もし仮に愛着に課題があるとしても支援者はそんな言葉は使わない。誰かのせいにして解決はしない。
148
子どもが思っていたように育ってくれないと不安だったり残念だったりするかもしれない。けれど、よく考えたらそれって、その子がその子として育っているということだから、本当は素晴らしいことなんだよね。期待を裏切られたら裏切られた分だけ、その子はその子として僕の想像の外側で育っているのだ。
149
子どもが言うこと聞かなかったり、可愛げがないなと感じたりした時こそ、その子がその子として生きているのだと実感する機会にしたいな。
150
職員を休職や退職に追いやった当人を庇いその環境を野放しにして、潰れていく人たちをあっさり切り捨てるような現状を許していいのかな。弱かったとか合わなかったとか潰れた方のせいにして同じことを繰り返すのかな。それが保育や教育の業界でまかり通っていることが何より情けないし悔しいし悲しい。