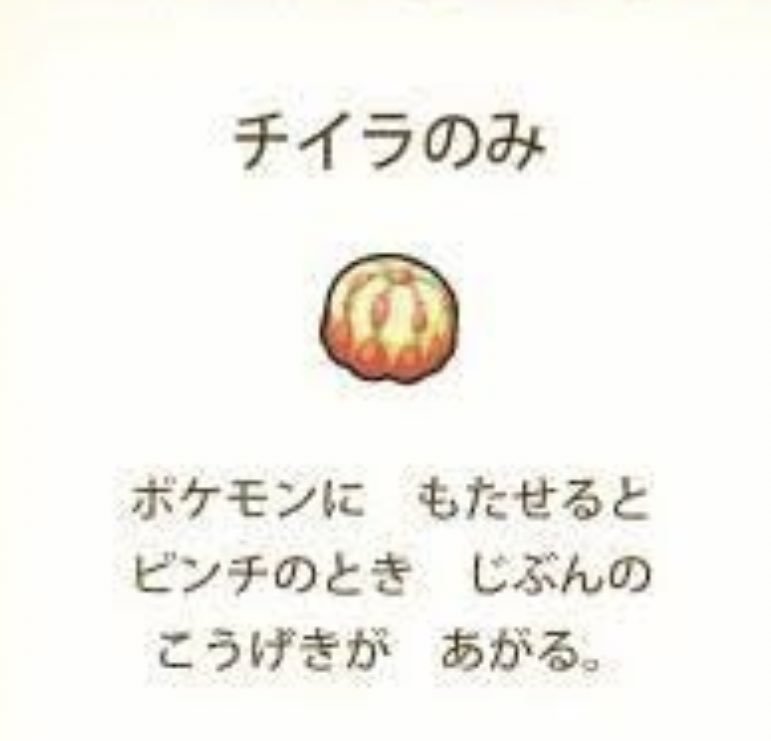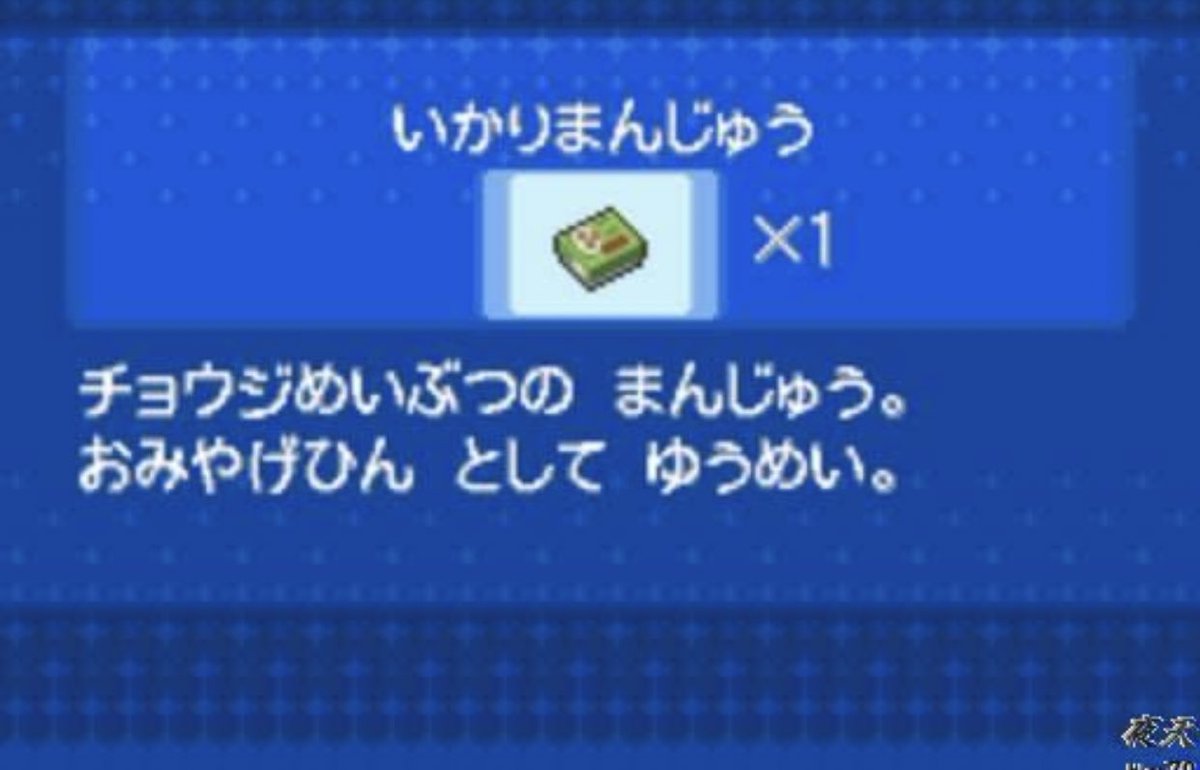276
@dayukoume 『動物を追う、故に私は〈動物〉である』を著したデリダの影響を受けた作品。言語等、人間に固有な幾つかの能力を挙げ、果たしてそれは固有なのか?と疑義を呈する議論を受け、「猫も歌うのだ!」と主張し猫と化した小梅氏は、動物と人間の境界を曖昧にし、人間性という西洋哲学の伝統を破壊するのだ。
277
@dayukoume 何故、抜け毛が「流れ星」とされるのか。哲学史に於いては、人間と宇宙との類比的関係から、人間は大宇宙に対し、ミクロコスモス(小宇宙)と捉えられてきた。そう、小梅氏は人間を小宇宙と捉えているのだ。小宇宙から抜け出た毛は…当然流れ星となる。大胆にも小梅氏は人間の中に一つの宇宙を見るのだ。
278
@dayukoume プリキュアはどのような存在だろう。我々にとってプリキュアは無論ヒロインであるが、そこには一種の偶像性が潜んでいる。偶像は、その死と同時に効力を失うが、有機的な身体を持つ小梅氏は自身の偶像化の為に全身の凍結による身体の保存を選び、“プリキュア”として崇拝される道を選んだのだ。遺作。
279
@dayukoume ハイデガー的「死への存在」を描く『100日後に死ぬワニ』におけるワニ君の死後、多数の商業展開が行われた。この商業化された「死」を、一部の人々は「電通案件」と呼んでいる。では、小梅氏はどうか。小梅氏は、自身の「まいチク」内での「死」が、決して商業化され得ないものだと強調するのだ。
280
@dayukoume 我々の持つ属性を色彩論の視座から言及する一作。個物の属性を「色」を用い次々と例示した小梅氏は最後に、「色はいろいろ…巴」と述べる。ゲーテの色彩環を巴という意匠を用い見事に示した小梅氏は、我々の属性もまた微妙なグラデーションから成るとし、個物の持つ属性を鮮やかに論じてみせたのだ。
281
@dayukoume エロ本充実コンビニの近くに引っ越した小梅氏の目的は当然性欲である。さて、ヴィルヘルム・ライヒは、マルクス主義と精神分析を結びつけ、プロレタリアートの性的欲求不満が政治的萎縮を引き起こすと主張した。ライヒの議論を踏まえた小梅氏は、大胆にもエロ本販売停止に反対するのだ。大問題作。
282
@dayukoume シンガーらは、『大型類人猿の権利宣言』を著し、人類の権利を類人猿らに拡張する試みを為した。此れに感銘を受けチンパン高校の先生になった小梅氏であったが、🐵らが🍌を神と見做す物神礼拝を行い、🍌から王権を授かったとする王権神授説を唱える現状に「🐵は所詮畜生だ!」と憤ったのだ。問題作。
283
@dayukoume 餅を見ただけで小梅氏はヒステリーを起こしている。先程注釈を加えた作品(お雑煮だと思ったらお雑巾でした)を踏まえても、小梅氏が餅(に潜む死)に対する恐怖を大いに抱いている事が分かる。日常に自己の死の可能性を見る小梅氏は、キューブラー=ロスの述べる死の受容プロセスを着実に歩むのだ。傑作。
284
ここで小梅氏は「圧力をかけられて震える鍋」という、擬人化を行なっている。道具をただプラグマティックなものとしてしか扱わない消費社会は、使えない道具をすぐに捨ててしまう。人間-道具の関係はプラグマティズムに支配されており、それが人間から道具へのパワハラたる「圧力」となっているのだ。 twitter.com/dayukoume/stat…
285
@dayukoume 「味覚」は、哲学史に於いて長らく低次の感覚とされてきた。一般に「何かを知る」というと、視覚や聴覚により「知る」のだが、小梅氏は視覚/聴覚優位の価値観を斥ける。🍎(視覚に拠る推定)を食した小梅氏は、それをミカンだと“味覚に依り”断定し、真なる世界を把握する為に味覚を用いよ!と説くのだ。
286
@dayukoume 不安を分析したハイデガーは、非本来的状態にある現存在がその事を漠然と自覚する事が不安に通じるのだと説いた。後輩芸人達の「不安」を分析した小梅氏は、後輩らにとっての非本来的状態の現前(リアル)が小梅氏自身であると悟り、彼らを本来的存在に戻す為、不安を齎す者として生きる事を決めたのだ。
287
@dayukoume 人生とは何かを思索した小梅氏は、「出会いと別れ」という定義から脱却し、生の段階説を発表した。この段階説によれば、生の第一段階は赤ちゃんであり、ヒトは常に未熟かつ他者に依存しなければ生きられない“人間”(ヒトの間の存在者)であるという。更に、第2段階の「あの世」では…
288
@dayukoume 鏡像段階説を唱えたラカンは、幼児は生後6〜18ヶ月の間に、鏡に映る自己の像を認識し、自己像を“自己”として同定するとした。さて、窓は確かに鏡ではないが、鏡の役割を果たす。実は幼児である小梅氏は、鏡像段階を経て、窓に映る白が雪ではなく、自身である事に気付き、自我を形成したのだ。処女作。
289
@dayukoume 小梅氏は夢見の状態だったと考えられるが、その夢でまたしても「東京湾に沈められる」という死を経験している。さて、シュタイナーは夢見の状態で、我々の自我が霊的世界に抜け出るとした。“象徴としての死”…小梅哲学の中心概念なのだが…を霊的世界で行う小梅氏は、平成を“殺し”、令和を生きるのだ。
290
@dayukoume 異端児とは、即ち狂人である。人間理性に全面の信頼を寄せた嘗ての西洋社会では、狂気は排除され、“無かった事”にされた。だが、確かに、そこに“異端児”は“居た”のである。人間理性に疑義を投げ掛ける小梅氏は、狂気の存在を身を以て示し、哲学界の異端児として西洋哲学の伝統を破壊せんとするのだ。
291
コミュニケーション的行為などを通じて、我々は「他者との相互理解」を深めるべきと考えられている。だが、我々は他者を「真に理解すること」が出来るのだろうか。話しても「意味がわからない」側面が、他者にはあるのかもしれない。小梅氏にとって、他者は、「根源的な理解不能性」を有しているのだ。 twitter.com/dayukoume/stat…
292
@dayukoume ポケモンに於ける進化は、ダーウィン的な、機械論的進化論に基づくものではない。寧ろラマルク的な、目的論的な進化だ。さて、ここでのライチは、チイラの実を指すのではないか。すると、中華まんは「いかりまんじゅう」を指す。小梅氏は、攻撃性を開花させたライチュウの様子を描き出したのだ。駄作。
293
@dayukoume ちなみに私はビアンカ派です。
294
@dayukoume 『神と髪』を著した神学者カール・レーフラーによると、日本語の「髪」の語源は「神」であり、その有機性に我々日本人はアニミズムの精神を見出したのだという。さて、永久脱毛を行ってしまった小梅氏はその死を嘆く。「髪は死んだ」…レーフラーの一節を小梅氏は見事に描いてみせたのだ。傑作。
295
@dayukoume 博物館に保存される物品は恐らく、「価値がある」とされる物品である。神秘主義思想に傾倒し、未来視の能力を手に入れた小梅氏は、「一万年後の価値観」から棄てられる自身のミイラを見て嘆き、博物館の仕事は、相対的な価値観から、凡ゆるモノを保存する事ではないか!?と博物学に疑義を呈したのだ。
296
@dayukoume 先日も述べたが小梅氏にとって「お餅」は死の象徴であり、欲望の対象でありながらも消費が不可能な存在である。ラカン的に言えば、欲望の不可能性から、父性隠喩として「ライオンのちんちん」が想像的にファルスの領域に現れたのである(🦁は父性)。小梅氏は見事に🦁の男性器を食してみせたのだ。駄作。
297
「食」と「性」の関係は根深い。フロイトの議論を持ち出すまでもなく、「棒状」のものが口に含まれるとき、我々は一種のエロティシズムをそこから連想してしまう。「ごぼう」はまさしく象徴的な「チンチン」なのだ。 twitter.com/dayukoumeAI/st…
298
@dayukoume プルードンは「財産とは盗みである」とし、所有概念を批判した。強盗は一般に悪だが、1億円の占有者もまた強盗であり、悪である。その悪は、生命維持に牛乳を必要とするゴジラの命すら奪う。プルードンの影響を受けた小梅氏は、収奪者たるゴジラ達が実は盗まれた側なのだと逆説的に描いてみせたのだ。
299
@dayukoume 遊戯王カ〜ドは、決闘者達にとって生死や人生を懸ける熱き競技である。さて、決闘者である小梅氏は、遊戯王のパックを大量購入したのだが、一発屋であり、収入が無く、100パック(約一万五千円)で自己破産してしまう。この事を畜生と嘆いた小梅氏は、大胆にもカードを“拾う”事を推奨するのだ。駄作。
300
@dayukoume 言葉により世界を分化出来ぬ存在にとって、目に映る光景は「光景」ですらなく、まして「世界」ですら無い。その視覚情報は科学的原理に還元したもの……即ち光に過ぎないと言えるだろう。小梅氏は、「光」が言語を伴い初めてゴボウへと分化される様を描き、言語論的転回以降の視覚認識論を論じたのだ。