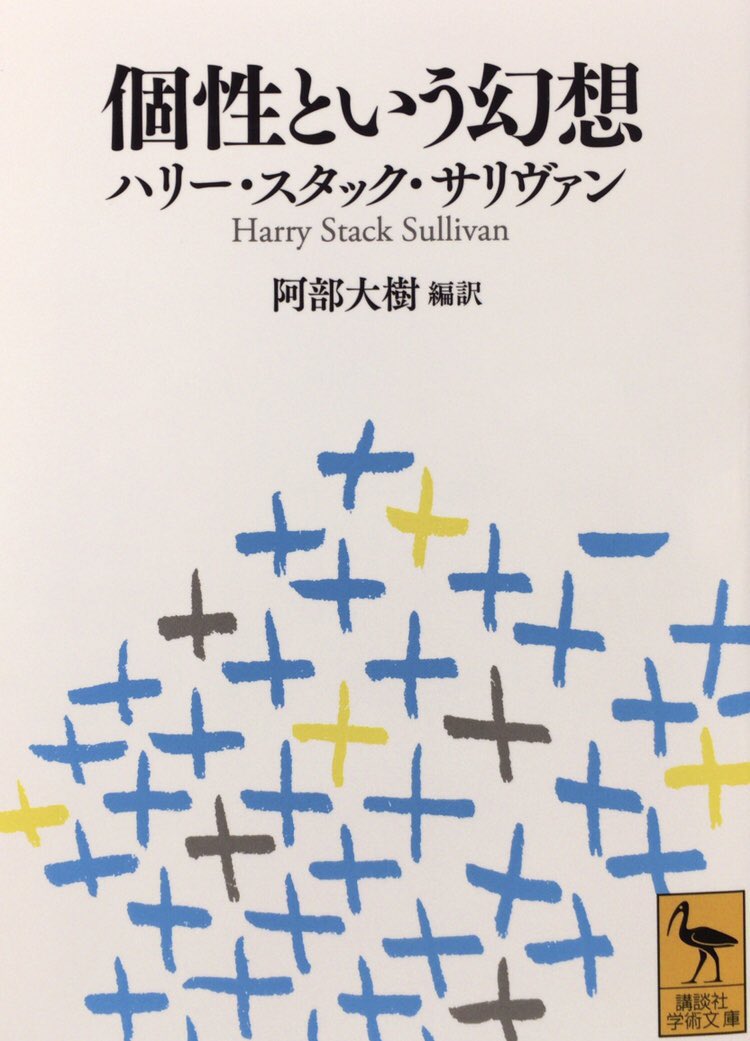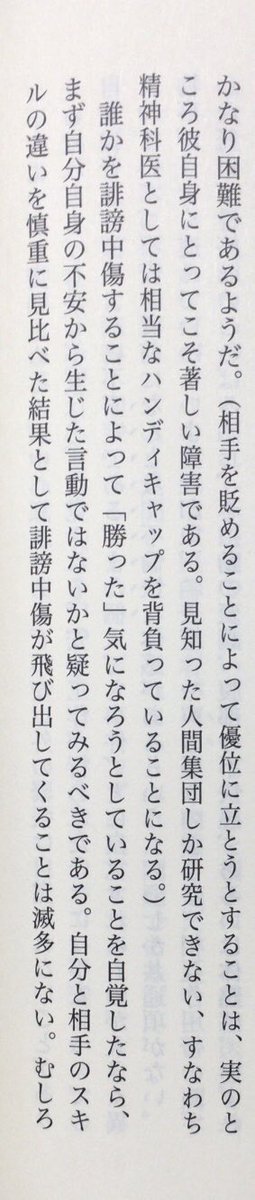401
402
404
405
406
407
408
409
410
411
412
414
416
417
420
当選して議員になる方に言いたいのは、今後の政治家生活において、一番奮闘したのが今回の参院選の選挙活動だった、ということにならないようにしてもらいたい。
421
422
423
424
425