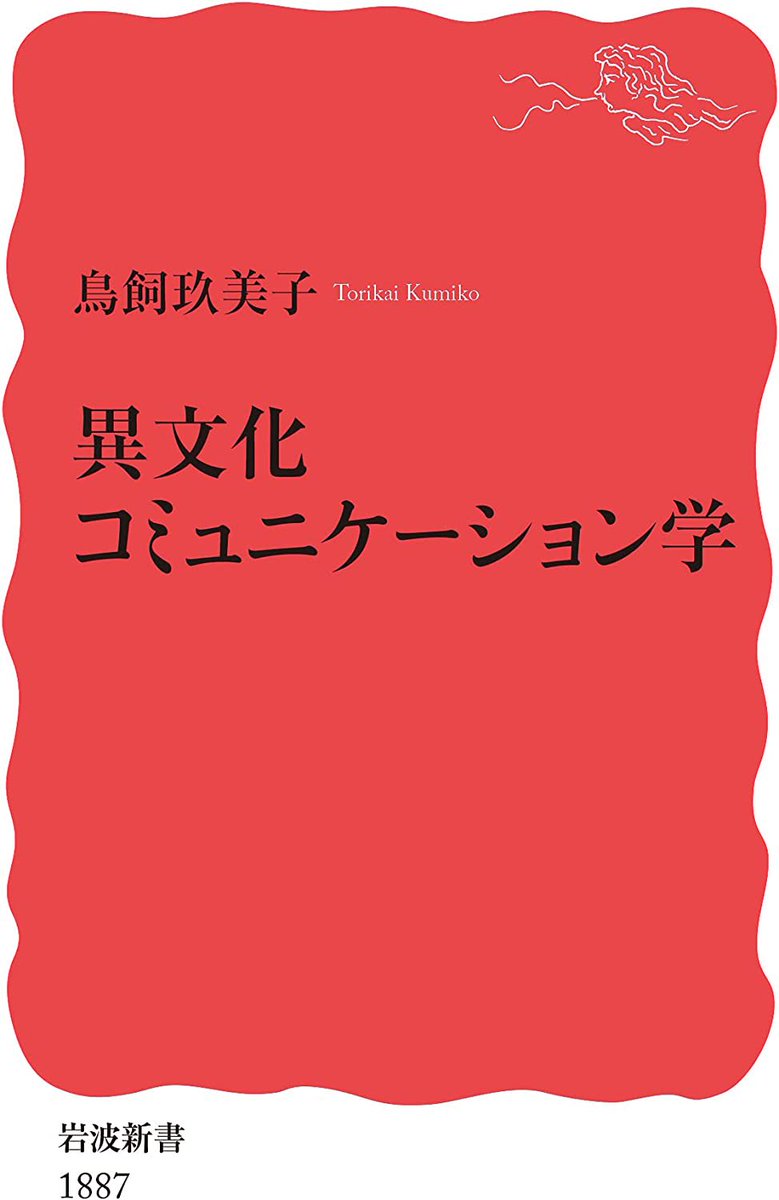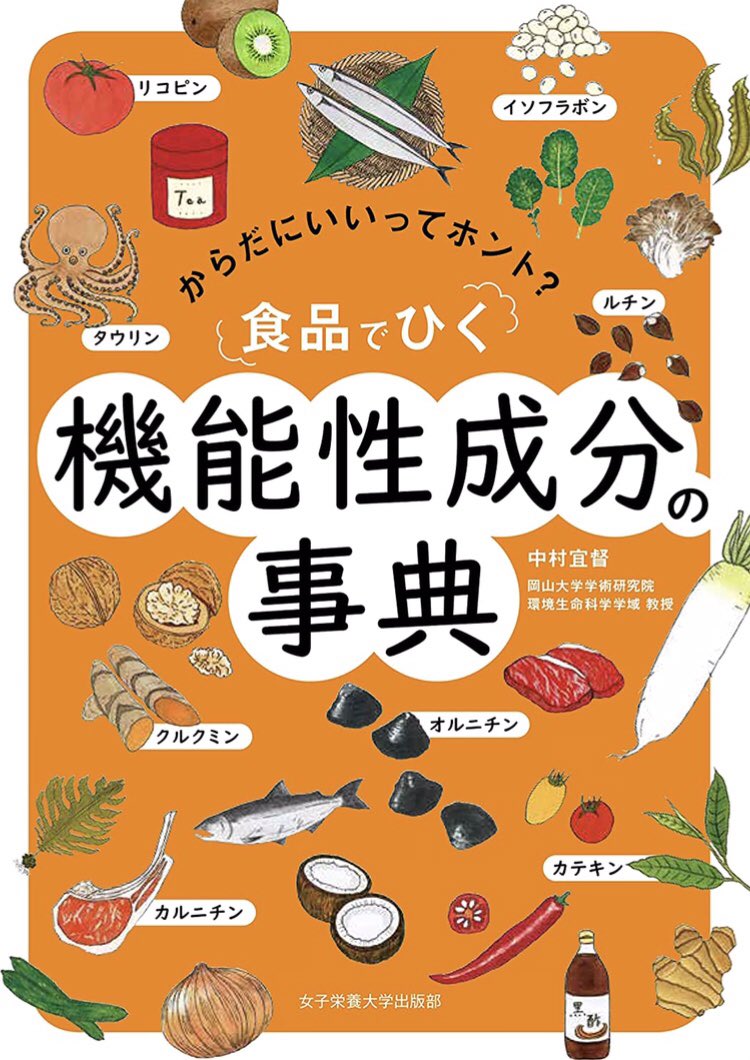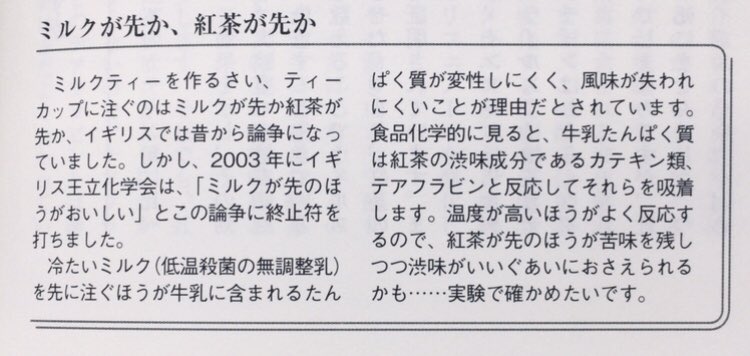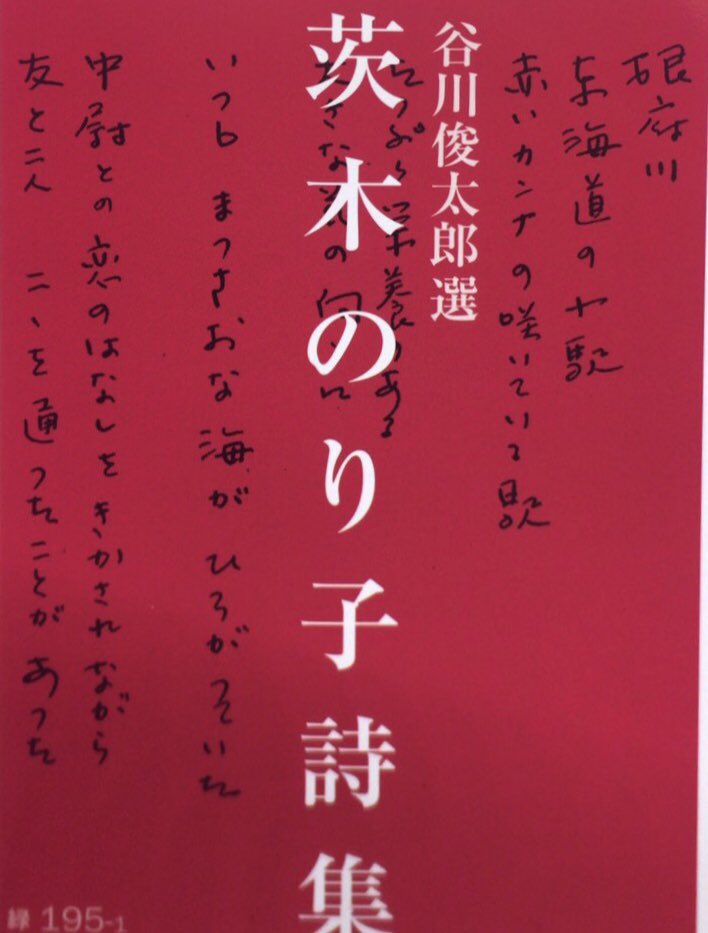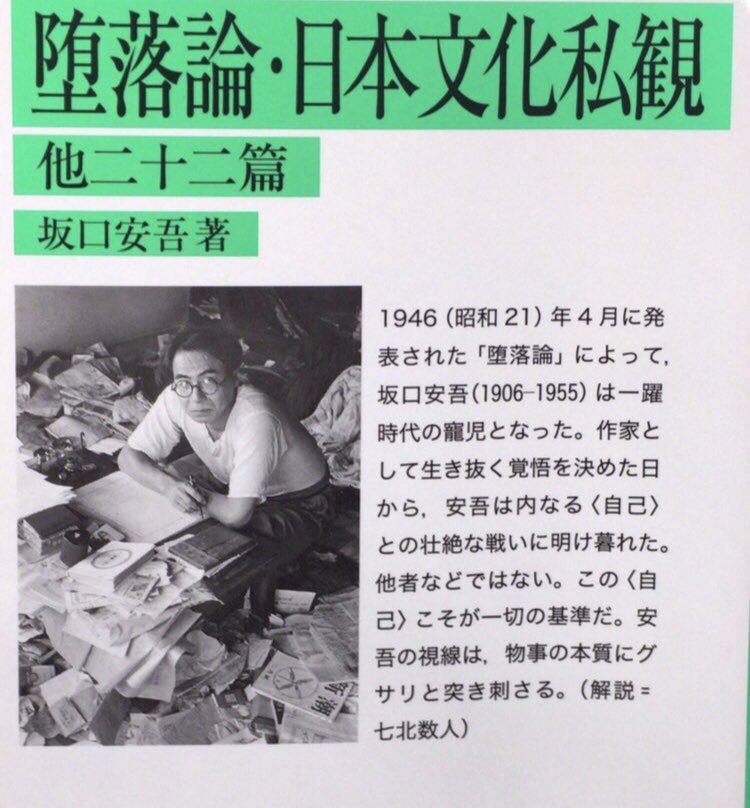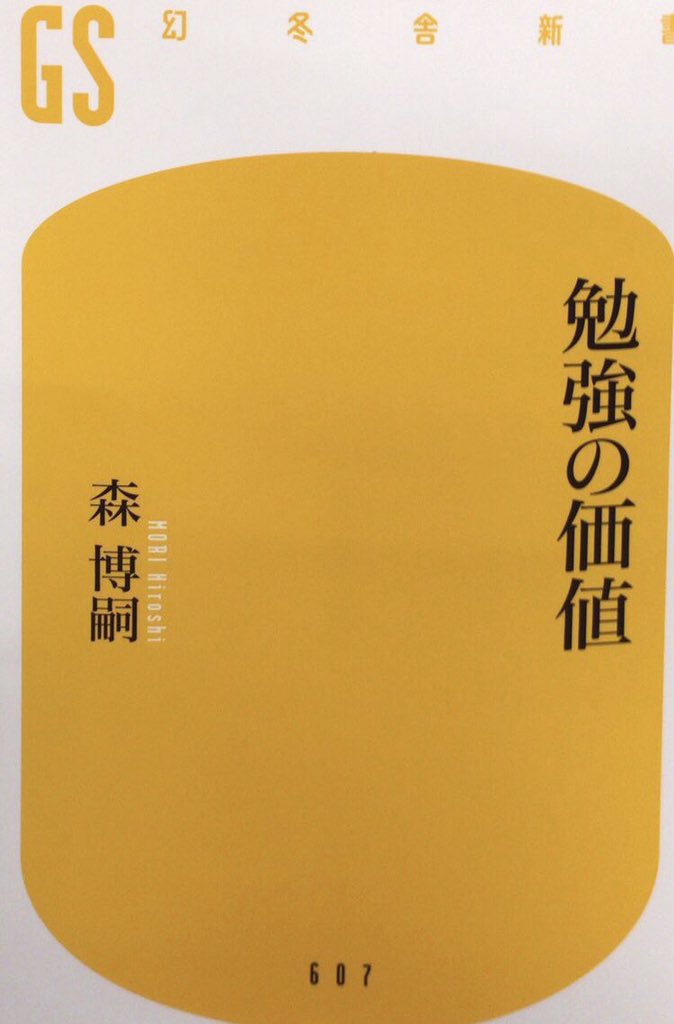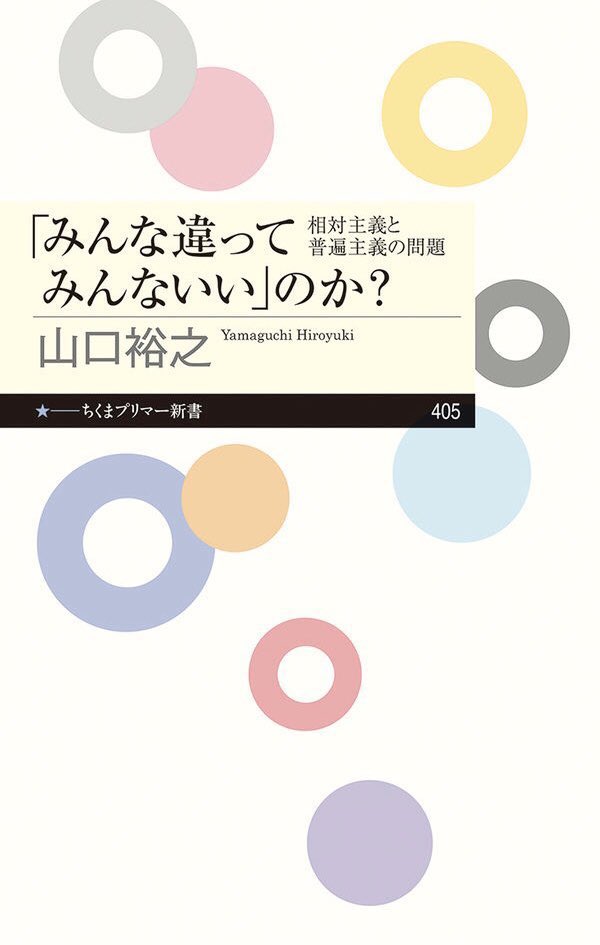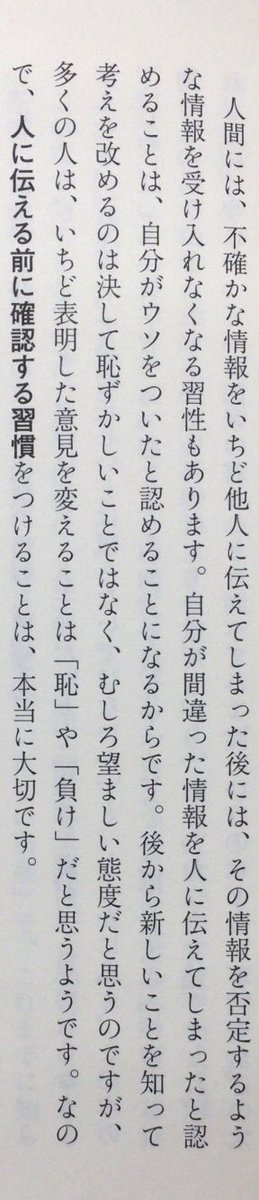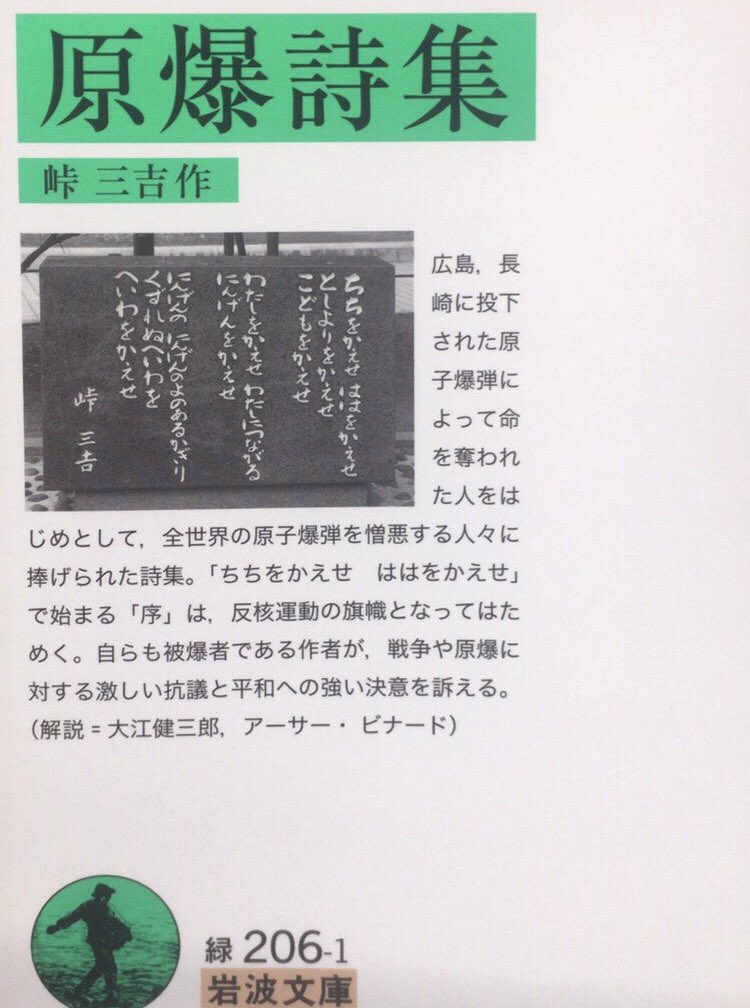1176
1177
1179
1180
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
「世界の猫の呼び方」
「猫(イエネコ)の世界共通の呼び方(学名)は「Felis silvestris catus(フェリス・シルヴェストリス・カトゥス)」です。」
(参照:服部幸監修『ニャンでかな?』P114)
#猫の日
1199
1200