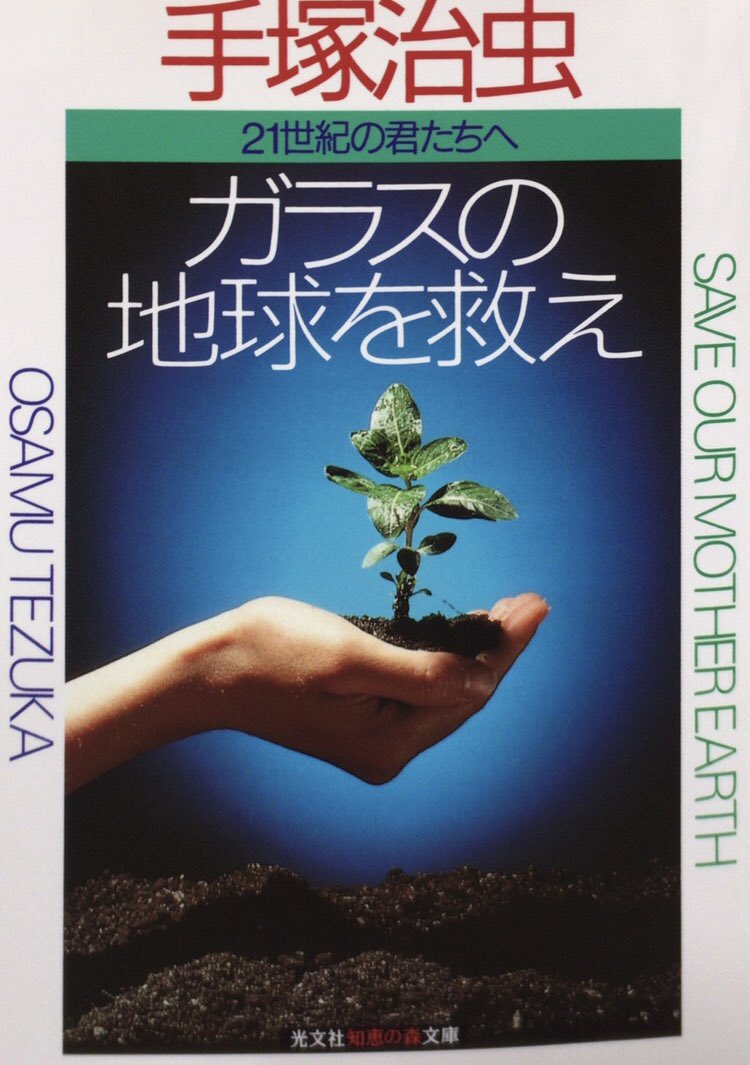1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
知人の古本屋店主と話していたとき、「「紙の本」という呼び方が好きじゃない。電子書籍の存在に引きずられている」という言葉に接したことがある。
上記の「紙の本」や「回転しない寿司」「白黒テレビ」のように、新しく登場したモノ・コトに対応して生み出された呼び名を「レトロニム」という。
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
誰かを擁護するときに、一番に「実際に会ったらいい人なんだよ」と「人柄の良さ」を強調してくる人は信用ならない。
1167
1168
1170
1171
1172
1173
1174
1175