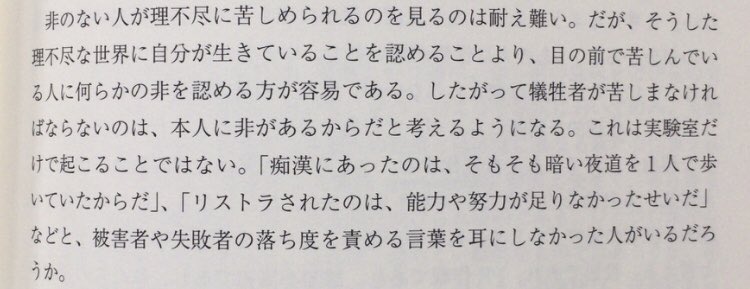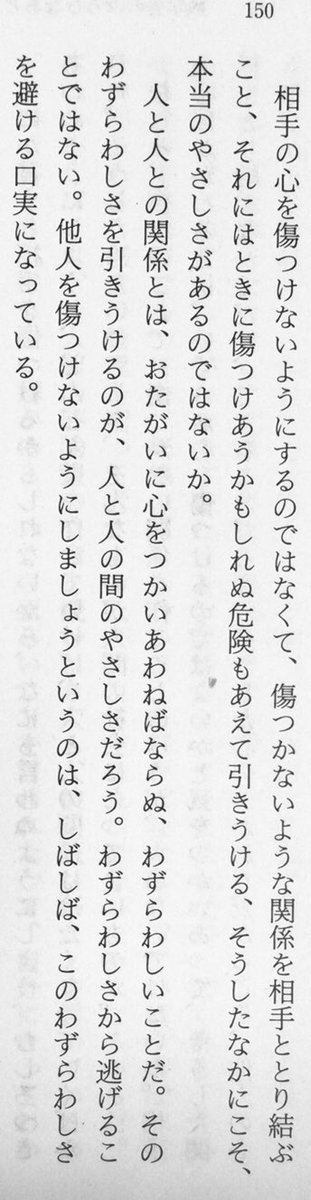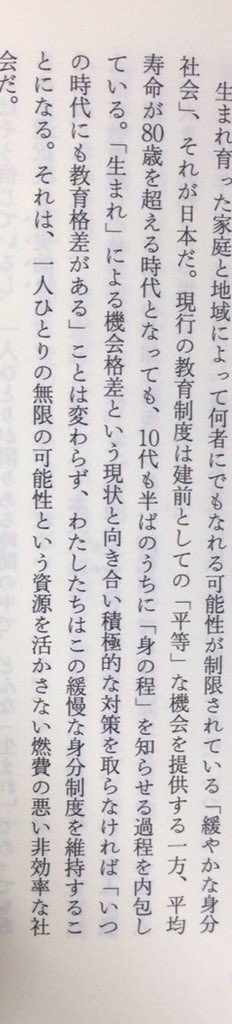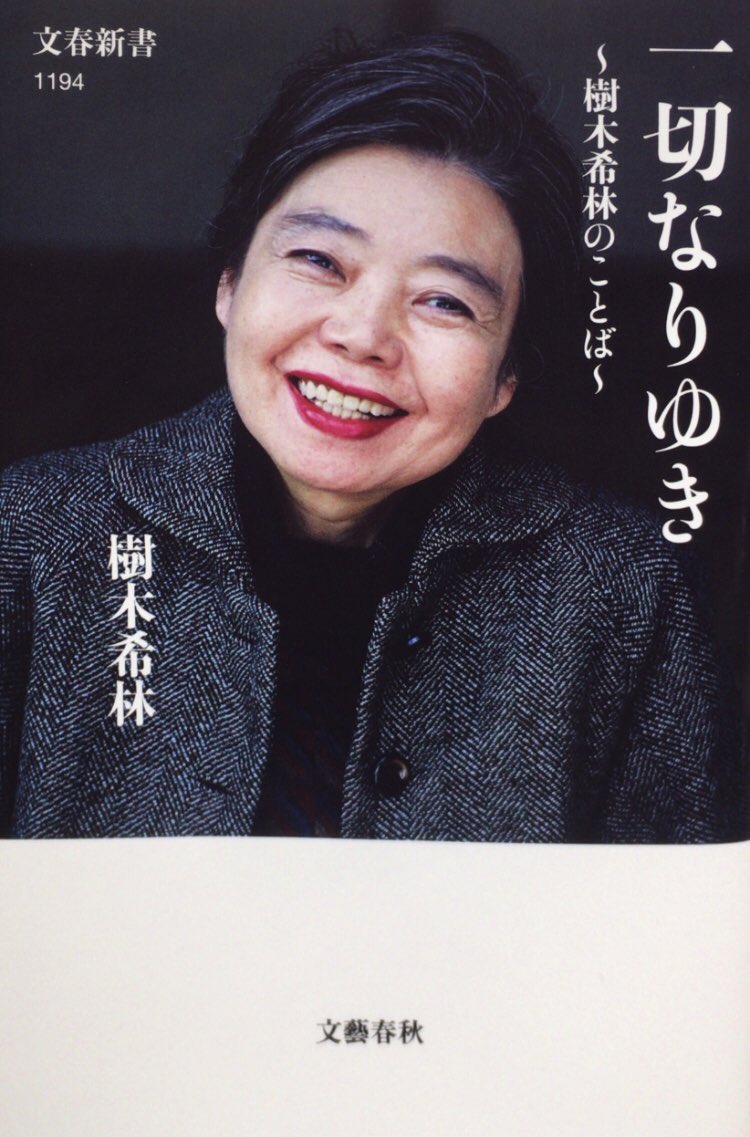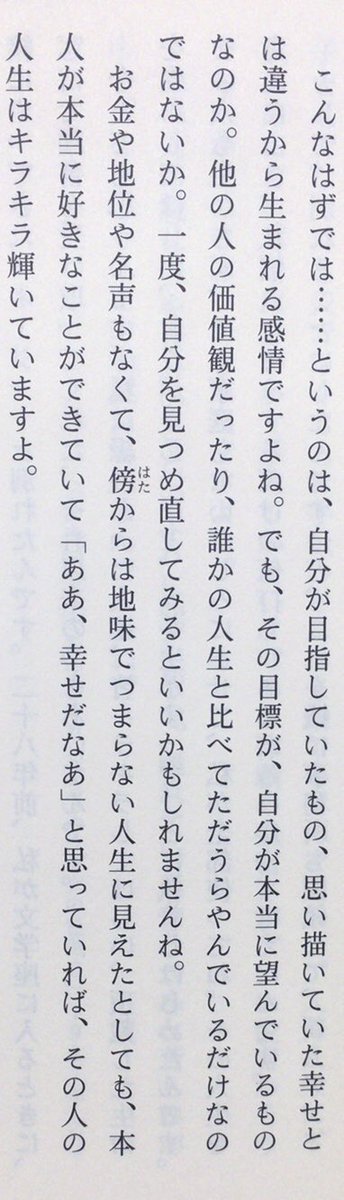1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
書店で気になる本を見つけたとき、家賃・食費・光熱費のことが頭をよぎって、購入を断念する人が多い国より、書籍代を充分に確保できる経済的余裕があるため、迷わず購入できる人が多い国の方がいい。
1110
1112
「言語というものは、有限な語彙と文法規則をつかって無限に多様な文を生み出すことができる奇跡的な想像力を持った道具であり、人間だけが駆使できるものです」(沼野充義・文、『ことばの危機』集英社新書、P114)
amzn.to/3XsS2jZ
1113
1114
【2023年度大学入学共通テスト(国語)出典一覧】
①柏木博『視覚の生命力』、呉谷充利『ル・コルビュジエと近代絵画』
②梅崎春生「飢えの季節」
③源俊頼『俊頼髄脳』
④白居易『白氏文集』
1115
1116
「音楽そのものにどれだけの力があるのかなんて、はっきりしたことは言えません。人によってはなんの意味も持たないということもあるでしょう、でも、ふとした瞬間に自分の中に音楽が入り込んで来ていることに気付く」(高橋幸宏『心に訊く音楽、心に効く音楽』より)
amzn.to/3waFkL3
1117
1118
1120
1121
1122
1123
1124
1125