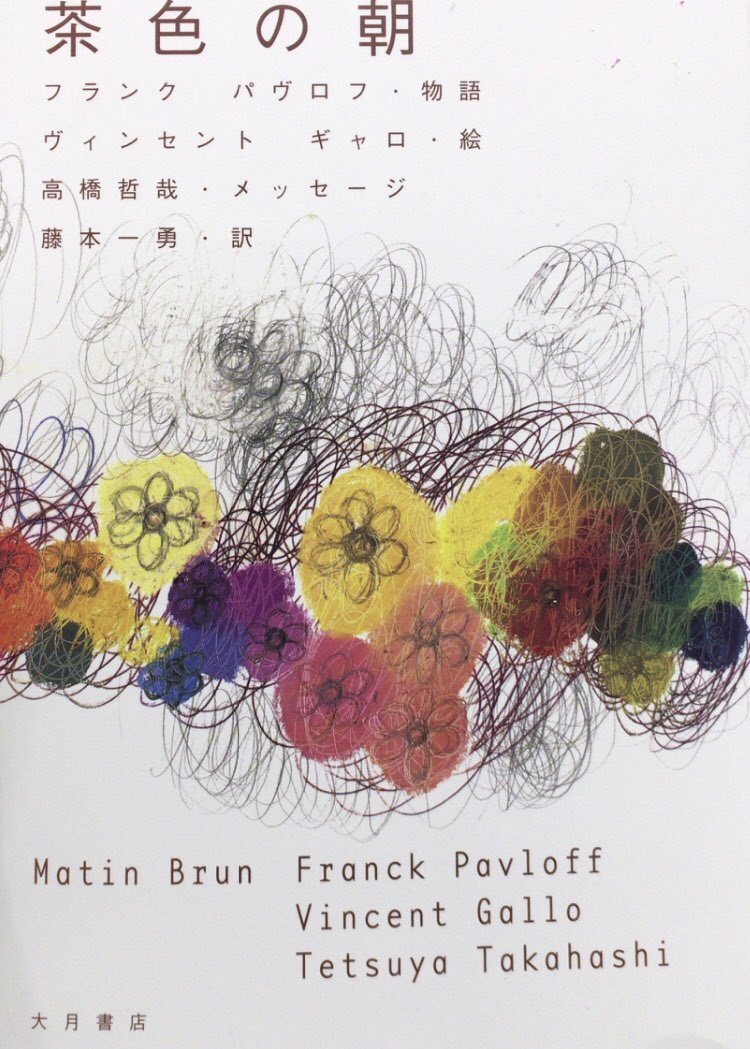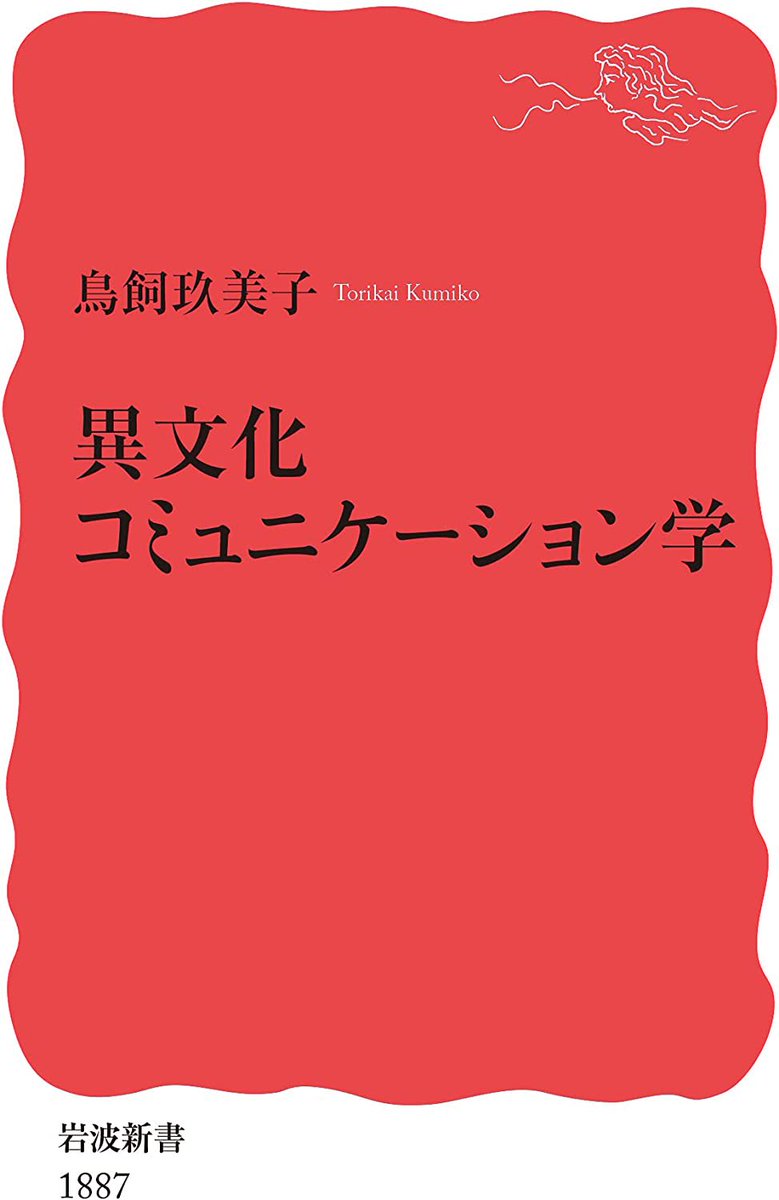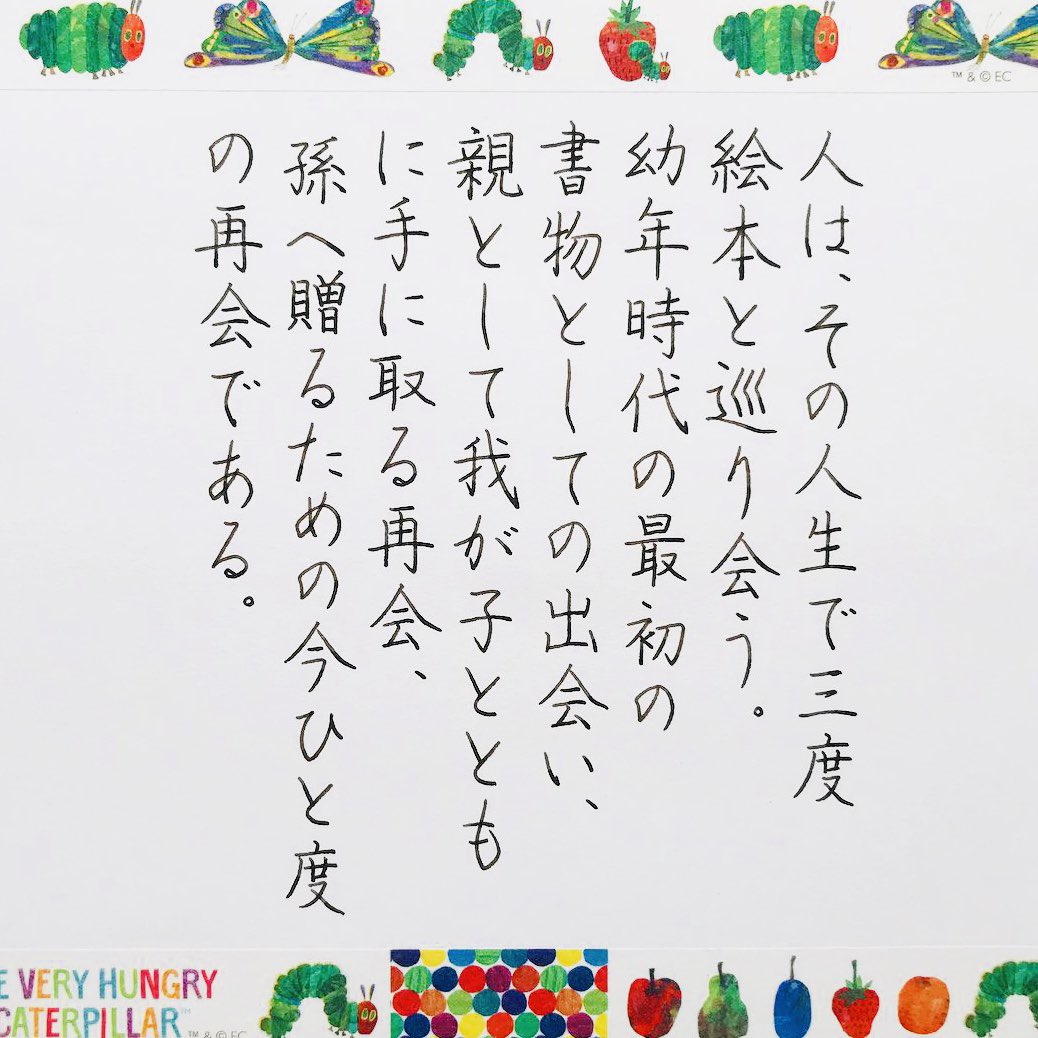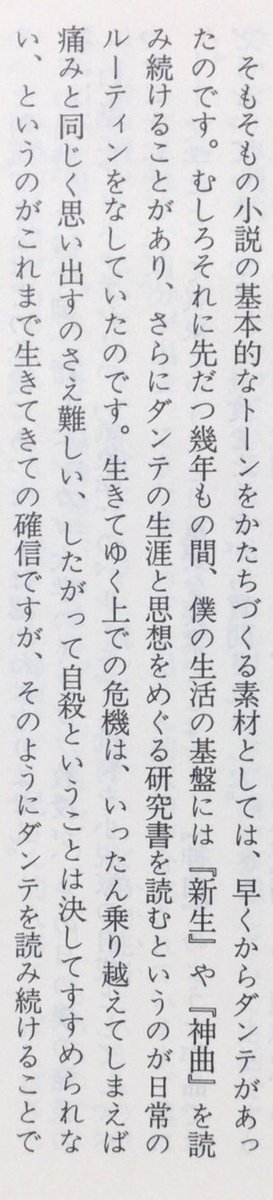201
203
204
205
206
209
210
211
212
213
214
大学で歴史学を専攻すると、所謂「歴史好き」の人と話が合わなくなる。
215
216
217
「go to read」という形で、図書カードを配って欲しい。本を読めば、自宅にいながら旅ができる。
219
220
「本好き」と言っても色んな形がある。
友人の一人は、ある一つの作品を文庫本がぼろぼろになるまで再読し、「買いなおして、これで三代目」と教えてくれた。
夢中になって何度でも再読できる作品に出会えた友人を、羨ましく思う。
221
SNSがなければ、刊行されていることすら気づけなかった書籍というのが沢山ある。書店に足繁く通ったとしても、自身の興味により視野が狭くなることは避けられず、どうしても見過ごしてしまったり、偏見から手に取らない書籍が生まれてしまう。この点で、SNSは自分と本をつなげてくれる貴重なツールだ。
222
最近、「とりあえず著名な人物の推薦文を載せておけばいける!」という考えが透けて見える帯をよく見かける。勿論こういう帯を見て「買ってみよう!」と思う人もいるのだろうが、一方で、手にとるのを避ける人もいるのである。「こんな帯でなければ、買ったかもな……」みたいな感じで。
223
224
それぞれ括弧には名前があります。
○( ⇨パーレン(かっこ)
○【 ⇨すみつきパーレン
○{ ⇨ブレース(波かっこ)
○〔 ⇨キッコー
○[ ⇨ブラケット
(岩波書店の栞より)
#意外にこれ知られてないんですけど
225