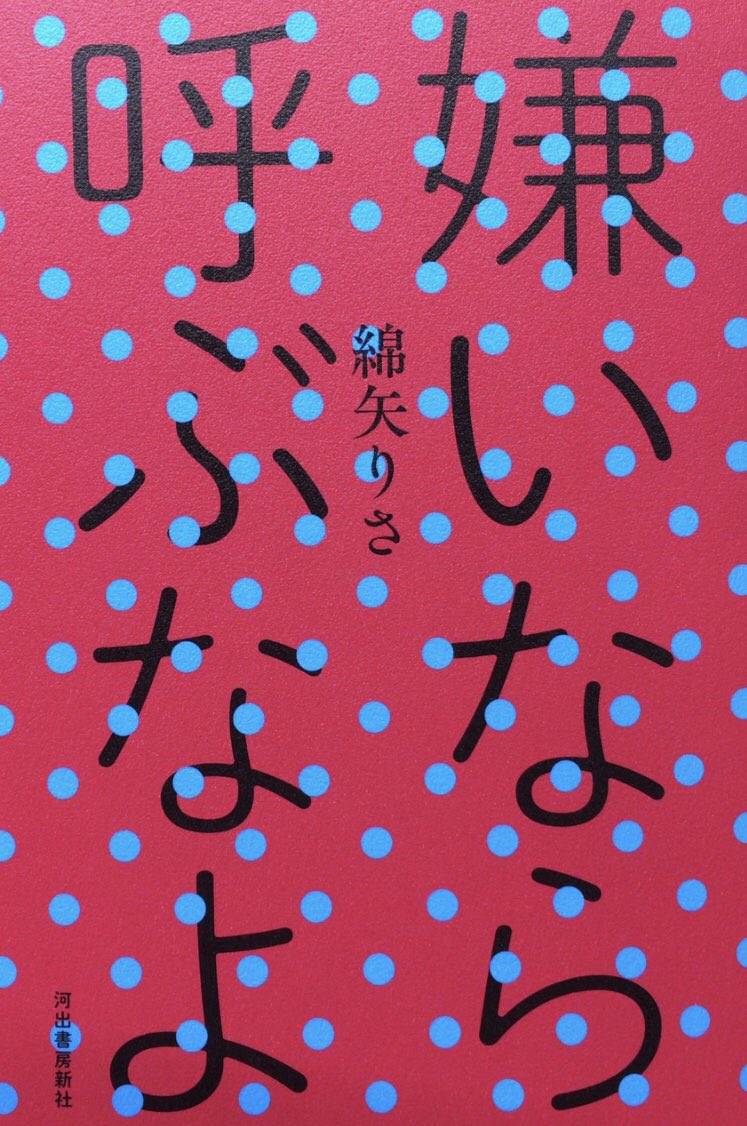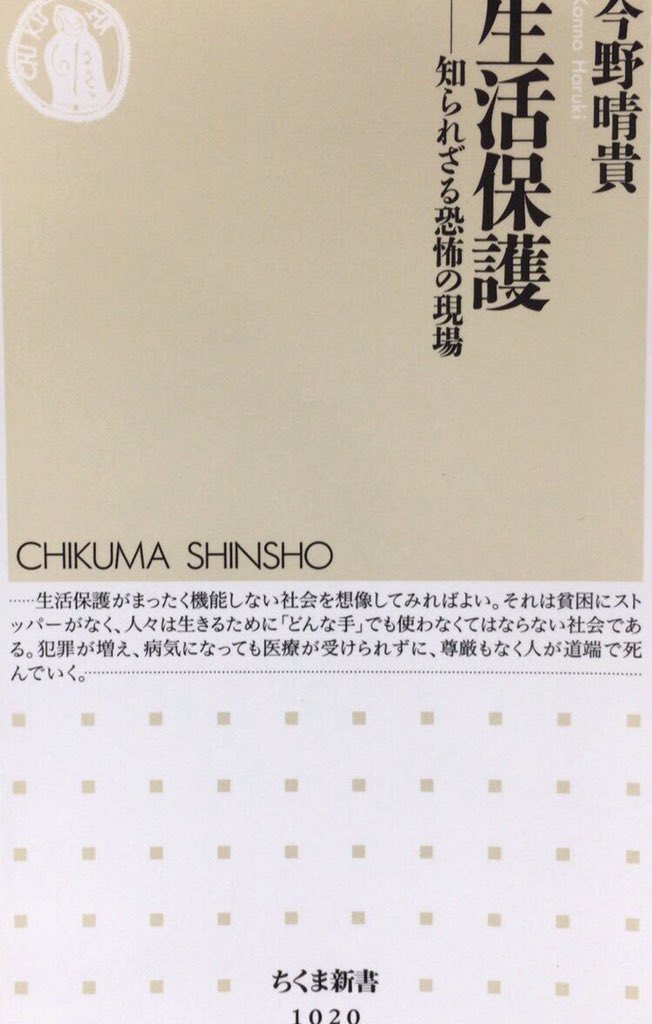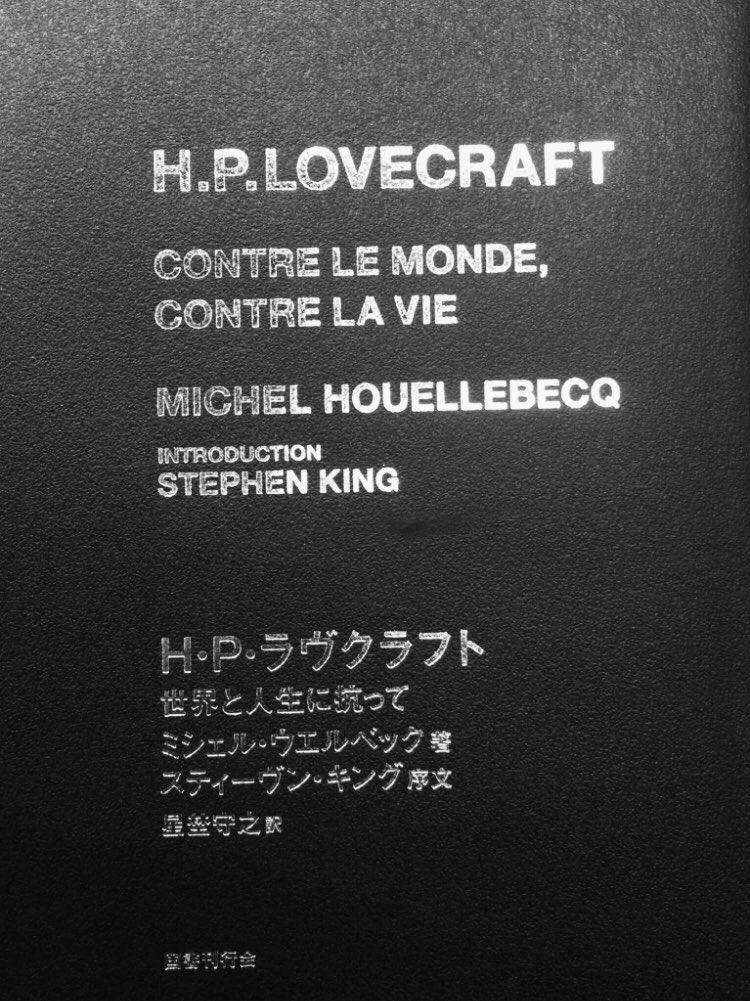226
227
せめて経済的な理由で自死を選択する人がいなくなるように、政府は行動すべき。
#クーポンやめろ現金配れ
228
229
231
232
234
235
236
237
238
239
「投票」は、国民がリーダーを選ぶ作業ではなく、国民そのものがリーダーであることを確認する作業である。
240
漫画家サトウサンペイさん死去。ご冥福をお祈りします。
広島原爆の日に読みたい、『フジ三太郎』の一作品を紹介します。
(参照:『U.S.-Japan Relations』1993年)
#広島原爆の日
241
多くの「弱者」が自分のことを「弱者」であると気づいていない状況ほど、政府にとって都合のいい状況はない。
243
244
245
246
248
250