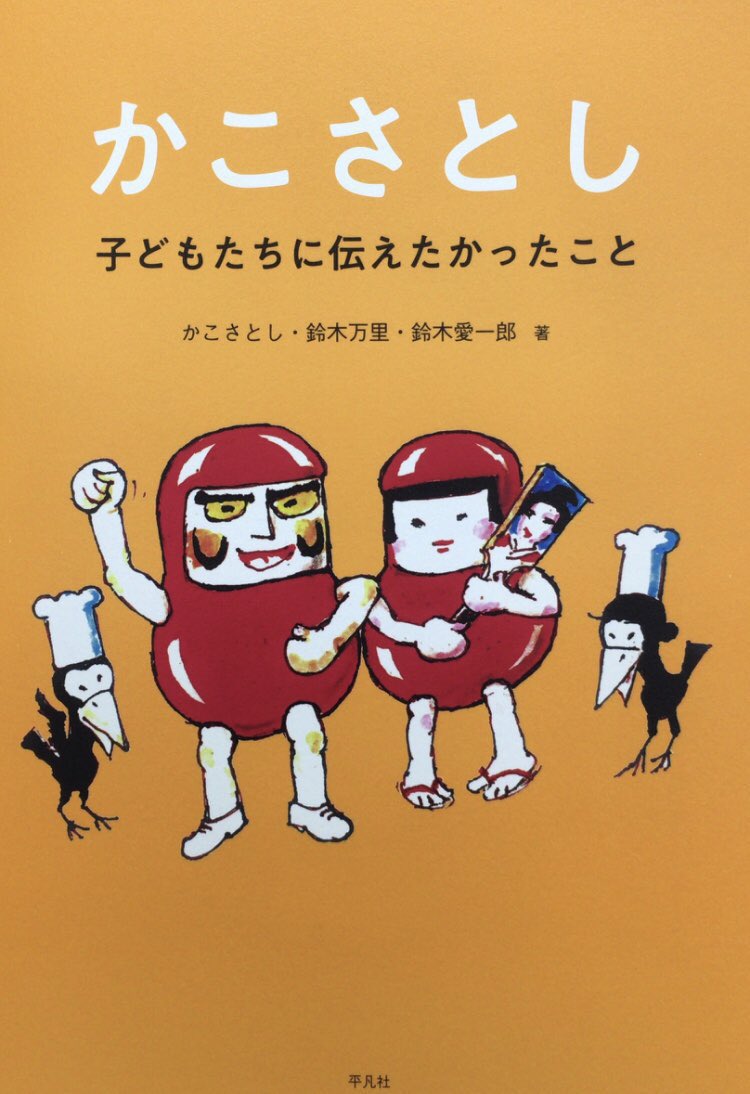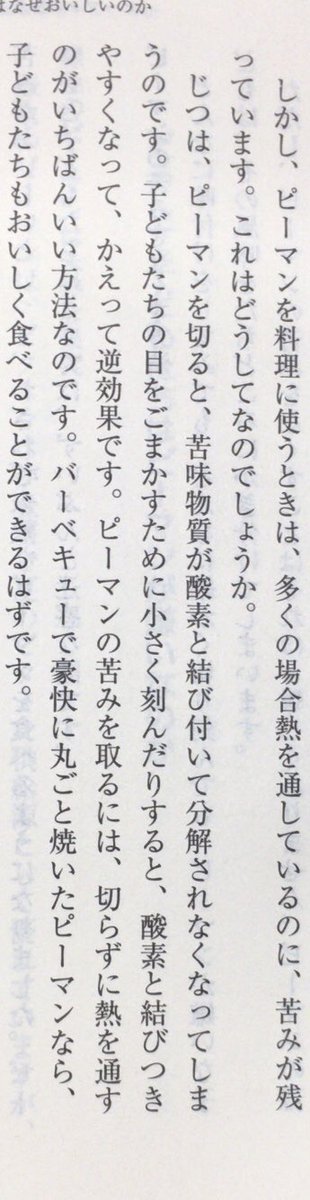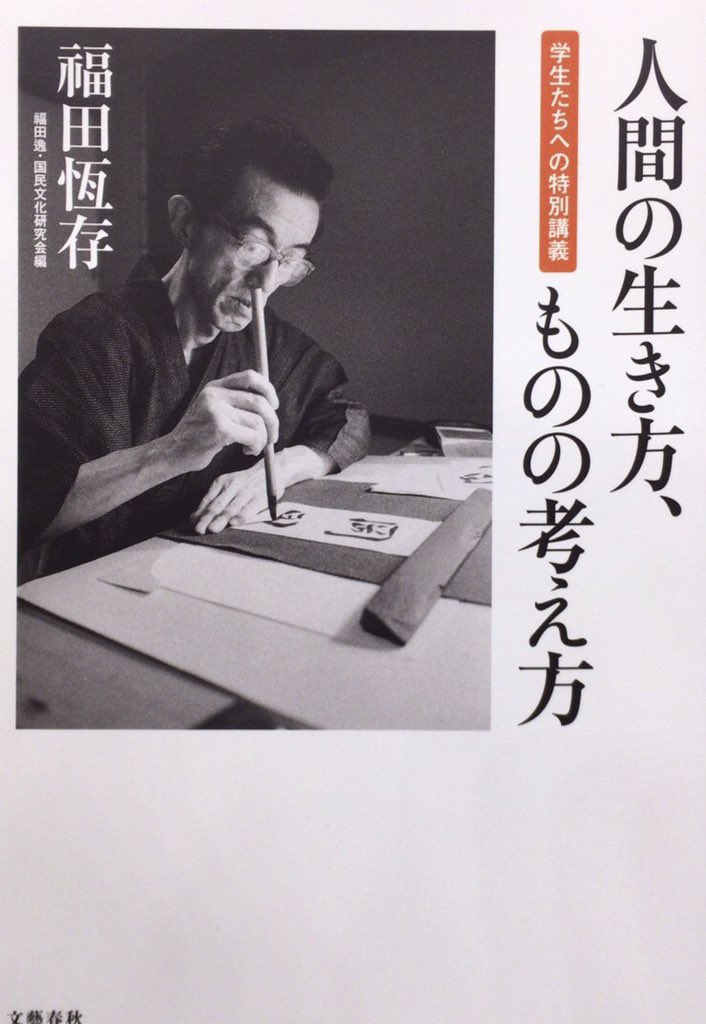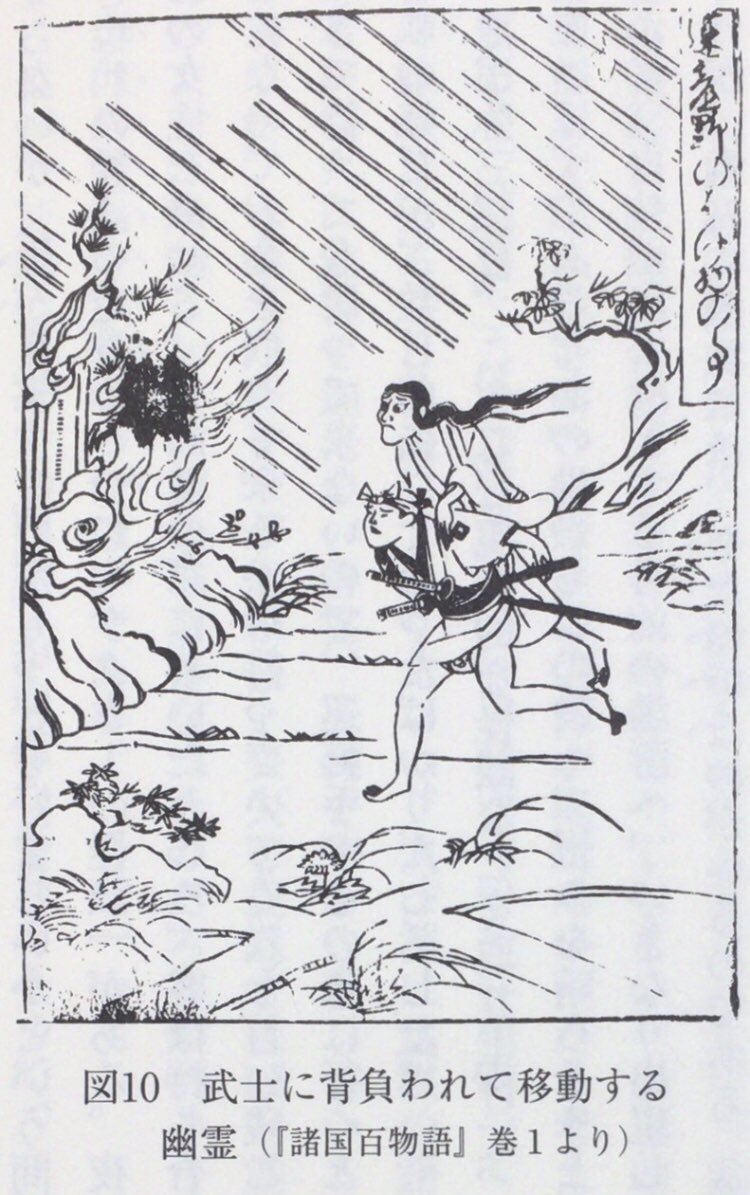1251
1252
1253
1254
1255
1257
1258
1260
1261
1263
1264
1266
「批判って、難癖をつけるとか、文句ばかり言う、ということとは違います。正しい批判精神を失った社会は、暴走していきます。批判することは、もっとよくなるはずと、理想を持っているからできること。」(『ほんとうのリーダーのみつけかた 増補版』岩波現代文庫、P33)
amzn.to/3OYXp7x
1267
1268
1269
「今後どういうふうな未来になるのか、どなたにもわからないのですが、これまでの変遷をしっかりと見極めることで、将来、未来性も、ちゃんと出てくるんだろうと、いうのが僕の考えです。」(かこさとし・文、『かこさとし 子どもたちに伝えたかったこと』平凡社、P98)
amzn.to/3zDnFyj
1270
1271
1272
1273
1275