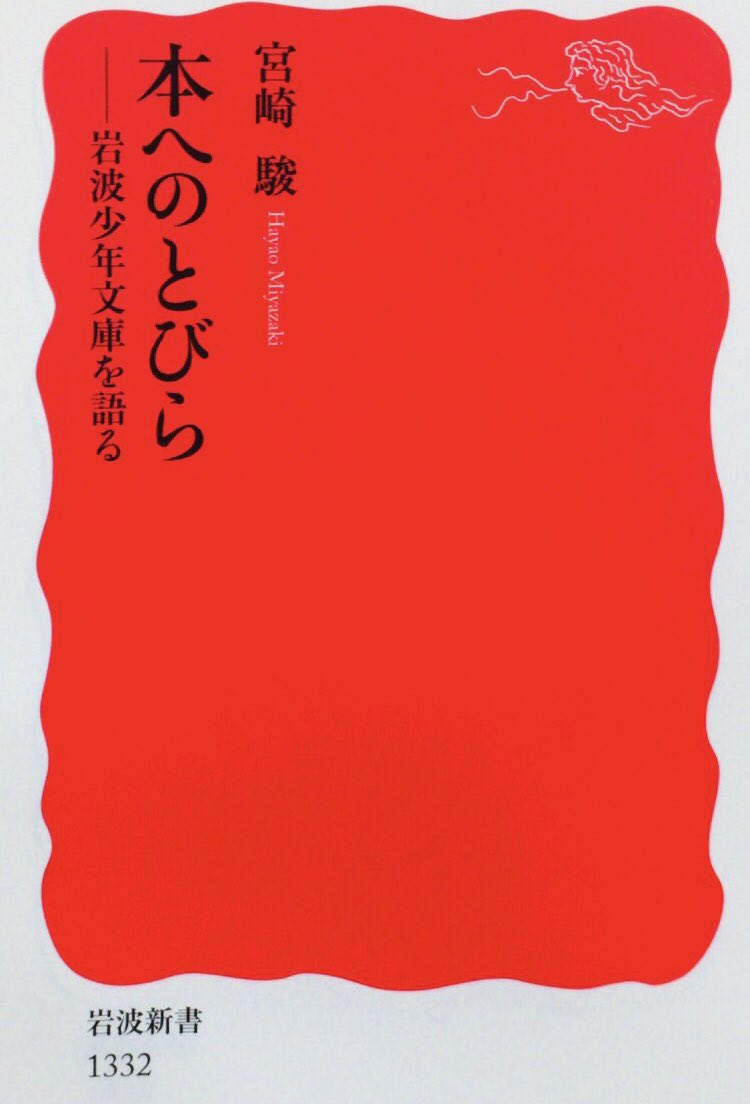1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1248
1249
1250