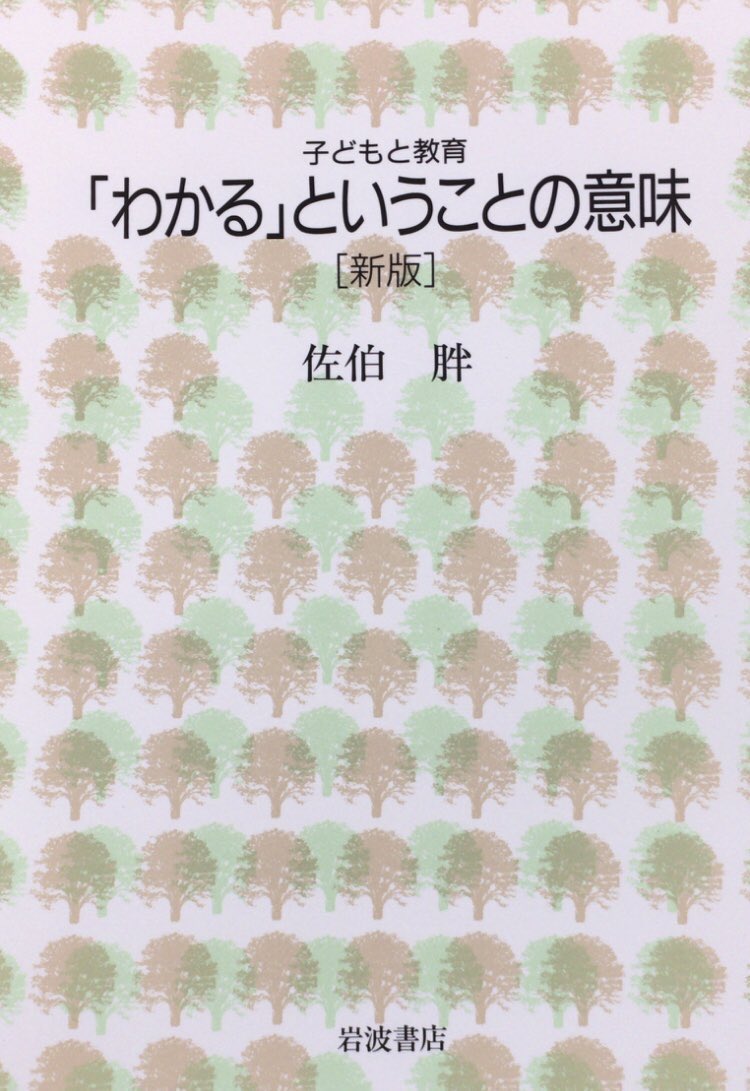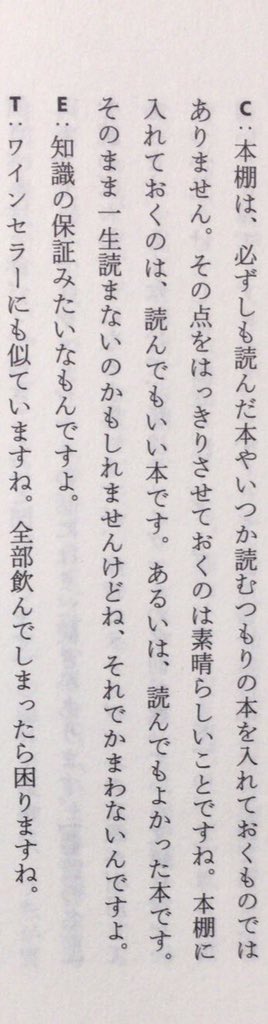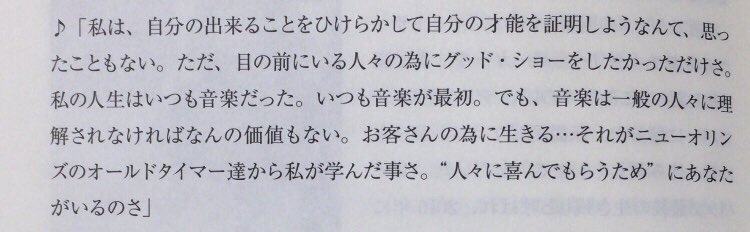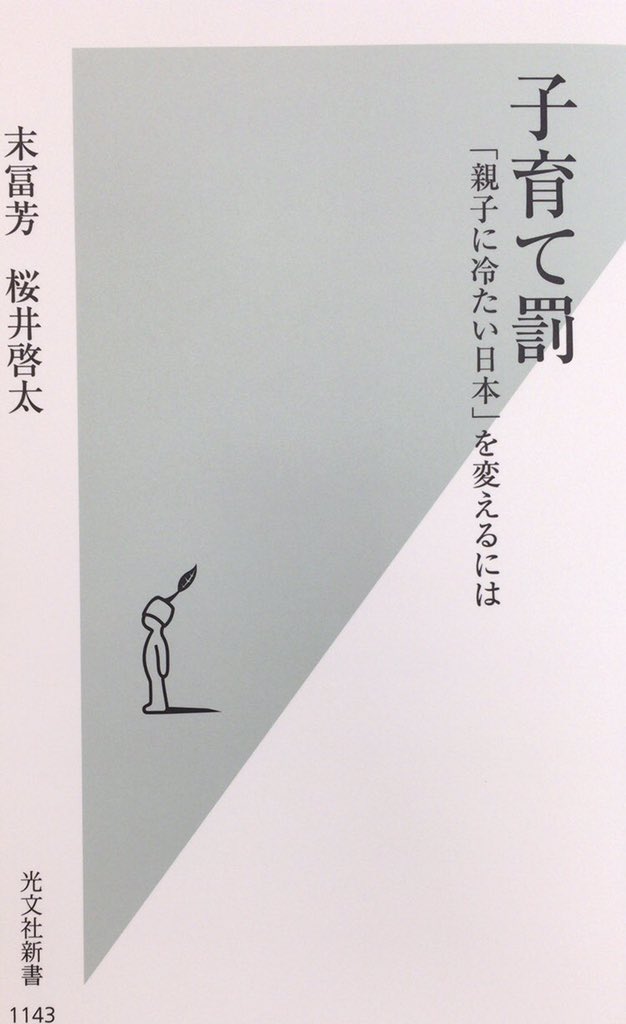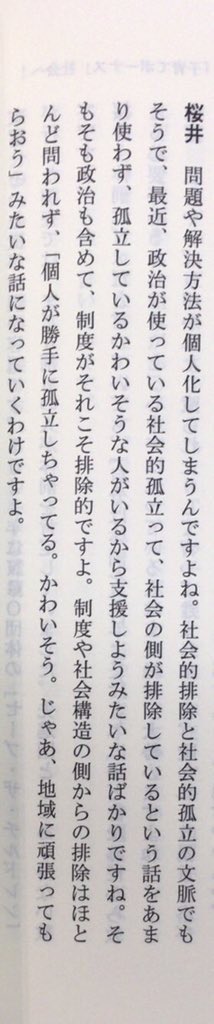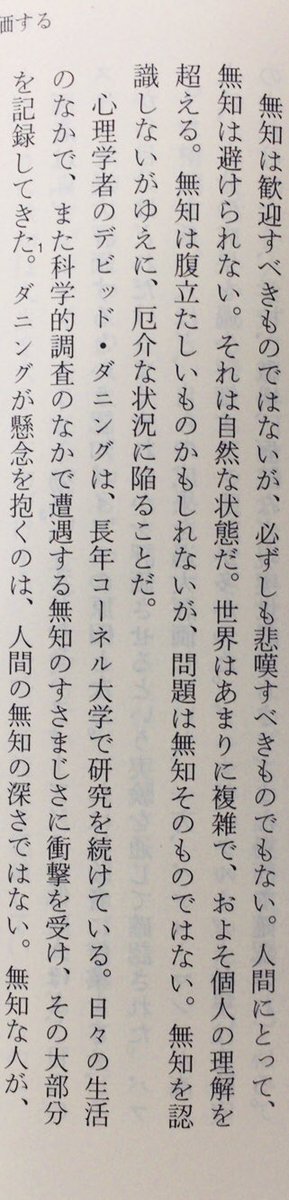1176
1177
1179
1180
逆立ちして現われた幽霊。
(参照:『片仮名本・因果物語』巻上、『幽霊 近世都市が生み出した化物』吉川弘文館、P9)
#幽霊の日
1181
1182
1183
1185
1186
1187
1188
【2023年度大学入学共通テスト(国語)出典一覧】
①柏木博『視覚の生命力』、呉谷充利『ル・コルビュジエと近代絵画』
②梅崎春生「飢えの季節」
③源俊頼『俊頼髄脳』
④白居易『白氏文集』
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200