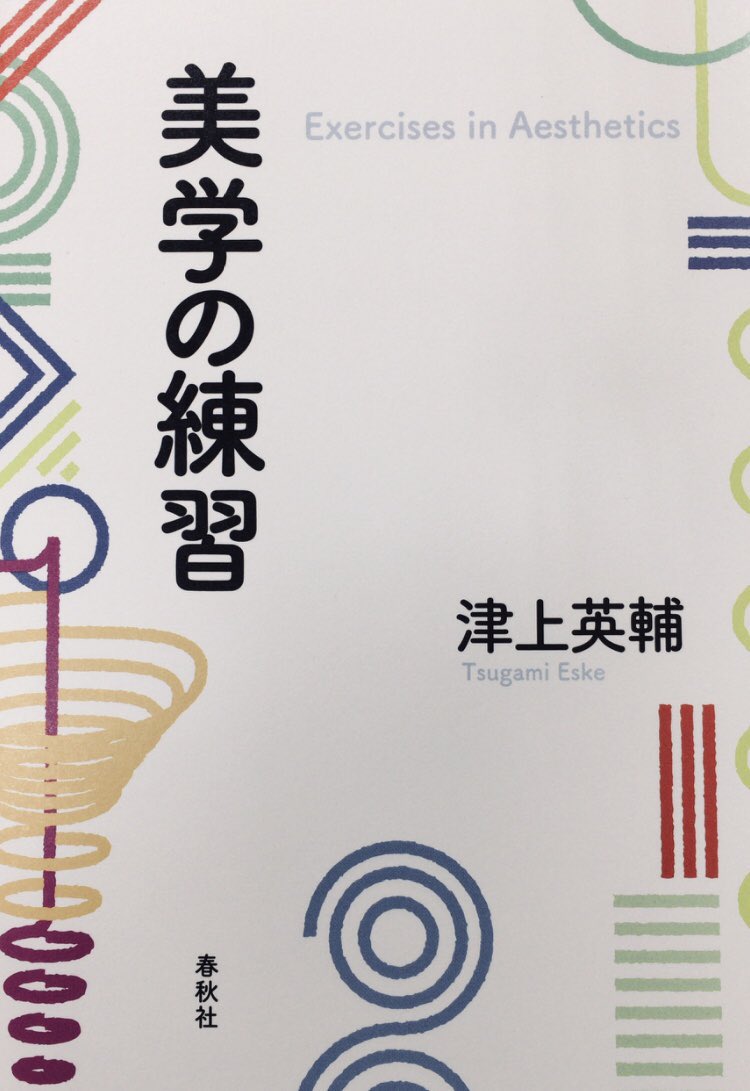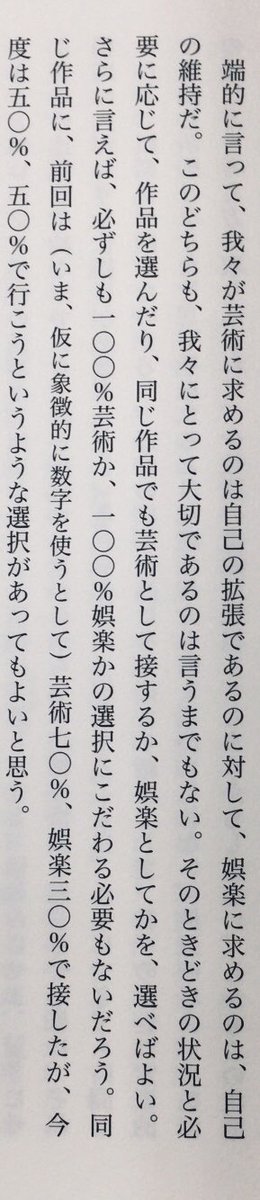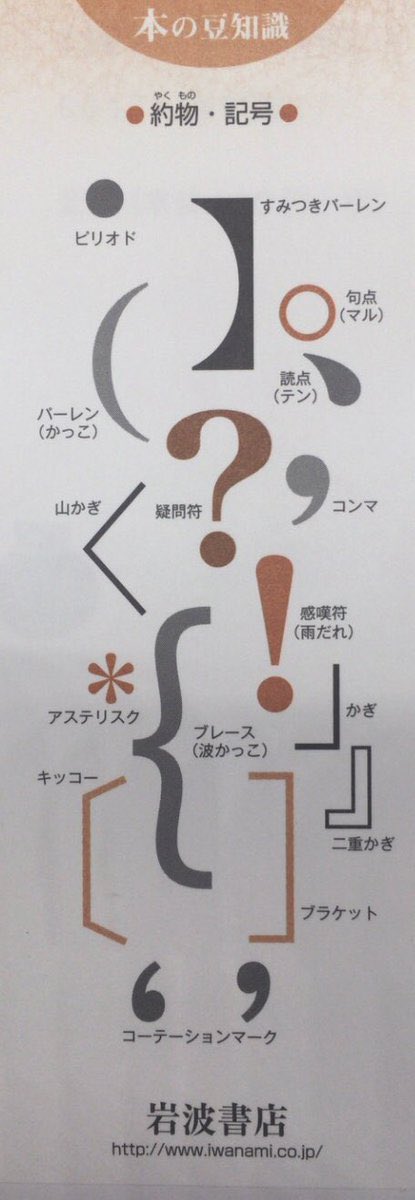1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
「男性にも女性にも、繊細でいられる自由があるべきです。そして男性にも女性にも、強くいられる自由がなくてはいけません。今や性別は、二つの相反する理想ではなく、ひとつの連続するスペクトラムとしてとらえる時代です。」(エマ・ワトソン:述、『だから私はここにいる』P150)
#国際女性デー
1164
1165
9月11日は、アメリカ同時多発テロ事件が発生した日。
「力によって敵意が減ることはない。恐怖は与えられても本当に人々の気持ちを解かすことはできない」(9・11テロ事件の翌月、医師・中村哲が国会で語った言葉)
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175