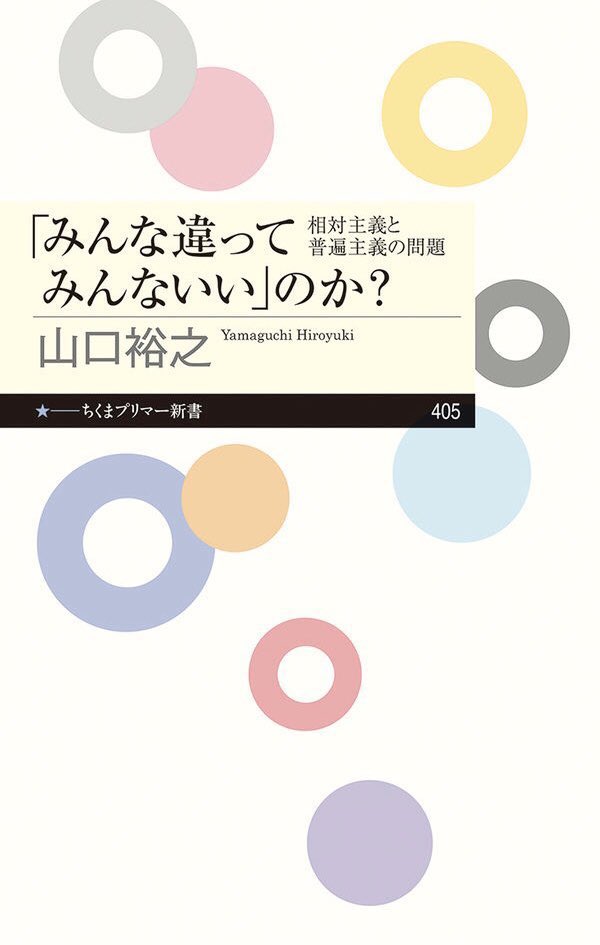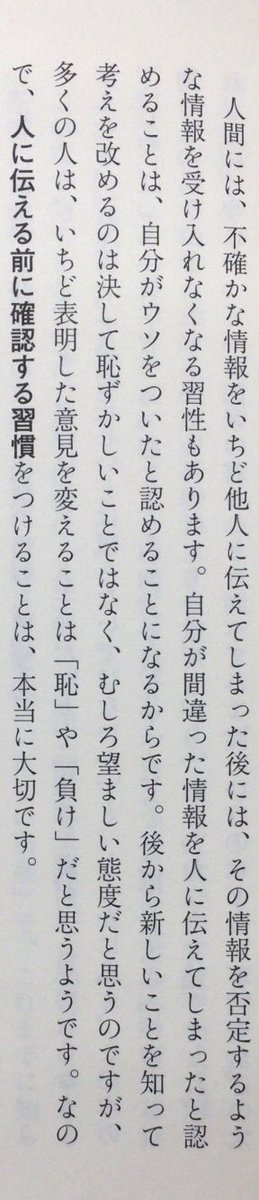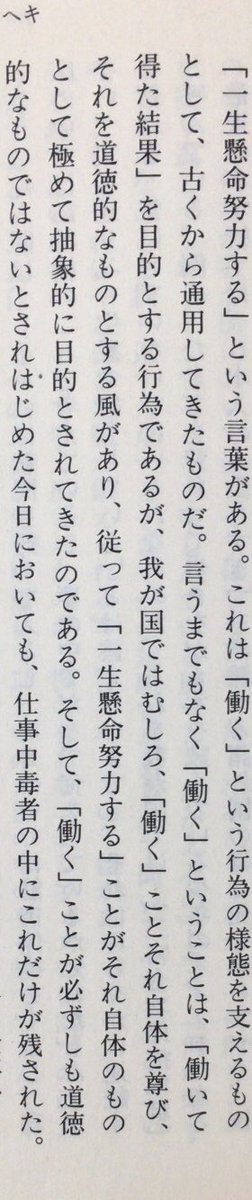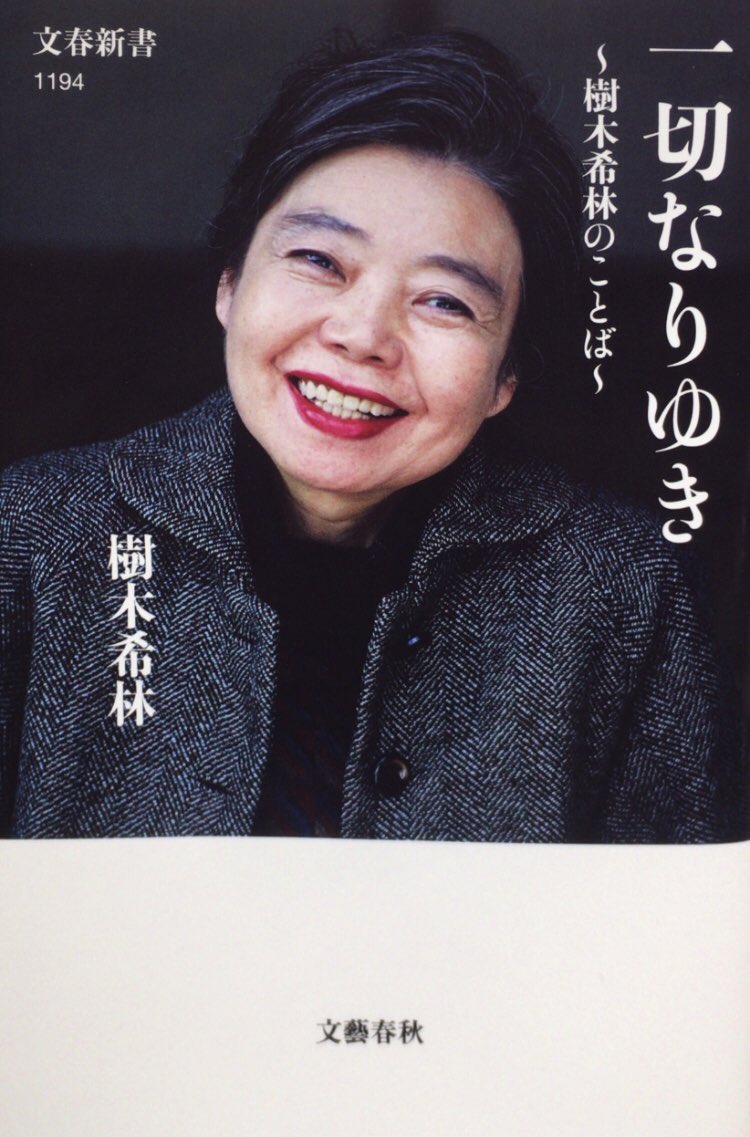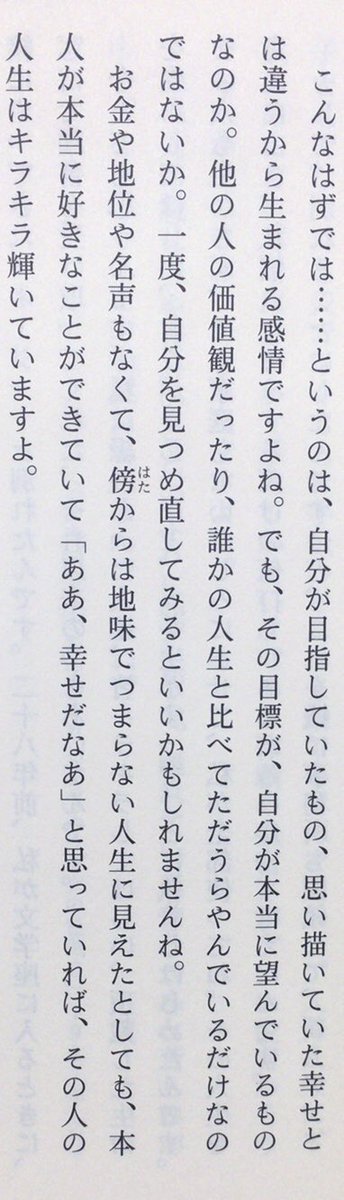1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
他者を頭ごなしに「お前は無知だ」と決めつける人間は、自身の知識の不足は断固として認めない。持ちあわせの知識を使って質問を繰り返し、相手が答えられない状況をつくれることが、博識の証明であると思い込んでいる。
1143
1144
1146
1147
1148
1149
1150