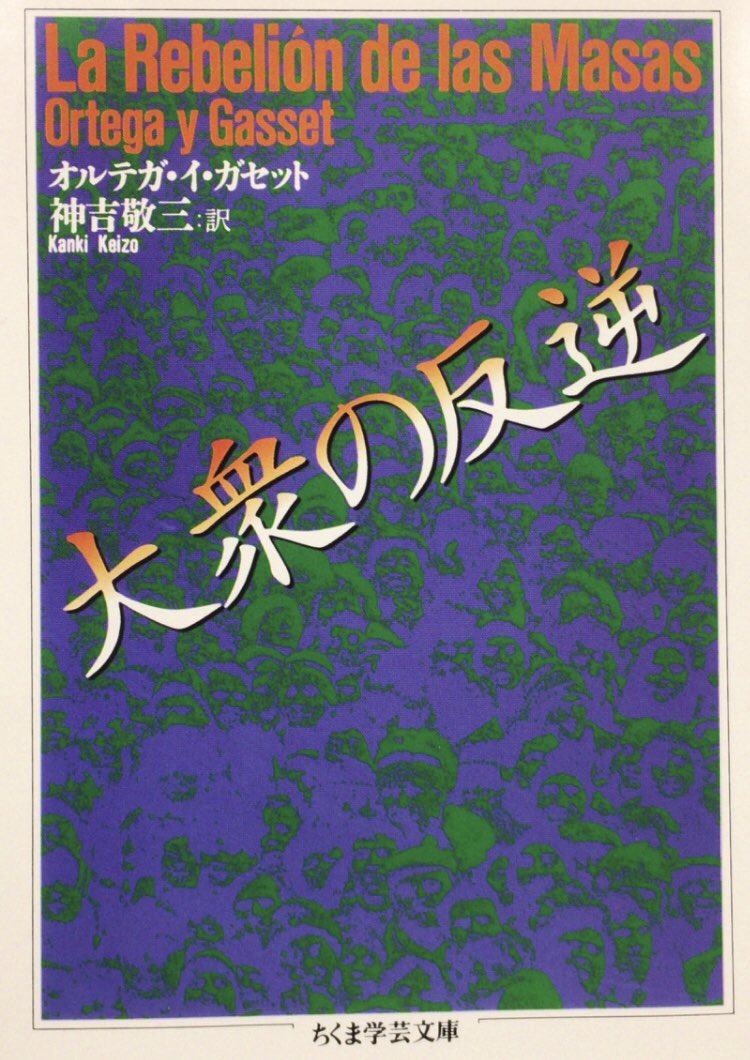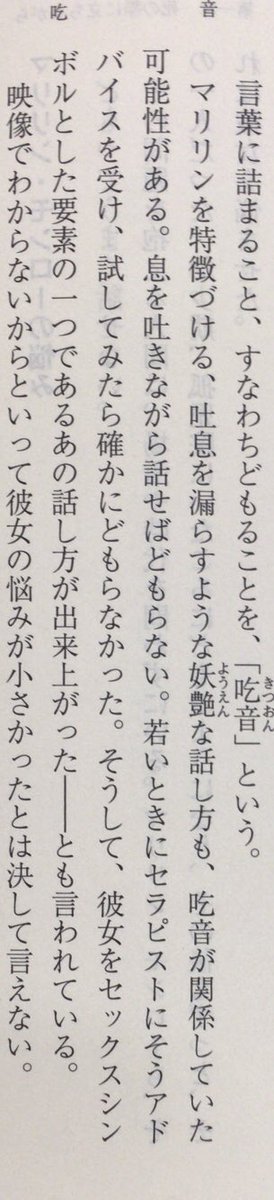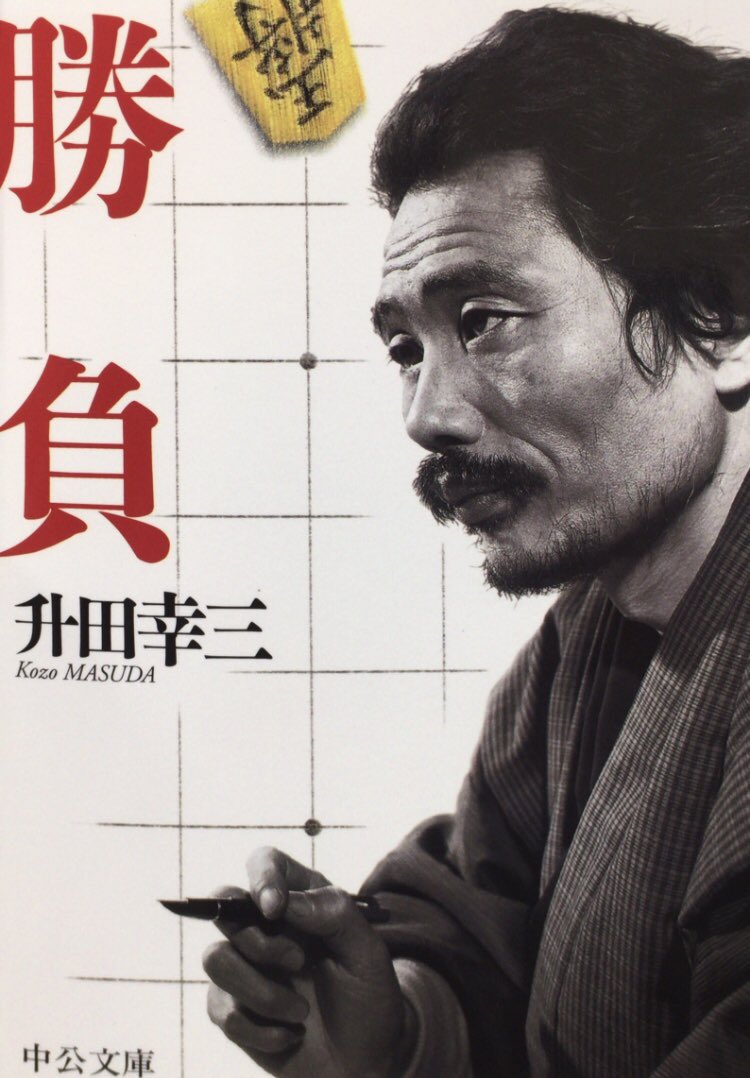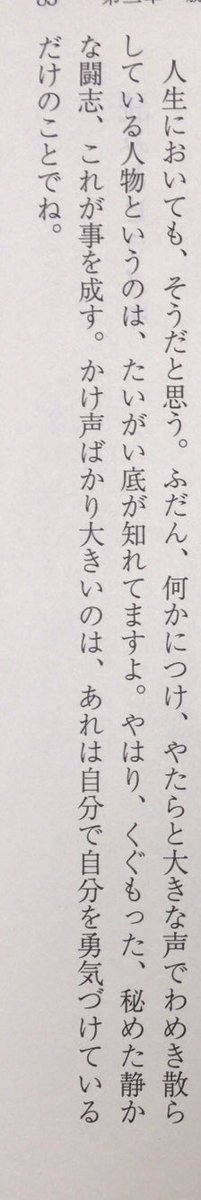1076
1077
1078
1079
1080
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
「ふだん、何かにつけ、やたらと大きな声でわめき散らしている人物というのは、たいがい底が知れてますよ。やはり、くぐもった、秘めた静かな闘志、これが事を成す。かけ声ばかり大きいのは、あれは自分で自分を勇気づけているだけのことでね。」(升田幸三『勝負』中公文庫、P83)
#将棋の日
1092
「若い時代が人生で一番いい時だなんて、輝いている時だなんて、一体全体誰が言ったのだろう。たとえいい時だったのだとしても、それを教えてくれる大人は誰もいなかった。大人たちは、劣るものとして、わたしたちを扱った。」(松田青子『女が死ぬ』中公文庫、P196)
amzn.to/3dO2DF7
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1100