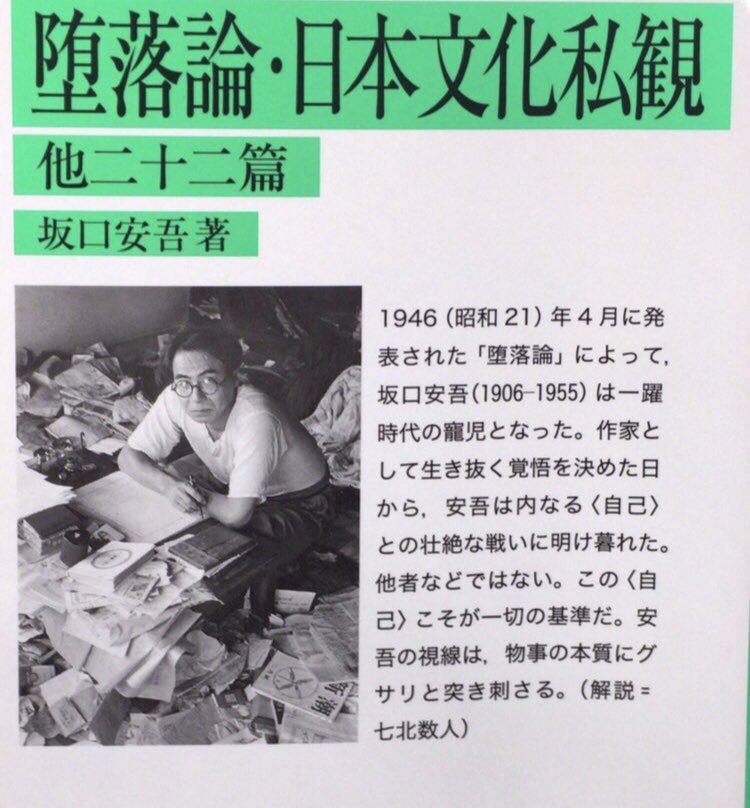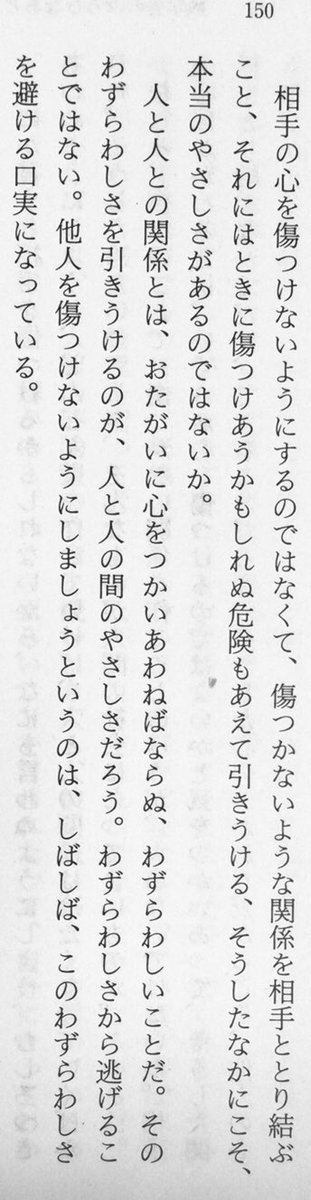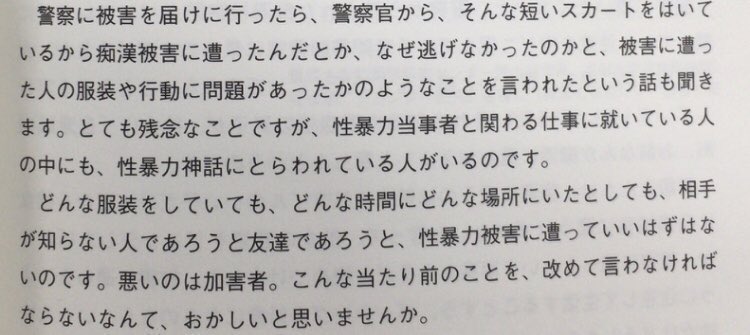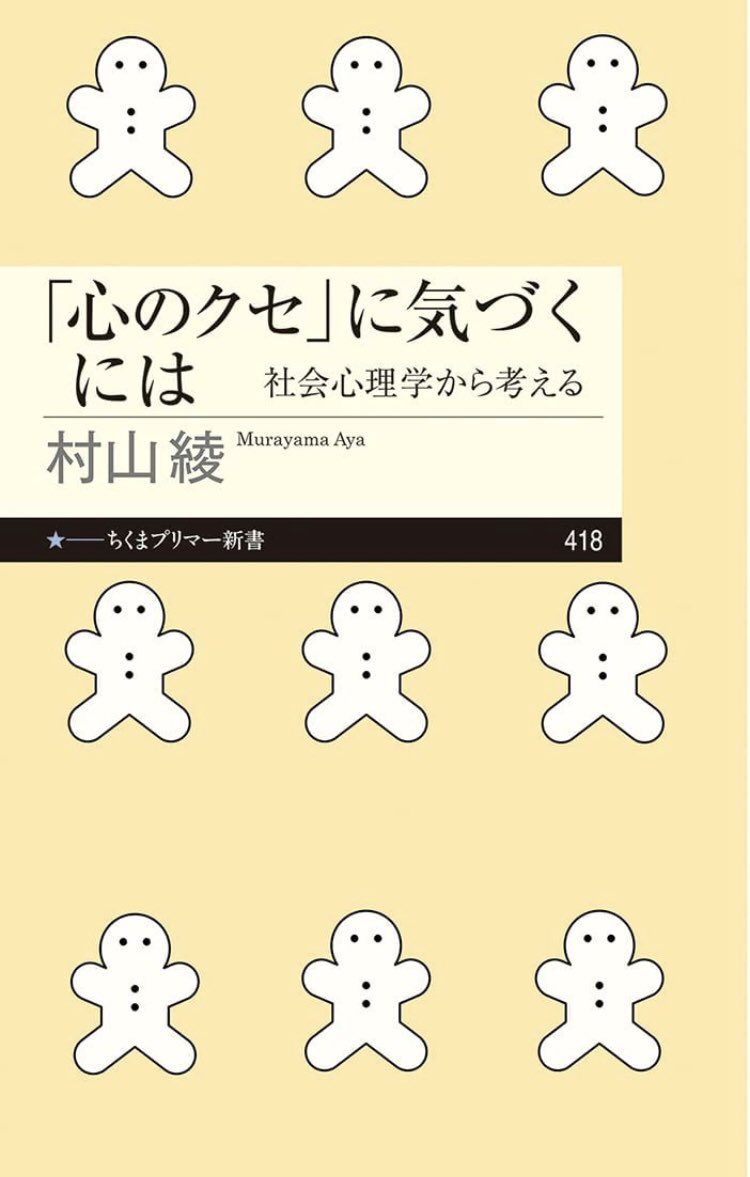1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050