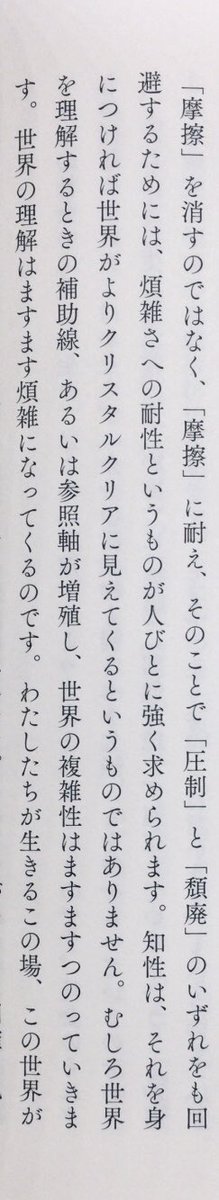976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
「言語というものは、有限な語彙と文法規則をつかって無限に多様な文を生み出すことができる奇跡的な想像力を持った道具であり、人間だけが駆使できるものです」(沼野充義・文、『ことばの危機』集英社新書、P114)
amzn.to/3XsS2jZ
991
「大切なことは、「人権」とは、その国のその時代に、やむにやまれず発した人々のうめき声であり、人権にしておかないと人間らしい生活が絶対にできないと考えた結果を、その時点で法的文書に書き残したものだ、ということである。」(『新版 主権者はきみだ』岩波ジュニア新書、P59)
#世界人権デー
992
994
996
997
998
1000