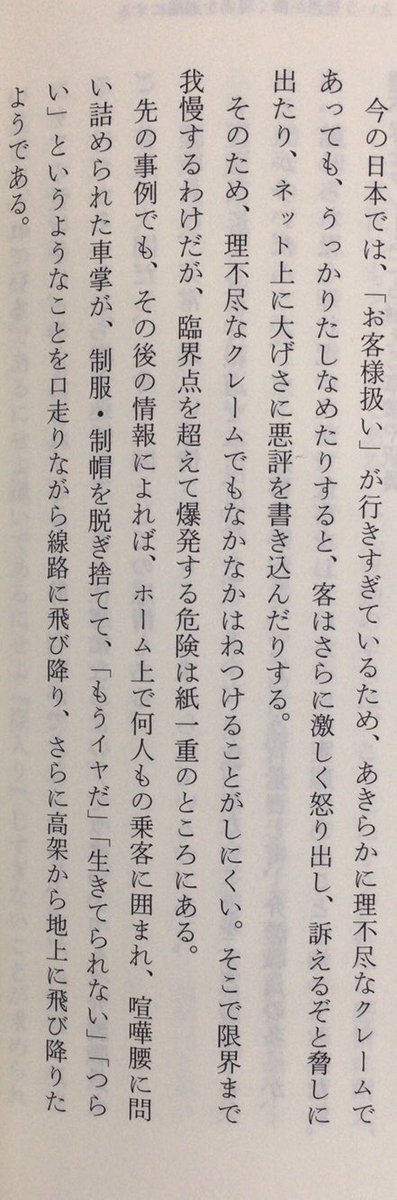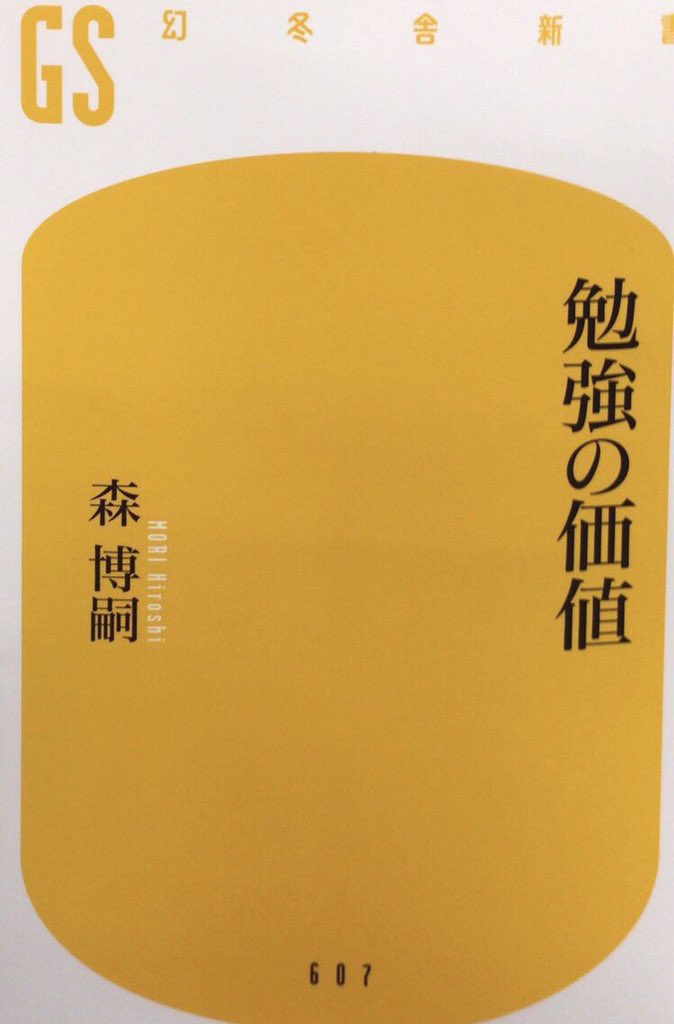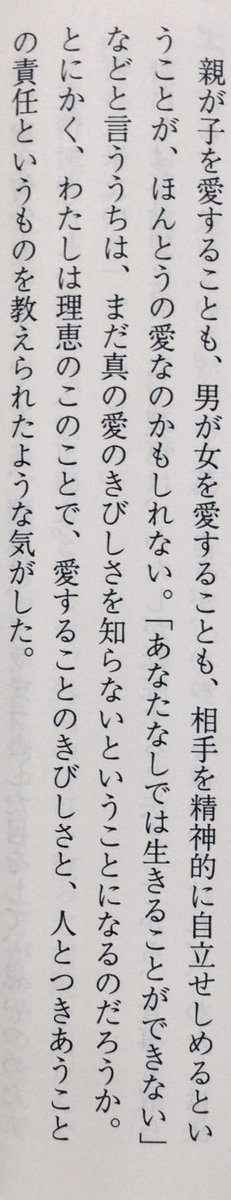1001
1002
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
かこさとしの描く「パン」が可愛い。
(参照:『現代思想』第45巻第17号、P5)
#パンの記念日
1012
1013
1016
1017
「自分の足で立つことは、誰にとっても必須である。ただ、何らかの理由でひとりでは生きられない時もあるし、支えが欠かせない立場におかれている人もいる。誰かと助け合うことが「自立」を阻害することにはならない」(『異文化コミュニケーション学』岩波新書、P162)
amzn.to/3b4eaPg
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025