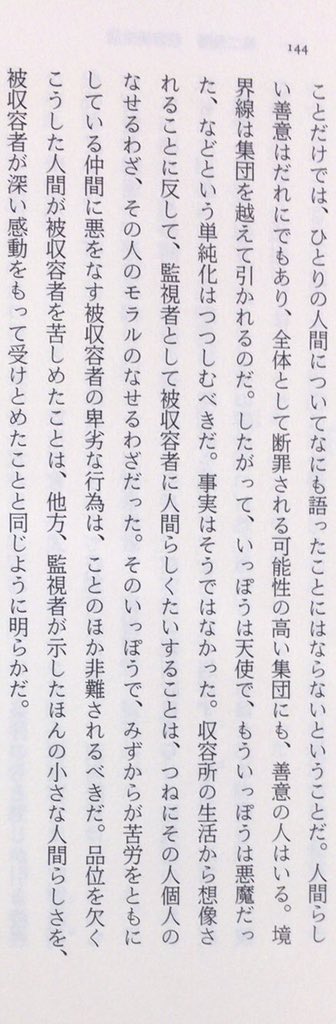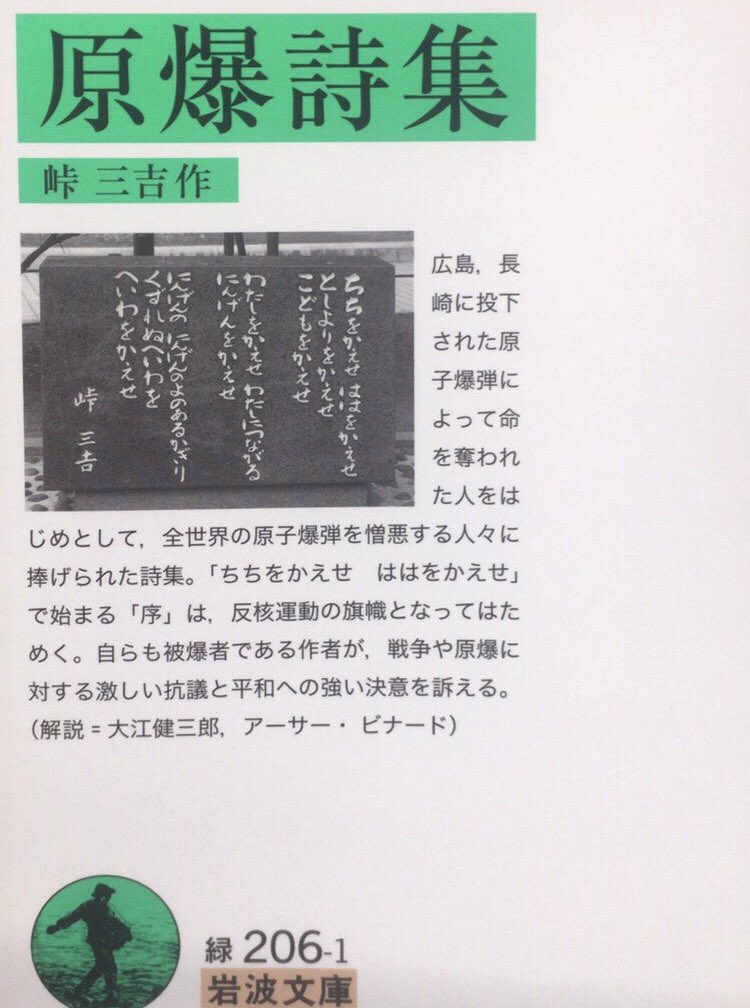951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
968
969
970
971
972
973
974
975