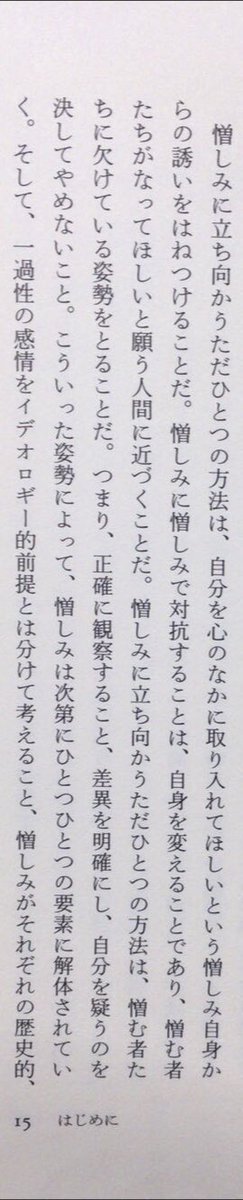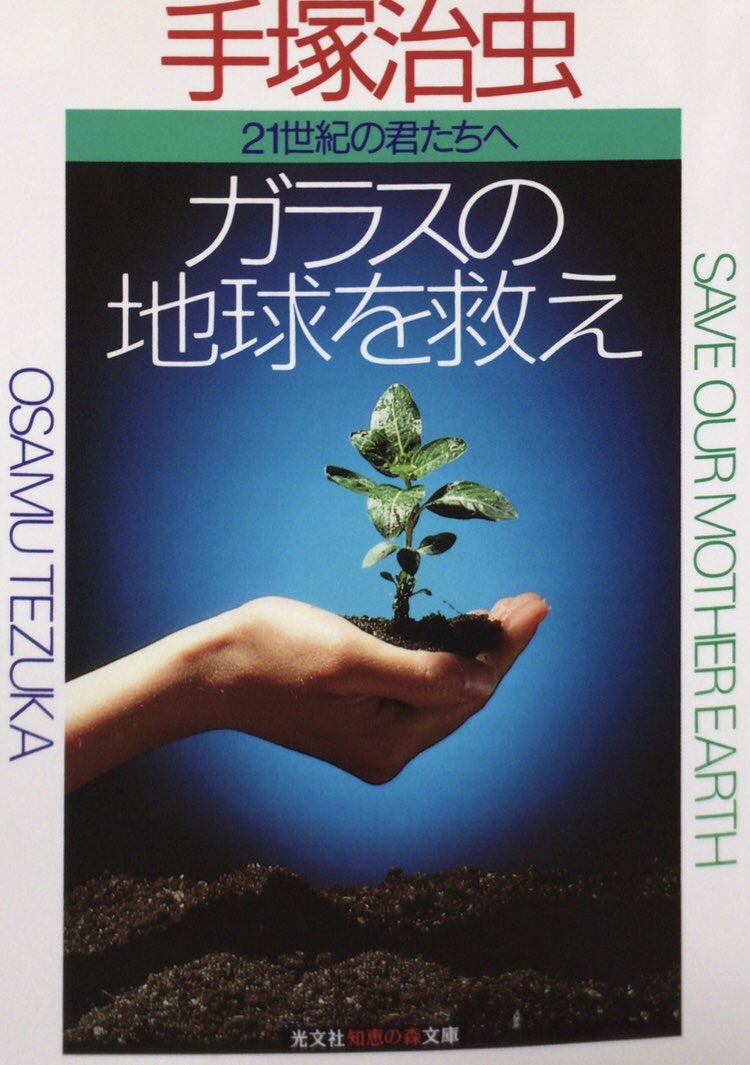926
927
928
929
930
931
932
933
934
一部の講談社文芸文庫Kindle版でセール(498円均一)が行われているようなので、お勧めの作品を幾つか紹介しておきます。気になる作品があれば、ぜひ読んでみてください。
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
947
948
949
950