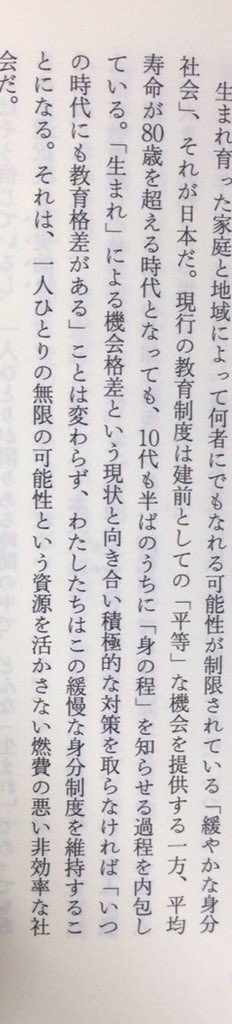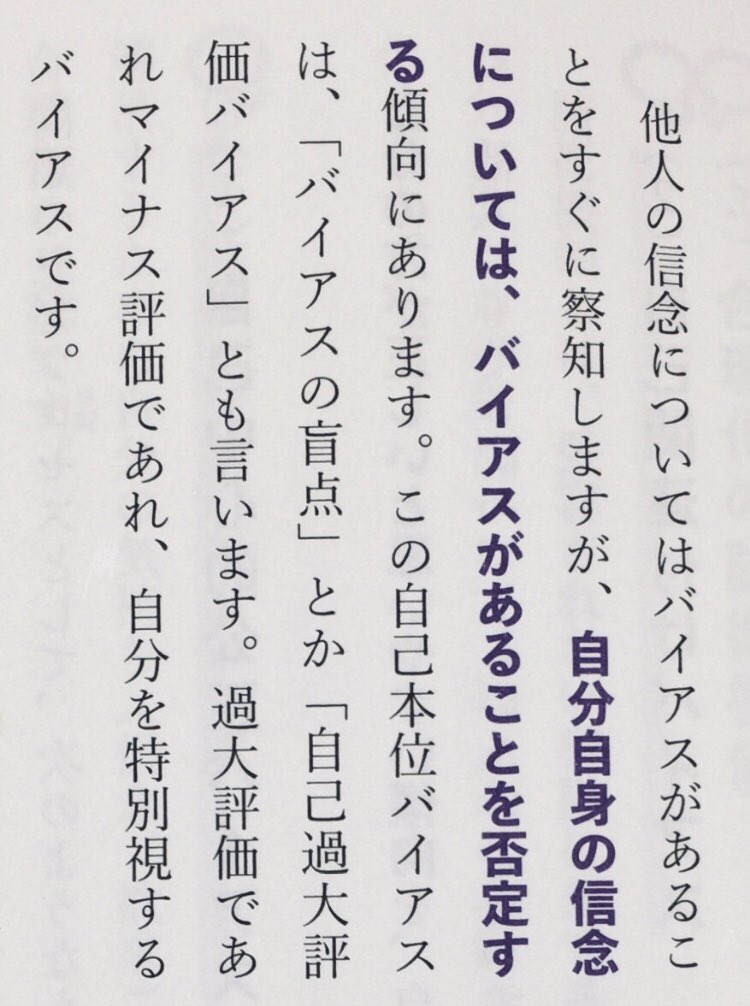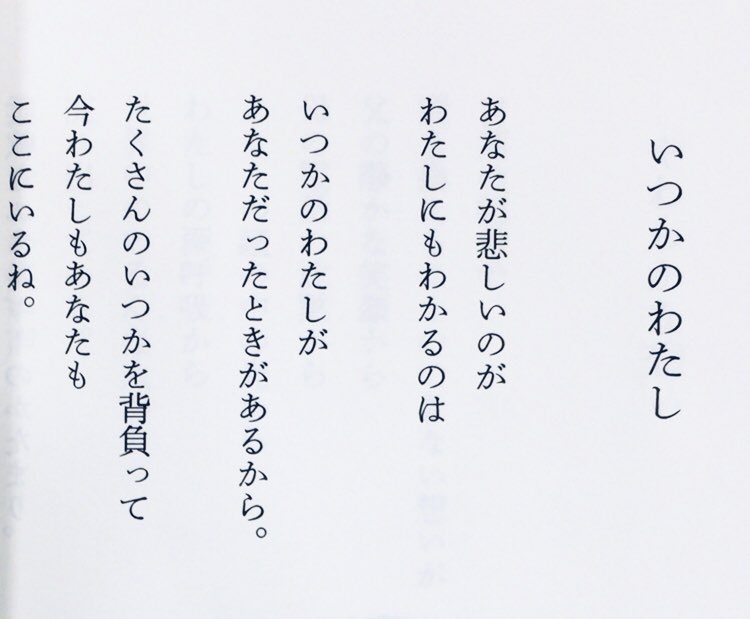901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
川端康成とワイアーヘアード・フォックステリアの子犬たち。
(参照:『作家の犬』平凡社、P36)
#愛犬の日
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925