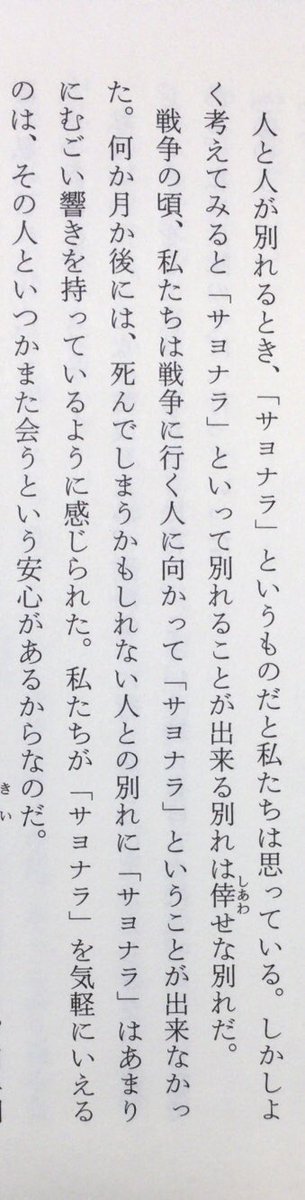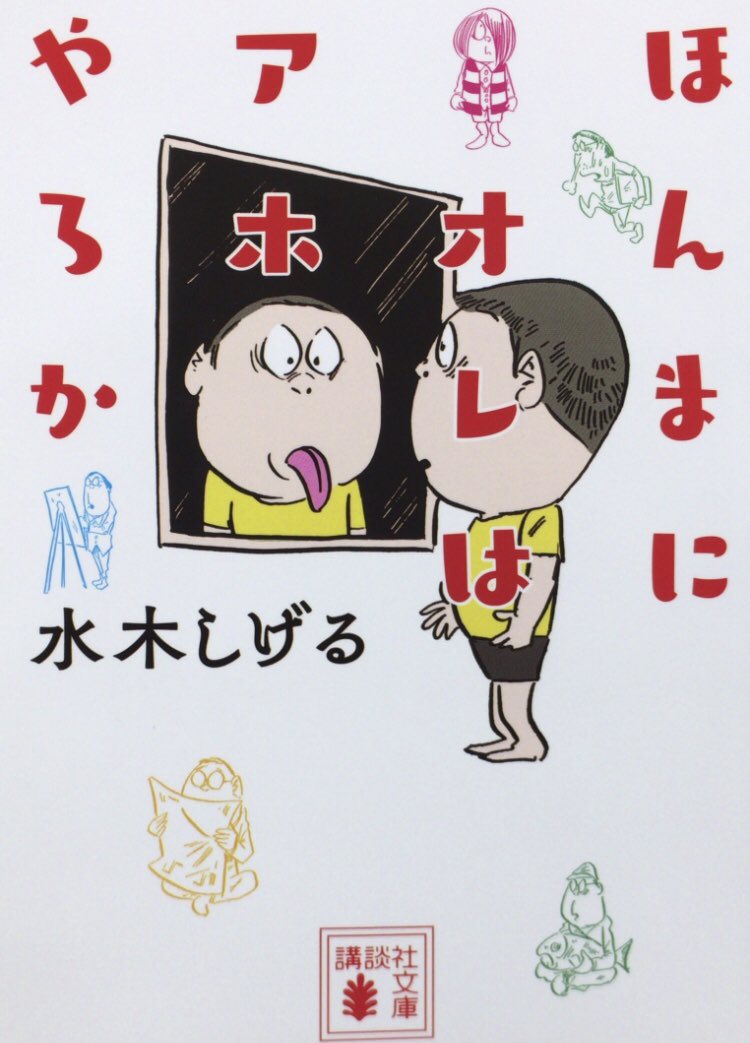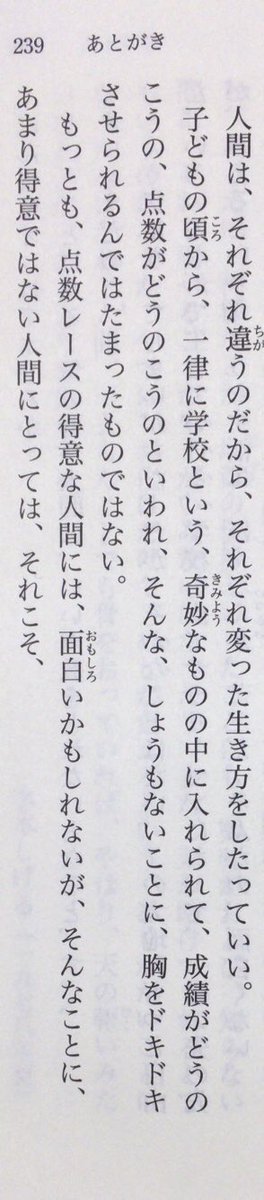876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
大学1回生の頃に使っていたノートを整理していると、所々に「AMD48」というワードが記されていることに気付く。自分で書いておきながら、何を意味するのか分からず、「こんなアイドルいたかな?」と頭を悩ましていたら、文脈から「阿弥陀如来の四十八願」の略語であることが分かった……。 #花まつり
894
895
896
897
898
899
900