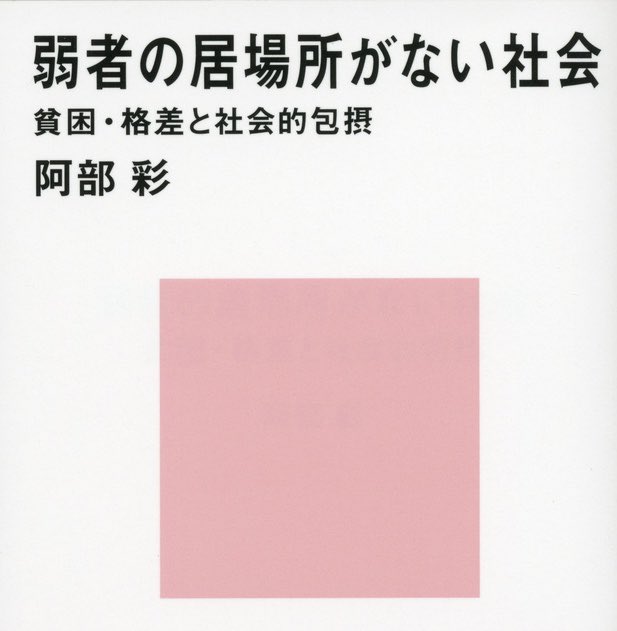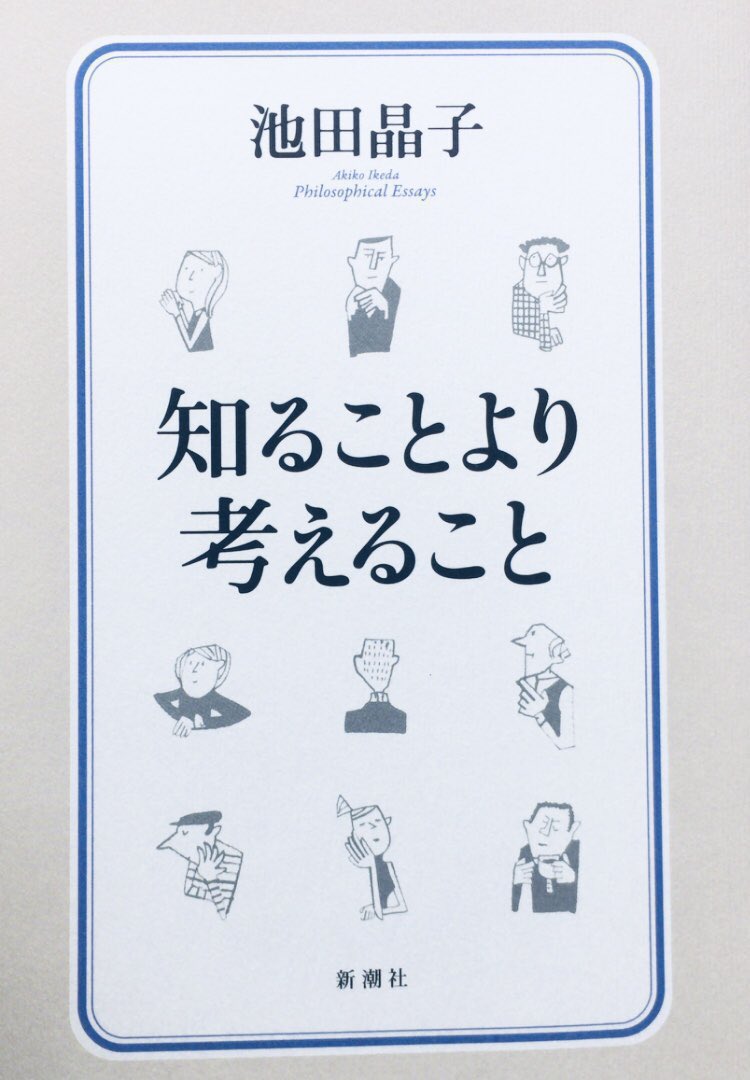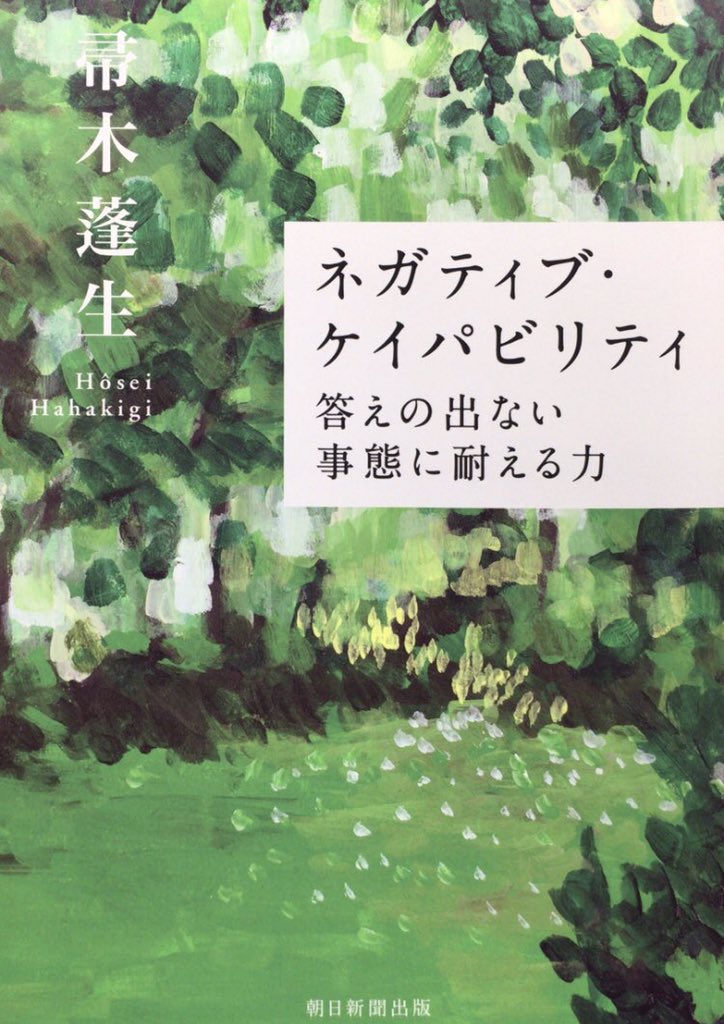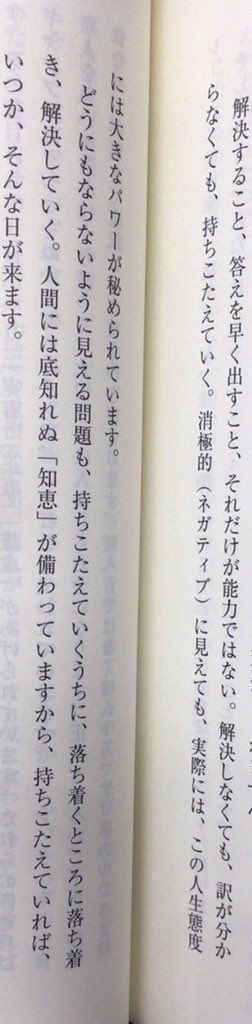851
852
853
人の価値を「生産性」という指標で計測するようなことはあってはならない。
854
855
856
857
858
859
860
862
863
864
865
誰かを擁護するときに、一番に「実際に会ったらいい人なんだよ」と「人柄の良さ」を強調してくる人は信用ならない。
866
867
868
869
「人間が自然を守る」「環境問題について語るとき、よくそういう言い方をする。でもそれは、ほとんど発想として間違いなんだと思います。人間が自然にかける負荷と、自然が許容できる限界とが折り合わなくなるとき、当然敗者になるのは人間です」(『音楽は自由にする』P245)
amzn.to/3K765a9
870
871
872
873
874
875