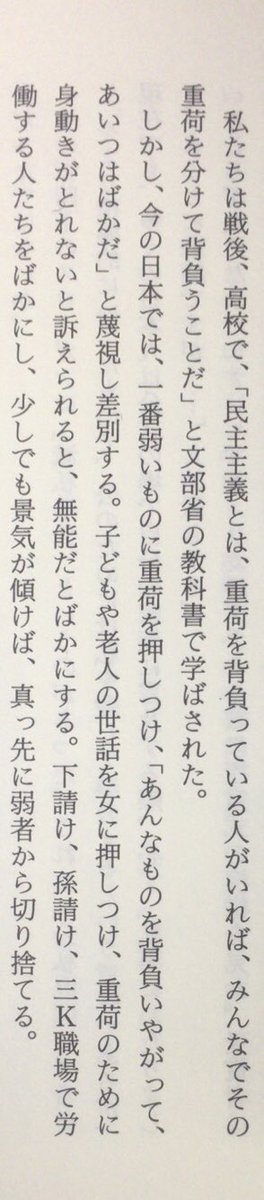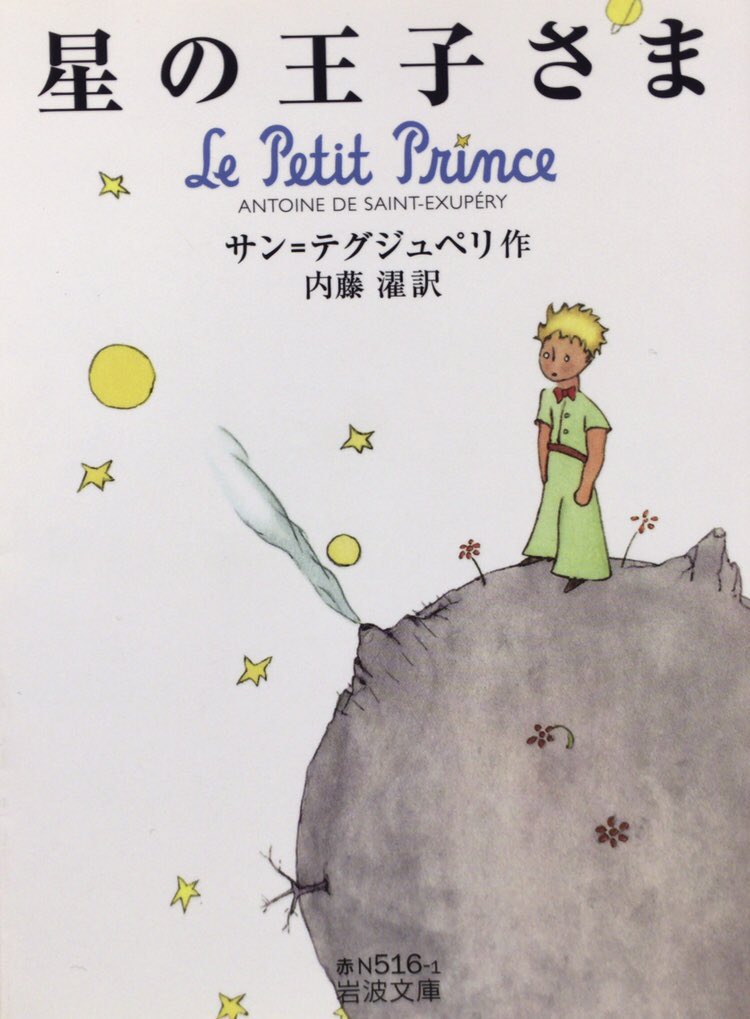826
827
828
830
831
832
833
834
835
ある科目を「役立つ/役立たない」の二分法で語りたがる人は、"誰にとって"そうなのかを示さず、曖昧にすることが多い。大概は、発言者一人の人生経験を指標にして、役立つか役立たないかを語っているにすぎない。これに対しては「あなたはそうだったんですねー」という感想しかでてこない。
836
837
838
839
840
841
843
844
845
846
847
848
849
850