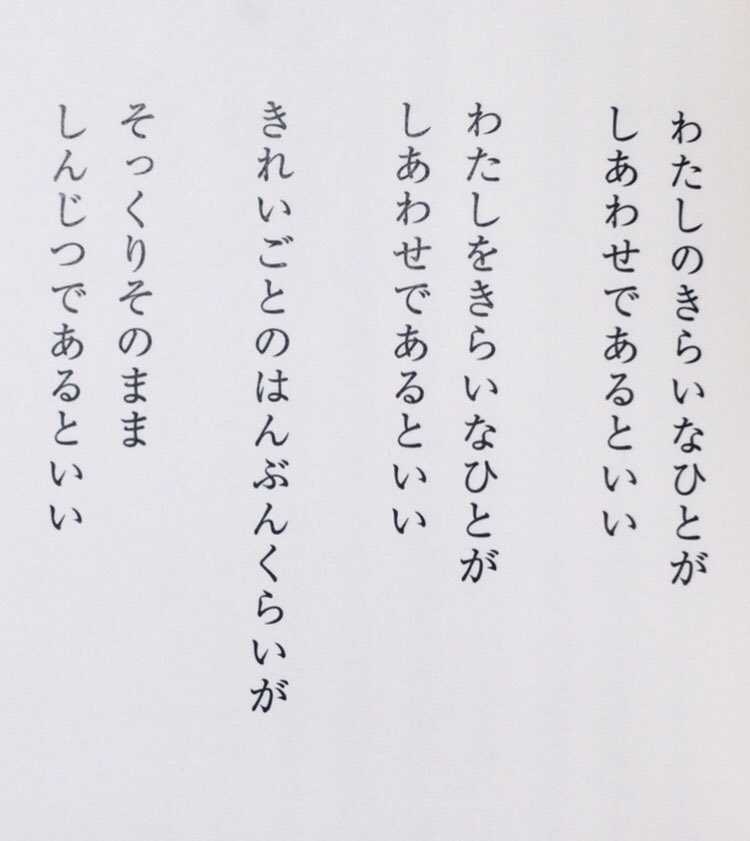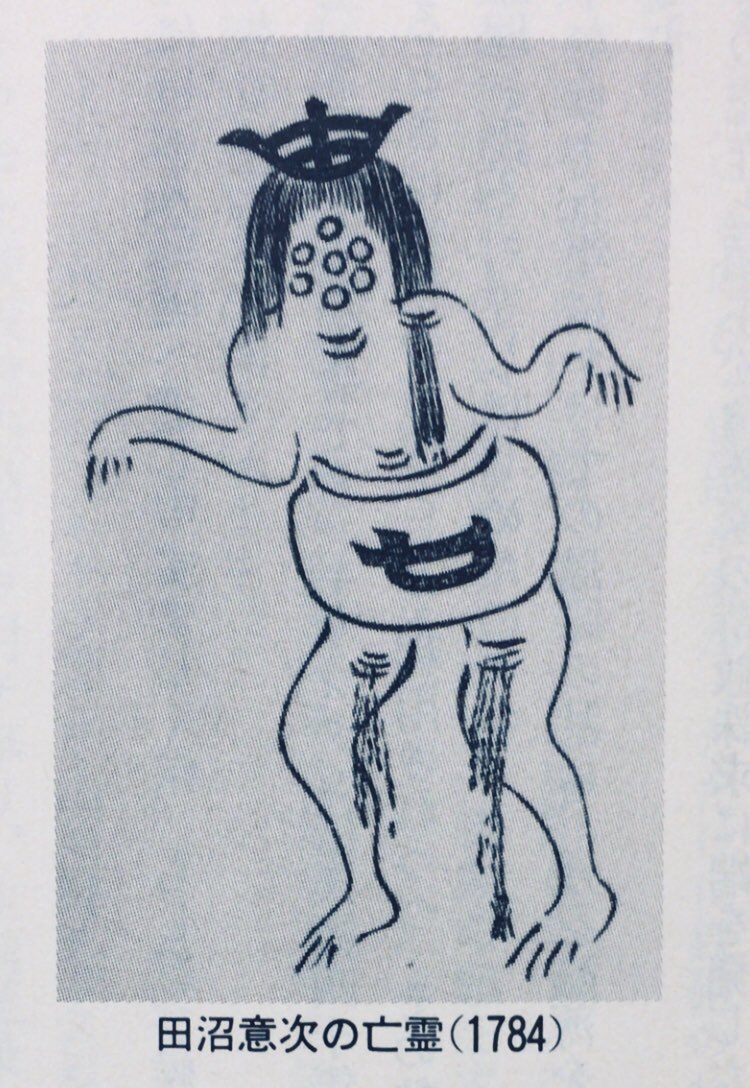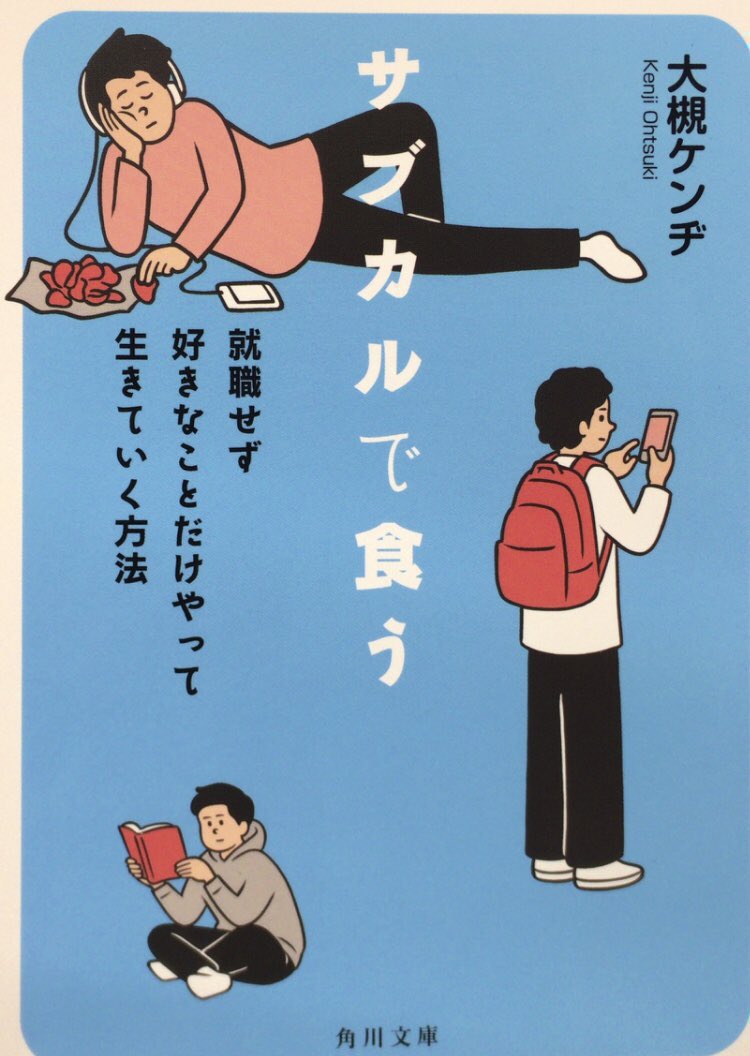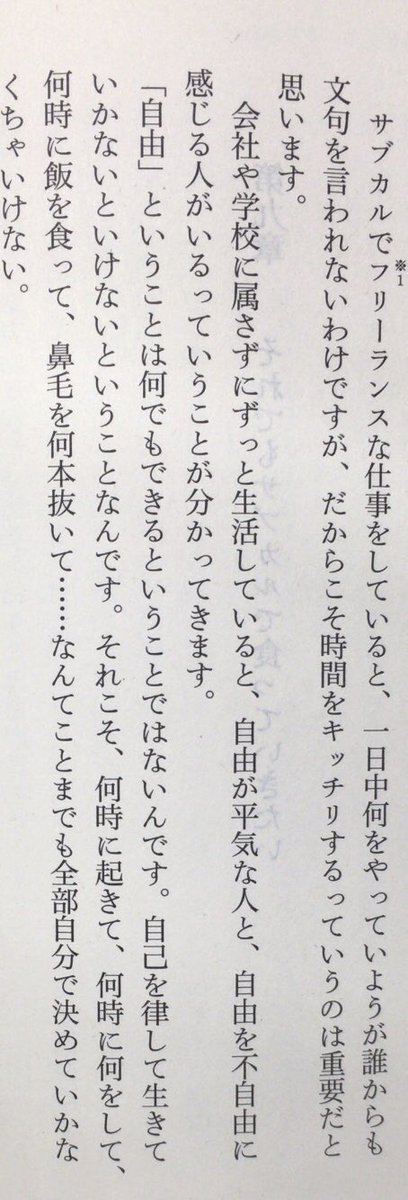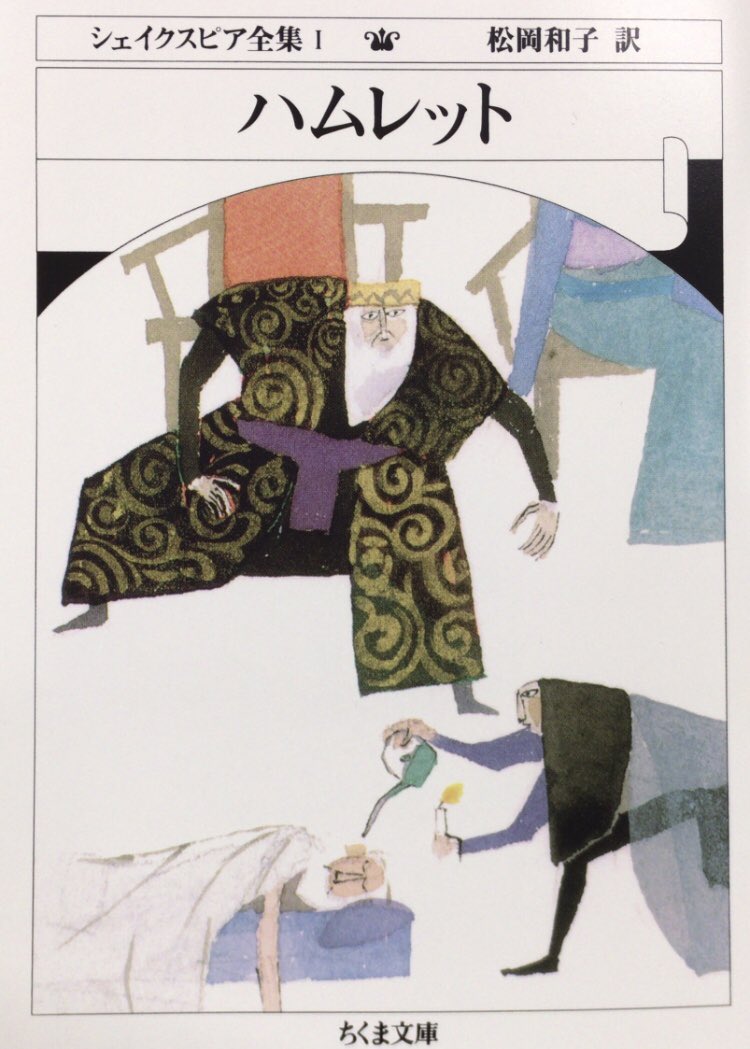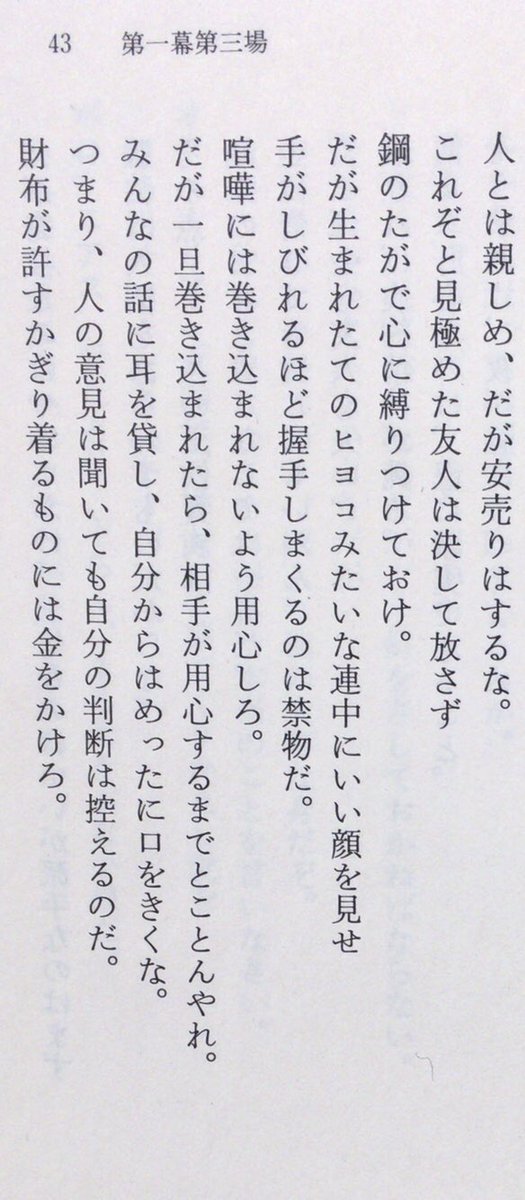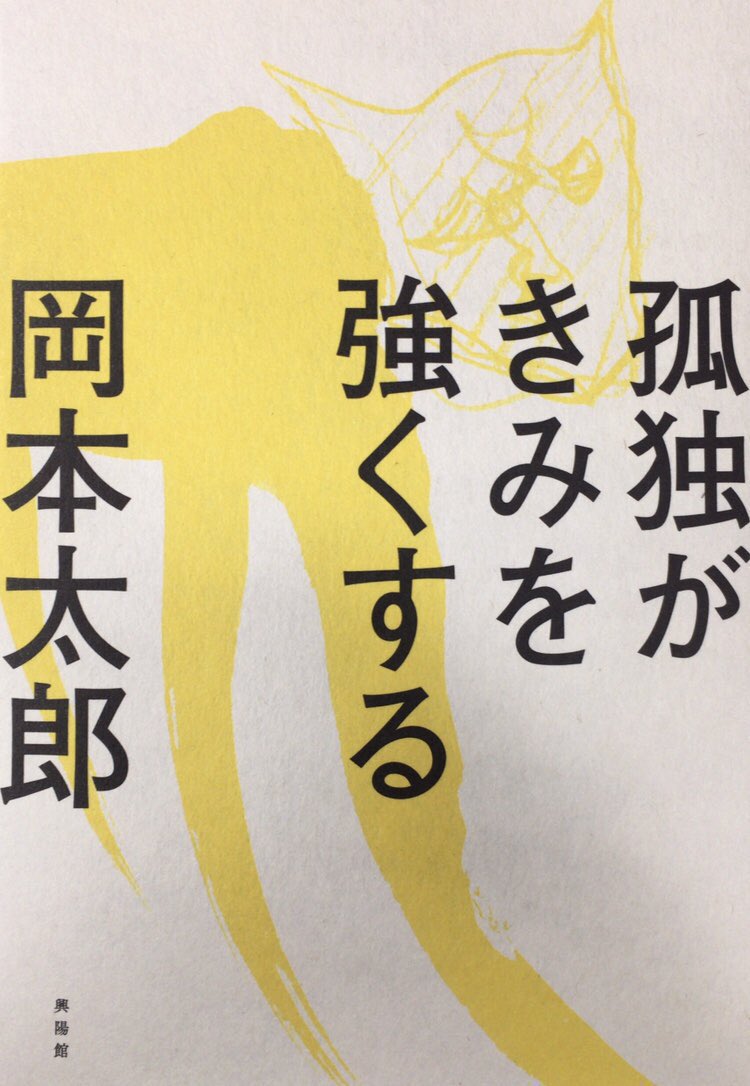801
802
804
805
806
807
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
820
821
822
823
824
825